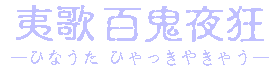
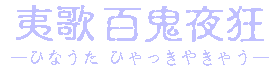 |
|
『百鬼夜狂』は、はじめ天明五年(1785)に編まれ、出版されました。四方赤良(大田南畝)を始め、当時活躍してゐた十六人の狂歌師が百物語戲歌を狂作、いや競作、百首を選んで纏めたものです。その後、妖怪をからかつた報いか、文化三年(1806)の火災で版木の大半を失ひました。が、世に再刊を望む聲高く、初版刊行三十五年後の文政三年、恐れを知らぬ蔦屋重三郎によつて補修され、再版されるに至りました。このテキストはその再版本を翻刻した『江戸狂歌本選集 第三巻』(東京堂出版)所収の「夷歌百鬼夜狂」を底本に作製したものです。注釋は恐れを知らぬ水垣の手になり、きはめて不備なものですので、ご教示・ご叱正いただければ幸ひです。 底本の編者「江戸狂歌本選集刊行会」の皆樣、ならびにアニメGIFなど素材を提供して頂いたPOKI樣(HP)・暗黒工房樣(HP)に感謝を捧げます。 |
| [見越入道](みこしにゆうだう)夜、道を歩いてゐると、ふと背後から異樣に長い影法師が忍び寄り、その影にすつぽり包まれて仕舞ふ。と思ふと、上からさかさまの首が伸びて來て、ぎよろりとした眼がこつちを睨んでゐる。……そんな入道すがたの化物を、見越入道とか單に見越とか言つた。實は月の光を受けた、枝ぶりのよい野寺の松だつた、なんてこともよくある話。 |
 [雪女]吹雪の晩など、山道を歩いてゐると出くはすことがあるといふ。顔が眞つ白で、美貌であるが、うつかり言葉を交はすと取り殺されて仕舞ふ。 [雪女]吹雪の晩など、山道を歩いてゐると出くはすことがあるといふ。顔が眞つ白で、美貌であるが、うつかり言葉を交はすと取り殺されて仕舞ふ。雪女も化粧をしてゐるのかどうか。いづれにしても化生のものだ、といふのである。 |
| [人魂]は昔から、晴れた月夜に現はれることは稀で、雨や曇りの晩に出ることが多いらしい。妄執の凝つて出來た迷ひの雲から、現世に晴らし得ぬ怨みを殘して死んだ人の魂が、ばうつとした光跡を引きながらさ迷ひ出るのである。 |
| 夜道を歩いてゐると、首ばかり白くあらはした女が前をゆく。美しく結ひ上げた髮の毛に誘はれて思はず近寄つてゆくと、女の髮に挿した象牙の櫛が、牙よろしく喉元に觸れさうになる。これまた恐ろしき夜行であり、夜狂であらう。 [蛇足]「首ばかり出だす」に轆轤首を匂はせてゐることは言ふまでもないが、ろくろ首は後ほど改めて詠はれる。 |
| [離魂病]魂が體から拔け出し、もう一人同じ人間が現はれる、と考へられてゐた病。どつぺるげんがあ。水に映つた月の光に、月も離魂病を病んでゐるのかと洒落れたのである。 |
| [うしろ神]暗い夜道を歩いてゐると、突然後ろから何かが髮の毛をひつぱる。やがて冷たい手で首筋を觸はつたりする。女の髮をくしやくしやに亂す、變な趣味を持つたうしろ神もゐるさうだ。 美しい後ろ髮が長く垂れてゐる姿に惹かれ、思はず後をつけて行きたくなるのは、男の「ながきためし」なのであらうか。 |
| [山男]深山に住み、はだか同然で暮らしてゐる。大柄で、身長六米に及ぶ者もゐるといふ。重い荷を脊負つて山道を歩いてゐるときに出くはすと、荷物を運ぶのを手傳つてくれたりもするさうだから、氣の優しいところがあるらしい。
[呼ぶ子鳥]は、普通カツクワウなどの鳥を指すことが多いが、この場合「呼名の怪」のこと。人の名を呼んで心神を奪ひ取る物の怪である。その正體は山彦と同一視もされたやうであるが、詳しいことは判らない。 峠で腰をぬかし、朦朧としてゐる山男。何ごとかと思へば、どうやら「呼名の怪」に名を呼ばれて心神虚脱に陷つてしまつたらしい。 |
| [切禿]とは、髮を切り下げて結ばずにゐる髮型、及びその髮型をした童子。有名なのは、歌舞伎「土蜘(つちぐも)」に現はれるキリカムロであらう。土蜘蛛が切禿の童の姿になつて源賴光を襲ふ、といふシインがある。「をりしも丑三頃 しんしんと更け渡る夜も烏羽玉の 切禿都育ちか京人形 ちよこちよこ歩むうしろ紐 お茶の通ひのにこにこにこと…」。
狂歌の「しにんす」は「死にしやんす」の約。 |
| ひゆうどろどろどろ……泥泥泥。 |
| 五丈はメエトル法で言へば約十五米。昔の人にとつては「途方もなくでかい」の代名詞みたいなもの。因みに奈良の大佛もその丈五丈ばかりなりけり。 |
 「金平(きんぴら)」は足柄山の金太郎こと坂田金時の子。怪力無雙の武勇傳の主人公。母親は山姥であつたといふ。[山姥]は恐ろしい脚力の持ち主で、風の如く山を驅け巡つた。 「金平(きんぴら)」は足柄山の金太郎こと坂田金時の子。怪力無雙の武勇傳の主人公。母親は山姥であつたといふ。[山姥]は恐ろしい脚力の持ち主で、風の如く山を驅け巡つた。 |
| [逆柱](さかさばしら)は、自然に生へてゐた時とは逆さに立てられた柱。家鳴りや火災などの原因として忌まれた。柱にされた木が腹を立て、家に災ひをもたらすと考へられたのである。 |
| [毛女郎](けぢようらう) ある男が遊女のもとに通つてゐた。その晩も高楼へやつて來たが、連子(れんじ)の前で髮を亂して立つてゐる女の後ろ姿を見かけた。あの女だなと思つて前へ廻つて見たところ、顔中いちめん髮が生へてゐて、鼻も目もあつたものではない。男はそのまま悶絶してしまつたといふ。 「繩手」は田のあいだの道、あぜ道。 |
| [楠亡靈]南朝の武將楠木正成の亡靈。 「もうねん」に妄念・もう寢んを掛ける。「七つがしら」は七つ時(寅の刻)の少し前の時刻をいふ。 |
| [小袖の手]小袖とは、袖口の狹い着物のことで、庶民の娘の代表的な晴着。生活が苦しくなると眞先に質屋に入れられる、代表的な質草でもあつた。そんなわけで、質屋や古着屋から手に入れた小袖には、もとの持ち主だつた娘の怨念が籠つてゐることが多かつたらしい。それが袖口から手になつてあらはれ、新しい持ち主を脅かしたのである。 |
| 屋根の棟の両端につけた瓦は、魔除けのために鬼の面を形どつてゐるものが多かつた。これを鬼瓦といふが、軒瓦にも鬼の貌をしてゐるのがあつたのだらうか。 |
| [せうけら]屋根の明り取りの窓から、何かが家の中を覗いてゐる。何ものかと思つて外に出てみると、影も形もない。…そんな覗き見妖怪を「せうけら」と呼んだ。 「庚申(こうしん)」は庚申待のことで、庚申(かのえさる)の夜、帝釋天や猿田彦を祀つて徹夜する習俗。その夜眠つて仕舞ふと、罪を「せうけら」によつて上帝に告げ口され、地獄に落ちるとか壽命が縮まるとか信じられた。「半兵衞」は、「知らぬ顔の半兵衞」、知らん振りを決め込む人の代名詞であるが、俗語で情夫も意味した。 |
| 那須の[殺生石]は、鳥羽天皇の寵妃玉藻の前(實は老狐の化身)が殺されて石と化したもの。これに觸れると祟りをなすと恐れられた。 |
| [さとり]は飛騨や美濃の山中に現はれた妖怪。人の心を讀み取る力があるといふ。山男の一種とも言ひ、ヒヒに似た體躯容貌をしてゐるとも言ふ。生け捕りにしようとしても、必ず事前に察知され、三十六計逃げるに如かずと案じたかどうかは知らないが、たちまち遁走するので決して捕まることがない。
「四さう」は四相、佛教で萬物の變化を示す四種の相をいふ。生・老・病・死、または生・住・異・滅の四相。四相をさとる、とは、無常を悟る、といふ意味に近い。 [鑑賞]さんろくさつてさるまなこ、さとり、とサ音を四つ重ねた流れるやうな歌ひぶりを味はひたい。 |
| [夜叉]は、もともと印度神話に現れる森の神で、人を害する惡と、財寶をもたらす善と、二面性をもつた神として怖れられ信仰された。これが佛教に取り入れられ、天龍八部衆のひとつとして佛法を護持する荒々しい鬼神となつたのである。狂歌は、「外面似菩薩(げめんじぼさつ)、内面如夜叉(ないめんによやしや)」(そとづらは菩薩のやうだが、そのじつ内面は夜叉のごとく恐ろしい)といふ諺をひつくり返したもの。 |