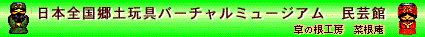
----広島県篇(4)----
----HIROSHIMA----
|
■三原人形(廃絶)■ 三原の城下町では、かって大型の三原人形が焼かれていて、大正10年頃まで、6軒の家が土人形を作っていました。 この土人形は、江戸末期に桜井兵助により作り始められたといわれています。節供人形が主体で最初は伏見人形にまねて作られましたが、後に博多人形の美しさにひかれて、その手法を取り入れたということです。 ■厳島管弦祭りの船(廃絶)■ 旧6月17日の厳島神社で催される「舟祭り」の御座船を模して作られたものです。戦後、いちじ復元品が作られことがありますが、残念ながらいまは廃絶しています。 また、いっしょに掲載されている「鹿猿」は、古い形のものです。 |

|
■たのも船(頼母、田面船)(宮島)■ この「たのも舟」は、一般に市販されているものではありません。 お盆の精霊流しに使われ、灯を入れて海へ流される豪華な舟です。土地の人々の家で作られます。 ■大竹の流し雛■ 大竹の流し雛は、ベニヤ板やボール紙に張り付けた立雛で、紙粘土の首に千代紙の着物を着せた一対の雛です。 大竹の雛流しの行事は、古くからありましたが、戦後絶えていたのを昭和33より3月3日すぐあとの日曜日に、小野川流域の木野川(このがわ)、穂仁原(ほにわら)など4地区で、市の観光協会と教育委員会の主催で行われようになりました。 制作者:畠中巨骨:大竹市油見町 ◇雛流し・流し雛 問い合わせ先◇ 大竹観光協会:大竹市油見3-18-11 大竹商工会議所内 TEL:08275-2-3105 大竹青少年育成市民会議(泉すみ子副会長):大竹市白石1-5-10 TEL:08275-3-1313 ■大竹の紙鯉■ 紙製の鯉のぼりの歴史は古いのですが、大竹の鯉のぼりの作り始めは、いまのところ不明のようです。大竹の紙鯉は、手漉きの紙で手描きの鯉のぼりです。 鯉のぼりの大きさは、全長1.5メートルから6メートルまで6種。真鯉と緋鯉があります。真鯉には金太郎が背に乗っています。 手漉きの和紙は長さ90センチ、幅60センチで、これを何枚かつなぎ合わせて鯉を作ります。鯉は袋になるように2枚を重ねて鯉の形に裁断し、裁ちはしで背や胸びれをつけてから、ハケで絵付けをします。 初めに目玉を入れ、次に胴体のうろこ、それから尻尾を描きます。裏面も同じように描き、最後に口輪をつけてでき上がりです。 この紙鯉は、県の最西端の大竹市の「広島県和紙商会」が作っています。 制作者:広島県和紙商会(大石雅子):大竹市天町 4-5-14..TEL:08275-2-2204
|

|
(1999.2.21掲載)