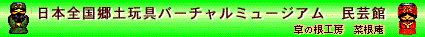
----広島県篇(2)----
----HIROSHIMA----
|
■田面(たのも)船■ 尾道では、伝統的な「尾道では、伝統的な「田面(たのも)船」と「三体みこし」が本庄政吉さんにより作られています。本業は神棚の制作で、この玩具作りは現在8代目です。 この玩具は、神棚作りで余った材料で、しかも片手間に手作業で作られるものなので、それぞれの季節が近ずかないと作られません。 田面船は、9月1日(旧暦の八朔)に、男子の生まれた家へ贈る船で、この船を曳いて産土(うぶすな)神にまいる風習があり、この頃になると作られます。 また、この船は、北国から鰊や昆布を運んできた船をかたどったと云われています。船腹には、波模様、鶴、鯛などの縁起ものが描かれています。 制作者:本庄政吉:尾道市久保1-1-1..TEL:0848-37-6414 ◆八朔(はっさく): 旧暦の8月1日。 昔農家ではこの日に秋の豊作を祈る習慣がありました。武士や公家の間でも八朔の贈答が行われました。 今でも一部の農村にこの行事の習慣が残っています。 |

|
■田面(たのも)人形■ 今は作られていませんが、八朔には田面船のほかに「新粉(しんこ)細工」の「田面人形」が作られていました。新粉(しんこ)細工は保存ができないので、掲載の人形は紙ねんどで再現されたものです。 八朔に新粉細工を作るのは、瀬戸内海沿岸の各地で、また尾道地域では内陸地方まで行われた習俗でした。 この新粉細工とは、米の粉を練って蒸し、臼でついてこねまわし、団子状にしたもので人形をつくります。食用染料を使って着色します。 人形には、馬乗鎮台、金時、すもう取り、三味線弾き、踊り子などが作られました。 三味線弾きは、吉原の芸妓が八朔に白小袖を着た故事にならったといわれ、姉さまとも呼ばれて女の子に贈られました。 ■尾道の三体神輿■ 三体みこしは、7月21〜23日の3日間、市内の久保八幡神社境内の、八坂神社の「祇園祭り」に出る神輿を模したもので、その頃に露店で売られます。 三体とは、スサノオの命の一つ巴、須賀八耳命の二つ巴、クシナダヒメの命の三つ巴ですが、 玩具のみこしの形はみな同じです。 祭礼の日、渡御の途中三ケ所で、三体のみこしがすざまじいぶっかり合いをします。 その有様を遊びにしたのがこの玩具で、三体を台の上に置いてトントンと台を叩くと、みこしがもつれ合い、ぶっかり合うように動くのを楽しみます。 いまは、作られていませんが、三体のみこしが一本の柱に取り付けられて、争いの様子を玩具化した「三体回し神輿」が以前には作られていました。 製作者は上記の田面船の本庄政吉さんです。
|

|
(1999.2.8掲載)