 |
| �M�������ف@1 | �M�������ف@2 | ��ԑ����}�� | �M�k�@��♍�6/8 |
 |
 |
 |
 |
�����Ă��āA�F���������킢�� * |
�܂��̎q������ * |
|||||
 |
* |
* |
|||
* |
* |
|||
 |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
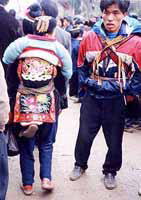 |
 |
|
* |
�M�z�� |