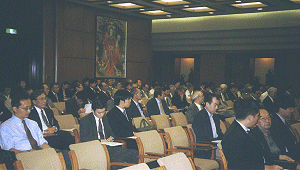 一つは、2000年10月に、この学会の記念すべき第二十回大会を、私の前任校において開催したことでしょう。経営学部の鈴木教授を委員長とし、幸いに多くの先生方、また院生諸君らが全面協力してくれたので、この節目の大会にふさわしいものにはできたのではないかと、いまもよき思い出になっています。
一つは、2000年10月に、この学会の記念すべき第二十回大会を、私の前任校において開催したことでしょう。経営学部の鈴木教授を委員長とし、幸いに多くの先生方、また院生諸君らが全面協力してくれたので、この節目の大会にふさわしいものにはできたのではないかと、いまもよき思い出になっています。(2002.10オリジナル作成/2024.3サーバー移行)
(三十周年を超えての、ぼやきとおまけ付き)
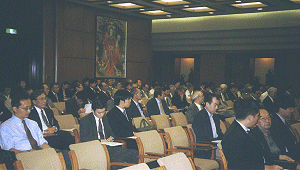 一つは、2000年10月に、この学会の記念すべき第二十回大会を、私の前任校において開催したことでしょう。経営学部の鈴木教授を委員長とし、幸いに多くの先生方、また院生諸君らが全面協力してくれたので、この節目の大会にふさわしいものにはできたのではないかと、いまもよき思い出になっています。
一つは、2000年10月に、この学会の記念すべき第二十回大会を、私の前任校において開催したことでしょう。経営学部の鈴木教授を委員長とし、幸いに多くの先生方、また院生諸君らが全面協力してくれたので、この節目の大会にふさわしいものにはできたのではないかと、いまもよき思い出になっています。

それからちょうど二十年前、この日本中小企業学会が設立された当時の写真が、私の手元にあります。この設立総会にあたっては、当然それにふさわしい記念写真などがあるはずなのですが、私はその手伝いで駆け回っている際に、自分のポケットカメラで、記念写真撮影直前のスナップを撮っていました。従ってピントもよくないし、ネガも古くなっているし、なにより「さあこれから記念写真」というところの直前の、皆さんそのモードに入っていない、あまりお褒めを頂けないような代物の画像なのですが、「歴史的史料」としての価値がないこともないでしょう(この写真は、私が日本中小企業学会のWEBページを担当していたとき、山中初代会長のスピーチの一部とともに公開をしていました)。

この写真に写っているなかで、すでに亡い、思い当たる方々のお名前を記せば(敬称略)、
初代会長山中篤太郎、小田橋貞寿(会長代行)、藤田敬三、磯部喜一、末松玄六、渡辺睦、中山金治、田杉競、山本順一、加藤誠一、中村精、磯部浩一、伊東岱吉(第二代会長)、尾城太郎丸、藤井茂、佐藤芳雄(第六代会長)、前川恭一、細野孝一、これらの諸先生です(ほかに亡くなられた方もこの中に写っているかも知れないのですが、写真の不鮮明と、私の知識不足でよく判明しません)。
そして最近には、間苧谷努、瀧澤菊太郎(第四代会長)両氏が亡くなられたという報を受けています。
この設立総会が慶大三田校舎で持たれた1980年当時、私は大学院に長逗留中で、ために総会のお手伝いには奔走しましたが、いまだ会員でもありませんでした。翌年、職を得るとともに会員にしてもらい、同年6月の第一回全国大会(大阪経済大学)で研究報告をした、これが私と学会とのかかわりの本当の出発点となったのです。
設立総会の会場には、当時の私にとっては本の中でしか名前を知らない諸先生方が目の前に数々並んでおり、いかにもまぶしい思いがしました。当学会設立という大きな目的を果たし、まもなく世を去った山中篤太郎大先生は会議開始前に、蝶ネクタイの装いで杖をつきながら、案内係の私のところへ来られ、「薬を飲むために水がほしいのですが、どこにありますか」と尋ねられました。直ちにその場所へ同行案内をして差し上げた、これが私の人生でただ一度、戦前戦後の中小企業研究の大御所、山中先生と言葉を交わした思い出です。
今年(2002年)、日本中小企業学会の第二十二回全国大会が専修大学生田校舎で持たれました。今回の大会では、学会の国際交流を積極的にすすめるという港徹雄会長の方針の下、私の知人でもある英国中小企業研究学会(ISBA)のRobert Blackburn 教授(Kingston University)をゲストスピーカーとして招待し、大いに親交を深めることができました。
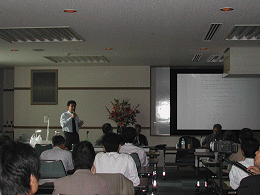 私にとってはまた新しい思い出を得られただけでなく、この二十年あまりという時間の隔たりのなかで、学会の設立と発展、研究の進展に道を開いてこられた多くの大先輩諸先生の、あのとき、あの場で、というそれぞれの活躍の姿と、今度の大会の各場面とが、なにか重なって見えてくる思いがします。
私にとってはまた新しい思い出を得られただけでなく、この二十年あまりという時間の隔たりのなかで、学会の設立と発展、研究の進展に道を開いてこられた多くの大先輩諸先生の、あのとき、あの場で、というそれぞれの活躍の姿と、今度の大会の各場面とが、なにか重なって見えてくる思いがします。
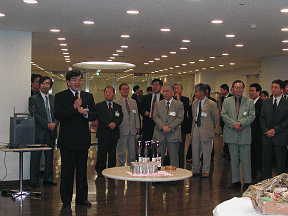
日本の学会は曲がり角などとは、もう十年来語られ続けてきたことです。学会のありようを活性化し、学問研究のレベルを高め、社会の要請にこたえられるものにしていくこと、それは私たちの世代の責務でしょうが、これからどれほどのことができるか、私にも確信はありません。
二十余年前に日本中小企業学会を設立した大先輩方、その努力と思いに比べようとするならば、いまからまた二十年後、いまの私たちのなしていることが今度はどれだけ評価されるのか、学問の進歩にいくらかでも寄与できたものとされるのか、なんとも申しようがないところです。
えー、さて
なお、私のキャンディッドフォトじゃない、この日本中小企業学会設立時の正式記念写真、以来30年近くが過ぎたいま、学会渡辺前会長の手元のものを公開用に提供いただきました。
学会webサイト上で見ることができます。それにリンクをしておきます。
懐かしさを通り越して、30年という歳月は誠に深遠なものがあると、この写真は語ってくれています。
うえの記述は2002年のことですが、2008年からはかく申す私が当学会の会長を務めている次第で、それだけでも歳月の隔たりは恐ろしいほどのものがあると、いまさら手遅れでもありますが、ともかく自覚せねばなりません。
ところで、この公式記念写真には私も写っているんですが、さて、どこにいるでしょうか?
2011年、もう30周年も通過
いまじゃあ、ついに30年を通り越してしまいました。私もなんとか学会会長職を終え、「楽隠居」めざしてまっしぐらです。
私の任期中にはあれこれ新しい事業を導入、仕事も増やしたが支出も増え、しかし会員数は大して増えず、逆に「行革」と「仕分け」の嵐で、「よけいな会費負担は切れ」とされた賛助会員の退会が相次ぎ、学会の財政事情を悪化させたという「評判」のみ残りました。おかげで、私のあとの会長以下、学会役員は大変です。
こんなところが私の能力の限界で、山中先生以来の偉大なる会長の方々はさぞや呆れておられることでしょう。それではとうてい、お仲間入りどころか隠居なども許してもらえないかも知れません。責任とって、ゼニを稼いでこいと叱咤されるとか。もっとも、戦後中小企業研究第3世代を自称する私としては、誠に無責任ながら、これからの第4、第5世代にがんばってもらうのみ、ついては学会運営にも画期的な発展を期待するのみ、許されざる隠居ではあっても、まあ精神的にはセミリタイアであります。
32回目は回り回って
日本中小企業学会の第32回全国大会(2012年9月)は、私が転職した先の嘉悦大学で開催されることになってしまいました。もちろん、1年以上前から決まっていたことなので、覚悟の上というのは当然でしたが、因果なことではあります。容易にリタイアはさせてくれません。
ただ、今回は在職の大先生方が既に諸事を分担実行されており、私は少々楽ができました。私の主な役目は、実は「撮影係」でありまして、大学のwebサイトに載せられた、これらのスナップはすべて私が撮ったのです。
あとは、ここにも写っている懇親会の司会で、結構言いたい放題をやったような記憶が頭の隅に残ってます。全国から集まられた会員の方々は、「あいつなんでこんなところにまたしゃしゃり出てるんだろ」と思われたことでしょう。
2019年秋、学会の役職から引退し、文字通り次世代にバトンタッチ
歳月が過ぎるとともに、人間は自動的に歳を取り、当然さまざまな仕事やお役目を、若い世代に継いでいくことになります。
私の研究人生にとって、一番大きな存在であった日本中小企業学会、その役職を、会長を含めて経験して参った私です。しかし、この歳になり、大学の職もすべて退いた身では、学会の担い手の使命も当然引き渡していかねばなりません。
2019年に役員選挙が行われ、次期の役員が決まりました。それにより、私は正式に、学会の役職から引くことができました。
日本中小企業学会の役職を、どれだけ経験してきたのか、あまり覚えていないのですが、記憶では、常任理事、編集委員長、副会長、そして会長を致してきたはずです。
おのれの思うところ、とりわけ学会運営体制の円滑化、大会の組織の責任明示化、査読学会誌の向上、さらには若手研究の奨励、国際交流の推進などを図ったつもりでおりますが、どこまで担うことができたのか、それは確信が持てません。微力を尽くした、という表現にとどまりましょう。
私の前、学会会長を務められた港徹雄氏、渡辺幸男氏はお元気ですが、その前、会長職にあった伊藤公一氏、小川英次氏は近年相次いで世を去られました。小川教授のあとの会長であった佐藤芳雄氏は早世され、もう20年が過ぎています。逆に申せば、私の言葉で、「戦後中小企業研究の第一世代、第二世代」の諸先生方はおおかたもう世になく、私を含めた「第三世代」は完全引退の身になったということになります。
次年度、2020年度の記念すべき第40回大会は、駒澤大学で再び開催されることが決まりました。私個人には誠に感慨深いものです。前回、20回大会から丸二〇年、私自身にも、学会と会員諸氏にも、そして日本の中小企業の実情、政策の動向にも、大きな変化の数々あったこの間と申せましょう。
駒澤大学において、次期大会を担われる、若い諸氏に大きな期待を寄せるとともに、「来年までは」なんとか元気でいて、二〇年目の思いを、多くの方々とともにしたいと、心から願うところです。
(2024.2)
それからさらに4年が過ぎ、学会の世代交代も急です。しかも、世界的パンデミックというえらい事態を迎え、学会大会なども「リモート開催」相次ぐという、かっては想像も出来なかったような状況が続きました。まあ、その分開催費用も抑えられるし、参加する側も交通費宿泊費など要らず、時間も大いに節約できるということで、「助かった」面もあるやに聞きますが、私のような古い人間には、ともかく面突き合わせ、「空気を共に感じる」中でなくちゃあね、という心根を容易に捨てきれません。その辺の物足りなさもあるゆえ、2022年の日本中小企業学会全国大会がともかく東洋大学で「リアル開催」となった(2021年の第41回大会は福岡大学会場だったが、リモート開催に)だけでも、嬉しいことでした。関係者には深く感謝しております。
ただ、この間に大事件となったのは、現職の学会会長であった佐竹隆幸教授(関西学院大学)の急逝でした。まさに学会を担われて活躍されていた人が病に斃れる、誠にいたましいことです。それだけに、私のようなロートルがまだ生きながらえている、そうした思いを改めて感じざるを得ませんでした。
前記の、2020年の第40回駒澤大学大会はリモート開催となってしまったものの、学会四〇周年ということで、私を含めた老体が「昔語り」をする機会を貰い、まさに「回顧談」的な代物を学会論集に載せて貰うことも出来ました。それなのに、次の時代の担い手が急逝する、なんと非情かつ不条理なことでしょうか。
→ つぎへ