
この学会の組織や大会の特徴を、日本の場合と比較しながら、見ていってみましょう。
英国中小企業政策・研究学会記
11月18〜20日、イングランド北東部で開かれた、「英国中小企業政策・研究学会第21回大会」に行ってきました。
私は、勤務校で「中小企業論」を担当し、「日本中小企業学会」の常任理事でもありますので、英国のcounterpartと言えるこの学会への出席は、さまざまな意味で興味深いものでした。
この見聞に加え、日頃私が考えている「独断と偏見」を縦横にちりばめて、一つの覚え書きとしてみましょう。
垣間見た英国中小企業学会の姿
この英国の学会は、正式名称を、Institute for Small Business Affairs(ISBA)の開催する、National Small Firms Policy and Research Conference と言っております。名前からは、「中小企業研究所」といった組織を想像しますが、実態としてはこれはまったくの学会団体(academic society)で、事務局のみが存在しており、おもにこの全国大会の開催や、ニュースレターの発行、その他を行っています。ただ、「会社」組織となっているのが特徴です。現在の会長は、マンチェスタービジネススクールのフランシス・チッテンデン氏(Dr. Francis Chittenden)で、理事(directors)には、ジョン・スタンワース ウェストミンスター大学教授、デビッド・ストレィ ウォーリック大学教授、そして私のいるキングストン大学のロバート・ブラックバーン教授など、現在の英国の中小企業研究を代表する人間たちが就いております。

この学会の組織や大会の特徴を、日本の場合と比較しながら、見ていってみましょう。
英国の学会の組織
第一に、この学会はその構成員をかなり広くとらえています。会員募集のパンフレットからみると、「中小企業のための政策の立案や実施、評価などにかかわる人々、ビジネスリンク、TECsといった中小企業のための施策実施機関、高等教育や上級教育機関、企業への助言サービスなどに携わる人々」に参加を呼びかけています。それに、毎年の全国大会に大会費を払って参加しますと、一年間自動的にISBAの会員になるのだそうで、かなり緩やかな組織です。
ただ、それはあとでも触れる、この学会の性格ならびに、そもそも英国の社会で「アカデミズム」が占めている地位ということにも大きくかかわっています。つまり、この学会は当初から、「政策」に直接関与するという立場をもち、そのため、中小企業政策関係者の参加を非常に重視してきたのです。それが会員構成や大会の主題、議論の方向に強く反映しています。
第二に、そうした経緯や構成上からも、学会の運営には、各方面の積極的な寄与を期待してきています。日本では、特に社会科学や人文科学の学会というのは大部分、大学教員らの会員の払う会費だけで運営され、甚だ貧乏なのですが、ISBAは、地域の施策実施機関、中央政府機関、さらに銀行やコンサルタント機関などの物心両面からの援助を受けてきています。このISBAの設立に寄与した、中小企業団体の一つである「私企業フォーラム」(Forum of Private Business)の総裁スタン・メンダム氏は、国際的な活動でも知られていますが、現在も理事のひとりで、ISBAの運営に影響力が大きいものです。
今度のダラムでの第21回大会でも、ダラムカウンティビジネス・リンク、DTI政府貿易産業省、ロイズTSB銀行、ダラムカウンティ開発公社、ダラム市、ACCA英国公認会計士協会がスポンサーとして名を連ねていました。このうちでもACCAは恒常的にISBAとの関係が深く、その運営に参加するとともに、共同で研究会やシンポジウムを開いたり、調査報告を出したりしています。英国の会計士は、中小企業への関心が高いのです。
第三に、したがって、学会大会もなかなか盛大なものです。大会はだいたい、各地のホテルなどを会場に開かれます。私がはじめて参加した、12年前の第9回大会は、開催担当はスコットランドのスターリング大学でしたが、会場はゴルフ場で有名なグレンイーグルスホテルでした。このホテルに泊まれるというだけで参加しようという向きさえあったくらいです。
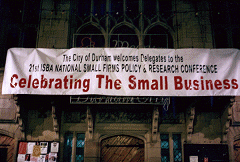 |
第四に、ですからもちろん大会参加費も安くはありません。今度の場合、個人参加・二泊三日の宿泊付ですと、450ポンド(約9万円)でした(2人でツイン同室を選ぶと、一人あたり400ポンドになる。同伴者ありの場合は、あわせて510ポンド)。大会のみの参加でも、275ポンド(約5.5万円)です。日本の学会とは一桁違います。もちろん、みんなが自腹を切って参加しているのかどうかは別ですが。また、英国の学会がみんな高い参加費を取っているわけじゃありませんが。
では、こうした形式や外見のことは別として、実際の大会の模様やそこでの議論はどうなのか、中身の方を見ていきましょう。
英国学会大会のもよう
○まず、大会での報告や議論はなかなか活発です。会費が高くて、豪華で、となっては、単なるお祭りやパーティになりかねませんが、これはまったく違って、あくまで学会大会としての水準を維持しています。当初のプログラムでは、3日間にわたって、29分科会、のべ78本の個別報告、連日続く全体会、そしてテーマ毎の7つのシンポジウムが用意されていました。もちろん、その通りにすべてが行われたわけではありませんが(そのおかげで、えらい目に遭いましたが)、大会の主題と、それぞれの研究報告が、活発にまた溢れんばかりに展開されていることは間違いありません。
残念ながらこの数字は、日本の場合とはこれまた一桁違います。
○ただ、これだけの数を3日間でこなすのですから、分科会の個別報告は、1件15分が原則です。これはかなり厳しいことは事実です。ですから、まあこうした学会大会に限りませんが、OHPなどのビジュアルツールを駆使し、短時間内で機動的に、要領よく、自分の報告をこなすのが、重要なスキルであり、そのための事前の準備も大事になってきます。
この点でも日本の学会では、いっこう要領を得ず、なにを言いたいのかわからず、またよく聞こえない、説明資料が甚だ乏しいといった「報告」が、延々一時間もかけてやられたりするので、参ります。
○そして、このISBAの大会への報告者には、フルテキストのペーパーを、4ヶ月近く前の期限までに提出することが義務づけられています。もちろん上限の制限もありますが、それが80本近く集められるのですから、大会当初に全参加者に配られるProceedingsは、電話帳並み、上下2冊からなる、のべ1400ページ近い代物で、もちろんこれを持ち歩くだけで恐怖ですから、資料やノートなども入れて、ショルダーバッグ付で用意されています。それにしても、これを持って帰るだけで憂鬱になります。
これだけあれば、現在の研究状況が一望できるという利点はあっても、あまりにボリュームがありすぎて、受け取ったとたん、読む気力がまず失せます。それにカバン付であっても、結局重いものだから分科会会場にも持ってこず、全然役に立っていない向きもあります。
まあ、9万円もの大会参加費は、ホテル代とメシ代と、それにこの電話帳及びカバンの値段なんだと考えれば、納得がいかないわけでもありませんが、ちょっと「舌切り雀の葛籠」的ではあります。
○フルテキスト、一本あたり20ページ近い文章は、確かにそれだけで独立したモノグラフとも言えるもので、いくらなんでも全部の報告なんかとうてい聞けなくても、あとでじっくり読んでいく材料にはなります。もちろん、結局ペーパーの事前提出がなく、載っていない報告もあるわけ(それどころか、結局報告者自体来なくて、キャンセルになったとか)ですが、載っている限りでは相当中身の濃いものです。
これに比べ日本の学会では、なんせ貧乏なので、ご予算の都合もあり、「予稿集」といったものがつくられても、割り当ては一本1ページ程度、ほとんど「項目名」が並んでいるのみ、といった事態が珍しくありません。それさえもなくて、「白紙」論文のままになっているとか。ただし、それですから大会開催前に参加者に郵送する、その場でも持ち歩きやすい、見やすい、メモをその場で書き込みやすいといった便利さはあります。そのかわり、報告者自身がさまざま配付資料や文章のコピーを用意してくるというのが慣例となってしまっています。
○このフルテキストは、その形式はもちろんのこと、表紙、書体から文字ポイント、レイアウト、ヘッダーに至るまで、細かく指定されてきております。それで、ボリュームに製本したときの体裁をできるだけ整えようというわけです。でも、実際の出来を見ると、こうした指定をまるで無視したようなものも堂々と出ており、編集責任者も苦慮するところでしょう。
私は、この指定をできるだけ忠実に守った(もっとも、全体の語数制限はかなり超過していたんだけれど、制限ページ数内には収めるという「曲芸」を発揮した)のですが、「WORD 6」形式指定というのにはちょっと抵抗感がありました。アメリカンスタンダードの押しつけ、MS世界独占への協力というのは愉快じゃありませんし、それにしたって、私のソフトは「日本語WORD」で、Ver.7相当版、何で一つ前でなくちゃいけないんだ?というところです。
それに、もちろん私は英作文に自信があるわけじゃないので、自分のドラフトをロバートに見て貰って、添削を受けました。英文の書き方ばかりじゃなく、中身の構成や表現、議論についても、いろいろ意見を貰いました。それは非常にありがたいことですが、なにせ「チョー多忙」な彼のこと、その時間を割いて貰うのも申し訳ないうえ、そんなこんなでなかなか彼の意見を聞く、朱の入ったドラフトを返して貰うといった機会が持てません。ご本人自身でさえ、自分のペーパーを仕上げて送らなくちゃいけないとわかっているので、非常に微妙なところとなります。
結局、7月末日という期限を過ぎること20日ほどで、ついには時間切れで自分の独断のみの部分も残し、大会組織委員会にペーパーを送らねばならなくなりました。でも、その後の様子で分かったことは、私は期限を守ることも大事と相当に苦慮していたのに、この期限については実におおらか、大会一ヶ月あまり前になってようやく送ったりしているのです。従来の「伝統」がわかっているので、ロバートも期限についてはいとものんびりしていたわけです。細々した形式まで指定してきたのですから、あとの編集印刷作業の手間は、それほどでもなかったわけでしょう。
○それにしても、こうしたペーパーの形式、また報告自体の方法、説明の進め方といったものは、形にこだわるようであっても、英国の学会においては非常に重要な要素であり、そうしたことを知る、身につけるというのは、「アカデミズム」の大切な修業の一部なのです。もちろんそれは学会や研究会、あるいは論文の作成といったことに限りません。大学などでの授業、あるいはさまざまな機会での講演や意見の発表、すべてに共通しているものです。これに加えて、研究の進め方と、議論のしかたという項を入れれば、欧米の大学教育と研究の多くの要素がカバーされるといってもいいでしょう。
逆に言えば、残念ながら日本の学会で少なからず見られる、「白紙」同様の「予稿」、なにを言いたいのか要領を得ない話し、実にはっきりしないものの言い方などからは、こうした場でさえこうなんだから、この人たちが自分の大学などで、いったい学生諸君にどういう「授業」をしているのかと、そのこと自体が疑問になってきます。そしてそうした「先生」の元で「教育」を受ければ、それ以上のものは出てこようがないでしょう。
今さらのように、「ファカルティ・デベロップメント」などという言葉が使われますが、なにも「大学教育どうあるべきか」なんて大げさなことじゃなく、「わかる話」を「わかる」ようにできる大切さ、それがわからない、できない人が自分で「学者」などと自称すること自体おかしいのだ、と、自戒を込めて痛感させられます。
まあ、OHPって何ですか、それはどこに頼むとやってくれるのですか、といったことも、恥ずかしげもなくひとに聞けるのは、日本の大学の良さ、おおらかさではあります。私?もちろん、かつて自分で調べ、試しました。OHPシートというのはこういう種類があって、一番簡単なのでは、コピー機にかければいいんだ、ということから。おかげで今度の機会では、カラーインクジェットプリンターで、カラーのOHPシートを用意し、また報告「初体験」の、センター最若手のサイモンに「手ほどき」をしてやることもできました。OHPの冒頭に、センターのロゴマークを入れるのが慣例だ、というので、そのファイルを貰って自分の分を作り、今度はそれで、ロバートの分までロゴ入れを手伝ってやることにさえなりました。
日本の大学では、今もって、黒板とチョーク以外の設備を何で教室に設ける必要があるのか、と考えられていますから。はっきり言って日本の「教育技術」は、明治以来「進歩」を停止しています。
○「停まってしまった」ところで何で「実害」がないのか、その辺は別としても、「実害」甚だしいのが、「本業」のはずの論文や著作です。私自身は、「形式」ばかりにこだわるのがいいとも思いませんし、たとえば「ハーバード方式」などと称される参照文献の表記や引用のしかたが最良なのか、疑問を持ってもおります(今度のISBAのもこの形式指定でしたが)。でも、そのくらいは「知っている」のも常識のうちです。それに、「形式にこだわらず」、内容は立派というのも珍しく、多くは形も中身もめちゃくちゃという方が適切です。
その点、こうした欧米の学会の報告や論文の「常識」は、「リビュー」の徹底、それに基づく自分の問題意識と視点の明示と、「研究方法」(methodology)の正確な記述説明です。これを欠いたものは、学術的にまったく認められません。悪くすれば、それが説明の大半を占めてしまう恐れもありますが、これ抜きよりはましと考えられています。日本の学会のひどい報告のように、別にそのいずれでもない、どうでもいいような前置きや言い訳や余談や道草で時間の大部分を費やし、中身には入らずじまいなんていうのとはやはり違います。
○それとは別な意味で、この学会の特徴として、「実証性」に重きが置かれているのにも注目できます。「空理空論」的な議論、あるいは「どこかの説の受け売り・解釈」といった議論がないわけではありませんが、あまり歓迎されていません。
これは、中小企業研究という分野の持つ特徴でもありましょう。日本中小企業学会をつくった山中篤太郎氏も、「調査なくして発言権なし」という考え方を強調されてきました。そして英国のISBAの場合、うえにも書いたように、当初から「政策研究」というきわめて実践的な分野を重視し、その「政策効果の測定」という問題にさまざまかかわってきたこと、さらに、学会をつくった人間たちに、ジム・カランやジョン・スタンワースといった実証「社会学」出身者が少なくなかったことが反映しているとも考えられます。
○しかし、「調査」というのは、危険な誘惑でもあります。「現実」に触れると、その魅力にとりつかれ、際限なくのめり込んでいってしまう、そして、その「一部」を「現場」から報告しているだけで、自己満足に陥る、これはありがちなことです。
もし英国のISBAがそうした「現場主義」のみに終始していたら、「中小企業研究」という伝統が皆無であった英国の学界で、これが学会としての権威を得ることは困難であったでしょう。今度の大会に出、またジム・カランやロバートらとのふだんの話などを聞いていて痛感されるのは、ジムらが「中小企業研究」をアカデミズムの分野として認知されるべく、いかに苦労をしてきたのか、という点です。
その場合大事なのは、「実証性」を支え、それを「学問」たらしめるような、うえにあげた、「問題意識」と「方法論」の確かさであり、そしてその実証研究の積み上げ・到達点を客観的に示し、確認していける「リビュー」の一般化です。この点に、ジムらの努力が注がれてきたのです。
もう少し別の言い方をすれば、「あそこに行きました」「これがありました」では話しにならん、ということです。「こういうことがわかりました」と書き加えてでも十分ではありません。「なぜ」、あそこへ行ったのか?「あそこ」は地図のうえのどこなのか?どうやって、そこへ行き、「これ」を見つけたのか?その「これ」は、「あれ」とはどこが違うのか?こういった問いを自分で発し、こたえられなくてはならないのです。
残念ながら、「中小企業の研究」というのは、そういう問いを忘れて、「現実」を追っているだけになる危険を多々はらんでいます。それだけ「現実」が多様で、さまざまな側面を見せているからです。これまた山中氏が用いた、「異質多元性」という表現も、英語で一般化しています。その「異質性」(heterogeneity)をあちこち追い求めていれば、一生かかっても、旅は終わらず、何のこたえも見つかりません。
ここいら辺への積極的な議論に深入りする前に、このISBA大会のその他の特徴を、駆け足で触れておきましょう。
実践的で実証的なテーマ
全体会では、政府やTECs、民間銀行などからの参加者を交えた、中小企業政策一般をめぐるパネル議論のほか、「企業家教育」「経営教育」が大きなテーマになり、実際の経験などを生かして、ダラム大学中小企業センター所長のアラン・ギブ教授、ロンドンビジネススクール講師・企業家経営基金(Foundation of Entrepreneurial Management)専務理事のジョン・ベイツ氏が講演を行いました。また、シンポジウムのテーマとしては、「経営と教育研修」「企業家精神と高等教育」「国際化への挑戦」「中小企業のマーケティング」「地域経済開発からの教訓」「情報化経営」「南部からの教訓」といったものがあがっていました。
分科会報告のテーマとしては、「中小企業の経営展開」や「望まれる政策課題・方法」がメインです。ただ、この学会の伝統を反映して、英国内のこと、またきわめてミニマルな話しが多いのは否定できません。「地域」にかかわる話しが少なくないのは、施策現場に関係している人々の報告が多々あり、それがまた大会開催地の特徴や課題を反映している面がつよいからです。長く産業衰退に苦しんできた、ダラムをはじめとする北東イングランドにとっては、これに代わる新産業の振興と企業の活性化は焦眉の課題でもあります。
英国以外にかかわる話しは、私の「日本の経験」以外では、中東欧やロシアの経済再建の中での中小企業支援といったもののみでした。近年、英国やEU各国は中東欧やロシアへの金融支援のみならず、施策面でもさまざま援助助言や経験提供を行っておりますので、かかわりが深いのです。一方、アジア系など、エスニックコミュニティからの企業家精神の発揮の話しもありますが、これはあくまで英国内のテーマです。
このほか見落とせないのは、「調査研究の方法」そのものを主題とした報告があることで、今回、ロバートが同じキングストンのデビッド・ストークスと組んで行った報告は、「英国の中小企業研究における企業オーナーたちとの対話:フォーカスグループの経験」と題し、キングストンのセンターが続けてきている、中小企業家たちとの交流グループの活動とそこから得られる研究面の成果を伝えるものでした。これは、私自身の報告と同時間にぶつけられたので、もちろん聞くことはできませんでしたが、かなりの聴衆を集め、相当熱のこもった場になったようです(他の報告者が来なくて、時間を目一杯使えたせいもある)。このように、「方法」自体がテーマとなり、大きな関心を呼べるというのは、重要な点でしょう。
 |
このほかでは、最近の施策の大きな課題にもなっている、「支払遅延問題」や「知的財産権問題」、情報化対応といったものにかかわる報告も目立ちます。
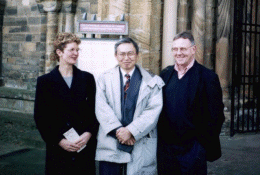 |
もちろん、我が国とは違い、「ベンチャー・ビジネス」などという「和製造語」が登場するはずもなく、また「ベンチャー企業(エンタープライズ?)」などという語も出てくるわけがありませんが、「成長志向型」企業を一般に表現する語としては、「High Growth」company、あるいはSMEといった用語が定着してきています。新たな事業を開拓する動きという意味で、「New Ventures」という表現は耳にしました。
いずれにしても、こうした「二つの階層」の違いをどう考え、扱っていくのか、ということは、英国の学会や行政関係機関のみならず、欧州規模でもしばしば問題となる点です。日本ではこの点を意識した議論が現在あまりに乏しいのは、不思議な気がします。あいまいにしてきわめて主観的、というより「気分的」な、「ベンチャー企業」なる和製語が定着してしまったこの国では、ともかく「中小企業」=マイナーにしてミゼラブルなもの、ぱっとしないもの、これと正反対の華々しいもの、先端的なイメージのもの=「ベンチャー企業」と言っていれば済むので、「規模」だの「成長性」だのといった小難しいことは一切抜き、マスコミ界はもとより、官界学界まで「気分」の議論でよし、となってきた模様です。
ちなみに、「血液型占い」同様、日本でしか通用しない「ベンチャー企業」なる造語を、異文化コンテクスト間変換のうえで、マスコミ関係者はどうやって使うのか、たまたまその過程を発見しました(某朝日新聞のWEBサイト)。原文で「new start-ups」と書かれた箇所を、「ベンチャー企業」と訳しているのです。マスコミやさんたちは、摩訶不思議な「翻訳ソフト」を持っていて、これに「変換作業」をゆだねている模様です。でも、どうして突然「カタカナコトバ」になっちゃうんでしょうか。私の「翻訳ソフト」では、「新出発」ぐらいにしかならないんですが。
若手研究者への機会の提供
今ひとつ注目できるのは、「若手研究者」たちへの対応です。前記のように、こんなに高い参加費では、若手の大学院生なんか参加できないだろう、あるいは「大物」の話しが多すぎて、若手の「かけ出し」的な報告など未熟のきわまりと閉め出されてしまうのだろう、といった心配はいりません。
まず、大会費の275ポンドは変わりませんが、宿泊については、豪勢なホテルじゃなく、「ビジネススクールレート」として、3スタークラスのホテルが提供され、その2泊込みで、シングルで375ポンドになります。そんなに安いとは言えないものの、泊まった若手の経験談では、ホテルも決して悪くなかったようで、院生への配慮はそれなりにされているわけです。
それ以上に有意義なのは、大会前日に開かれる「Doctoral Day」です。こちらは参加費と昼食・一泊宿泊付で何と20ポンド(約4000円)、さらに前夜に泊まってもプラス50ポンドです。この安さは、ACCAが全面的なスポンサーになり、会場もダラム大学ビジネススクールを用いるためです。
この「Doctoral Day」は、院生レベルの研究発表の場であるとともに、研究方法やペーパーの書き方、発表のしかたまでを指導助言する、きわめて教育的な機会です。そのための講演やワークショップが用意されています。個人の発表の形式も、「Poster Session」と称して、各500語以内のサマリーペーパーと、一枚のポスターの掲示によるものとなっており、あとでこれへの講評と助言が与えられます。私が実際にこの場を経験することはできませんでしたが、これまた参加した若手によると、きわめて有益かつ活発であったそうです。
こうした「Doctoral Day」は、毎年の大会毎に開かれています。つまり、ISBAとして若手の育成を非常に重視している、ということなのです。ですから、もちろんこの「Doctoral Day」だけじゃなく、大会での報告にも、若い研究者らの顔が目立ちます。院生レベルが単独で自分の研究報告を行うのは難しいようですが(現在この国では、「Ph.D学位の取得」が事実上、「一人前の研究者」としての認知となってきています)、「指導教授」格との共同研究の共同報告というのは珍しくありません。もっとも会場からの厳しい質問に対しては、もっぱら指導教授の方が回答役になってしまう、という観はありますが。
単独報告を行えるレベルでも、まだ聞き慣れない名前、若い顔が目立ち、また会場内に若い姿が多々あるのは、頼もしい限りです。この分野で、新しい世代の研究者が続々育っているのです。
この点、残念ながら「日本中小企業学会」の実態はお寒いばかりです。私のような、いわゆる「戦後団塊世代」クラスがようやく中堅レベル、それから下というと、もう指折り数えられるほどの数で、二〇代なんていうのは「貴重品」としか見えません。こう言っては語弊もありますが、もう勤務の方では「現役引退」またはその間際という、「大家」の方々の姿が依然目立ちます。ですから、会場ではやたらに白髪と禿頭がならんでいて、突如「超高齢化社会」に紛れ込んでしまったような錯覚を覚えるのが(自分のことを棚に上げて)、昨今通常の風景なのです。これは、社会科学系の学会にはほぼ共通してみられる傾向のようで、若い世代を引きつけられる、華々しい存在の一部の団体を除くと、ひたすら高齢化、後継者不足の一途にあるようです。
その理由を問うのはこれまた容易ならざることですが、少なくとも、学会団体に限らず、各大学等を含めて、「若手育成」には実に多くの欠陥があったと言わねばなりません。それで「われわれは研究に専念するにはあまりに多くの教育負担を抱えている」なんて、恥ずかしくて、口が裂けても言えません。
もうちょっと有り体に、かつまたあくまで個人の独断と偏見として言えば、日本の大学に、「研究者育成」なんていう機能がそもそもあったのか、過去も現在もきわめて疑問です。「ほったらかし」と、「院生をいじめて喜ぶ」と、そればっかしと、私は率直に思います。一方では、「どうせほとんどの学生はやる気もないし、こんな難しい学問のことを語っても、まるっきり理解できないだろう」と、いい加減な「漫談」で日々の授業を過ごし、他方では院生らをつかまえて、「おまえらなんて不勉強なんだ」とか、「こんなことしかできないのが研究者をめざすなんておこがましい」とか、「どうしようもないバカ」とか罵声を浴びせ、あるいは仲間うちで笑いものにしているのが、昔も今もニッポンの「大学教師」の実態なら、さっさと「教育」の看板を下ろして、「趣味業」の屋号を出すべきでしょう。
その結果がいまのていたらくですから、「企業社会」や政治行政同様、「ニッポン的経営」の積年のつけのたまった末のいまの崩壊劇を挽回し、再び欧米に伍していくのは、この世界でもあと20年は無理のようにも思えます。
「アカデミズム」の普遍性とニッポンの現実
さて、ともかく英国の学会と学会では、アカデミズムの「形式」と「方法」がきわめて重視されていると記しました。この印象は今回の機会でいっそう深くなりました。もちろん、それはいわゆる「欧米の学問」のルールであり、したがってまた「グローバルスタンダード」化しつつもあります。
もちろん私は、「欧米化」=いいこと、それが世界の正しいルールとし、また、そのまねをすることが即立派なことだなどという、素朴な「欧米崇拝論者」のあとを追おうというつもりではありません。相も変わらぬ「アメション組」が、「アメリカの学界はこうだ」などと、形だけの知識を振り回し、あまつさえその「理論」を絶対のものと信仰し、この「普及につとめる」のが使命と信じて疑わないという、この30年来続いているニッポン「社会科学」の状況には、いい加減にせいよ、と言いたくなります。こういう「天動説」こそ、まさしく「学」の進歩の敵です。
でも、まずその「多数派」のルールと作法を知らないことには、土俵、じゃなかった、リングにも登れません。もちろん、あちらさんの「議論」や「理論」に何の知識もなくて、「独自の道」をひとり勝手に歩んでいるというのも、別に「進歩」じゃありません。「社会科学」である以上、その「社会」の現実こそが最優先されるべきであり、空理空論の形を競ったところで空しい、という批判も可能ですが、その「現実」をどのように理解し、再構成するのか、という「方法」と、それをどのように同じリングのうえで表現主張するのかという「形式」を抜きに、いくら「現実はこうなんだ!」と力説しても、誰も聞いてくれません。
「学問」というものは、議論・論争があって進歩を遂げられるのであり、あくまでそうした議論のための共通の言語系ないしは表現方法をともにしないことには、議論が成り立たず、したがって「進歩」のしようもないわけです。逆に言えば、「自分だけわかっている」というだけでは、社会が共有できる財産としての「学問」にはなり得ません。「趣味」と「学問」はそこが違います。
では、いったいなぜ、欧米ではすでにある程度「制度化」されたアカデミズムの形式と方法がそこまで力を持ち、アメリカ合州国に次いで多くの大学を擁するニッポンでは、何で気息奄々なのでしょうか。もちろん、それはニッポンの大学教師が不勉強で怠慢なのばかりだからだとか(主としてマスコミ関係から繰り返されるコトバ)、あるいはマスコミなどが学問への不信を振りまき、学問的にはゼロのような連中を厚遇するからだからとか(大学教師関係のホンネ)、勝手な批判はいろいろ可能でしょうが、それでは「学問的」議論にもなりません。
ここには明らかに、客観的制度的な条件の大きな落差があります。
その最大のものは、「アカデミズムへの社会的評価の定着と制度化」があるかどうかだと思います。分かりやすく例を示せば、少なくとも英国の「知識層」は、大学教員や研究者だけじゃなく、ジャーナリストだろうが、政治家だろうが、コンサルタントだろうが、エコノミストだろうが、社会活動家だろうが、あるいは作家や企業経営者さえもが、大部分「アカデミックな」関心と探求と、表現の形式と方法なり、その積み重ねなりを身近に活用し、あるいは少なくともそれを理解し、ある程度の「敬意」を払っているという事実です(ここでは、こんなことは自然科学・技術学系の話しではあまりに当たり前なので、あえて省略し、主には社会科学や人文科学の関連でのみ語っております)。小さなことですが、新聞の評論や投書でさえも、そうした形式にむしろ「こだわっている」ということさえ感じさせます。自分の議論はどういう方法にもとづいているのか、その根拠なり証拠なりになる「文献」や「資料」は、誰の、どんな著作に拠るのか、こういうことは最低限きちんと書く、そのくらいは「常識」だということです。ですから、狭い意味での「学界」と、共通の言語体系をもっていると言えるのです。
これは言うまでもなく、ニッポンの現実とはほぼ180度違います。その違いを生むきっかけとなっているのは、その「アカデミズムの体系」そのものを制度化し、これを教育伝授してきた、大学などの高等教育機関と、あるいはその影響下にある一般学校教育と、社会とが、「アカデミズムの社会的使用価値」を認めあう、という関係を維持しているというところに求められましょう。もう少し分かりやすく言えば、「大学などでの成績」や「学位」が、そのまま社会での地位を得ていく物差しとして、それがすべてではないにせよ、依然相当に物言っているということです。そして、今度の英国滞在で痛感させられることは、少なくとも今のところ、この正の相関関係はむしろ強まってきているという事実です。全般的な教育熱の高まり、大学への進学率上昇と大学の増加、さらに社会人学生の増加は、「より高い教育」「学位」への期待を加速する方向に働いています。
もちろん、そうした状況が理想などとし、紋切り型に日本の現実を卑下しようと、私は試みているわけではありません。このような形で「アカデミズムの支配」が制度化され、続いてきたことが、西欧社会にさまざまなひずみと動脈硬化をもたらしてきたことも事実でしょう。「アカデミズム」はヘタをすれば、現実離れした形式主義、自己保身的な保守主義を生み、多弁にして無内容な人間ばかりを増やし、また「知識層」と「一般勤労者層」との根深い対立を生むことも、こうした社会を注意深く見てくれば、よくわかります。また、小学校時代から、「一人前の口をきく」、「なんでも『自己主張』が先である」、という「個性」を育ててきた教育と社会通念は、実際には甚だ中身のない、「言い訳ばかり達者」な人間を生み出している面を否定できません。
でも、あれほどの高い「進学熱」と、社会からほとんどまったく評価されない、「アカデミズムの教育」の成果とが、四〇年来共存してきているニッポンというのが、世界の中でも異常な存在なのは、誰も否定できないはずです。それはお隣の韓国を見てもすぐにわかりましょう。
その結果、日本では「読み書きそろばん」といった一般的な知識・スキルの教育の普及状況では、世界屈指と言える水準を維持してくることができましたが、「アカデミズムの形式と方法」はまったく社会の孤児となっています。それに依然準じて行われてきた「大学教育」の内容と評価に、一般企業はじめ社会は、ある程度の羨望とまたある程度の軽侮を示しても、自分たちの側のマジな意味での「評価」につなげようという気はまずありません。そして、現状にあわせるために、「アカデミックなはずの教育」のレベルが低下せざるを得なくなるから(そうでないと、みんな「卒業」できなくなるから)、悪循環的にますます信頼を失うという事態になるのです。大学の「卒業証書」が「学士号」であるということなど、いまやほとんどだれも気にもとめていません。「大学入試合格」の能力証明の有効期間が四年間あって、四年間分授業料を納めて、そしてともかく卒業めざし、「人並みに」かたちだけは整える要領と適応力を持っているという「証明書」というのが適切でしょう。
このため、たとえば、きちんとした「研究」や、その成果の「公表」という能力は全くない人たちが、社会の「知識?層」を構成してくることになりました。自称「ジャーナリスト」や「評論家」(これまた、世界にもまれな「職業分類」ですが)といった方々の少なからぬ部分は、方法も形式もへったくれもなし、ともかく「受けりゃあいいんだろ」というシニシズムに自信を深めて、はっきり言えば、世界の「アカデミズム」のコミュニティでは「横紙破り」と言うより、「盗作」に近いものを堂々と並べて、得々としています。「アカデミズム」の最低の仁義では、ともかく出所典拠を明らかにすること、さもないと、「犯罪」になるだけじゃなく、自分の主張の客観的根拠も示せない、ということになっておりますが、それさえろくにご存じない方々が、「法に触れなけりゃいいんだろ」といったまねを平然とやるわけです。ましてや、従来の研究や主張の「リビュー」やら、検証の根拠や方法の明示やら、そんな七面倒くさいことはきれいさっぱりなし、ということにするのです。
ですから、こうした方々が、得意の話術で「講演」をぶって回り、聴衆を魅了するのも、TVでお笑い的うけをとるのも、それはご自由ですし、また明らかに一つの優れた能力ですが、残念ながら「アカデミズム」との対話が成り立ちません。そして不幸にして、この悪循環的分断のスパイラルからは、どちらの側が優勢となるかという勝負はとっくについてしまっているのです。
英国のように、アカデミズムの世界の与える評価が、社会での地位に相当影響を及ぼすとなりますと、その声望が維持されるというだけじゃなく、共通の言語系をもっている同士が、それぞれの領域を超えて、「知識層」という階層を形成することになり、その中での利害がいつまでも維持再生産されることになります。ですからまた、そこに新たに加わる層が、アカデミズムの枠組みでの「評価」を手にしていくことに何の障害もなく、「同じ仲間同士」で話の通じることが、その後の「職業」にそのまま役立つわけです。もちろん繰り返し言ってきたように、それが本当に「役立つ」のかどうか、単なる多弁にして実行力なしになりかねないのではないか、これが、厳しい国際競争を強いられてきた企業やそれに関連する仕事のうちで問われてきたことも事実でしょう。
ただ、これは既存のアカデミズムの維持再生産の場である、大学や学界にとっては、誠に好都合なことです。その権威が容易に揺るがない、というだけじゃなくて、積極的には、言葉を共有する同士が、大学などの枠を超え、社会に広く存在し、対話と共同の機会がさまざま実現できます。しかしまた別のシニカルな見方で言えば、「アカデミズムの知識の市場」が、再生産を可能にするほどの規模で存在しているということでもあるのです。
「会員」資格は要るか?
前者の意味を敷衍すれば、今度の英国中小企業学会で見てもわかるように、学会の「会員資格」などというのをあまり杓子定規に振り回す必要はなくなります。別に大学教員や研究機関の人間だけじゃなく、政府・行政機関、中小企業支援機関、金融機関、会計士、コンサルタント、ジャーナリスト、そしてもちろん企業家自身など、さまざまな仕事に現在就いている人たちが、この場に参加して、「共通の言葉」で話せる、発表をし、意見を述べ、討論ができるわけです。そして近年の進学率上昇もあって、こうしたところにも、MBAどころか、Ph.D学位を持っているような人も少なからずいるのです。もちろん、学位が参加の前提じゃありませんが、ここに参加する人たちは、「論文」とは、「学会報告」とは、という基本的な考え方、形式と研究方法についての認識を相当程度共有して来ているわけです。
こういった行き方の学会は、英国社会でも幾分異色なのかも知れませんが、ともかく、自由寛容にして、なおかつ「暗黙のご了解」(tacit consensus?)がある世界、と言っていいでしょう。なんせ、ISBAは毎年の大会参加者は全員、一年間自動的にISBA会員になったことになります、としているくらいです(会員集め策でもありましょう)。つまり、毎年大会に参加していれば、それだけで「終身会員」になってしまうわけです。
この点、日本の学会では、そうしたリベラルな姿勢はなかなかとりにくいのです。たとえば、日本中小企業学会の場合、その「会員資格」の範囲を原則としてどの辺までにするか、というのが、20年近く前の発足時の重要な議論の焦点であったように聞いています。特に、他の社会科学系学会などと異なり、この分野に直接にかかわる方々でさえも、政府行政機関、地方自治体、各中小企業団体等の職員、さらに中小企業診断士、税理士の方々など、英国以上に、全国に万余といるわけです。もちろん、六〇〇万中小企業の企業家の方々のうちにも、「学会活動」に関心を持たれるひとが決して少なくないでしょう。そういった方々がどんどん学会に参加してくれ、大いに学問的な議論と研究を盛り上げてくれれば、こんなにいいことはないのでしょうが、そしてそれで学会もお金持ちになれるのでしょうが、これはさまざまな危険を有するというのが、学会設立時の論点であったわけです。
つまり、まさしく「アカデミックな研究と議論」にまるでなじまない、それでもご本人は立派な「研究」をしているつもりの方々が多数入ってきて、およそ「学会」の体をなさなくなってしまう恐れです。特に、こう言ってはなんですが、職業によっては、「○○学会会員」とか「役員」とかの肩書きを「売り物」にしたい向きもないとは言えないでしょう。
そういった姿勢を、「権威主義」とか、「古くさい象牙の塔へのこだわり」とか非難し、あるいは、しょせんは「アカデミズム」の社会的権威が限りなくゼロに近いから、自分たちの方から「境界線」をひいて、自己防衛・自己主張を図っているんだとか、批判することも可能です。でも、たとえば医学系の学会のように、ともかく大学医学部を出て、医師資格を持っていれば、医学研究専門家とともに、同じ学会に「参加できる」というのと、同じように見てもらうわけにはいかないでしょう。こういった世界では、いわゆる理工系の多くの分野とともに、「アカデミズム」の言語系、形式と方法が相当程度、共通の理解として普及しているわけで、そうでないと、ものがものだけに、とんでもないことがおこりえます。極端な表現をすれば、医学の学会に、「血液型占いから見た新たな性格治療方法」なんていうのをひっさげて「報告」をしようとか、機械技術の学会に、「永久運動機関の大発見!」を提出しようとか、そういう人はいない(たまにはいるのかも知れませんが)、ということです。またいたとしても、そうした「研究」の方法論自体という入り口で、一発でやられてしまいます。この「方法」は、誰もがともに認識し、共有できているわけです。
その点、幸か不幸か、社会科学や人文科学系では、たとえ欧米社会でさえも、「なんでもあり」になる可能性を持っています。別に人間の生死にかかわるわけじゃなく、飛行機がそれで空中分解するわけでもなく、「言いたいやつはなんでも言わせておけ」としておいても、ほぼ人畜無害なわけです(たまにはそれを本気で振り回して、ソ連を崩壊させ、いままたロシア連邦を崩壊させたりもするが)。これはある意味では、きわめてリベラルで、それだけに多様性と発展の可能性を持っていると言うこともできますが、下手をすれば、限りないレベルの低下を招く可能性も大です。ですから、ニッポンの多くのジャーナリストのように、ともかく「アカデミズムなんてナンセンス」と「全否定」をしてしまうのを別とすれば、アカデミズムの側が、自己確立と、その形式と方法づくりに努めざるをえないものではあります。
こうした形での、枠組み・形式や、「資格」認定や、「境界線」づくりは、絶対的に肯定はできなくても、また絶えず見直しを迫られざるをえなくても、やはりある程度必要なものでしょう。「批判的挑戦」は大いに歓迎するとしても(それこそが「学問」のラジカルさです)、いわゆる「箸にも棒にもかからない」、全然共通の言葉で議論ができない、そういったものを「学会」が歓迎するわけにはいかないものです。
たとえば、「激動の時代の中小企業経営者はこれをやれ!」といったたぐいのもの、これを企業関係者の集まりで一席ぶったり、「指導助言」にあたったりするのは別に構わないし、私だってそれに近いようなことを無責任に言ってきた記憶もありますが、それをそのまんま、「学会報告」にするというのでは困りましょう。「これ」とはなにか、なぜそうなるのか、なにがその根拠なのか、他の「道」はないのか、こうやったら、またああいう問題は生じないのか、そういった研究と主張の方法を示してくれないことには、議論も批判もしようがないわけです。全国の企業経営者ウン千人にアンケートを出して、このような設問をして、このような分析結果を得た、また、「○○理論」の考え方はこの場合応用可能だ、この理論への批判はこれこれ、その応用結果はこれこれとあるが、自分はこのようにこれを位置づける、といった話になって、ようやく「議論」にのってくるわけです。
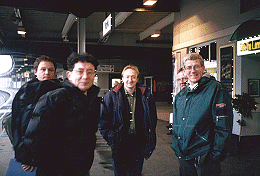 |
アカデミックな市場はどれだけあるか
さて、英国の学会は、そんな風にして、自分で「境界線」を引かなくても、「アカデミズムの形式と方法」へのコンセンサスを前提に、門戸を開きながら、それなりの「権威」を維持してきています。それは、これに対する共通の認識と評価を、広く定着させているからです。それとともに、実はこのアカデミズムの再生産に好都合な、大きな「市場」を維持しているからだとも言えるのです。
うえに、「学術論文」と書きました。これも日本では容易ならざる問題です。全国の大学や研究機関は、その重要な責務の一つとして、「学術雑誌」を出すようなかば義務づけられていますし、各学会や諸団体もさまざま、学術雑誌やそれに近いものを出しています。しかし、こと社会科学系などに関する限り、商業的にペイしているものはごくまれでしょう。「良心的に」出された商業的学術雑誌は、経済学関係など大半つぶれてしまいました。いまある学術雑誌は、大学やら、いろいろスポンサーあってこそようやく続いているのです。
学術雑誌のみならず、学術的な書籍となりますと、これはもう奇跡に近くなければ、刊行は難しい状況です。いま出せるのは、文部省科研費や各大学などの出版助成金など、「補助金つき」か、さもないと、大学の講義「教科書」用として、相当数の購入が見込める場合のみと言って差し支えないでしょう。そうでもなければ、どこの出版社が、初めから赤字覚悟の出版など引き受けてくれるでしょうか。
この状況は昔も今も大差ないのだ、という説もありますが、少なくとも間違いないのは、こんなにたくさん大学があって、こんなにたくさんの学生がそこで学んでいて、こんなに多くの卒業生が社会に出ているというのに、それらは「市場」としてはほとんどゼロに近いという事実です。「教科書指定」というような「経済外的強制」がない限り、学生はまず「学術書」や「学術雑誌」など買いません。
それどころか、ゼミなどでの「テキスト」とした本を買わない、「買わずに済まそう」と試みている、こんな実態を私も目撃して、つくづくいやになってきた経験があります。「最小の努力で最大の効用」、まさに「ホモ・エコノミックス」の見本はニッポンの学生にあり、というわけです。まあ読んでもよくわかんなくても、積ん読に陥っても、「ボクらはこんな学問をやっているんだぞ」とカッコつけるだけでも、テキストくらい持っている、持ち歩く、いくらなんだってそれが「学生の見栄」というもんじゃないか、という私の「古典的大学観」は見事に裏切られました。
ましてや、卒業してのちまで、「先生の本」を買わなくちゃならないような義理なんかさらさらない、これが現実です。
ですから、出版社も生存をかけては厳しいもので、たとえ「教科書採用」といった条件に恵まれていてさえも、ともかく「できるだけ堅くなく」、「ひとめで読みやすく」、「注なんかいっぱいついているのはダメ」、というのが、出版社の通例望むところです。書店の店頭で、気軽に手にとってもらえること、これが「製品戦略」としては大事で、それはまた書籍の「価格政策」にも顕著に反映してきます。いま、2000円を超えるとなかなか買ってもらえない、また、4000円台以上の値段が付いているとなるとほぼ絶望的、これが出版業界の常識です。値段を下げるためには、これまた短く、簡単で、よけいな図表などはできるだけなし、そういったコストダウン策が前提で、結局「学術的」なものはきわめて出版困難とならざるをえません。
もちろん、すべての出版物が「学術的」である必要などありませんし、誰もが気軽に読んでくれるものを書く、それも優れた能力であり、また「研究者」の別の責務でもありましょう。それは世界中どこでも同じことです。「ベストセラー」を出せる学者というのは、やはりどう見たって尊敬に値します(「帝国大学」の肩書きなどのせいでなければ)。私の経験から言ったって、この「業界」の水になじみきって、やたら小難しくものを言うのは平気になっても、「誰もにそれをわかってもらう」ようにするというのはどんなに難しいことか、大変な努力がいると思えます。
ですからいまのニッポンでも、「適度に堅く」、適度に読みやすいような経済・経営雑誌などはまだまだ続いています。それは結構なことですが、ただしそういったものは決して「学術雑誌」ではありません。まして、けばけばしい「ハウツーもの」「時事解説もの」「大予想もの」といったものの多くは、「こうすれば儲かる、うまくいく」といった大演説同様、断じて「学術出版物」ではなく、アカデミックな方法にはなじまないのです。
そうした実態が、日本と欧米とでそれほど違うわけではありませんが、ただ、欧米、とりわけ英国や米国のアカデミズムには決定的な「市場的」利点があります。「英語圏」というのは、先進諸国中で多くの人口を擁しているだけではなく、いまや実質的な「国際共通語」になってしまっており、英語で出される学術雑誌や学術書は初めから、世界中で相当の数が売れるという期待が持てるのです。たとえば、同じ分野にかかわる、世界中にある大学図書館の1/2が買うとしたところで、それだけで数千の単位になることは明らかでしょう。そして、関係する研究者などが個人で買う分もこれに加わるわけです。残念ながら、日本語で出るものなど、国外では、売れてもせいぜい一〇の単位にとどまりましょう。
この「英語世界支配の強み」だけではなくて、学術書や学術雑誌を購読する人種が決して少なくない、これも否定できない事実です。こういったものは確かに、それを「必要とする」人間以外手に取りがたい面はありますが、またそれだけでなく、その「形式」や議論の「流れ」を知らない、親しみがないものには非常に取っつきにくい、抵抗感の大きいものでもありましょう。ですから、大学などの場での、アカデミズムの方法と形式に対する訓練を経て、その言語系を共有する同士が、大学などの枠を超え、社会に広く存在していれば、少なくともその人たちの関心や仕事のうえの必要に訴えられる範囲の学術的刊行物出版物には、まだかなりの市場が見込まれるわけです。
まして、現在その「訓練中」の学生諸君らにとっては、本来こういうものを読まずしては、単位修得などおぼつきません。単位をとるというのは、単に惰性的に講義を聴き、学年末のペーパーテストを適当に埋めればいいというのではなく、普段に、その分野の基本的リビューにもとづく「必読文献」を読み、それについてのレポートを書き、セミナーの場でのディスカッションに参加し、そして最終的に自分なりの論文をまとめることが要求されます。そのための基本的な能力育成や形式理解の「訓練」を不可欠の要素として重視しているのが、「大学教育」なのです。ですから、ここだけで相当に本が売れそうですが、もっとも英国などの学生は貧しいので、自分でなかなか買えません。その代わりに、「指定必読文献」となるようなものは、大学図書館に相当部数常にそろえて置いて、学生諸君の必要をほぼ満たせるようにしています。ですから、ここでの売れ行きもかなりの数でしょう(ちなみに、それでも決して十分ではないらしくて、4月頃、キングストン大学の学生組合の新聞に投書があって、「建物にペンキを塗ったりするカネがあるのなら、必読の文献をもっと図書館に入れてくれ」とありました)。
ともかく、一般的に言って、日本の市場で「学術論文」や「研究書」を出すというのは、残念ながら遙かに困難とせざるをえません。ですからそれがわかっている、気の利いた人、能力ある人はとっくの昔にニッポンをあきらめ、自分の論文は国際学術雑誌にしか出さない、そうでなければだいたい注目されない、としています。そのかわり、「国際的」ほどではなくても、欧米での学術雑誌は「レフェリー制」が通常入っていて、アカデミックな内容と形式、そして今日掲載に値する水準と新しさがないと、載せてもらえません。研究書にしても、たとえばPh.D論文を本にするということが奨励されていて、出版補助金をもらえるしくみがいろいろありますが、そのかわりにこっちでもレフェリーの審査が要求されます。まあ、審査を経るくらいですから、よけいに「権威」があるわけです。
「市場」が大きければ、そこに参入を希望するものが多数あり、競争が生じ、市場の「価格」指標としての水準が高くなる、その逆であれば、逆の結果となる(ちょっと違うか)、こういうことです。
見過ごせないのは、こうしたニッポンの現実の結果、残念ながら「学術雑誌」の権威も水準も概して低下の一途をたどり、また、アカデミックな形式の軽視は当たり前のように蔓延しているという事実です。ここまで書くと、私が四方八方から恨みを買う、嫌われるという恐れ大なのですが、なんせ大学などの「学術雑誌」に書いたところでほとんど権威がない、誰も読んでくれない、もちろん全然報われない(文化的にも経済的にも)という状況が一般化し、多くのところで甚だ寂しい、発行を継続するだけで困難な状況に陥っています。カネはまだ大学が出してくれても、肝心の寄稿者がいないのです。一方、先にも記したように、アカデミズムの物差しから見れば、およそ噴飯もの、盗作切り張りや、軽すぎて吹けば飛びそうなものばかりが「出版物」となり、ともかく「勝てば官軍」なんだろと、そういった代物でも並べている方が得意満面で肩で風を切って歩いています。
私は別に「偏見」があるわけでも、また「自分たちの縄張り」を守ろうとのケチくさい根性で言っているわけでもありませんが、ここ10年来の「新設大学ラッシュ」と、「大学生き残り作戦」の結果、かなりの数の「ジャーナリスト」「評論家」の方々が「大学教授」の肩書きに転職を遂げました(その他の研究機関関係から転じた方々もまた多いのですが、そちらの方々の多くは、むしろへたな大学教員以上に、「アカデミズムのグローバルスタンダード」になじみ、また外国の大学などでそういった訓練を経てきているのですが)。そういう方々がそれにふさわしい「アカデミックな方法と業績」を持って、崩壊寸前の「象牙の塔」に新風を吹き込むというのならそれも結構なのですが、へたをすると、「本を書いている」「名が売れている」ということで、TVタレント的に「呼ばれ」、本人もそれでいっぱし「学者」になったつもりでいる、という恐れ大ではないか、とも思っております(私は、「ジャーナリスティック」な取材や表現方法が無意味などと決して思っているのではありません。それは生半可な「学問」よりよほどだいじです。でも、それと「学問」とは重なり合うところを持ちながらも、相当にそれぞれ違う、むしろ違うからこそお互いに存在の意義がある、といっているのです)。「うける」本、メジャーな名前ということと、「学問」とは同じではありません。
むしろ恐いのは、そういった方々が大学という場をえて、新たな「学問」にチャレンジし、大いに成果をあげる可能性より、自分たちの「思いこみ」であり、世界の「アカデミズムの世界」ではまったく通用しない、自己流のやり方、大言壮語、調子はよくても、全然積み上げも証明も論理もないようなものをふりまわし、へたをすれば「盗作まがい」も知らぬ顔で、そしてそんな「オレ流」を多くの学生諸君に伝染させていく可能性の方が大きいのです。これでは、ニッポンの大学はいよいよ「ジ・エンド」です。
ニッポンの大学というのはそういう存在なんだ、と割り切ることも可能ですし、そうでないとこの社会では生き残れない、資金的財政的に破綻する恐れもありますが、ただし、世界の中での「ニッポン異質論」をさらに広めることも必定です。学問の作法を知らない「教師」と、「学問」なんか生きていくうえでなんの役にも立たないと信じている「学生」と、ともかく「大学に合格できた」ということのみを認めよう、大学の「学問」の価値もその与える「評価」も無視しようという「社会」と、この3つがそろって、ニッポンの大学を支え、そしてそれを「世界の学界」の孤児としていくわけです。
続く
以下、
「アンケートの数字というのは正しいか?インタビューは真実を語っているのか?」−厳しく問われる実証の方法
* このISBAの全国中小企業政策・研究学会の第22回大会は、1999年11月17日〜19日、リーズメトロポリタン大学ビジネススクールの主催で、リーズ市で開催されます。今度のテーマは、99年欧州通貨統合を横目に見て、「中小企業 欧州への戦略、成長と発展」(Small Firms: European Strategies, Growth and Development)です。
詳しくは、こちらへ。
→ 第十六部へ