


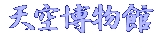
 |
 |
 |
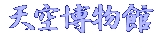
|

|
花粉光環の発見
ヨーロッパでの発見最も遡れたところでは、 M.G.J. Minnaert の著書、“De natuurkunde van't vrije velt”の第一巻“Licht en kleur in het landschap”(初版1937年) の第5版(1968)をベースにした(?) 英訳版“Light and Color in the Outdoors”の 1993年の版には 「雲以外の粒子で、青空の中に見える光環」の話が出ています (184節の最後の段落)。 初版には該当する部分はなく、どの版からこの話が入ったのかは調べられていませんが、 「花粉」という原因は特定されていないけれども、そういう光環が見えた、 という例があったのかと推察されます。 1998年の“Sky & Telescope”誌 7月号の Jari Piikki 氏の記事“A New Kind of Corona” には、「1990年代前半にフィンランドのアマチュア天文家が、 青空の中に見える風変わりな光環に気づき、やがて花粉の飛散量との関連に気がついた」 と書かれており、1994年に撮られた写真などが載っています。 おそらくこれが最初の花粉光環の発見であり、この記事が、最古の「花粉が原因とはっきりしている 光環に関する文献」でしょうか (これ以前にきっとフィンランド語の記事がありそうな気がします…)。 ちなみに光環を見せる花粉を飛ばす木としては Birch (樺), Pine (松), Juniper (ヨウシュネズ、セイヨウネズ), Alder (ハンノキ), Spruce (トウヒ) などが挙げられています。 いつ書かれた文書かは判りませんが、 こちらの同じく Jari Piikki 氏のフィンランド語のページ を (Google 翻訳で英語にして^^;) 読むと、「1989年に最初に発見された」となっていて、 1989年と1991年のスケッチが載っています。 最初の「発見」が 1989年で、花粉光環であることが判ったのが 1990年代前半、ということでしょうね。 花粉が原因であることが判った後、それ以前の記録も見つかっているようです。 日本での発見さて、日本では、上述の Piikki 氏の記事で花粉による光環を知ったと思しき 山形県衛生研究所疫学情報室の高橋裕一氏、 農水省農業環境技術研究所大気生態研究室の川島茂人氏らが、 1999年に山形市でスギや松、コナラの花粉による光環を観測し、 日本花粉学会会誌の短報として報告の論文を載せています (日本花粉学会のページ から PDF がダウンロードできます)。 これが、日本で観測された&スギ花粉で観測された&日本語の、 花粉光環に関する最古の文献だと思われます。
そして翌年のシーズン、スギ花粉の飛散量の予報を見つつ、狙って光環が見られることを確認し、 ほぼスギ花粉による光環で間違いないだろう、となりました (それでも長らく、記録のページでは慎重に「スギ花粉が原因と思しき光環」という感じで書いてましたが…^^;)。 その後、高橋氏らの花粉学会会誌の論文もタイトルだけみつけました (中身を読めたのは2013年)。
そうこうしているうちに他のウェブサイトにも花粉光環の文字や写真が載るようになり、 SNS なども通じてだんだん存在が知れ渡ってきて、今に至ります。 References
関連項目
|
 |
Contact:
aya@ |
Copyright 1998-2025, AYATSUKA Yuji |