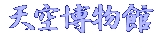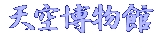光環 corona
“こうかん”と読みます。“光冠”とも書きます。
太陽や月のすぐ周りを取り囲むように現れる光の輪で、
暈と呼ばれることもありますが、内暈
などの暈 (ハロ)とは違います。
英語では“corona”(コロナ) ですが、皆既日蝕のときに見られる
太陽の表面近くの corona とは名前は同じでも全く別のものです。
雲の中の水滴や氷の粒により光が回折することにより見られます。
太陽や月に近い部分は青みがかった白、
そして外側が赤くなっています。
場合によってはその外側にさらに青っぽい領域、
赤っぽい領域が繰り返すこともあります。
大きさは通常、だいたい1°〜5°のようです。
水滴などの大きさによって回折の度合が変わるので、大きさ、色のつき方は、
時と場合によって変化します。
見るたびに違った光環が見られるわけですね。
水滴の大きさが揃っているほど、きれいに色が分離します。
水滴の大きさが小さいほど、輪は大きくなります。
大きさの違う水滴が混ざっていると、縁がきれいな円形にならないこともあります。
色づいた輪の内側の白っぽい部分を特にオーレオール (aureole)
と呼ぶこともあります
(この部分だけを指して暈と呼ぶこともあるようです。
また、この部分だけを指して光環と呼び、
その外の色付いた部分は光輪と呼んでいる文献もあります
(その場合、太陽の反対側に見える光輪
をどう区別して呼ぶのかは知りません))。
水滴の大きさがばらばらなときには、
この白っぽい部分が広く、そのまわりに赤褐色の縁どりがついたような、
色がはっきりと分離しない光環ができます。
これのことを指してオーレオールと呼ぶ場合もあるようです。
大規模な火山噴火があったときなどは、噴煙に含まれる微粒子が空を覆い、
それによって光環が見られることもあります。
これはビショップの輪と呼ばれます。
さらには、
スギ花粉などの花粉が大量に飛んでいるときは、
それが原因で光環が見られることがあります (左の写真)。
これを花粉光環 (pollen corona) と呼びます
(→ 花粉光環の発見)。
スギ花粉は一部がややつぶれた球形で太陽が高いと光環はほぼ円ですが
(左の写真)、
太陽が低いとその形状を反映して縦長の光環になります。
雲で見られる光環と違って水滴による乱反射で邪魔されないため、
青空の中に二重・三重のきれいな色のを見ることができます。
ヨーロッパではマツの花粉が大量に飛ぶようで、
マツの花粉は独特の形をしており、詳しい説明は省略しますが、
光環の形も独特なものになります。
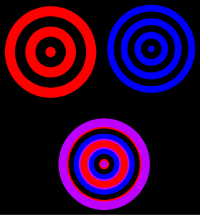
|
図1: それぞれの色の輪(上)と
それを重ねたもの(下) |
高校の物理で習ったのを覚えている方もいらっしゃるかと思いますが、
回折というのは、小さな穴を空けた板に光を当てると、
穴を通った光が壁に幾重もの輪を描くような現象です。
例によって光の波長により輪の幅が変わります。
青い光の輪の幅は、赤い光の輪の幅の 2/3 ほどになります。
これらの各波長の輪を重ね合わせると、色づいた輪や暗い部分が出来上がります。
大雑把に模式図(図1)を描いてみました。
かなり簡略化して描いてあります。
本当は輪は滑らかに明るくなったり暗くなったりします。
外側に行くほどぐっと暗くなるし…。通常は二重くらいが限界でしょう。
太陽の周りの光環は眩しくて見辛いことも多いのですが、
水溜りに写す、サングラスを通して見る、
などの手段でいくらか見やすくなります。
とはいえ、目をやられないように注意して見ましょう。
関連項目
|