


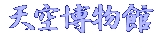
 |
 |
 |
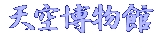
|

|
彩雲 iridescent cloud, cloud iridescence
さて、この現象が見られる仕組みは、基本的には 光環と同じで、 雲の水滴による光の回折です。 太陽から来た光が比較的均一な大きさの水滴の集まりを通過すると、 光の波長と水滴の大きさに応じた縞模様を作ります。 一方、雲の縁近くでは、雲の水滴がどんどんと蒸発していっています。 そうすると、水滴の大きさは (雲の縁に近付くほど小さいサイズで) 揃う傾向になります。 この二つを合わせると、雲の縁からほぼ雲の形に沿って、色が着くことになります。 色が淡いのは、他の波長の光(の縞)も幾らか混ざってしまうからです。 見えやすい色は、赤、緑、青の順のようです。 彩雲は、高層の巻雲や巻層雲や巻積雲、高積雲などでよく見られます。 水滴の蒸発が盛んで、どんどんと雲の形が変わっていくような時や、 強風に雲が運ばれていく時には、 一瞬の間に色の変わっていく彩雲も見ることができます。 これは、もちろん、色が太陽に対する場所と水滴の大きさに依存しているからです。 彩雲は、高層の巻雲や巻層雲や巻積雲、高積雲などでよく見られます。 水滴の蒸発が盛んで、どんどんと雲の形が変わっていくような時や、 強風に雲が運ばれていく時には、 一瞬の間に色の変わっていく彩雲も見ることができます。 これは、もちろん、色が太陽に対する場所と水滴の大きさに依存しているからです。 太陽に非常に近い位置だと、光環と彩雲は区別が付けづらいことが、 というかあんまり厳密に区別は出来ないような場合もあります。 筆者の考えとしては、太陽を中心とする円形、もしくはその一部に近ければ光環、 雲の形に依存したような形であれば彩雲、と思っています。 広い範囲で雲の中に鮮やかな色が現れる、 環水平アークが、 彩雲と誤解・誤認識されることもあるようです。 しかし、環水平アークは各色がはっきりとしていて (特に、 青色が彩雲では環水平アークほどきれいに現れないことが多い)、 かつ横に長く現れるなどの違いがあるので、 判っていればだいたい見分けられる思うのですが、 見分けづらいことも多いようです。 そういうのも引っくるめて広義の彩雲と呼ぶことも考えられるでしょう。 関連項目
|
 |
Contact:
aya@ |
Copyright 1998-2025, AYATSUKA Yuji |