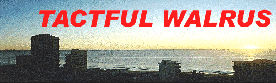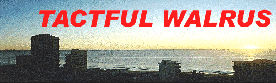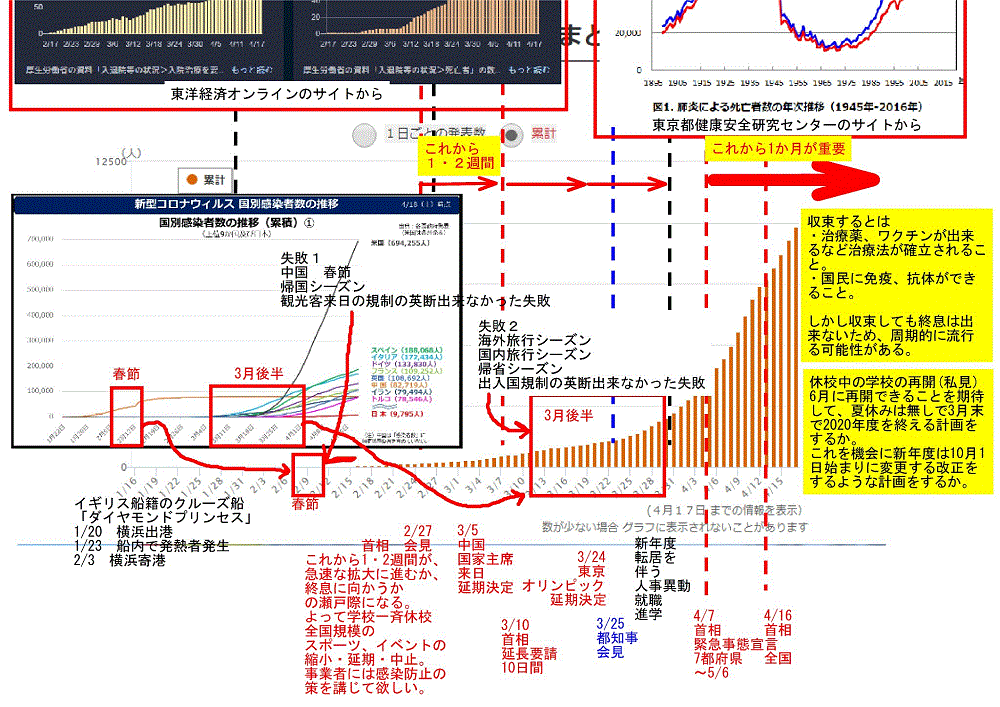-
平成時代の自己判断によるリモート作業
-
平日であろうが休日であろうが、自宅で、夜、もしくは深夜未明に、思いついた時に仕事をやろうと思えば出来るようになったのは会社からノートPCが貸与されるようになった20世紀末期の1998年頃。
さらに会社から貸与されたノートPC、PHS、モデムカードなどを持参し、特にお客様先に直行したり直帰し始めた21世紀初頭の2001年頃。
自宅で、時にリモート・アクセスなどしながら、翌日の、もしくは週明けの準備をしたことが何度か、何度もありました。
準備作業ですから独り割り込みも無く集中することが出来、とても有意義で重要な時間でした。
やりたいと思った時に、やらないといけないと思った時に、集中して作業が出来る。
在宅で、独りで出来る業務、独りで出来る作業を、自分だけの都合で出来る
、そのメリットを感じていました。
いずれも平成の時代のことの思い出であり、令和の時代の今はとても出来るお話ではありません。
令和の今、やろうものなら、
「平成かよ!」
-
新型コロナウィルスの時代、浸透したリモート環境を横目に出勤し続けたその時代
-
思い起こせば2020年2月27日の夕刻。
学校の職員室に鳴り響く電話の呼び出し音。
父兄からの問い合わせで現場の先生方は知ったらしい学校一斉休校命令。
関西のライヴハウスで複数名が感染したり、パチンコ店で複数名が感染したり、飲み会の参加者が感染し始めました。
そして感染者には、感染前、数日間にした行動報告を要求され、その報告に記載された行動は、遠まわしに、直接的に、次から次へと禁止になっていきました。
2020年4月9日の午後。
既に家族は引っ越し、住まいも引き払い仕事場で異動の最後の挨拶していた方々に、突然、法務大臣の鶴の一声で発令されたらしい異動停止命令。
それ以外にも命令・指示・策があったと思いますが、印象的で当時も今も「それはありえないでしょう」と思い出すのはこの2つのトップの思いつき位でしょうか。
当時、きっと過ぎ去った出来事は忘れてしまうからと書き残していた2020年3月頃のメモ。
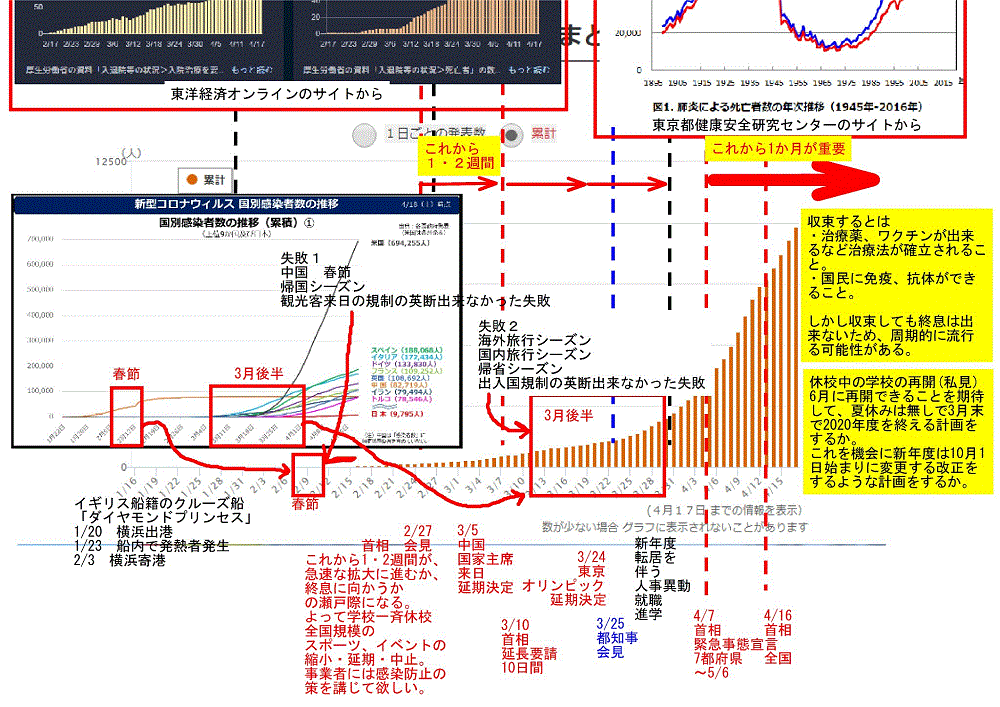
-
感染リスクを抑えることを目的に、世間ではリモートワーク環境と体制が整えられていきました。
その結果、満員電車に揺られ、人が行き交う中を歩き通勤するストレスを感じることなく、自宅で一人、作業が出来る恩恵が社会に浸透していきました。
そして私がお世話になっている会社でも「週2日間まで」の在宅勤務制度が適用されました。
しかし私は2023年11月から始める在宅勤務に向け、リモート勤務訓練を始めた2023年7月までその「週2日間まで」の在宅勤務制度を利用したことはありません。
それは私と一緒に働いてくれている若人たちにも在宅勤務することなく毎日、通勤してもらっていました。
従事する業務、リモート勤務をしなかったその理由
-
定年する3年ほど前から従事する業務は、ざっくり「プログラムの開発、開発したプログラムの運用維持、保守」です。
定年後、再雇用頂いた後も従事する業務に変更はありません。
業務の概要はほぼ以下となります。
1. 何かを意見交換しながら考え決める。
2. 何かを依頼するために説明する。
3. 粒度は様々ですが担当ごとに割り当てられたタスクを作業する。
4. タスクの作業中、発生した疑問・問題・課題、思いついた改善策を相談し解決する。
5. 細分化したタスクのアウトプットをレビューする。
6. メールの送受信をする。
7. 「1.」~「6.」をやり続けながら、数十台のPC上で稼働するプログラムの運用維持。異常終了時のリカバリ作業。
出勤しても在宅勤務でもその効率や生産性に変わらないのは「3.」、そして「6.」位でしょうか。
割り込みを考えると出勤するよりも在宅勤務の方が集中できるかもしれません。
「1.」「2.」「4.」「5.」は、チャット、Web会議などを活用することで可能かもしれません。
問題は「7.」です。
数十台のPC上で稼働するプログラムから送信されるメールを確認しながら、時にディスプレイの状態を観察しています。
またプログラムがアクセスするサービス内のデータの状態も観察しています。
それらのプログラムが異常終了したならば、速やかに検知し、リカバリ作業をする必要があります。
リモートでは、プログラムが稼働する数十台のPCのディスプレイの状態を確認出来ません。
そのためプログラムが途中で停止していることを確認することができません。
数十台のPC上で稼働するプログラムから送信されるメールは時に遅延することもあります。
そのような場合、プログラムが稼働する数十台のPCのディスプレイの状態を確認する必要があります。
しかしリモートでは、プログラムが稼働する数十台のPCのディスプレイの状態を確認出来ません。
もちろんプログラムが稼働するPCにアクセスし、フォルダ内のログなどのファイルを確認することは出来ます。
最終的に異常を検知したら、異常かもしれないと思ったら、そのPCにアクセスし適切な対処をする必要があります。
万が一、ネットワーク障害が発生した場合、その状況がわからなくなります。
ましてやPCに接続することも出来ません。
そうするとステークホルダーに迷惑をかけてしまいます。
それだけは避ける必要があります。
OSにパッチ(更新プログラムなど)が適用された場合の再起動は余裕がある時にするにしても、突然、OSが不安定になり、PCを再起動する場合、誰が対応出来るのか。
もちろん交代でリモート勤務をすることも考えました。
しかし当時も、各人、各々のタスクを担当していました。
各人が各人のタスクに集中するあまり「7.」をつい疎かにしてしまう事もありました。
そういう時に限って何かが発生したものです。
そのような状況にも関わらずリモート勤務を実施した時、今までと同等の運用を維持し続けることは出来るのか。
もし出勤予定者が発熱など突発的に休みとなった場合、業務を継続することが出来るのか。
以上から円滑な日常業務を過ごし続けるには全員が出勤するのが最善
であると2020年に結論付けた次第です。
-
フル・リモートの限界
-
「
2023年秋に移住することにしました。
移住したら通勤することが出来なくなるので、次回の再雇用契約の更新のお話は辞退するかと思います。
」
と、お世話になっている会社の上司に伝えた2022年の年末。
幸か不幸か2020年からのコロナの流行で世の中にリモート・ワークが認知され、その環境が整備されました。
さらに少子高齢化で労働人口は減るばかりの世の中。
その社会の流れ、社会情勢からか、この老人がお世話になっている会社にも2023年春に適用条件付きフルリモート制度の運用が開始されました。
そして2023年の初夏、この老いぼれに想定外のフルリモートの在宅勤務のお話をいただきました。
2023年11月から始める在宅勤務に向け、2023年7月から「週2日間まで」の在宅勤務制度を利用したリモート勤務訓練をしました。
そして2023年11月から在宅勤務が始まりました。
在宅勤務している環境
-
2023年11月に移住し入居して最初に在宅勤務 1つ目の環境の整備し、在宅勤務が始まりました。
ところがその環境で半年も過ごしていると職する時の我慢出来そうで我慢出来ない課題・問題が表面化してきました。
そこで、それらの課題・問題を解決するために在宅勤務 2つ目の環境を整備し、現在に至っております。
在宅勤務するに必要なこと
-
在宅勤務の可否は一にも二にも自制心、自律性に左右されるかと思います。
自制心、自律性はあることが前提となります。
正直、この1年間、己との闘い!
と感じた日が全く無かったと言えば嘘になります。
こういう時は本当に辛いです。
人の目というのは本当に重要、その存在は偉大です。
このような時はとにかく己と闘う
しかありませんでした。
もしくはフレックス制度のコアタイムという全員が勤務する必要がある時間帯が過ぎたならば勤務することを止めました。
しかしながらこの敵無き闘い
は例え出勤していても同じですが。
ここで話は変わりますが出勤、リモートに関係なく重要なことは小学生の国語、算数が出来ることだと思います。
20年ほど前、子供が開く小学校高学年の算数の教科書を、20年ぶりに読みました。
その時、思ったのは「小学校高学年の算数が出来るか出来ないかは、文章の読解力があるかないか、でした。
これも出勤、在宅勤務に関係無いと思いますが、必要なのは、
- 文章を読むことが出来る。文書を読むことが出来る。
- 文章を書くことが出来る。文書を書くことができる。
- スライド・ショーの読解力。
- スライド・ショーの表現力。
- そして加減剰余、四則演算が出来る。
かと思います。
もうこれは今更、ジタバタしてもどうしようもない、40年間以上のサラリーマン人生の延長でいくしかない日々です。
生産性について
-
生産性という尺度に関していえば業務の内容次第だと思います。
「3. 粒度は様々ですが担当ごとに割り当てられたタスクを作業する。」、そして「6. メールの送受信をする。」だけを考えれば、生産性に大差はないと思います。
それ以外はチャット、Web会議などを利用して行うのですが、やはり対面とは違います。
事前に作成した文書、スライドを表示しながら、ほぼ一方的に説明し、質疑応答するだけならば、対面でもリモートでも大差は無いように思います。
いえ、かなり違います。
リモートでは説明している時、相手が理解出来ているのか、補足や追加で説明した方が良いのか、受け入れているのか、納得しながら聴いているのか、見ているのか、などボディ・ランゲージがわかりません。
逆に説明を受けている時、疑問・不明点など生じた時に相手に対し何気に意思表示することも出来ません。
お互いの顔が見えない、小さい論理画面に相手のカメラの映像を表示する機能はあるものの、ネットワーク回線の太さなどの制約でカメラをオフにすることが殆どです。
それらの結果、Web会議で無音の瞬間、無音の間が多くなり、その積み上げた分だけ生産性は落ちます。
また対面の打ち合わせでは度々、話しながら、聞きながら、ホワイト・ボードに図や表、単語などを書いていき、検討しながら考えをまとめていくことも度々ありました。
これを共有したPCのディスプレイでやる使い勝手の悪さ。
というよりも現在、提供されている環境では出来ません。
打合せに参加する任意のPCの画面を共有するのですが、書き手に対し読み手がいる、どうしても一方通行となる情報発信となります。
共有する画面を切り替えるその時間も生産性が落ちる原因の一つです。
計画的な打ち合わせではなく、少し確認したり、相談したいことが生じ、作業する相手に割り込む際、出勤していれば相手の姿を見れば割り込みしても良いかわかります。
一目見て、良さそうならば割り込みますし、その状況によっては後にすることも出来ます。
打ち合わせする前は、打ち合わせした後も。
検討し資料を作る時は。
あれこれ考えている時は。
何度、「少しだけ良いですか」と話しかけて始めた会話をしたことか。
逆に「少しだけ良いかな」と話しかけられて始まった会話をしたことか。
仕事は、「少しだけ」で始まる会話の連続、積み重ねの結果かもしれないと振り返る今日この頃です。
ところがそれをリモートでしようすると、チャットで呼びかけ、相手の応答を待つ必要があります。
その応答が直ぐにあるのか、はたまた応答があるまでの時間を予測することが出来ません。
結局、その待たされる、相手の応答があるまでの時間、生産性が落ちます。
在宅勤務で出来ないこと
-
- オフィスにあるPC群の画面を同時に複数台の画面を観察することが出来ません。
- オフィスにあるPC群を再起動することが出来ません。
- バディ(buddy)、仲間、ご一緒いただいている若人たち、その時々の状況を、一目、横目で見て確認することが出来ません。
- 作業を次から次へと依頼する時、対面ならば、その作業をする姿を見れば、どのような状況か、円滑に進んでいそうか、まだまだ時間を必要としそうか、何となくわかります。
しかしリモートではそれを感じることが出来ません。
- オフィスで障害が発生したことをタイムリーにわかりません。
オフィスが混乱が発生してから、何が発生しているのかがタイムリーにわかりません。
その障害に対し、オフィスで何を行われようとしているのか、何をしているのか、タイムリーにわかりません。
その結果、障害に何をしなくてはいけないのかの検討が遅れ、かつ情報も少ない中での検討になります。
検討した作業を、オフィスにいるバディ(buddy)にお願いした後、作業の状況を背中で感じることが出来ません。
そのお願いをした作業をしている時、オフィス内にいる他の方が割り込みし、その作業を中断させたりしてもわかりません。
その割り込みを止めることも出来ません。
もしかしたら認識していない異なるお願いがされてもわかりません。
その割り込みの結果、他の作業をし始めてもわかりません。
- その障害がネットワークにある場合、在宅勤務側は何もできません。
電話でやり取りするしかありません。
しかし現実、オフィスにいる側は在宅勤務者と電話している余裕など無いと思います。
上記のことは、長年、活動しているプロジェクトだから成立していることです。
バディ(buddy)、仲間、それなりの時をご一緒いただいている方々で、スキルなどお互いを知っていることで成り立っています。
バディ(buddy)に出来る出来ないがわかる。
逆にバディ(buddy)から在宅勤務する老人の出来る出来ないがわかる。
だから、かろうじて成り立っていると認識しています。
在宅勤務で本当に出来ないこと
-
- 上司、同僚、年上、年下の方々の働き方を見ることが出来ません。
背中を見て覚える、ということが出来ません。
定年再雇用の高齢者となった今ではなく、新人、初級者、中堅の年代の頃を思い出すと、その時々の少し経験の長い方々、新人の頃ならば初級者、初級者の頃ならば中堅者、そして常に熟練者の方々、その方々の行動を観察、のぞき見、パクリなどすることが本当にためになりました。
しかし在宅勤務ではそのようなことは出来ません。
また逆に何度も手を差し伸べてくれ、助けてくれました。
そのようなことも期待できません。
多分、特定の方から平成かよ!
と言われてしまいそうですが。
- 困難な状況、問題・課題を突破しながら、進行させ、新しいことを成し遂げる、発見すること。
それがリモートで出来るか否かは正直、わかりません。
今、そのような高度なことはやっていませんから。
在宅勤務での今の課題
-
戦前昭和の格言「やってみせ 言って聞かせて させてみて 誉めてやらねば 人は動かじ」。
これをどのようにやったら良いか。
それがこの半年間の一番の課題です。
余談ですが2020年に
円滑な日常業務を過ごし続けるには全員が出勤するのが最善
と結論付けてから時が流れ、バディとの経験値も増えました。
そこで2020年からご一緒頂いている方々にも組織のルール「週二日まで」ですが可能な時は在宅勤務して頂いております。
back to 在宅勤務
back to 〜 ルーム・ツアー 〜 ユーティリティ(家事室)
back to