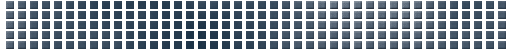
史話余録ホームページ
『切り抜き情報』
2003年6月15日号
【自分とたたかう人々】
発行者・マルジナリア研究所
 『切り抜き情報』言い伝えたいこと |
 『切り抜き情報』免疫力を強める |
 トップページへもどる
トップページへもどる◎ふと会話が途切れた。その瞬間を突くように、河辺さんが切り出した
◎医師に説明を求め、納得してから
◎今できることは、明日に残してはいけない
◎仕事をこなすだけの医師への怒り
◎母の方にはほとんど顔を向けず、パソコンを操作しながら話す
◎「ケアの本質」を著した哲学者メイヤロフの言葉。
◎あれでよかったのかとの痛苦な思い。涙があふれ、体中が熱くなったと
◎主治医にカルテのコピーを要求。主治医に「思い」は伝わらず
◎忙しさがかえって心地よいのではないかとの自己疑問
◎自分に余裕がないのにどうして人に優しくできるか
◎病院では患者さんに上からものを言いがち
◎乳がん体験者による病院訪問運動
◎技術よりも寄り添う心が欲しい
◎スズメに教えられる
| 【文献 1】 ふと会話が途切れた。その瞬間を突くように、河辺さんが切り出した [東京都小金井市にある聖ヨハネ会桜町病院のホスピス棟は、すでに夜のやみに包まれていた。一九九八年三月二十一日。一一六号室では、ホスピス科部長の山崎章郎(ふみお)さん(五二)が、結腸がんを患いベッドに横たわっていた大手造船会社のシステム・エンジニア、河辺龍一さん(当時四一)と雑談していた。妻の貴子さん(四三)は夫の背中をさすりながらやりとりを聞いていた。ふと会話が途切れた。その瞬間を突くように、河辺さんが切り出した。「先生、これまでのみなさんはここをどう渡っていったのですか」 一瞬の沈黙。河辺さんが続けた。「夜眠ると再び目を覚まさないのではないかと不安で。自分の命はあと一週間ぐらいではないでしょうか」 山崎さんは、「魂が叫んでいるようだ」と感じた。逃げてはいけない。死という未知の世界に進んでいかなければならない患者が、その「道行き」への不安やおそれを口にしたときは真っ正面から向き合わねばならない。]。 [河辺さんには、それまでホスピス医として九百人近い患者を見取ってきた体験の中から、四十代で亡くなった男性とのやりとりを紹介した。男性は死後の世界を信じていた。死ぬ前に山崎さんに「あの世からサインを送る」と約束した。サインとは、風のない日にろうそくの炎を揺らすというもので、実際に揺れたら「私が揺らしたと考えてほしい」と男性は話した。そんなエピソードを交え、山崎さんは一時間ほど「魂」についての話を河辺さんにした。そして、「自分も死んだらみなさんに再会できるのを楽しみにしているんですよ」と語りかけた。河辺さんは、「ぼくも魂は生き続けると思っています。あの世に行ったら、お酒の好きな先生のためにいい飲み屋を探しておきますからね」と笑った。河辺さんはそれから一週間後に逝った。ホスピスでの体験を山崎さんとの共著の形で「河辺家のホスピス絵日記」という本にまとめた貴子さんはこう振り返る。「あの時、山崎先生は夫と私の顔をずっと見つめながら話しをしてくれた。途中、何度か看護婦さんが先生を呼びに来ても、一度も振り返らず、時計も見なかった。もっと仕事がしたい、二人で世界中を旅行したいという夢はかなわなかったけれど、目の前の患者さんと話すのが何より好きだという山崎先生と最後に出会えたことは、本当にうれしかった。]。文・松本一弥。 山崎さんは、精神科医のキューブラー・ロスの「死ぬ瞬間」を読んだことなどがきっかけで、ターミナル・ケアの世界に入った。著書「病院で死ぬということ」を1990年に出版。91年から桜町医院でホスピス医に。 この記事は、読者(横浜市、田中弥生さん(52)からのメールが発端で朝日記者が取材したものである。 |
|
【文献 2】 医師に説明を求め、納得してから 2002年2月14日、山内隆久さん亡くなる。慢性骨髄性白血病で。/ 2002/02/ 20/『朝日新聞朝刊』/ 「患者になって……」山内隆久さんを悼む/社会心理学者の立場から医療事故について研究し、昨年10月から2カ月間、コラム「患者になって考えたこと」をくらし面に連載してくださった北九州市立大教授の山内隆久さんが、14日に亡くなりました。50歳でした。山内さんは慢性骨髄性白血病の治療のため、昨年8月に東京の国立がんセンター中央病院で白血球や赤血球をつくる「幹細胞」の移植を受けました。10月末には同病院を退院しましたが、ドナーの細胞がつくりだす血液に体が抵抗作用を起こすようになり、11月に再入院、昨年末にはご本人の希望で出身地の九州に戻り、九州大学附属病院で治療を続けていました。その前後から、免疫機能の低下に伴う感染症も併発し、闘病は厳しさを増していました。しかし、妻の桂子さんによると、山内さんは重症になってからも日々、病状と治療について医師に詳しい説明を聞き、一つひとつの治療を自ら選び、納得したうえで受けることにこだわりました。意識を失う直前まで採血結果の一覧表を取り寄せ、医師に説明を求めていたそうです。「医師には治療を依頼しても、人生を預けるわけではない。人生を決めるのは自分の権利だし、責任だ」最後まで、その言葉通りの闘病生活でした。「患者になって考えたこと」は山内さんが病床から発信したメッセージでした。 |
|
【文献 3】 今できることは、明日に残してはいけない 西川潤さん。咽喉癌を克服。「内発的発展」を主題とする著書。 2002/02/22/『朝日新聞朝刊』/ 〔「何としても生き続けなくては、と歯をくいしばった」。咽喉ガンを克服した経済学者の西川潤・早稲田大学教授(65)が、「人間のための経済学」(岩波書店)「仏教・開発・NGO」(新評論)など3冊を立て続けに出版し、大来賞と、フランス政府の教育文化勲章を受賞した。舌の付け根部分に違和感を覚えたのは99年夏。舌の半分を削除し、腕の筋肉を切り取って残った舌に移植した。退院後の著書の共通主題は「内発的発展」。人間と自然の相互依存の大切さに自発的に目覚めることを目指し、仏教の「かいほつ」に通じる。「大病によって、物事には、うまくいかない時があり、いつ何が起こるかわからない、ということを悟った。今できることは、明日に残してはいけない」〕 |
|
【文献 4】 仕事をこなすだけの医師への怒り 仕事をこなすだけの医師への怒り。匿名会社員、主婦、飯沢春美さん 2002/03/07/『朝日新聞朝刊』 大学病院に通院。左胸の痛み。狭心症の疑いといわれ。[医者の言うことに間違いはないと、まじめに薬を飲んでいたのですが、さすがに不安になって、)検査結果に基づいた診療方針の説明をお願いしたところ、担当の医師は「前回説明したでしょう」とけんもほろろ。理解できていないと伝えると、怖い顔をして検査報告書をちらつかせ、流れるような早口で説明を始めました。最後は「私はきちんとした検査結果に基づいて方針を立てています」。逆ギレ状態で、素人は口を出すなと言いたげでした。その後も、聞けば聞くほど疑問があふれてくる。ところが医者は、これ以上時間を浪費したくないといわんばかりでした。]埼玉県、会社員、37歳。 |
|
【文献 5】 母の方にはほとんど顔を向けず、パソコンを操作しながら話す 2002/03/07/『朝日新聞朝刊』 母が脳こうそくで入退院。大学病院で診療を受けている。[体が不自由で難聴の母のために付き添っていますが医師の態度にいつも疑問を抱いています。母の方にはほとんど顔を向けず、パソコンを操作しながら話すか、カルテに記入しながら話すかのどちらかです。とても義務的に、画面を見ながら早口で話すのを見ていると、仕事をこなすだけとして感じられません。年を取った母一人で医師の説明を聞いても、すぐに理解するのは無理だと思いました。母の話が通じているのだろうかと不安にもなります。患者の数をこなすのだから仕方ないのかもしれませんが、「3分診療」とはこのことかと納得した次第です。]東京都、主婦、飯沢春美さん、48歳。 * (マルジナリア)これは、「こなす」というのも確かにあるが、多くの医者が、医療の反対側にも、大切なもう一つの「医療」(心、気持ちなどもそうだ)があることを知らないか、気付かないか、知っていても触れたくないか、ということなのだ。多くの医者は、この「もう一つの医療」については、誰かがやるだろう、少なくとも自分はもっと高度なことを考え研究しているんだ、というのである。そうでない医者もいる。相手の自己実現を助けるのがケア |
|
【文献 6】 「ケアの本質」を著した哲学者メイヤロフの言葉。/「最も深い意味で、その人が成長すること、自己実現することを助けることである」と/医師種村健二朗さんの発言 2002/05/19/『朝日新聞朝刊』/ [私は県立がんセンターで緩和ケア担当をしています。(略)「ケアの本質」を著した哲学者メイヤロフは「一人の人格をケアするとは、最も深い意味で、その人が成長すること、自己実現することを助けることである」と述べています。(略)患者さんが自然の経過としての死について語り、苦しみ、苦しむことで成長し、苦しみから開放されてゆく過程を、敬意をもってかかわることが、緩和ケアなのです。(略)が、私の職場でも、こうした考えが完全には肯定されていないのが現状です。]医師 種村健二朗
宇都宮市 61歳 |
|
【文献 7】 あれでよかったのかとの痛苦な思い。涙があふれ、体中が熱くなったと 「患者はどう死を迎えていけばいいのか」/足立優子さんの体験 2002/05/19/『朝日新聞朝刊』/ [父は60歳で脳梗塞のため全身マヒになりました。その時、「命を救うことが使命」という医者の言葉と、「父の尊厳を大切にしてあげたい」という家族の思いのすれ違いを強く感じました。父の唯一の意志表示は「アー」という声と、力をこめた瞳でうなづくことだけでした。しかし約1年半後、先生から気管切開を勧められました。「患者さんも楽になる」という先生の説得で同意したのですが、術後すぐに後悔しました。父の声はただの息となり、何の音も発することはなく、瞳は光さえも失ったように見えました。それから3カ月後、父はこの世を去りました。その後、手にした本の中で、最後の人間的な表現方法を奪う気管切開はすべきでないという趣旨の医師の言葉を読み、涙があふれ、体中が熱くなりました。患者はどう死を迎えていけばいいのか、家族と共にお医者さまにも考えていただきたいと思います。]会社員 足立優子(川崎市 40歳) |
|
【文献 8】 主治医にカルテのコピーを要求。主治医に「思い」は伝わらず 「この制度を採り入れてまだ1年ほどで申請も少ないので、医師も驚いてしまったのです」と看護婦さん/笠井宏子さんの発言 2002/05/23/『朝日新聞朝刊』/ [4年前に公立病院で乳がん手術を受け、現在は通院中です。最近、受付のパンフレットに「診療情報の提供はお気軽に申し出てください」とあるのに気づき、思い切ってカルテのコピーをお願いしました。主治医は私にカルテを見せ、ていねいに説明してくれました。でも、コピーについては「説明だけでは納得できませんか」と難色を示されました。私の主治医は病院の都合で、この2年間に3人代わっています。抗がん剤、ホルモン剤の投与が自分にとって適切だったのか疑問をぶつけると、医師によって説明は違いました。自分の病気の情報は自分で知り、理解しておくことが、今後の治療法の選択のために必要だと考えたのです。ようやくコピーの承諾を得たのは1時間後。それでも私の思いは医師には伝わらず、残念でした。ただ、診療室にいた看護婦と、「医療相談室」でコピーを渡してくれた事務職の女性が、私の気持ちをくんでくれました。「この制度を採り入れてまだ1年ほどで申請も少ないので、医師も驚いてしまったのです」「自分の体のことを知るのは当然の権利。だれもが気軽に制度を利用できるよう、医師と患者の橋渡しをしていきたい」 そんな言葉にとても勇気づけられました。
大阪市 自営業 笠井宏子さん、48歳] |
|
【文献 9】 忙しさがかえって心地よいのではないかとの自己疑問 「いつの時代も未熟な医師を育ててきたのは患者さんたち」と医師渡辺佳夫さん/医師はなぜ忙しいのかと 2002/05/26/『朝日新聞朝刊』/ [死亡診断書を書くたびに、この患者さんはよくぞ最期まで私の方針に従って下さったと思う。そして、果たして自分は、その期待にどれほど応えてきたのだろうかと思う。いつの時代も未熟な医師を育ててきたのは患者さんたちであり、優秀な指導医や詳細な医学雑誌はその次であった。患者さんから離れて医師の成長はあり得ない。しかし最近、医師はコンピュータに向かう時間が増し、ベッドサイドにいる時間が減ったと思う。なぜ医師はいつも多忙なのか。忙しさがかえって心地よく、あえて自らを過密スケジュールに追い立てていることはないか、そうすることで反省と修正の場である病院の検討会に出なくてすむし、患者さんのために考えようとしない自分を正当化する理由にもなる。患者さんの立場からは言いにくいかもしれないが、セカンドオピニオン(主治医以外からの意見)に基づく真剣な問いかけなどで、「忙しい医師」に働きかけてほしい。医師
渡辺佳夫 津市 50歳] |
|
【文献 10】 自分に余裕がないのにどうして人に優しくできるか 「看護婦の仕事は忙しすぎます」「研修医を終えた後の医師の教育は不十分」と速水由紀さん 2002/05/26/『朝日新聞朝刊』/ [看護婦からも一言いわせて下さい。病院に7年勤めましたが、正直言って、辞めて良かったと思います。看護婦の仕事は忙しすぎます。人手不足は慢性的、交代勤務でヘトヘトです。休みの日にひたすら寝ていることも多く、若い女の子の生活ではありません。自分に余裕がないのに、どうして人に優しくできるでしょうか。一緒に働いた若い医師の高慢さも、許せませんでした。同じ治療を自分の家族にも施せるか、自問して下さい。ほかの医師に相談しても「専門分野が違うから意見できない」。研修医を終えた後の医師の教育は不十分だと思います。医療事故が相次ぎ、現在の医療に不安を抱いている人は多いでしょう。それは看護婦であっても同じです。人材の確保と、医師に必要な知識の習得と人格形成ができるシステムの確立を願います。
看護師 速水由紀 静岡県熱海市
29歳] |
|
【文献 11】 病院では患者さんに上からものを言いがち 喜志訪問看護ステーションの事例。所長の小埼洋子さんの発言。「病院では患者さんに上からものを言いがち」と 2002/08/22/『朝日新聞朝刊』/ [大阪府富田林市の喜志訪問看護ステーションで活動する看護師は、ほとんどが大病院での勤務実績を持つ。「病院での看護は総合的だけど、患者さんに上からものを言いがちです。訪問看護は、ある意味で他人の生活に入り込み、患者さんと深くかかわる。その分、得るものも大きいのです」。所長の小埼洋子さんはそう話す。] |
|
【文献 12】 乳がん体験者による病院訪問運動 20000609『朝日新聞朝刊』 ワット隆子さん。英国人の夫と一男一女 60歳。 [「乳がん患者の不安な気持ちは、体験者が一番よくわかる」と、ボランティアによる病院訪問を六年前に日本で始めた。米国で生まれたこの運動の創始者にちなむテレサ・ラッサー賞を、がん撲滅に取り組む国際的な団体「インターナショナル・ユニオン・アゲンスト・カンサー」から受けた。患者は、回復に向けてあらゆることに手をのばす。体験者はその一助に手をさしのべる。そんな意味をこめて「リーチ・トゥー・リカバリー」と呼ばれるこの運動は、五十カ国に広まっている。三十七歳の時に乳がんの手術を受けた。行動的で、くよくよしない。そんな強い性格だったはずが、「再発への心配。社会復帰できるかどうか。不安でいっぱいでした。翌年、新聞への投書をきっかけに、同じ病気を体験した仲間と「あけぼの会」をつくった。会員は今、三千五百人。早期発見のための啓発、様々な相談受け付け、会員同士の助け合いと活動の場は広がっている。病院への訪問は、それより一歩、現場に近づく。ただ、訪問ボランティアを受け入れている病院は、全国でわずか六カ所しかない。「素人になにができるとか、よけいな知恵をつけられては困るとか、なかなかお医者さんや看護婦さんの理解が得られなくて……」 ボランティアは、自分の症状との比較など、治療に関することはいっさい触れない。「口出ししてはいけないことを研修で学びます」。患者の経済的負担はない。ボランティアも七十人ほどとまだ少ない。富山県内の病院から依頼があったが、近くにボランティアがおらず、やむなく見送ったことも。「ボランティアを受け入れる側も送り出す側もまだまだ手探り。これからです。]。20030614記 |
|
【文献 13】 技術よりも寄り添う心が欲しい 2003/06/12『朝日新聞朝刊』 [母が他界した。脳血管性痴呆症を発病して12年、私は在宅で介護した。後半の5年間は訪問看護に来ていただいた。寝たきりになって一時はうんうん唸ってばかりだった母が、看護師さんと歌を口ずさんだり、短い言葉を話したりできるようになった。私は、母はもう痴呆老人ではなく、穏やかに死を待つ一人の尊い人と思い、「おばあちゃんは賢いねえ」と、何度も語りかけたものだった。4月、発熱を繰り返した後、呼吸困難になり入院した。亡くなるまでの病院での9日間、一番不満だったのは看護師の態度だった。声もかけずに黙ったまま点滴を替えていく。何か質問すると、「医師でないと答えられない」と言う。死んでいく人や看取る家族へのいたわり心一つ感じられない。技術よりも寄り添う心が欲しい医療現場であった。鳥取県 鈴木早苗さん 57歳] |
|
【文献 14】 スズメに教えられる 2003/06/14『朝日新聞朝刊』 [5月のある日、庭で子スズメを拾った。とっさに家に入れ、箱の中に新聞紙を敷き、パンを牛乳に浸して、ピンセットでやった。1晩越すと元気になり、1週間ほどすると3メートルくらい飛べるようになった。その「自立」の早さは驚くばかりだ。鳴き声も、ピーといっていたのが、いつの間にかチュンに変わった。が、人なれしすぎて、私から離れなくなった。首の周りを回る。カーディガンの中に潜る。用事をする時は、エプロンのポケットに入った。パソコンを打つ時は、肩に止まった。ピーを見ていると、「本当にスズメ?」と思ってしまう。いつかはスズメを手のひらから空へ羽ばたかせるのが私の娘の夢だった。それなのに、(そのスズメは)不慮の事故で死んでしまった。やはり、親鳥から離れた子スズメを自然に返すのは難しい。でも、子スズメを育てたことは我が家の「宝」になった。私の涙に「お母さん、泣くな」と言った娘は一つ頼もしくなった。母の日を挟んだ2週間、スズメが必死に生きる知恵と勇気を教えてくれた。]。 |
|
【日録・余録】 20021204 自分とたたかい、自分を「しっかり」、確立しようとしている。そしてそのためにこそ、一瞬、一瞬を、懸命かつ赤裸々に、費やそうとしている。 心に残る言葉が、そこにあって、発せられる。そのたたかい方、その生き様、その言葉を、受け止めて、自分もまた日々の瞬間を、大切にしようと志す。 「しっかり」ということは、可能か?十分に可能だ。 誰しもが、「何か」は、てっとりばやく、発見しているはず。 そしてそれは最初はささやかなものだが、そのうちに、深さと広がりを持つようになる。 そうやって、人は、「てっとりばやさ」と「思想の深み」の二つを手に入れる。 20030526 新聞の切り抜きをやってよかったと思うのは、闘病において自分自身とたたかう人の発言に接する時である。そのほとんどが「投稿欄」であるというのも特徴といえるだろう。よほどの思いで投稿しているのである。受け取る方も覚悟がいる。 それはまた、生き方の貴重な記録でもある。 人々に伝承されなくてはならない。瞬間的に、迅速に、波及しなくてはらない。そのための知恵が必要だ。 |
 トップページへもどる
トップページへもどる