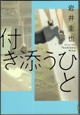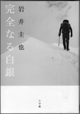| 1. | |
|
「文 身」 ★★ |
|
|
2023年03月
|
普通の状況だったら多分、本作を読むことはなかったでしょう。 それくらい凄みのある、極めてダークな作品。 こうした類のダークさは、私の苦手なところです。 「最後の文士」と評された無頼作家の父親=須賀庸一が死去。 父親とはずっと絶縁状態でしたが、大勢の人から頭を下げられて頼まれ、やむなく実娘の山本明日美は喪主の座に。 その葬儀の後、山本明日美宛てに届いた宅配便、差出人は須賀庸一と記されていた。 その中身は 400枚にも及ぶ原稿用紙。そしてそこに書かれていたのは、須賀庸一と弟・堅次という2人の驚くべき物語だった。 須賀庸一の私小説(主人公は菅洋市)、執筆していたのは庸一ではなく堅次だったのか。半世紀も前に自殺したと伝えられていた須賀堅次は、実は生きていたのか・・・。 小説と言えば虚構のもの。一方、私小説と言えば、それは事実を土台にした虚構。 しかし、もし虚構と事実の順番が逆だったら・・・・・、恐ろしいことを考え付いたものだなぁと思いますよ、ホント。 自分が作ったシナリオどおりに人間を操る、それはもう神あるいは悪魔の仕業に他なりません。 最後の一文に戦慄。悪の連鎖は断ち切れないのでしょうか。 序幕/1.虹の骨/2.最北端/3.無響室より/4.深海の巣/5.巡礼/終幕 |