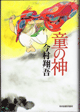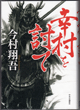| 1. | |
|
「童の神」 ★★ 角川春樹小説賞 |
|
|
2020年06月
|
平安時代、京の近辺には、朝廷の支配下に属さない古くからの民たちがいた。 鬼、土蜘蛛、滝夜叉、山姥、等々、如何にも恐ろし気、まるで化け物といった名で朝廷人たちは彼らを呼ぶ。その総称が“童”という次第。 朝廷支配下に属さない彼らを執拗に攻撃し、根絶やしにしようとするのが、源満仲とその跡継ぎである源頼光。 源頼光といえばすぐ思い起こされるのは“酒呑童子”伝説。伝説では酒呑童子が悪側、源頼光とその四天王(渡辺綱・卜部季武・碓井貞光・坂田金時)が正義側とされていますが、本作は正悪を逆に描いたストーリィ。 伝説とは、常に勝った側が描く故に、負けた側は常に悪とされてしまいますが、事実は本当にそうなのか。 偽計、奸計をめぐらし、彼らを<人に非ず者>と一方的に決めつけ、女子供を構わず皆殺しにしようとする頼光らの側に、本当に正義はあるのか。 後に摂津竜王山の滝夜叉、大江山の鬼、葛城山の土蜘蛛らを連携させ、朝廷軍に対する抵抗勢力のリーダーとなるのが、自領の民を守ろうとして朝廷軍に攻め滅ぼされた蒲原郡の豪族=山家頼房の嫡男だった桜暁丸(おうぎまる)。 最初から最後まで、童たちと頼光率いる朝廷軍との戦いに尽きるストーリィ。暗澹たる気持ちになるのも仕方ない処。 しかし、ふと思うとこれは、やはり山の民を描いた隆慶一郎一連作品から遡るストーリィではないか。また、秀忠率いる江戸幕府に最後まで抵抗し続けた影武者家康らの戦いに類似するストーリィではないか、と思った次第。 最後は、壮快な幕切れ。 自分らしい生を全うした童たちの姿が愛しく目に浮かびます。 なお、坂田金時=金太郎も元々は足柄山の山姥という童の出自なのですが、早くに朝廷軍に降伏し、京人に仕えたという設定。 序章/1.黎明を呼ぶ者/2.禍(わざわい)の子/3.夜を翔ける雀/4.異端の憧憬/5.蠢動の季節(とき)/6.流転/7.黒白の神酒/8.禱りの詩(いのりのうた)/終章.童の神 |