7 関東周辺の温泉 7-5 群馬県北西部の温泉 7-5-2 成分の特徴 硫酸塩ベースの泉質が多いこの地域の温泉は、無色澄明でとくに変わった色や濁りもなく、みんな似たようなお湯ででバリエーションに乏しいと評されがちです。違いがわかるベテランの温泉通にとっても、それぞれの温泉の個性をズバリ表現するのはかなり難しいみたいです。この項では、温泉成分を比較してみることで、それぞれの温泉にどんな共通点や違いがあるかを見ていきます。
この地域の温泉はイオンの組み合わせがとてもよく似ていて、Na、Ca、Cl、SO4の4種だけで成分の90%以上を占めてくるわりと簡単な構成になっています。それぞれのイオン比率が増減することで泉質名がちょっとずつ変わってきますが、基本的には同系統の温泉とみてよさそうです。 【四万タイプ】 四万新湯、四万山口など (図の左がわ) 【水上タイプ】 水上、法師、川古、四万日向見など (図の右がわ) 【川原湯タイプ】 川原湯、沢渡、湯平、花敷、猿ヶ京など (図の真ん中へん) |
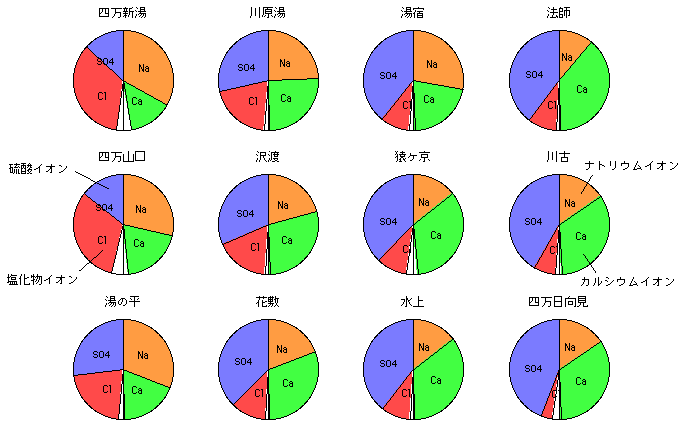
図7-5-2 おもな温泉の成分円グラフ(mval比)
|
イオン比率でみる関係 円グラフだけでは相互の関係がいまいちよくわからないので、下図7-5-3にはイオン比率を表すグラフを用意してみました。グラフの上方はカルシウム(Ca)が多く、下方はナトリウム(Na)が相対的に多くなるように表現されます。 こういう直線関係がある場合のふつうに考え方としては、両タイプを端成分とする起源の異なる温泉があり、それぞれの混合によって中間の温泉がつくられているとみるのが一般的です。たとえば、四万タイプは海水起源、水上タイプは天水起源だろうかという具合です。ところがしかし、温泉水の同位体による研究(松葉谷1989など)では、ほとんどの温泉は天水を起源とすることで共通することが判り、別々の成因があることは支持されません。この地域の温泉の成因を説明するためには、両タイプの温泉が同時にできるような仕組みがあるようです。 さて、図のなかには直線関係から外れる温泉もいくつかあります。湯宿温泉は左下のほうに位置し、やや芒硝泉(Na-SO4)の泉質に寄っているのが変わっています。この原因はいまいち不明ですが、湯宿温泉の背後の山は大きな地滑り地帯になっており、岩石の粘土化変質がみられるようです。こういう岩盤を通ってくる温泉では、粘土鉱物のイオン交換でCa→Naの変化がおきることが知られているので、そういう作用があるのかもしれません。 |
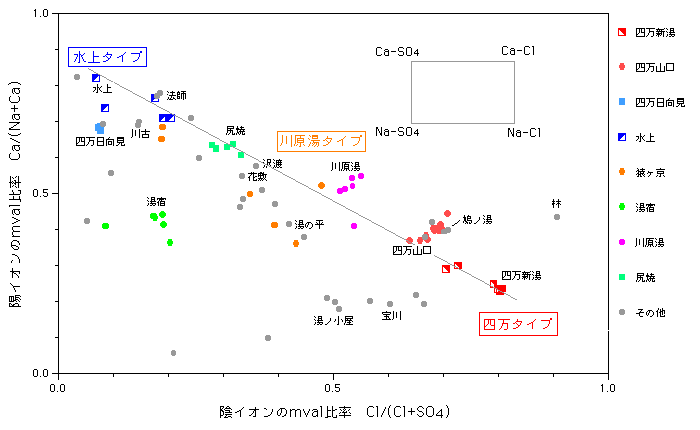
図7-5-3 おもな温泉のイオン比率の関係(mval比) 縦:Ca/(Na+Ca) 横:Cl/(Cl+SO4)
|
硫酸イオンと泉温の関係 水上タイプの温泉は石膏(Ca-SO4)成分を多く含むことが特徴なので、この点から少し検討してみましょう。下図7-5-4では、この地域の各源泉の泉温によって硫酸イオン(SO4)濃度がどう変化するかを表しています。一見したところでは散漫に分布するかのようですが、40℃あたりにピークがあって、高温になるほど硫酸イオン量がしだいに減っていく関係がわかります。 水上(諏訪・天狗源泉)や猿ヶ京(湯島源泉)、川原湯などは曲線にほぼ近くなっています。高圧状態では石膏の溶解度はもう少し増えますが、地下では源泉の温度もさらに高いでしょうから、ほぼ石膏に飽和しているものとみられます。これらの源泉は平衡に達するほど長い時間をかけて充分に岩石と接触し、熟成が完成した温泉だといえるでしょう。 水上と猿ヶ京の分布はずいぶんバラついており、低温源泉では硫酸イオン濃度が極端に薄くなります。図中の左下端に位置するポイントは希薄なNa-HCO3型の低温泉で、これらとの混合が考えられます。両温泉ともに昔からの源泉の周囲に新しい掘削が行われて規模が拡大しましたが、本来の温泉源の湯脈はかなり狭い範囲にしか存在しないのでしょう。 さて、四万タイプの温泉はどうかとみると、四万山口などは泉温からしてかなり硫酸イオンを含んでいても良さそうなものですが、意外に低濃度です。これは温泉が湧出する岩石がグリーンタフではなく、石膏分の少ない花崗岩だからだろうと考えられます。また、奥利根エリアの温泉は図のいちばん下の方にならび、硫酸イオンの含有量は非常に低くなっています。これも湧出母岩がグリーンタフではなく、ずっと年代の古い基盤岩になっているからでしょう。 |
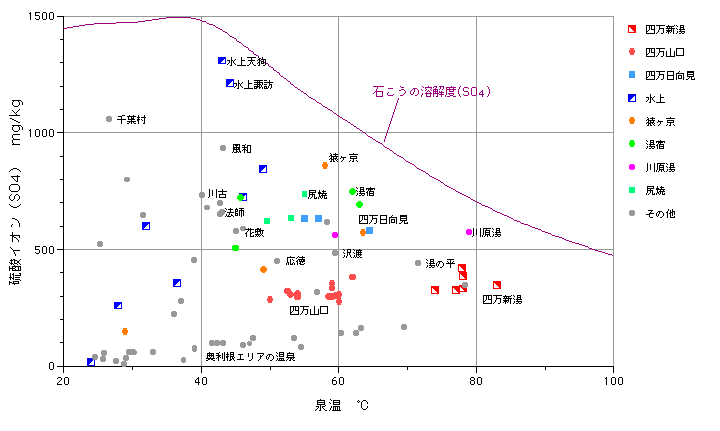
図7-5-4 泉温と硫酸イオンの関係