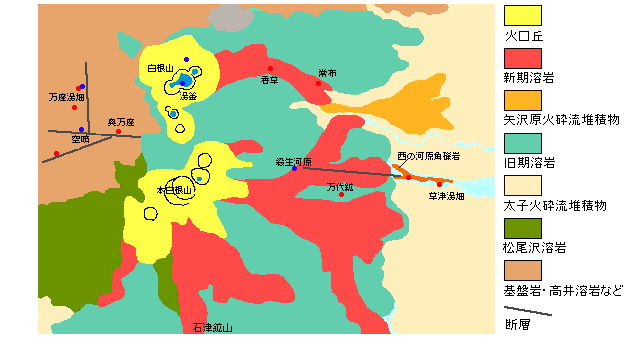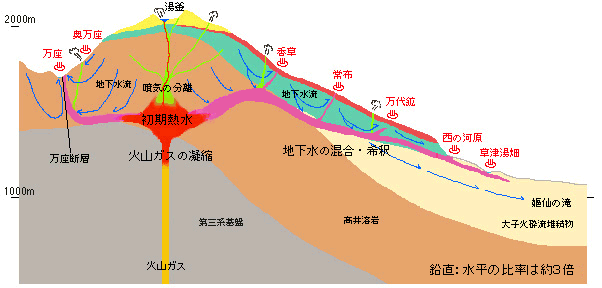温泉のできかた
いささか大胆な推測もまじえて、温泉のできる様子をモデル的に断面図で表してみました。
<初期熱水の生成>
草津白根火山のマグマ溜まりは山頂下約3km(標高-1km)あたりに存在するとみられています。しかし、山体内で起きる火山性地震は湯釜の東側山頂下500〜2000m程度の比較的浅い部分に多くなっています。これは、深いマグマから上昇してきた火山ガスが凝縮をはじめ、液体と気体の2相が混じりあっている状態のために振動・共鳴しておきる地震だと考えられています。やかんのお湯がグラグラ煮えくり返っている様子を想像していただければ近いと思います。
平林(1999)は、草津白根山全域で湧出する温泉水の成分量は1日あたりCl-で12.8トンSO42-で27.5トンで、これをまかなうためにはマグマ起源の火山ガス(H2O=90%・HCl=1.0%・SO2=0.83%と仮定)が一日あたり80〜110万立方m供給されているだろうと計算しています。なんかすごい量のように聞こえますが、普通の火山でもSO2にして静穏時で10トン/日程度、活発化すると数100〜1000トン/日くらいは放出しているそうですから、草津白根山のガス放出量が特に多いというわけではなさそうです。最近噴火した三宅島など、SO2にして3000〜10000トン/日も出しているそうですから、これはまったく驚異としかいいようがありません。
凝縮した火山ガスは、Cl-=22g/L・SO42-=33g/Lという高濃度の強酸性熱水をつくって、山頂下500mくらいのところに熱水溜まりを形成していると考えられてます。これを仮に「初期熱水」とよんでおきましょう。
<火山噴気の分離>
前項でも触れた山本ほか(1997)の研究では、初期熱水のイオウ同位体比は+29(0/00)くらいだと見積もっています。日本の第四紀火山岩に含まれるイオウ同位体比の平均が+6(0/00)くらいですから、何か特別に重いイオウが濃集するメカニズムが働いていることが予想されます。山本らは、初期熱水ができるときに、SO2の不均質化によりH2SO2に富む液相とH2Sに富むガス相の分離がおき、液相のほうに重いイオウが選択的に濃集するのだと考えました。このときの熱水の温度は150〜200℃くらいであると試算されています。
2・SO2 + 4・H2O → 3・H2SO4 + H2S
こうして分離した硫化水素(H2S)に富むガス相(CO2もかなり含む)は、山頂北部付近から噴気として放出されています。
山頂火口湖である湯釜は、その水じたいはほとんどが天水(雨など)だとみられていますが、これに噴気が突入しても現状のような強酸性の湖水はつくられません。大場(2000)は、初期熱水のかなりの量が湖底から注入されているものとみています。湯釜の湖水の変化は火山防災の面から注目され、常時観測されています。マグマからのガス放出量が増えたりガス組成が変わったりすると、その影響が最も速く表れるのが湯釜だと考えられているからです。
<熱水の移動>
初期熱水はやがて山体の周りへ移動していきます。移動通路は謎ですが、一つの可能性として断層の存在が有力です。万座付近では、基盤岩(高井溶岩)に、奥万座と空噴を結ぶほぼ東西方向の断層があります。草津付近では殺生河原と湯畑を結ぶ地下に潜在的な断層があることが各種の調査からわかってきています。これらの断層が熱水溜まりの付近まで届いていれば、大量の初期熱水を運ぶ通路となるでしょう。香草と常布の地下がどうなっているかはまったく資料がありませんが、おそらく同系統のべつの断層が潜在しているのではと思います。
さて、東麓(草津方面)に下った熱水は、基盤岩を通過している間は浸透地下水の混合をほとんどうけないで、地表付近まで上昇してくるものと思われます。ところが、旧期溶岩のあたりまでくると大量の浸透地下水とめぐり会うようになります。新・旧期の溶岩はどちらも隙間が多い浸透性の高い岩質なので、山体への降水はほとんど溶岩の下へ潜って地下の川をつくっているからです。初期熱水はこの地下水の川の流れに沿って、混合をうけながら次第に山麓の方へ流下してくるものと考えられます。いっぽう、西麓(万座方面)に下った熱水は、最後まで基盤岩を通っていくのでほとんど地下水の混合をうけません(空噴でも高いイオウ同位体比をもつ)。前項(図4-2-3-4)のイオウ同位体比の変化は、この様子をよく現しているように思えます。
東麓(草津方面)に下った熱水は混合希釈されてもなお強い酸性なので、溶岩の中を通過する間に岩石の成分を大量に溶かし出していきます。しかし、西麓(万座方面)に下った熱水は、基盤岩のすでに古い時代に変質をうけた岩石を通過するので、草津方面とは溶かし出してくる成分が違ってきます。
<温泉の湧出>
東麓(草津方面)
溶岩の中をはるばる下ってきた熱水は、草津付近まで達するあいだに初期の20倍くらいにまで希釈されていますが、温度はいぜんとして80〜100℃程度を保っているとみられます。これが殺生河原あたりでは大量の地下水と接触し、熱交換で生じた蒸気が大規模な噴気地帯をつくっています。この噴気には熱水から分離した硫化水素(H2S)もたくさん含まれています。トリチウム(三重水素)を使った調査では、草津湯畑の温泉水は滞留時間8年の地下水が、約17年を要して湧出してきたものだとわかりました。つまり、草津の温泉水の大部分は、25年前に殺生河原より上に降った雨・雪からできているということです。
さて、東麓では、溶岩の下に大子火砕流堆積物が分布してくるようになります。これは溶岩より浸透性が高い地層ですから、このままでは温泉水はどんどん地下に浸透していくはずです。しかし、幸いなことに、大子火砕流堆積物はすでに大量の地下水で満杯になっていますから、熱い温泉水は冷たい地下水の上を浮くようにして、旧期溶岩との境界あたりを流れていきます。やがて旧期溶岩がぷっつりと切れるところから、地表に顔を出してくるのが西の河原や湯畑などの町内の自然湧出泉です。湧出しなかったぶんは、地下水に混じってさらに流下し、嫗仙の滝のような谷の切れ込んだところでたまに湧出するのが見られます。
ここで明らかなように、もし地下水の水位が下がるようなことがあると、町内の温泉は地下に潜って湧出してこなくなります。さらに、山体部へ浸透する地下水量が減少すると、温泉水自体が草津まで到達して来なくなる恐れだってあります。草津の温泉をいつまでも守っていくためには、豊かな地下水が貯えられるような環境を山体の全域にわたって保全することが何よりも大事だってことがわかります。
西麓(万座方面)
万座温泉の湧出は、草津に比べて複雑です。東西性の断層を通って移動してきた熱水は、奥万座あたりで硫化水素(H2S)に富む噴気を分離します。この噴気は地表付近で浅い地下水と接触して奥万座温泉をつくっています。熱水は空噴あたりまでくるとこんどは南北性の断層につきあたり、この断層に沿って上昇してきているとみられています。地表までの間には、断層へ浸透している深層地下水や表層を流れてくる奥万座温泉水などと複雑に混じりながら出てくるために、湧出口によって成分や泉温の違いが大きくなっています(前項参照)。弱アルカリ性のさわらび源泉は、深層地下水が熱水と混合しないで湧出してきているものと考えられます。
<筆者の空想 − 万座はなぜ正苦味泉か?>
万座温泉はマグネシウムに富むという変わった特徴があります。日本の酸性泉の平均値は30.7mg/L(後藤による)ですから、その3倍近く、空噴きなどは9倍も含んでいます。この理由を明らかにした研究報告はまだ出ていないようですので、筆者が勝手に空想していることを書いてみます。万座付近の岩石(高い溶岩)は温泉変質で白っぽくなっていますが、もともとは緑色に変質した岩石です。これは地熱地域ではごく普通に見られる広域的な変質で、緑泥石という鉱物がたくさん生じているからです。緑泥石は粘土鉱物の1種で化学組成はなかなか複雑ですが、
[Mg2・Al(OH)6]・[Mg3・(Si3Al)O10・(OH)2]
で表されるマグネシウム緑泥石というのがあります。一般にはMgの部分にはFeが均等くらい入っているのが普通です。ややこしいですが要するにマグネシウムに富む鉱物が岩石にたくさんあるということです。
緑泥石ができる変質作用は、火山性食塩泉ができるような弱アルカリ性の環境下ですから、ふつうの火山ではごく深いところにあります。いっぽうの酸性泉はだいたい火山の山頂付近に湧出しますから、両者が接触することはまずほとんど皆無といっていいでしょう。ところが地質の説明で書いたように、草津白根山は山頂部が一方的に隆起したような上げ底構造になっていますから、緑泥石を含む変質岩の中を酸性泉が通過するという珍しい現象が起こっています。もし、緑泥石が強酸性水で分解し、鉱物中のマグネシウムが温泉水に大量に溶け込んでくるとしたら、万座はなぜ正苦味泉か? という答えになるような気がします。
[7-2章 参考図書・参考文献]
|