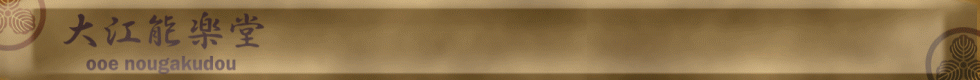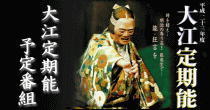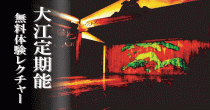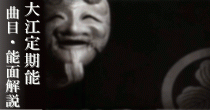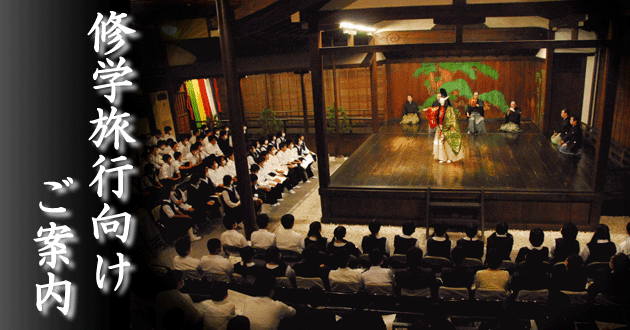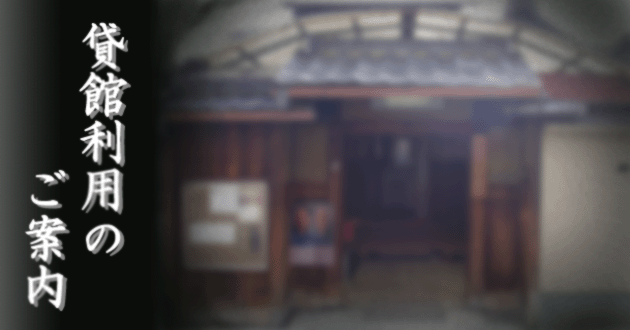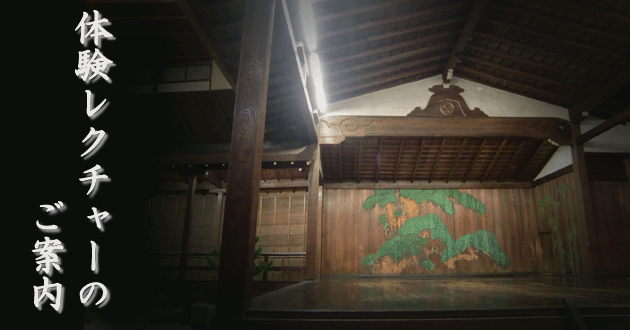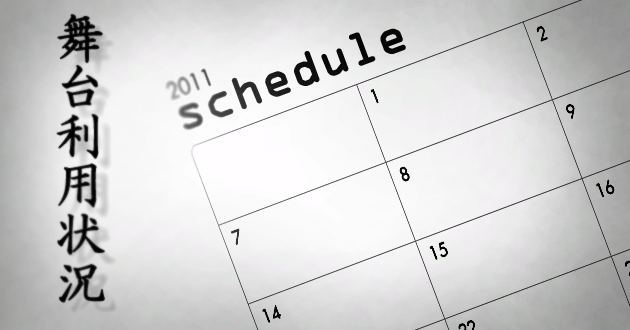能・班女について

美濃国(現・岐阜県)野上の宿の遊女、花子(シテ)は東国へ下る途中宿に立ち寄った吉田少将(ワキ)と恋に落ちます。契りを交わした二人は形見に扇を取り交わし、必ず再会すると約束し別れます。花子はそれ以来、扇ばかりを見つめ勤めを行わないため、怒った宿の長(アイ)は花子を宿から追い出します。
《中入り》
東国からの帰りの途中、再び野上の宿に立ち寄った少将は花子が宿にいないことを知り落胆し都へ戻ります。失意の中都へ戻った少将は糺の下賀茂神社へ参詣します。すると偶然にもそこに班女と呼ばれる女、すなわち花子が現れます。宿を追われた花子は少将を恋焦がれるあまり心乱れて都まで上ってきたのです。神に祈願をささげる花子に少将の供の者(ワキツレ)が狂って見せよと促します。花子はその心のない言葉に誘われるようにして次第に心を乱し始めます。形見の扇を手にし少将の不実を嘆き又、玄宗と楊貴妃の睦まじい仲を羨み、秋の扇と捨てられた班婕妤(はんしょうよ)に自分を重ねその身の上を悲しみ舞を舞います。逢いたくても逢えない、想えば想うほど募る恋心に花子は悲しみ、そして一人涙を流すのでした。それを見ていた少将は班女の持つ扇に気が付き、扇を見せるように頼みます。扇を見合わせた二人はお互いが探し求めていた愛しい人であることを知り、再会を喜ぶのでした。
花子の一途な想いを扇を用いて描くとても抒情的な物語です。情感のこもった謡、狂おしい恋心を表す舞がありますが狂女物にある「クルイ」はなく、クリ、サシ、クセ(能の小段)があり中ノ舞を舞います。狂女物ではありますがどちらかというと三番目物に近い位置づけの作品です。また曲名にもなっている班女というのは、前漢の武帝に寵愛を受けた班婕妤(はんしょうよ)の略称で、趙飛燕(ちょうひえん)に帝の愛を奪われたことにより、我が身を秋になると捨てられる夏の扇に例えて嘆いた詩「怨歌行」を作りました。以来、捨てられた女を秋の扇というようになり、この曲の主人公、花子も扇の縁で班女と仇名されたのです。
能面「若女・増女」について