水道で行われる塩素消毒についてその概要をとりまとめました。
塩素消毒にはその注入の方法や用法にいくつかの派生法があります。不連続点塩素処理についても取り上げます。
消毒効果が減耗することについて,及び,その対策としての塩素の追加について。
塩素の注入設備とその概要について。
消毒全般についてはこちらをご参考ください。
| 作成者 | BON |
| 更新日 | 2009/11/08 |
日本では,水道法によって,供給水には残留塩素があるものとすることに定められています。しかし,海外ではこの限りではなく,国によって消毒の考え方には違いがあるようです。塩素消毒は,コストと効果の点で非常に優れた消毒方法ですが,塩素臭や副生成物,設備の劣化などの欠点もあります。ただ,安全志向は結構なんですが,巷に流布される噂では,塩素消毒の欠点ばかり強調されているような気がしてなりません。ここでは,塩素消毒に関する情報を取りまとめます。
| 塩素消毒 水道で行われる塩素消毒についてその概要をとりまとめました。 |
|
| 塩素消毒の派生法 塩素消毒にはその注入の方法や用法にいくつかの派生法があります。不連続点塩素処理についても取り上げます。 |
|
| 管内減耗と追塩 消毒効果が減耗することについて,及び,その対策としての塩素の追加について。 |
|
| 塩素の注入方法 塩素の注入設備とその概要について。 |
|
| 消毒とは 消毒全般についてはこちらをご参考ください。 |
【参考】
2001/08/10 消毒に関する情報のページを分離しました。
1)塩素消毒の特徴
塩素消毒は,水道において用いられる最も普遍的な消毒方法で,水道法において,給水栓水で保持すべき残留塩素の量が規定されております。昭和32年の水道法制定により,遊離残留塩素 0.1mg/L を確保することが定めらています。
| 水道法
第二十二条 水道事業者は,厚生労働省令の定めるところにより,水道施設の管理及び運営に関し,消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない 水道法施行規則 (衛生上必要な措置) 第十七条 法第二十二条の規定により水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は,次の各号に掲げるものとする。
|
もっとも,この0.1mg/L という基準は,塩素の消毒効果を考えるとかなり高めの数字だそうです。一説には,戦地や軍艦などの基準値がもとになっているとか。消毒全般の詳細については消毒のページを参考してください。
日本では,水道水の消毒には塩素系消毒剤以外の使用を認められていなかったのですが,その他の消毒剤の使用についてもさまざま研究されており,近いうちに法改正などによって使用できるようになる可能性もあります。
残留塩素は,水道水の性状,塩素注入量,時間帯,気温,滞留時間などの条件,そしてなにより採水地点によって値が大きく変化します。残留塩素の統計データは,他の水質項目の有意性を判断するためには必要(たとえば一般細菌や過マンガン酸カリウム消費量など)ですが,統計に掲載された数字をもって代表値とすることはできないことが他の水質項目と異なる点でしょう。
塩素そのものに関する物性の情報は,消毒剤及び消毒副生成物の項目(12水質に分類)にてとりまとめました。
| 消毒剤及び消毒副生成物 塩素に関する特徴は別項です。 |
2)長所と短所
塩素消毒の長所には以下のようなものがあります。
一方,短所には以下のような点が挙げられます。
3)注入方法
塩素の注入方法にはいくつかありますが,詳しくなりますので後述します。
| 塩素の注入方法 塩素の注入設備とその概要について。 |
消毒塩素の注入量に基本的には比例しますが,有機物や,特にアンモニアの存在により急速に消費されますので,原水によってはより多くの塩素剤を投入する必要があります。また,鉄やマンガンの酸化剤として塩素を使用する場合があります。
これらの性質を利用するケースもあります。次項目,塩素消毒の派生法を参照してください。
| 塩素消毒の派生法 塩素消毒にはその注入の方法や用法にいくつかの派生法があります。不連続点塩素処理についても取り上げます。 |
塩素の注入量については,浄水場からの出口時点での残留塩素で0.3mg/L(要確認),給水栓で0.1mg/Lとなっています。ただ,アメリカでは浄水場から出るときの残念の既定は,C×Tで既定されているそうでして,確かに消毒の概念から考えると,こちらの合理性がありそうです。ここで,Tは浄水池の全容量に対する滞留時間ではなく,短絡流を考えて計算値の15%をとることになっているのだそうです。※2
【備考】
※1匿名希望さんの作成分をいただきました。注入率の計算方法についてはいずれ。
※2水道サロン第100回,河村先生記念講演から。
塩素消毒法には,浄水処理工程中における塩素注入の時期と注入量とによって前塩素法,後塩素法,2重塩素法,過剰塩素法,不連続点塩素法,クロラミン法などの用法があります。
前塩素には,主として3つの目的があります。
まず,塩素のもつ酸化力によって水中の溶解性物質を酸化し,その後の除濁プロセスや触媒プロセスによって除去する場合です。鉄,マンガン除去のため,これらを酸化して不溶化するための酸化剤としての使用がこれにあたります。塩素を使用すると,鉄については数秒程度の時間で酸化が完了して不溶化しますが,マンガンの酸化には数十時間が必要であり,そのままでは酸化による不溶化はできません。しかし,マンガン砂(既に2酸化マンガンが表面に析出した砂)の存在のもとでは,これが触媒の役割を果し,2酸化マンガンを連続的に,良好に除去可能です。
次に挙げられるのが,有機物などの分解のための酸化剤としての役割です。ただ,トリハロメタン類など,消毒副生成物の問題と背中合わせのため,最近ではあまりこの目的での前塩素は使用されなくなってきています。
3つめは,殺菌・殺藻剤としての使用です。汚染の進んだ原水に対して急速ろ過を適用する場合など,微生物の繁殖によってろ過池が閉塞するケースがありますので,これを抑制する目的で用いられます。生物処理などを導入する場合はこの意味での前塩素処理はできませんので,非常に苦労することがあります。
原水の有機物量が多い場合などに,塩素とこれらの接触によってトリハロメタン類が生成する場合があります。そこで,塩素の注入点をなるべく後ろにして,懸濁質などに含まれる有機物を極力除去した後に塩素注入し,さらに接触時間を短くすることによってトリハロメタン類の生成を抑制することが考えられました。
水中にアンモニア類がある場合,塩素はアンモニアとよく反応し,クロラミンという化合物になります。クロラミン自体の殺菌力に注目し,これを積極的に生成,比較的清浄な原水に適用するのがクロラミン法です。クロラミンが0.1mg/L以下であればクロラミン臭を気にする必要はありません。
過剰塩素法は,アンモニアによる塩素要求量以上に塩素注入を行う方法です。過剰塩素法をさらに理論的に詰めたものが不連続点塩素消毒といわれるものです。
不連続点塩素処理とは,主としてアンモニアによる塩素要求を把握し,これを適正に超過する消毒塩素を注入することで,適正な消毒効果を得ようとするものです。水に塩素を注入すると,塩素注入率と残留塩素量の間の関係に,大きく3つの段階が発生することが分かっています。
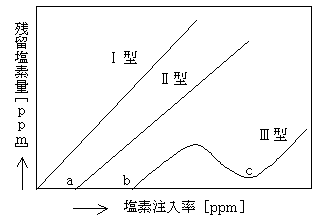 塩素要求量がゼロの水。
塩素要求量がゼロの水。不連続点塩素法は,不連続点と水の味臭の消滅点とが一致するので,味臭をほとんど完全に除去することができ,さらに殺菌効果もほぼ完全であり,また残留塩素も適当に残すことができ,色度が除かれる等の利点があるとされています。
反面,全ての水が必ずしも明らかに不連続点を示すとは限らず,また原水の水質によって不連続点の位置が左右されるので,水質変化の激しい場合には,塩素注入量の決定に熟練した技術が要求されます。また,この方法は1種の過剰塩素法であるので,塩素所要量の大きいことも欠点の一つといえるでしょう。
【参考】
水道施設設計指針 1990,解説 P.248・上水道工学要論 P.203〜208,水道の水質管理 P.92〜95
1)塩素の減耗とは
残留塩素(遊離塩素)は水道水中でじょじょに減少し,消毒効果を失ってしまいます。このため,長い時間や距離を送水する場合,受水槽や高架水槽のように滞留時間が長い施設を設ける場合などでは,塩素の消毒効果が時間とともになくなってしまう可能性があります。
そこで,注入時点でおおよその塩素の減耗の状況を予測し,それを上回る濃度での注入を行うことが,一般に行われています。「配水システムにおける残留塩素の濃度測定方法」によると,管末の残塩濃度は以下のような式で表される,とされています。
Cを残塩の残存率とよび,C=Ct/CO で表します。ここで,
2)追塩
塩素の減耗の対策として,中継ポンプやタンク,管内などで,消毒剤を追加することがあります。このような,塩素を追加する操作を「追塩」とよびます。管内の残存率を計算して注入率を算出したとき,薬注点付近の塩素濃度が高くなり過ぎる場合や,上水を長距離輸送する場合などで,この追塩を行うための設備を設けることがあります。
しかし,追塩設備は,常時使用しなかったり,次亜の補給が面倒なこと,などの欠点があり,十分に維持管理されないケースがままあるのが実情です。配管網の設計時になるべく到達時間を短くしたり,均等にすることで,追塩設備を避けるのが賢明でしょう。
なお,最近では,電解式水道滅菌装置(俗にいう電解水,酸性水と同じもの)のように,特に薬品を搬入しなくてもよいタイプも実用化されてきているようですので,今後は消毒の方法も,少し幅が広がってきそうです。
【備考】
消毒塩素を水道水に供給する方法にはいくつかあります。塩素注入のための装置としては,大別して塩素ガスによる方法と次亜塩素酸ナトリウムによる方法の2種類があります。また,酸化力を失った塩素イオンを遊離残留塩素の形に再活化する装置も開発されています。
(1)液体塩素
塩素ガスの注入は,主として大規模な,歴史のある施設で残っています。初期には液体の塩素を直接ローリーで搬入し,直接注入されることが多かったそうですが,劇物である塩素ガスの取り扱いが難しく,高圧ガス取り扱いの資格が必要なために,小規模な事業体ではほとんど採用できません。最近は,大規模な浄水場でも次亜塩素酸ナトリウムの使用が普通です。
【備考】
1)概要
次亜塩素酸ナトリウム(以下,次亜)は,液体塩素と比べて取り扱いが容易で,安全性が高く,法規制を受けないため,水道界では広く用いられています。次亜の消毒効果は遊離塩素によるもので,次亜による遊離塩素の水中での振る舞いはほぼ液体塩素と同じです。薬液タンク内に液体で保管でき,専用の定量ポンプで注入します。
塩と電解によって現地で生産する方法もあります。これは,装置としては(3)に準じ,これに塩を加える形で行われます。
2)次亜注入装置
薬注設備は取水流量に対して比例注入とするのが普通です。使用薬品は購入次亜塩(有効濃度10%液 )でいいでしょう。この場合の注入装置の容量計算は,以下の式になります。
処理水量×注入率×(100/濃度[%])×(1/比重)×10-3[ml/分]
貯水槽の容量は10日分(設計指針より)ですから,平均注入率×10日で計算してください。既製品の容量は,20,50,100Lなどとなっていますので,適当なものを選ぶとよいです。ただし,特に注入量が小さい場合など,タンク内で希釈できるように水栓を設ける場合があります。
3)次亜の貯蔵と注意事項
使い勝手のよい薬品であるがゆえに,安易に使われてしまうことが多いのは世の常。次亜についても,そのような問題が生ずることがあります。このような事象について,厚労省からよく整理された事務連絡が出てますので要約します。
【備考】
厚労省事務連絡 平成18年3月30日 浄水処理における次亜塩素酸ナトリウムの使用にあたっての留意事項について
(3)製造次亜
現場で塩と電気分解により次亜やオゾンなどの消毒効果を有する液を生成する方法。いくつか方法があるようですが,勉強中ということで勘弁を。日本では塩素剤の使用が義務付けられていることもあって,あまりクローズアップされていませんが,(4)と併せて今後は発展する兆しありと見ています。
最も,爆発するから怖いなんていう未確認情報も...また,塩は精製度の高い,臭素が含まれないものを使用してください。
【備考】
水電解消毒置とは,追塩など有効な装置で,電気分解の要領で塩素イオンを次亜塩素酸イオンに再賦活化するものです。なお,メーカーによっては,追加塩素の代替としてではなく,水にもともと含まれるミネラル塩としてのCl-で十分である,としているものもあります。
この反応はアルカリイオン水の製造時に副産物として出る「酸性水」そのもので,医療現場などでは消毒用として活用されています。この方式の優れる点は,ほぼ電気のみでほとんどメンテナンスフリーの運用ができる(つまり次亜を貯留しなくてもよい)こと,このため自動化が容易であること,などです。まだあまり普及しているとは言えませんが,特に小規模な事業の追塩などで非常に効果的であると考えます。
水道用として製品化している企業のうち,装置イメージなどをわかりやすく紹介しているクロラーのページをご紹介します。
| クロラー@【理水化学】 塩素の注入設備とその概要について。 |
他にもいくつかあるようです。資料をもらったことがある分のリスト...
【参考】
050515 クロラーに関する情報に誤りがあったのせ修正しました。関係各位にはお手数をおかけしました。