具体例を集めます。
環境影響の評価手法については研究段階ですが...
| 作成者 | BON |
| 更新日 | 2009/02/04 |
地球環境の保全に関する関心の高まりとともに,水道においても環境対策の必要性が認識されるようになってきました。もとより,自然環境から原水を得てこれを配水し,また人間生活のもっとも基本的な衛生環境を担う水道事業は,環境への意識も高いものがありました。しかし,その評価手法や水源対策以外の取り組みについては,まだまだ発展途上にあります。ここでは,水道と環境対策に関する知見などを集めたいと思います。
| 環境対策事業 具体例を集めます。 |
|
| 環境影響評価 環境影響の評価手法については研究段階ですが... |
【参考】
(1)省エネ対策の具体例
省エネ対策の具体例について,水道産業新聞に3月4日付けで要約が掲載されました。非常にわかりやすくまとまっているので,引用させていただくこととしましょう。
|
<取水・導水工程〉>
<沈殿・ろ過工程>
<高度浄水処理>
<排水処理工程>
<送水,排水工程>
<総合管理>
<その他>
|
【備考】
水道産業新聞に3月4日付記事から。
水道にとって水源環境の保全は,環境対策のみならず,原水の品質向上のための取組みでもあります。関連のページを参照ください。
| 表流水水源の保全 水源保全対策の事例。表流水関係。 |
|
| 地下水源の保全 水源保全対策の事例。地下水に関連するもの。 |
【備考】
エネルギー回収としては,水道水及び原水のもつエネルギーを利用するもの,水道施設のもつ広い用地や施設という資産を有効利用しようとするものなどがあります。
ある識者のお話ですが,水道で使用する電力エネルギーは日本全国で見ると1%程度とのことで,交通が使用する電力が2%程度であることからも,非常に大きな位置を占めていると言えるわけです。ちなみに,電力消費の80%程度がポンプ運転費とのことで,ポンプの必要ない配水をできるだけ考えることが省エネルギーに大きな役割を果たすのだそうであります。
1)水力発電
水源や貯水池から浄水場までの導水水位差を用いた発電の取り組み。筆者が知る限り,東京都東村山浄水場,北九州市本城浄水場などで事例があります。最近では,インラインポンプの製品化もかなり進んできているようで,私の方にも問い合わせをいただいたことがあります。
 北九州市水道局 本城浄水場 水力発電設備 北九州市水道局 本城浄水場 水力発電設備
北九州市の頓田貯水池から本城浄水場までの自然流下導水管の末端に発電装置を取り付けたもの。37kWと小規模ですので横軸の水車式で,既設の着水井に上から落とす形で取りつけてあります。 導水管末水車発電の設置には通産省の補助制度がありますが,申請するためには発電所を作るのと同じ申請書が必要なので,既設施設の構造資料の調査など,大変な苦労がいります。 |
|
東京都東村山発電所,違った,浄水場の導水管末発電設備。こちらは水量が多いので軸流式のようです。水車発電の能力は600kWです。水力は有効活用できるケースが限られますが,比較的取り出せるエネルギーが多いこともあるので,積極的に検討されてはいかがかと。 |
浄水場には広い敷地がありますので,沈殿池などの覆蓋を太陽電池パネルで構成する取り組みが行われています。太陽電池パネルの低価格化や設置補助制度の充実などもインセンティブとなっていますが,特に,最近のセキュリティへの意識の高まりをうけ。沈殿池やろ過池の上部を覆蓋する工事を行う場合にこれに併せて行われるケースが増えてきました。
|
広大な敷地を持つ浄水場のうちでも,屋根を持つ浄水池の上の敷地や,沈殿池など構造物の屋根に太陽電池パネルを設置する動きがあります。発電量は微々たるものですが,敷地の有効活用の一種ではあるかと思います。 |
|
こちらは浄水場の膜処理設備の上に太陽光発電パネルを設けた事例です。ちょっちわかりにくいとは思いますが,膜処理棟の屋根の南側一面にパネルが装着されています。 |
|
こちらは取水場の覆蓋を兼ねたパターン。上の道路から悪さをするなどを防ぐ目的を兼ねた例です。公園の散歩道からもよく見えるので,PRとしても役に立ってる例でしょう。 |
このほかの導入事例としてとりあえず私が知っている範囲としては,愛知県名古屋市鍋屋上野浄水場,三重県企業庁の磯辺浄水場,北九州市某浄水場などがあります。
また,風力発電も一部に研究的に導入されますが,発電量が限られるので大々的な取組みにはなっていないようです。でも,安価な風車もでてきましたので,今後はこれまでより増えるかも知れません。東京都東村山浄水場でみたことがあります。
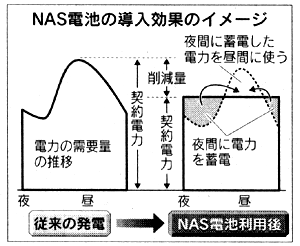 電気の需要は夏期や昼間に多く,夜に少ないのですが,電気は貯蔵が難しいため,各電力会社では,最大の需要に併せて施設整備を行っています。このため,昼間の電力需要の抑制に対するインセンティブは,電力会社の共通の施策となっており,夜間電力の料金を抑え,中間の料金を上げるなどの対策が採られています。
電気の需要は夏期や昼間に多く,夜に少ないのですが,電気は貯蔵が難しいため,各電力会社では,最大の需要に併せて施設整備を行っています。このため,昼間の電力需要の抑制に対するインセンティブは,電力会社の共通の施策となっており,夜間電力の料金を抑え,中間の料金を上げるなどの対策が採られています。
水道の場合,需要の変化に柔軟に対応する必要性から,特に圧送系の送配水に大きな電力を必要としています。たとえば,東京電力の単一顧客のうち最大のものは東京都水道局だそうですから,水道界としても,電力の抑制や夜間電力の活用は非常に大きなインセンティブがあります。
このような背景のもと,先般,東京都水道局がNAS電池(ナトリウム硫黄電池)の蓄電設備の導入を決めたことが報道されました。図は,これを解説する日経新聞(020515)に掲載された図です。一説には鉛蓄電池の三倍の密度を持つとのことで,特に電力の逼迫している地域においては,夜間,昼間の料金差を活用したこのような設備の導入についても積極的に研究する余地があると思います。水道産業新聞020516によると,200kWと300kWの2箇所の稼働で,投資を差し引いても15年あたり計8500万円のコスト縮減が見込めるほか,私的には停電対策としても効果的との説明が興味をそそられます。
また,PFIの先駆事例として有名な東京都の金町浄水場やその後の事業も,夜間については受電,料金の高い昼間は発電,という運転スキームで運用されています。詳しくは東京都のサイトへどうぞ。
| PFI事業事例 PFI事業を実際に行っている事業の事例。 |
【備考】
環境対策のうち,もっとも熱心に行われている分野が,建設残土や浄水汚泥のリサイクルでしょう。
1)建設残土
建設残土は,毒性などの心配がほとんどないケースが多いので,用途さえあれば処理せずに使用できます。
ただ,まれに,自然由来のヒ素の含有率が高いケースなど,そのまま利用できない場合もあります。この場合は,なにもしなければ「自然の土」だったものが,掘り返した瞬間から産業廃棄物になるので大変厄介です。
2)汚泥再利用のポイント
浄水汚泥については,その処分自体が大きな問題になりかねない事情から,積極的なアプローチがされています。有効な再利用が可能かどうかは、以下のようなチェックが必要になります。
このうち、1については、技術屋さんの得意分野ですが、2や3が非常に難しいです。もともとリサイクル財というのは、「先に商品の供給があってあとから販売先を探す」という、商材の扱いやすさの面でみて致命的なハンデキャップをかかえています。汚泥の再利用とは、技術マターではなく、流通マターなのです。
3)リサイクル方法
建設残土や浄水汚泥の再利用の主な方法には以下のようなものがあります。
![]()
 浄水汚泥の再生販売例
浄水汚泥の再生販売例
右は,販売されている再生土の例として,以前現場で写真を撮ったものです。浄水汚泥は基本的には河川を流れてくる良質な土で,園芸土としての利用は積極的に行われております。若干の懸念としては,使用された凝集剤が残っていて,施肥に悪影響を及ぼす場合があること,といったところですか。
阪神水道企業団の尼崎浄水場では,浄水場で出た汚泥を加工して園芸土としたものを,場内の上部利用で誘致したホームセンターで販売されています。ある意味Zeroエミッションかも(^o^)
【備考】
汚泥のページから移動しました。