それでは、ヘラクレス♂幼虫を前蛹状態から人工蛹室とする場合に、あっしなりに思ったこと注意している点などについて紹介させて頂くとしよう。あっしは人工蛹室にはオアシスなどの園芸用吸水性発砲スチロールを利用している。加工が簡単で形も自由に出来るところが良い。最近は100円ショップでもよく見かけるようになり、コスト面でも気に入っている。まだご存知ない方は(いるかなぁ?)、くわ馬鹿のこちらの記事をご覧頂きたい。
オアシスにも色々なサイズのものがあるようだが、100円ショップも含めそこらで普通に手に入る物の大きさは大体が約23×11×8cmくらいである。ヘラクレス♂の場合であればこれをまるまる1個使用することとなる。「この大きさじゃ足りない〜!」ってことはまずないであろう。あってほしいが。(^^;;
人工蛹室の形状は、掘り起こしたオリジナルの蛹室の形状に出来るだけ近付けるようにしてやれば良いだけであるが、あっしはだいたい下図のような感じに仕上げている。
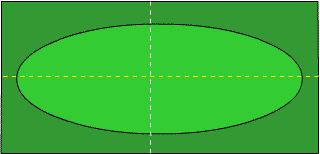 | 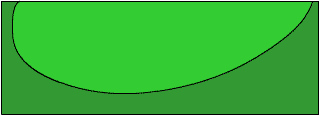 |
Fig.1 | Fig.2 |
まず蛹室の幅であるが、これは幼虫がどのように蛹室を作るかを想像すれば、一番広い部分は幼虫が丸まった直径くらいになると考えられる。クワガタには当てはまらないが、蛹室を横に作るタイプのカブトであれば同じことが考えられるであろう。ヘラクレス♂では7〜8cm程度である。ただし蛹化時と羽化時の人工蛹室をそれぞれ別の物にするのであれば、蛹化させるためだけの人工蛹室は、少し幅が狭い方が良いかもしれない。Fig.2は、Fig.1の黄色い点線で切った断面図であるが、中心に重心をおく感じではなく頭部側の長さを十分に取り緩やかな傾斜とすることが角曲がりを防ぐには大切だと考えている。
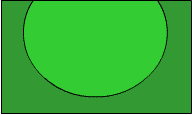 | 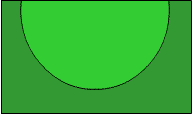 |
Fig.3 | Fig.4 |
Fig.3は、Fig.1の白い点線で切った断面図である。あっしは蛹化からそのまま羽化まで(活動を開始するまで)ほったらかしてしまうので、Fig.3のような形状としている。このような形状の方が羽化をする時に起き上がりやすいと考えているからである。深さも十分にとっている。Fig.4のような感じに仕上げてしまうと蛹化時には問題はないとは思うが、羽化時に問題がありそうに思う。
形が決まったら、人工蛹室内部の削りカスを水をジャバジャバかけながら指で綺麗に洗い流す。オリジナルの蛹室の内壁はサラサラした感じの手触りなのであるが、水を含んだオアシスは滑りが悪くなるので、内壁の水分はキッチンペーパーなどで軽くおさえて取るようにしている。一時の気分の問題だけで結局後で湿ってきて変わらなくなるか。(^^;;
こうして出来上がった人工蛹室に前蛹を入れ、中プラケに入れて保湿している。また、いつ幼虫を取り出して移動させるかについては、前に紹介した蛹室を暴くタイミングと一緒としている。
だいぶ長くなってしまったが、もちっとお付き合い下さいまし。それではまた画像をご覧頂きたい。

この個体もご覧のように角が曲がってしまった。(またもや右曲がり。(^^;;)飼育ケース側面から蛹室内部が見えるといったことはなかったので、ずっとそのままほったらかしておいたのであった。んが、羽化してから数日後に蛹室をそっと暴いてみたら、そんなに酷くはないが角は曲がってしまっていた。これはあっしの許容範囲を少々超えている。そしてまた次の画像をご覧頂きたい。

これが上の個体が羽化してから蛹室を暴いてみた時の画像である。思っていたよりも蛹室の長さがあり、よく見てみると小さな「窓」(画像の中の黄色い矢印の部分)が頭部側に確認出来た。外部からは気が付かなかった。窓があると言うことは幼虫が作ろうとしていた蛹室の長さには少々足りなかったのであろうが、それにしてもたったこれだけ足りなかっただけでも角曲がりが起きてしまうとは、、、そんなものなのであろうか?右曲がりが多いし。うーむ...
このように蛹室を暴いてしまった場合、成虫は自ら更に蛹室を壊してしまうことはよくあることである。ところがオオカブトは、前にもふれたが蛹室の中でクワガタのように仰向けになって寝ていることがよくある。この行動の理由はよくわからないが、足への負担を軽くするといったことが考えられる。そして蛹室を暴いた後に自ら更に蛹室を壊してしまった場合でも、マットの上で仰向けに寝ていることもよくあるのである。その場合、足が引っ掛かるところがないために起き上がるには苦労してるように思えた。最初に見た時には☆してしまったのかと思った。
そのようなことが発生してしまった場合にも人工蛹室を作って移してやっている。その場合にはそんなに形状に気を遣う必要はない。足が引っ掛かり寝返りが出来ればそれでOK!成虫はその中でもよく仰向けになって寝ているところを見る。活動を開始する時が近付いてくると、人工蛹室の上に登っていたり、壊したりといった行動をとるようになる。羽化後十分に休ませてやることは長生きをさせてやるためにも重要なことなのではないだろうか。

