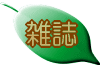第一章 「監督」
一九八七年、大学四年の夏のことだった。ぼくは教室で授業がはじまるのを待っていた。しばらくすると友人がやってきてとなりに座った。そして、
「この本、読んだことあるか?」
と言って一冊の文庫本を寄こした。
『監督』というタイトルと、ボカしてはあるが一目で広岡達朗と分る人物がユニホーム姿で腕を組んでいる絵が目に入った。全体的に赤茶がかった表紙だった。
「読んだことないよ」
とぼくは言った。
そのころ、その友人やぼくを含めた五、六人の仲間は全員プロ野球ファンで、誰かのアパートに集まってはビールを飲み、ナイター中継を見ながら野球談義に花を咲かせていた。そのなかで、ぼくはいつも広岡達朗の戦い方を引き合いに出し、どう戦うべきかを力説した。一九七八年にスワローズを日本一に導いて以来、ぼくは広岡達朗の大ファンになっていた。日本シリーズやプレーオフで彼がどんな手を打ち、結果がどうだったかを詳細に再現できた。彼について書かれた本は、本人の著書も含めてすべて読んでいるつもりだった。だがこの『監督』はまだ読んでいなかった。海老沢泰久という作家も知らなかった。
「貸してくれるのか?」
とぼくはきいた。
「やるよ」
と友人は笑った。
講師がやってきて授業がはじまった。
だがすぐに講義に飽きてしまった。とても暑い日で、シャツはじっとりと汗ばんでいた。窓の外ではセミが狂ったように鳴いていた。
ぼくはこっそりと机の下で『監督』を広げた。
あっという間に虜になった。そうとしか言いようがない。読みはじめて間もなく、あまりの面白さに度肝を抜かれた。それはもう、稲妻が体を貫き、眠っていた細胞が覚醒され、心臓をわしづかみにされたような衝撃だった。
混乱しているぼくの様子に気づいた友人がとなりから小声で、
「面白いだろう」
と言った。
「すごく面白い」
とぼくも小声で言い、力強くうなずいた。
だが、貪るようにどんどん読み進んだわけではなかった。反対に、普段よりもていねいに読んだ。たしかに気持としてはどんどん読みたかった。しかし同時に、文字の一つ一つがダイヤモンドのように輝いて見えた。いくら面白いからといってどんどん進んでしまうのはもったいなく感じられた。それで、ぐっとこらえてダイヤモンドの一つ一つを確認するように読んだ。
そういう読み方で不都合を感じることはなかった。思わせぶりな書き方がされていなかったからだ。二つばかり例を挙げるとこうだ。
「エンゼルスが三位に落ちるまでにそう時間はかからなかった。六月最後の名古屋でのドラゴンズとの三連戦に三連敗すればよかったのだ。そしてエンゼルスは三連敗した」
「もし最終回に得点できなかったら延長だ。そして得点はできず、延長戦にはいった」
つまり、読んでいて生じる疑問に対して即座に回答が用意されているのだ。
こうした例は他の作品でも随所に見られる。海老沢作品では、疑問を抱き続けながら読むストレスとは無縁なのだ。
『監督』の興奮は三日後に読み終えるまで続いた。いや、読み終わっても続いていた。数日間、読後感に陶酔していたからだ。
ぼくはそれまでに野球小説はずいぶん読んできているつもりだった。しかし心の底からハラハラドキドキできたものはアメリカのものにいくつかあるだけで、日本のものでは皆無だった。それでいつの間にか、日本の野球小説に期待をしなくなっていた。それが見事に裏切られた。
読み終えたのは、そのとき一人暮らしをしていた町田のアパートでだった。夕方だった。ぼくはいても立ってもいられず、とりつかれたように自転車に飛び乗って駅ビルに向かった。そこには一フロア全体を占めた、近所で一番大きな書店があったからだ。覚えたばかりの、海老沢泰久という作家の他の作品を読まずにはいられなかった。
自転車をこいで風を切りながら、ぼくはこの作家に対して『監督』が面白かったこととは別の喜びをかみしめていた。この一九八七年の時点で、まだ三十七歳の若い作家だったことだ。老作家やすでに亡くなっている作家だったら過去の作品を読むことはできても新作を期待するのは難しい。しかしそうではなく、自分より十三歳上なだけだった。これから長い期間、ずっと楽しみにしていける。そのことがうれしかった。
一九七九年に西武ライオンズが誕生した当時、ぼくは埼玉県に住んでいて、テレビ埼玉で開始から終了まで中継されるライオンズの試合をよく見ていた。だが最初の三年間はあまりの不甲斐なさにあきれ果てていた。負けても悔しさが麻痺し、
「またか」
ぐらいの気持しか湧かなくなっていた。そして外野席で応援する少年ファンの「あーあ」というため息に胸を痛めていた。だが四年目に広岡達朗が監督に就任してから一変した。『監督』の次に読んだ『みんなジャイアンツを愛していた』にはそのときのゾクゾクするようなドラマがぼくの知っているとおりに書かれていた。その年のライオンズの躍進を取り上げた記事や本はいくつも読んでいたが、これほどぼくの興奮を正確に呼び起こしてくれる文章に出会ったことはなかった。
もうこの作家に対するぼくの信頼はゆるぎないものになっていた。だからそのあとの『F1地上の夢』でも『F1走る魂』でも、ぼくはF1のことは無知だったが、単純に楽しみながら読んでいけばよかった。ぼくが知っている野球の興奮が正確に書かれているのなら、F1のことも正確に書かれているに決まっているからだ。
「彼はこみいつた事情を、それについてまつたく知らない相手に、詳しく、わかりやすく、そしてすばやく伝達することができる。彼の叙述は明晰で、彼の描写は鮮明である。彼はずいぶんややこしい事柄を、もたもたした口調にならずに、こともなげに伝へてくれる」
これは『ただ栄光のために』における丸谷才一氏の巻末解説の一節だが、ぼくが海老沢作品に夢中になった理由はこれに尽きる。読んでいてよどみなく理解できることがこの上なく心地いいのだ。立体パズルが組み合わさるように、言葉がピタッと心に収まる感じだった。よく分らなかったり、違和感を覚えるところはひとつもなく、スッキリと頭に入ってきた。そして余計なものが削ぎ落とされている爽快感があった。実際の本の厚さよりも長い物語を読んだ気持にもなった。凝縮感があったのだ。どうして平易な言葉だけでそんな作品が出来あがるのか不思議だったが、とにかくそういう作品群は、ぼくの心を理屈ぬきにワクワクさせた。
ぼくは今でも忘れない。風を切りながら自転車で町田の書店に向かったときのことを。そのとき買えたのは、『みんなジャイアンツを愛していた』、『F1地上の夢』、『F1走る魂』、『ただ栄光のために』の他には、『F2グランプリ』、『孤立無援の名誉』、『空を飛んだオッチ』、『夏の休暇』、『二重唱』、『さびしい恋人』である。『ただ栄光のために』と『F2グランプリ』と『さびしい恋人』以外は全部単行本だった。持ち帰るのにかなりの重さだったが、それは幸福な重みだった。そして部屋の机に積み上げたときの厚さは、幸福の厚さだった。