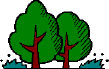|
<1> 公案
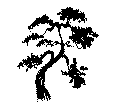

香厳和尚は言った。
「それは口で枝にぶら下がっている、樹上の人のようなものだ。手は枝をつかんでお
らず、足も樹に触れていない。その樹の下に別の人がやって来て、彼に祖師の西来
意を問う。もし答えなければ、問うた者の要求に応じぬことになる。もし答えるならば、
命を失ってしまう。このような時、彼はどう答えたらよいか...」
<“祖師”とは初祖・菩提達磨のこと...“西来意”とは、禅の真髄のことです>
さあ、香厳禅師はとんでもないことを言っています。いったいどう答えたら良いので
しょうか。まさに、答えたら樹から落ちて命を失います。しかし答えなければ、禅問答
に答えられないことになり、禅的な力量を示すことが出来ません。
禅の修業をしている者であれば、せめて一声なりとも発し、その力量を示したいも
のです。が、しかし、「あ、」とでも「う、」とでも言ったら、とたんに樹から落ち、命を失っ
てしまいます。
<・・・ さて、どうしたらいいのでしょうか ・・・>
この公案はの命は、まさにこの“絶体絶命”の中にあります。無門禅師の言う...
“参禅はすべからく祖師の関を通るべし、妙悟は心路を窮めて絶せんことを要す”
...という言葉が当てはまります。うーむ、それにしても、黙っていてもラチが開きま
せん。どうせ死ぬ命です。「あ、」とでも言ってみますか...すると、やはりというか、当
然というか、高い枝から樹下へ落下して行きます。しかし、口はきけますし、まだ地面
には叩きつけられておらず、生きています。少し角度は変わりますが...
この時、この絶体絶命の数秒間・・・
あるがままの一句とは・・・とのようなものでしょうか・・・
生きているが、答えられない高い枝をくわえ...一方、下に落ちて死んでしまっては
答えられない地面の上...答えることが出来るのは唯一、落下している数秒間のみ
です。
さあ、数秒後には確実に死ぬ時...善悪の区別が何になるでしょうか。また、美醜
の差別が何になるでしょうか。愛憎がいったいどうだというのでしょうか。このギリギリ
の“命”の瞬間、そのような二元的幻想から来る万物の一切が消し飛んでしまいます。
あるのは、眼前している、この世のナマの風景、リアリティーの世界だけです。
その時・・・そこには、私の“真の命”のみが光り輝いています・・・
この公案で、香厳禅師は私たちをこの絶体絶命の断崖へ追いこみ、禅の真の姿を
分からせようとしています。しかし、断崖から落ちてしまっては禅になりません。追い
こまれ、追いこまれて...“窮鼠(きゅうそ)猫をかむ”...と言われるように、絶体絶
命の中で私たちは一変するのです。この、一変することが、禅では大事なのだと言わ
れます。
禅匠はしばしば、その追い込まれた状況を、“絶体絶命”とか“大地黒漫々”とか
表現します。結局、そこに追い込むのは、そこで苦悶し、“一変”あるいは“転ずる”こ
とが目的なのです。そして、この“変”・“転”へ至る道が、修行になるわけです。この
“無門関・48則”も、その修行のための公案です。
< 12月8日、明けの明星>
釈尊(ゴータマ・シッタータ)は、空前絶後の苦行をされた後、九死に一生を得
て、尼蓮禅河(にれんぜんが)の西岸で乳酥(にゅうそ)を食べられました。それか
ら、巨大な岩の上に菩提樹がまばらに生えている金剛座へ行き、そこで覚
醒に至る最後の座禅に入ります。
文献によれば、釈尊は7日間座禅し...12月8日...ついに明けの
明星を見て、“一変”されたといわれます。
つまり、釈尊は苦行で悟られたのではなく、“変”ずることによって悟りを
開き、仏陀となられました。私たちが、禅を学びながら求めている“変転”
も、この釈尊が覚醒して仏陀となられた過程なのです。
この、“覚醒”・“悟り”とは何かというと、これまで幾つかの公案で見てき
たように、「無」であり、「無我」であり、「内外打成一片
(ないげだじょういっぺん)」
のことです。“無門関”もそこに見えます。
<2> 香厳撃竹(きょうげんげきちく)  (1999.8.31) (1999.8.31)
<これはすでに“正法眼蔵・草枕”の方に文章がありますので、これを借用します> <参考・ジャンプ>
“竹の音を聞いて大悟するもの”
とは・・・
これは、香厳禅師のことでしょうか
...香厳禅師は、唐の末期の時代の人で、
“無門関”の第五則に登場しています。非常に聡明な人物でしたが、長年の修行
にもかかわらず、ついに悟ることができませんでした。それで、「画餅飢に充たず」
と言って、今まで勉強してきた書物や筆記したものを、全て焼き捨ててしまいまし
た。そして、絶望の中で修行も諦め、師のもとをも去りました。
その後、慧忠(えちゅう)国師の墓所に参拝し、そこで墓守として一生を終わる決心
をしたそうです。ところが、それほど真面目に取り組んでいた人ですから、師のもと
を離れても、まさに“心路を窮めて絶する”状況にあったようです。言い換えれば、
禅的な機は熟しきっていたのです。自分では絶望し、完全に諦めていても、つい思
いはそっちの方へ行っていたのでしょうか。
そうしたある日のことです。悶々と庭掃除をしていた香厳は、瓦礫をはき集め、
竹薮の中に捨てました。すると、小石の一つが、“カチン”と竹に当たりました。こ
の小石が竹に当たる音を聞いて、香厳は忽然と大悟し、笑い出したといいます。
<この小石の音を、聞いて見て下さい...全存在を、この小石の音の中に叩き込
み、自らが...カチン...と響いてみて下さい。そこに、別世界が広がっていきま
す...>
長い間探し求め、最後は絶望の縁にまで追いつめられていたものが、“カチン”と
いう素朴な音で大悟したのです。理屈をこね回して悶々としていた日々がうそのよう
に、カラリと大悟したのです。この例からも分かるように、このようなことは教えて分
かるものではありません。まさに、香厳のように、自ら大悟するほかはないのです。
そして、悟ってみれば、香厳のように笑い出すほど身近にあるものだったのです。
<
しかし、では私自身に、そんな豪快な大悟がやってくることがあるのかというと、
難しいように思います。
まず第一に、私には“心路を窮めて絶する”という状況がありません。これは、性
格から来ているものなのでしょうか。それとも、時代という一般化した風景なのでしょ
うか。いずれにしても、釈尊の時代や、禅の隆盛した中国の唐の時代とは、背景の
文化が大きく異なってきています。しかし、それでもなお、これからは益々仏教の時
代と言われています...>
(
以上、正法眼蔵・草枕より...)
<3> 無門の評語 ...口語訳 
たとえ流れるように弁舌さわやかでも、何の役にも立ちはしない。たとえ一大蔵経
を説き得ても何にもならない。もし本当にこれに答え得るならば、死んだ人を生き返ら
せ、また生きた人を殺すことができよう。しかしもし答えることができなければ、弥勒
の出現を待って、彼に問うがよい。
死んだ人を生き返らせ、また生きた人を殺すことができよう とは、“悟り”を開い
てそれに執着している者からは悟りを奪い、迷える者は明に転じるほどの力量があ
るということです。つまり、二元的対立を完全に超越した、非常に明快な境地にいた
ることが出来るということです。
弥勒の出現を待って、彼に問うがよい とは、釈尊の滅後56億7000万年後に
この世に降臨するという弥勒菩薩(未来仏)を待つより仕方があるまいということです。
それにしても、仏教ではこんな途方もない数字がポンポンと出てきます。しかし、こう
した天文学的な数字は、とりあえず比喩的と解釈しておくより仕が方ありません。
|
 香 厳 上 樹(きょうげんじょうじゅ) /香
厳 撃 竹
香 厳 上 樹(きょうげんじょうじゅ) /香
厳 撃 竹 
INDEX