|
( 1999.12. 8
)
第1章/無我の考察・・・
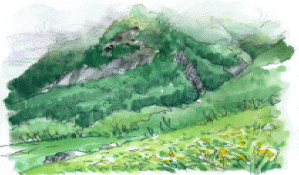  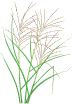 
第一部/“無門関峠への道程”/で言ってきたのは・・・
見るものと見られるものは、同じ一つのものであるということ...
その二つの間には、全く切れ目も境界もないということ...
第二部/“無門関峠の永遠”/で言ってきたのは・・・
永遠とは、無時間であるということ。そして、時間もまた二元
論的な幻想であるということ...
第一部、第二部ともに、言っていることは、二元論/二元性の超越です。これらの
言葉を、思想として理解するのは容易です。しかし、禅とは、この哲学的思想を、真
に自己のものとして体現することにあります。したがって、そのために修行が必要に
なってくるわけです。ここでは、私の細々とした体験をもとに、その修行について考察
して行きます。
(
私自身も、道元禅師や無門禅師から学んできています。歴史的にも大禅匠は多数お
られるわけであり、どうか、そちらの方からもしっかりと学んでください。それらは、歴史の
荒波を乗り越え、多数の先人達によって完成されてきた聖典です。
一方、この“特別道場・草枕”/“無門関峠の道場”は、未熟者の私が、右往左往しな
がら試行錯誤し、そこに足跡を残していくことに価値があると考えています。笑いも共感
もあると思いますが、ともかく真剣に取り組んでいます.....)
繰り返しますが、“無門関峠の道場”の各部において、この二元性の超越というこ
とが主要なテーマになっています。この“二元性超越”の概念は、その時折に別の角
度から現れ、この同じ概念を新発見し、その深さを再認識していくことになります。ま
た、自らがこの概念の新たな側面を次々と発見し、それを体現していくということは、
修行が進んでいるということを示しています。
<1> “無我”の風景
さて、修行に入る前に、第一部、第二部からの流れで、“無我の風景”というもの
を再度考察し、確認しておきたいと思います。結局、この“無我”というものの意味を
理解しておくことが、修行の近道になると思うからです。
私たちは“無心”とか、“無我の境地”といった言葉を、一度は耳にしたことがある
と思います。また、多少なりとも禅に関心のある者なら、これは趙州禅師の「無」であ
り、倶胝禅師の「1指」であり、無門禅師の「内外打成一片」のリアリティーを指し示し
ていることを理解すると思います。では、これは具体的にどのような風景なのでしょう
か。このような祖師の名言を離れ、もう少し分かりやすい私達の言葉で考察してみる
ことにします。
“無我の境地”と言うと、まず意識の中に何も無いカラッポの状態を連想するかも
知れません。むろん、これは間違いではなく、遥かな高い意識状態になると、あらゆ
る物事の形態が溶けて消えうせ、ただ光が光自身を見つめている状態になると聞き
ます。むろん、煩悩との境界線あたりをうろついている私たちには、縁遠い話ですが
...
ちなみに、道元禅師に次のような短歌があります。
花紅葉 冬の白雪見しことも
思えばくやし 色にめでけり
この世の花、紅葉、真冬の雪景色と、実にさまざまな風雅を遍歴してきた
ものだ...しかし、それも思い返せば、色をめでているわけだ。これは禅の
真髄ではない...
直訳すればこんな意味ですが、この気持ちを歌に託しておこうと言ったと
ころでしょうか...その道元禅師の風雅と、それと対立する深い解脱の超
意識を、20世紀世紀末の私たちが眺めているわけです...
さて、道元禅師は、色をめでる心を“くやし”と、言っておられるわけです。
芸術家ならば、まさにその“美”を追い求めているわけですが、二元的な“美
醜”や“色彩”や“風雅”さえも、反省の材料となるわけです。道元禅師の御
心の、遥かな深さが思いやられます...
<さあ、道元禅師を離れて、グンと目線を引き下げてきましょう...>
“無我の風景”とはどのようなものかということです...
“無我の境地”では、もちろん下らない“煩悩”は消え去っていなくてはなりません。
しかし、意識そのものが何も無い真っ白な状態というわけではないのです。目には無
意識下でも風景が流れ込んできます。音も自然に耳に入ってきます。したがって、こ
れらを無理に意識から追い出す必要はありません。むしろ、これらはあるがままに目
に映し、音は聞こえるままにまかせておけばいいのです。その上で、意識がカラッポ
であればいいのです。この“カラッポ/空”とは、何も考えていないと言うことであり、
ここが“無我”になるわけです。一口で言えば、煩悩の消えた、クリアーな無意識の
流れと言ったところでしょうか...
“動”の中でも、“静”の中でも、この“空”の状態に慣れ親しむことが“無我”の修行
ということになります。歩いている時、散歩している時、単純な仕事をしている時、修
行の場はいくらでもあります。しかし、こうした意識の状態は、求めれば散じてしまう
と言われています。したがって、こうしたリアリティーは、強く求めたりじっと見つめた
りすると、かえってそれを見失ってしまいます。車の運転と同じように、肩に力が入っ
た状態は良くないということです。
第2章/修行・・・
(1999.12.31)
  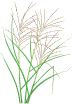
さあ、仏道の修行、禅の修業とはどの様にやったらいいのでしょうか...
また、何を求め、何が達成されるのでしょうか...
ここでは、それを具体的に考察して行きます...
この“無門関峠”は、私が鉈(なた)とコンパスで切り開いていく未踏の山道であり、歴
史的な各宗派とは無縁です。また、いきなり、庭掃除と雑巾がけというのは、いかに
も禅寺らしいのですが、ここではあくまでも文章による理解を前提とし、その上で実践
修行していくという手法を取ります。
<1> 意識のパラダイムシフト...
“悟り”とは、理解するものではなく、意識のパラダイムシフトです。
修行とは、その“無我”の真実を体現していくことです。
最近、“無門関・草枕/巌喚主人”を書きましたが、その中の “無門の頌 (じゅ)”
に適切な表現があります。大きな文章ではないので、その全文を再度ここに示してお
きます。ここには、私たちが何故、なかなか悟りに至れないかが説明してあります。
結局、その“悟り”というものの実態がわからなければ、ただ迷うばかりであり、なか
なかそこには至れないというわけです。
************************************************************** “無門の頌 (じゅ)”
<無門の頌(じゅ)> /...口語訳
求道の人が真に目覚めぬのは、
旧来の分別意識にとらわれるためである。
これは果てしない生死輪廻(しょうじりんね)のもとである。
だが愚かな人々はこれを本来の人と思い込む。
(
この詩はもともと、長沙禅師の作ったものです。無門禅師はこれを公案を評する“頌”として使っています。)
この詩の表面的な意味は、きわめて分かりやすいと思います...私たちはなか
なか、旧来の分別意識を捨てきれません。そして、それゆえに、“真”に目覚めること
が出来ずにいるということです。さあ、内容をもう少し掘り下げてみましょう...
愚かな人々は、旧来の分別意識に座標軸を置き、そこから“真”を求めています。
そして、それゆえに、“真”に目覚めることが出来ないのです。禅で繰り返し示してい
るのは、そうではなく、旧来の分別意識の“座標軸”そのものを捨てよと言っているの
です。つまり、私たちは、知らず知らずのうちに、“識神” (
阿頼耶識/あらやしき/人間の分別意
識の源 )
こそが自己の根源だと思い、それが捨てきれないのです。しかし、言い換えれ
ば、その“自己”こそが、まさに邪魔物なのです。その“自己を捨てた時”、悟りはお
のずとそこに輝いています。したがって、“悟り”とは、理解するのもではなく、“真”に
目覚めるという、“意識におけるパラダイムシフト”なのです。“識神”(阿頼耶識 )にあ
る意識の土台そのものを、“無我”という別のものと入れ替えることなのです。
道元禅師も、こう言っておられます...
仏道を学ぶということは、自己を学ぶことである。自己を学ぶということ
は、自己を忘れることである。自己を忘れるということは、総てのものごと
が、自然に明らかになることである。
( “正法眼蔵”/現成公案より )
************************************************************* “無門の頌 (じゅ)”
さて、何を修行すればいいのか...これで、だいぶ明確になってきたと思います。
これまで、
第一部、第二部で、二元論/二元性の超越が“悟り”への道だと言っ
て来ました。では、何故、座禅のような修行が必要なのでしょうか。それは、ここが
まさに理解するだけの哲学と、それを体現し実践して行く宗教との違いでしょうか。こ
の、理解から体現への過程が修行になるわけですが、修行によってさらに理解が進
むことにもなるわけです。
いずれにしても、禅は言葉の限界、言葉による理解の限界を超えた領域に展開し
ています。しかし、言葉による理解は、私にとっては唯一の伝達手段であり、“理解”
と“実践”は、今後も車の両輪のように展開させて行きます。
<2> 座禅 ・ 数息観 ...“無我”の実践
前にも何遍か述べましたが、私は座禅の“独学”は、放棄したままになっていま
す。むろん、諦めたわけではありません。ただ、都会での日々の生活に追われ、そう
した座禅をする環境にはないというのが現実です。しかし、考えてみれば、禅に興味
を持ちながらも、私のようにその環境に無いというのは、ほとんどの人の実状ではな
いでしょうか。しかし、このような都会生活の雑踏の中でさえ、禅の修業は可能だと
いうこです。私自身の禅の修業も、まさにこのような都会生活の雑踏の中で行ってい
ます。
静かな地方都市や、のどかな田園風景の中では、より恵まれた環境にあります。
また、寺院等で参禅ができれば、それに過ぎる環境は無いように思います。
さて、修行の話しに入ります...
<座禅>
むろん、座禅ができれば一番いいのです。あらゆる機会を捉え、座禅会
等に参加してください。また、多くの禅寺があり、座禅に関する多くの出版
物もあります。いずれも俗世間の未熟者の私の見解などよりは、数段優れ
たものです。是非参考になさってください。
私も、いずれは都会生活を離れ、座禅ができるような環境になることを
夢見ています。しかし、それはそれとして、私は次善の策として、最近“数
息観”というものを実践しています。これは、腹式呼吸で、ゆっくりと数を数
えていく方法です。朝夕の通勤時や、散歩の時、車の運転中、あるいは単
純作業などをしている時などがお勧めです。ただし、車の運転中はくれぐ
れも事故を起こさないようにお願いします。
<数息観>
“数息観”では、ゆっくりと息を吐き出しながら、“ひとーーー ”と、数え
てきて、それからゆっくりと息を吸い込みながら、“ーーーつ”と、10秒前後
をかけて数えます。そして、同じように、“ふたーーーーーーーつ”、“みー
ーーーーーつ”と、数えて行くわけです。10まで来たら、最初からやり直し
てもいいですし、100まで数えてもかまいません。
これは、つまり、“座禅の呼吸法”なのです。しかし、こんなことでも、し
だいに“禅定”に入っていけるものです。むろん、“禅定”に入る以前の段
階では、呼吸が安定し、非常に静かな気持ちが実現してきます。この安定
した静かな気持ちが、禅においては何よりも大切なものです。
************************************
“無門関峠の道場”では、“数息観による精神の安定”と、第一部、
第二部で言ってきた“二元論/二元性の超越” を統合させ、いわゆる
“無我の禅定” に入って行くことを目指しています。
これは言い替えれば、“座禅”と“公案の参究”であり、これがいわ
ゆる“修行”として展開して行くことになります。
***********************************
< 六祖・慧能の頓悟.../No.1>
禅宗の開祖・菩提達磨は、インドから海路で南方中国に渡ったと言われ
ます。そして、そこから陸路で北方へ向かい、“北魏”
の少林寺に入られ
ました。この大陸に真の仏法を伝えるため、高齢をおして決死の布教に
やって来たわけです。この菩提達磨以降、禅宗は中国全土で隆盛を極
め、それはやがて海を渡って日本にも伝わってきます。
日本への仏教の伝来は、すでに聖徳太子の時代に隆盛期があります。
しかし、禅宗が本格的に日本に入ってくるのは、鎌倉時代以降ということ
のようです。ちなみに、道元禅師は、この時代に大陸に渡った学僧の一人
で、日本における曹洞宗の開祖となります。
さて、初祖の菩提達磨から数えて、六祖めに慧能という人物がいまし
た。この南方からはるばるやってきた貧しい青年は、五祖の居られた黄梅
山にたどり着き、ここで米つきの仕事をもらい、修行を始めました。そして、
半年後に衣鉢を受け、追われるようにして黄梅山を去ります。
(このあたりは“無門関第23則”になっています。)
そして、後に慧能は六祖になります。が、慧能はあの黄梅山での半年
間は、終日米つきをしながら、“無我”の禅定に入っていたと言われます。
したがって、私たちも座禅以外にも、修行の方法はいくらでもあるというこ
とです。
ちなみに、この六祖・慧能の活躍した時代は、日本から渡った遣唐使・
阿倍仲麻呂が唐の宮廷で活躍した時代にほぼ一致します。しかし、禅宗
が日本に伝わってくるのはこの隆盛期の唐の時代ではなく、次の宋の時
代ということになるようです。道元禅師が中国大陸に入ったのもこの宋の
時代であり、無門禅師が大陸で“無門関”の編纂を始めたのは、道元
禅師が日本へ帰国された二年後頃と記憶しています.....
(
この六祖・慧能の話は、私の書いた短編小説、“唯心”の中で詳しく描写むしてあります。現在準備中。)
|
![]() 無
門 関 峠 の 人 間 原 理
無
門 関 峠 の 人 間 原 理
 < 第三部 >
< 第三部 >

![]()


