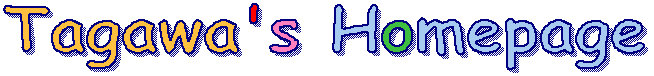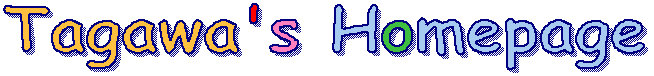|
4月下旬に滝子山に登った後、混み合うゴールデンウィーク中の登山は避けたところ、その後、所用が立て込んだ上に、
天候不順が続いたこともあって、漸く山に行けたのは 5月も下旬の 26日であった。
行き先は奥多摩の酉谷山 (とりだにやま)。この山は 3年前に登っていて 2回目となるのだが、今回は山よりもタワ尾根を登ることが主目的である。
滝子山の寂敞尾根が楽しかったことから、すぐに同じく地図上で破線コースとなっているタワ尾根が思い浮かんだものの、先に述べた状況でなかなか実行できず、漸く念願が叶ったという次第である。
5月26日(水)、4時半過ぎに自宅を出発。
横浜ICから東名高速道下り線に乗り、続いて海老名JCTにて圏央道に入って、日の出ICまで進む。
いつもならICを下りて都道184号線を西(左)へと進むのだが、新しい車のナビは東(右)を示したのでその指示に従ってみる。
184号線を 5分程進み、瀬戸岡の交差点にて左折して国道411号線に入る。暫く道なりに進んでいくと、畑中一丁目の信号にて国道411号線は右に折れるが、
小生の方はそのまま直進して都道45号線 (吉野街道) に入る。
順調に車を進め、梅ヶ谷峠入口の交差点に至ったところで、いつも走っている道となる (無論、都道45号線のまま)。
はてさて、どちらのルートが早いのであろう?
暫く道なりに進み、古里駅前の丁字路にぶつかったところで左折して再び国道411号線に入る。
そこから 10分程進み、奥多摩駅入口の交差点を過ぎたすぐ先の信号 (日原街道入口) にて右折して日原街道 (都道204号線) へと進む。
後は道なりであるが、所々、道幅が狭い場所があるので、対向車に気を付けねばならない。
川苔山の起点となる川乗橋バス停を過ぎ、日原トンネルを抜ければやがていつも利用している駐車場で、到着時刻は 6時34分。
平日にも拘わらず、既に5台の車が駐まっている。
車内で朝食をとった後、身支度を調えて 6時43分に出発する。
駐車場入口にある料金入れに 500円を投入した後、日原街道をさらに先へと進む。
すぐに前方に稲村岩が見えてくるが、駐車場では後方の鷹ノ巣尾根に紛れ気味あった稲村岩も、ここではかなりの存在感を示している。
なお、天気の方であるが、一応青空は広がっているものの、うっすらと雲のベールがかかっているのが気になるところである。
車道を 20分程歩くと、やがて道が 2つに分かれる。左は天祖山・雲取山、右は日原鍾乳洞で、
さらに、そこにある標識には右 酉谷山の文字も見ることができる。しかし、鍾乳洞の先、小川谷林道を歩いて酉谷山避難小屋へと至るコースは廃道らしい
(但し、小川谷林道から七跳尾根経由にて酉谷山に登れるようだ)。
右に道をとり、鍾乳洞方面へと進んでいくと、やがて前方左手上部に、建物の半分近くを崖上に突き出した建物が見えてくる (無論、コンクリートの架台が支えている)。
一石山神社 (いっせきさんじんじゃ)で、本日登るタワ尾根はこの神社が起点となっている。
石段を登り、まずは神社本殿に参拝する。時刻は 7時9分。
その後、神社の境内を左手に進み、社務所の左手 (こちらからは右手) から山に取り付くが、いきなり急登が始まり少し面食らう。
足下はあまり踏まれていない感があるものの、かといって不明瞭という訳ではない。息を切らせつつ急斜面をジグザグに登っていくと、立派な落石防止柵が現れ、
そこからは少し滑りやすい斜面の登りが続くようになる。
あまり踏まれているとは言い難い道も、やがてしっかりとした道に変わり、加えてやや朽ちかけて入るものの人工的な石段が所々に現れて驚かされる。
さらには、斜面を登り切ったところにベンチも置かれていたのでビックリである。
かつては結構登られた山だったのであろうか。ベンチ到着は7時38分。
ありがたいことに、ここからは傾斜も緩み、歩きやすい道が続く。
左がスギの植林帯、右が自然林の斜面を登っていくが、所々に赤テープがあるのが心強い。
緩やかな登りも、徐々に傾斜が出始め、周囲に岩が現れるようになる。やがて、いかにも石灰岩という感じの大きく白い岩を過ぎると、斜面の先に林立する大きな岩々が見えてくる。
驚いたことに、ここにも石段があってその岩場へと続いているが、途中でロープに遮られ、道は岩場への直登を避けて迂回するように左へと進む。
周囲はスギの植林帯となり、その中をジグザグに登っていく。
この植林帯を抜けると、足下は完全に岩場に変わり、道は岩の間を登っていく。
見上げれば、先ほど見えていた林立する大きな岩々の箇所は抜け出しており、すぐ先に稜線が見えている。
そして、小さな岩と土が混ざり合った斜面を登りきると、そこには東京都のマークが彫られた標石と、その傍らには 『日原 →』 と書かれた、今登ってきた道を示す標識が置かれていた。時刻は 7時57分。
ここで道は左に 90度曲がるので、上から下ってきた場合、そのまままっすぐ進んでしまわないように標識が置かれているようである。
ここからは暫くの間、幅の狭い尾根道が続くようになる。傾斜が緩やかなのが嬉しい。
すぐにまた東京都のマークが彫られた標石が現れる。事前に読んだこのタワ尾根の登山記録には、基本的にこの標石を追っていくことになると書かれていたので、標石が見つかったのはありがたい。
申し訳ないほど緩やかな道が続く。先日の寂敞尾根でもこのような場所があったが、まるで人が登るために作られたような尾根道である。
また、ここまで殺風景であった周囲の木々の中に朱色の花をつけたヤマツツジが見られるようになる。
もうそろそろ一石山のはずと思いながら、周囲に目を配りながら進んでいくと、細い木に括られた 『一石山 1007m』 の小さな標識を見つける。
時刻は 8時1分。
一旦少し下って登り返すと、そこからは左がスギの植林帯、右が自然林といった形の尾根をほぼ直線的に進むことになる。傾斜も緩み、ほぼ平らと言って良い状況が続くのが嬉しい。
やがて、再び傾斜が現れ始め、その斜面を登り切って植林帯を抜け出すと傾斜もほぼ無くなり、さらにはその少し先で斜面が広くなる。
一旦窪地に下りた後、その先の土手のような高みに登っていくのだが、足下は落ち葉の絨毯になっており、踏み跡が不明瞭、少し不安を抱きつつ目の前の高みに登る。
嬉しいことに、尾根に登り着くと赤いテープが見つかったのでホッとする。
テープに従って進路を左にとり、やや狭くなった尾根を進む。
傾斜はほとんどない土手のような道が続く中、やがて先の方に、右手を挙げてゴールするロードレーサを想像させる赤ペンキ印が描かれた木が見えてくる。
そして、その木の裏には 『人形山(にんぎょうやま)』 と書かれた標識が架かっていたのであった。時刻は 8時25分。
展望はないものの、周囲を見渡すと、驚いたことに 『人形山』 と書かれた標識が沢山見つかる。中にはカラフルなものもあり、これがウトウの頭にある有名な標識までのプロローグとなる。
人形山から一旦下ると、右手に、小さな岩が乗っかっている岩が見える。その形が人形に見えなくもないので、
この山の由来になったのではないかと勝手な想像を巡らせる。
ここからも暫くは歩きやすい、土手のような形状の尾根が続く。その尾根がやがて広い尾根に変わると、少し先に 『金袋山(きんたいさん)』 と書かれた標識が見えてくる。
山の名の通り、金袋を形取った手の込んだ標識であるが、下部が剥ぎ取られたようになっていたのは熊の仕業であろうか。時刻は 8時50分。
ここからも緩やかな道が続く。道が緩やかに右にカーブした後、広かった尾根もやがて狭くなり始めたところで、足下にギンリョウソウを見つける。山でこの草を見るのは何年ぶりであろう。
土手のような道は少し狭くなったり広くなったりと変化するものの、傾斜は総じて緩やか、木漏れ日の中、新緑を楽しみながら進む。
やがて、緩やかながらも登り着いたピークに 『篶坂ノ丸(すずさかのまる)』 と書かれたカラフルな標識を見つける。
時刻は 9時14分。
ここの標高は 1,456mなのだが、目指すウトウの頭が 1,588.0m、そして酉谷山が 1,718.3mなので、駐車場をスタートしてから約2時間半にも拘わらず、
まだまだ道遠しといったところである。
ここで休憩すれば良かったのだが、休むに適した岩とか倒木も無かったので、飲み物を口にしただけで先へと進む。
少し進むと、基本的に登り一辺倒だった道に変化が現れ、木々の幼木が多く生える斜面を下るようになる。
しかし、それも長くは続かず、再び登り斜面に入るが、傾斜は緩やか、時々平らな道も現れる。
左手樹林越しには天祖山と思しき山が見えるものの、木が邪魔をして見通すことができない。
暫く進むと、今度は右手樹林越しにチラリと山が見える。目指す酉谷山かと思ったが、その山の右に小さな高みがあるので、恐らく日向谷ノ頭、そして坊主山であろう。
スッキリと見通すことはできないものの、ここまで展望を得られなかっただけに、山がほんの少し見えただけでも元気が出てくる。
暫くは緩やかな尾根道が続く。歩きやすいのはありがたいが、その分、なかなか高度が上がらないため、後半が厳しくなりそうである。
周囲は緑の木々が多いものの、この辺の足下には下草が全く見られない。
やがて、少し傾斜が出始めると、周囲には岩が現れ始める。岩は白いのでこれも石灰岩と思われる。
この奥多摩の山々は火山活動によって形成されたものではなく、かつて海底に堆積した地層が隆起したもので、主に花崗岩や石灰岩からできているとのことである。
そのため、秩父の武甲山と同様にセメントの材料となる石灰岩が多く採取されている。
実際、この尾根の西側にある天祖山の北東側斜面は石灰岩採取のため大きく削られている。
岩場が続くかと思われた斜面であるが、すぐに岩場は終わりとなり、再びごく普通の斜面が続く。
斜面の先を見やれば、尾根の先に空間が見えるので、もしかしたらウトウの頭ではないかとの期待が出てくる。
しかし、それ程甘くはなく、登り着くと道は左へとさらに尾根上を進むことになる。ただ、嬉しいことに右手の展望が先ほどよりも開けるようになり、
日向谷ノ峰、坊主山、そして七跳山 (ななはねやま) 方面が見通せるようになる。
ここからは細い尾根のアップダウンが続く。木の根がむき出しており、岩屑が散らばっている道を進む。傾斜が然程ないのがありがたい。
木の根が絡みついている小さな岩場を、足下が柔らかい道を辿って左から迂回していくと、すぐに歩きやすい斜面となり、
登り着いたところには三等三角点が置かれていた。ウトウの頭に到着である。時刻は 10時2分。
ここには有名な標識が 2つあり、一つは何と陶板製、もう一つは木製で、どちらにもウトウ (海鳥の一種) が描かれている。
ただ、木製の標識の方は木の根元に落ちていたので応急的に木に括り付けたが、後から思えば、もう少ししっかりと留めるべきであった。
この頂上で暫し休憩。ここからは樹林越しに天祖山の石灰岩採取現場、そして雲取山を見ることができる。
10時9分に出発、先へと進む。ここからは下りが続く。
下っている最中、サイレンが鳴り、その後にドーンという音が聞こえる。石灰岩採取のために発破を仕掛けたのであろう。
下り着いた所からはまた細い尾根道が続くようになる。小さなアップダウンを繰り返しながらこの細い尾根を通過すると、道は登り斜面に変わり、途中から周囲に岩が現れるようになる。
やがて大岩が現れるが、その岩を左側から迂回すると、道は下りに入り、少し広い鞍部に達した後、再び登りが始まる。
道は谷の突端を詰めていくような感じで斜面を登っていく。所々に見られる赤テープがありがたい。
谷を詰めて支尾根の一つに登り着けば、そこからは岩場となって、少し道に迷ってしまう。
薄い踏み跡を辿って、岩の左側を進むと、すぐに右上に青、赤のテープが見つかる。岩と木の根、そしてフカフカして滑りやすい斜面を登って、岩場の上部に登り着けば、すぐに歩きやすい尾根道となり、
その先でモノレールが現れる。時刻は 10時42分。
道は一旦モノレールから離れて小さなピークに登るが、そこには 『大京谷ノ峰』 と書かれた標識が木に括り付けられていた。
時刻は 10時44分。
道は再びモノレールと合流した後、暫くの間、モノレールに沿って進んでいく。
モノレールが設置されるだけあって傾斜は緩やか、歩きやすい。
一方、この頃になると天候の方は曇り気味になり、時々雲が切れて日が差すという状況に変わっている。
小さなアップダウンを繰り返しながらモノレールに沿って歩く。
周囲には紅紫色の花を咲かせたミツバツツジ (と思う) が見られるようになる。途中、『1,500m/1,780m』 と書かれた標識があったが、
これは標高では無くモノレールの長さを表しているものと思われる。
ということは、あと 280m モノレールと平行して歩くということである。
やがて、モノレールは一旦下った後、今までに無い上り勾配を進む。そして、登り着いて前方を見ると、モノレールの車体が停まっており、ご丁寧なことに、
そこには 『終点(1,780m)』 と書かれた標識が置かれていた。時刻は 11時4分。
ここまで来れば、都県境尾根はもうすぐである。暫くは土手のような尾根道を辿る。
途中、嬉しいことに左手に雲取山、芋木ノドッケ (芋ノ木ドッケ) を見ることができたが、その後方に青空は無く、雲が多かったので、本日、酉谷山からの富士山は期待できないようである。
ほぼ平らだった道も、広い斜面にぶつかり、斜面をジグザグに登っていく。
そして、11時12分、滝谷ノ峰 (タワ尾根ノ頭) 直下の縦走路に登り着く。この道を左に進めば長沢山、芋木ノドッケに至り、酉谷山は右である。
しかしその前に、目の前の滝谷ノ峰に登るべく縦走路を横切ってそのまま斜面に取り付く。
斜面につけられた薄い踏み跡を辿る。
最初は傾斜が少し急であるが、一登りすれば傾斜は緩み始め、ミツバツツジの小群落を過ぎると、傾斜はさらに緩んで、頂上も近いことが察せられる。
しかし、倒木を避けながら 1つ目のピークに登り着いたものの、ここは滝谷ノ頭頂上ではないようである。
さらに先へと進み、2つ目、3つ目のピークに至ったが、滝谷ノ頭の標識が見つからない。
少し疲れてきたので、11時27分、4つ目のピークにある境界見出標に腰掛けて食事とする。
地図を見ると、このまま先に進めば水松山 (あららぎやま)、長沢山、芋木ノドッケに至ってしまうので、どこかで東(右)へと進まねばならないと知る。
しかし、その取り付きが分からないこと、さらには肝心の滝谷ノ峰の頂上が不明なこと、そしてこの時間になると完全に曇り空となってしまって雨の心配まで出てきたことを考慮し、
先程の縦走路まで戻ることにする。
11時38分に出発、辿って来た道を戻る。
途中、何気なく見上げると、何と 『滝谷ノ峰』 と書かれた立派な標識が木に括り付けられているのが目に入る。
これでストレスを貯めることなく酉谷山へと進むことができる。時刻は 11時42分。
となると、ここから東に進めば尾根伝いに酉谷山へと行くことができるはずであるが、先にも述べたように雨の心配もあるため、
安全を期して縦走路まで戻ることにする。
その縦走路には 11時48分に到着。左に道をとって酉谷山を目指す。ここからは 3年前に通った道なので、もう安心である。
滝谷ノ峰の山襞に沿ってつけられた道を進む。さすがに正規の道だけあって良く整備されていて歩きやすい。
12時11分に滝谷ノ峰から下ってくる尾根と合流し、そこからさらに少し進むと、酉谷山直登ルートの分岐点 (行福のタオ) に至る。
時刻は 12時17分。
左に道をとって山頂に向かう。なお、右は酉谷山を巻いて避難小屋へと至る道である。
少々疲れが出始めた身にとってこの登りは辛いが、急登はないと知っているのでゆっくりと登っていく。
やがて左手樹林越しに両神山が見えるようになる。少し靄っている中にボッーと浮かび上がるギザギザの山容はなかなか魅力的である。
小さなピークに登り着くと、その先に酉谷山の頂上が見えてくる。もう少しである。
そして、12時46分、酉谷山の頂上に到着。頂上には誰もいない。
ここからの展望は良いのだが、思った通り本日、富士山は見えない。
それでも、南東方向に本仁田山、御岳山、そして大岳山が確認でき、大岳山の右手前からは雲取山に向かって石尾根が始まっている。
石尾根ではまず六ツ石山が確認でき、その左後方には御前山がその山頂部分を見せている。石尾根は稲村岩尾根と合流した後、鷹ノ巣山に至り、その右に日蔭名栗山、高丸山が続く。
本来ならば、高丸山の右後方に富士山が見えるはずである。
なお、登ってきたタワ尾根も見えるものの、少々木が邪魔をしている。さらには、少し場所を移動すれば雲取山も見ることができるが、こちらも木々が邪魔である。
正面の鷹ノ巣山を見ながら食事をした後、13時丁度に出発する。緩やかに下り、土手のような尾根を進んでいくと、
やがて 『右 酉谷山避難小屋』 の標識が現れるので、尾根を外れて右に下る。時刻は 13時10分。
すぐに避難小屋の屋根が見えてくるが、その手前で先ほど分かれた酉谷山を迂回する道と合流するので (酉谷峠)、左に曲がって縦走路を進む。時刻は 13時11分。
ここからは再び都県境尾根を進む。アップダウンの少ない歩きやすい道が続く。左側の山に取り付いて尾根上を進むこともできるようだが、日向谷ノ頭、坊主山はパスする。
急斜面のキワに設置された木製の桟道を渡った後、暫く進むと、縦走路から外れて左の山に取り付く道がうっすらと見えている場所に到着する。
ここがどうやら七跳山への登り口らしいと検討をつけ、縦走路を外れて山に取り付く。時刻は 13時48分。
緩やかな斜面を登っていく。この山に登る人も多いのだろう、斜面には明確に道ができている。やがて、『山』 と彫られた標石が立つ場所に登り着いたものの、
ここは七跳山の頂上ではないようである。
さらに進んで、小さなピークに登り返せば、そこが七跳山の頂上で、『山』 そして 『秩』 という文字と 『32』 という数字が彫られた標石がある他、手作りの標識が木に括られている。
時間は 14時2分。
喉を潤した後、東へと進む。ここで北の方へと進めば、大平山へ行くことができるようであるが、さすがに体力的に厳しいと思い、
素直に縦走路へと下る。正規の縦走路には 14時14分に合流、再び歩きやすい道が続く。
暫く進むと、左側の斜面に岩が多く見られるようになり、その後、斜面を横切る桟道が続くようになる。ここが石橋の岩場と呼ばれる場所のようだ。時刻は 14時20分。
この桟道を過ぎると、縦走路の周囲にシロヤシオが多く見られるようになる。これはなかなか見事。白い花が咲き乱れる中に濃いピンク色の花も見られるが、こちらはアカヤシオではなく、
ミツバツツジのようである。
しかし、このシロヤシオの群落を通り過ぎると、周囲に一切花が見られなくなるから不思議である。
順調に進んでいくと、やがて天目山の取り付き口が現れる。
これはショック。ハナド岩に立ち寄ってタワ尾根、石尾根を眺め、天目山は省略するつもりだったのだが、先程の大きく左にカーブするところがハナド岩への分岐だったようで、
ウッカリ標識を見落としてしまったようである。
こうなっては、天目山に登らざるを得ない。縦走路を外れて左に道をとり、斜面を登る。時刻は 14時52分。
傾斜は然程キツクないが、疲れた体には厳しい。それでも何とか登り続け、小さなアップダウンを経て最後の登りに入る。
その登りに入る手前で満開のシロヤシオに元気をもらう。
斜面の先にある岩に大きな赤丸の印が見える。これは記憶通りである。
何とか斜面を登り切り、灌木が密生する中を泳ぐように進んでいくと、やがて上方に頂上標識が見えてくる。
天目山到着は 15時5分。やはり富士山は見えない。
それでも東の方角には蕎麦粒山が見え、その右に川苔山、その右に本仁田山が続く。本仁田山の右後方には大岳山がシルエット状に見え、さらに右に御前山も見えている。
御前山の右手前からは石尾根が始まり、六ツ石山、鷹ノ巣山、日蔭名栗山、高丸山、七ツ石山と続いて、酉谷山からは見えにくかった雲取山に至っている。
雲取山の右手には芋木ノドッケ、白岩山も見ることができる。
雲取山の手前には天祖山も確認でき、天祖山の前をウトウの頭を中心としたタワ尾根も見えている。
また、目を凝らせば六ツ石山の右後方に三頭山も確認できる。
15時7分に下山開始。南へと下る。この天目山には三ツドッケの名もあるように 3つのピークがあり、先ほど登ってきた道に 1つ、
そしてこれから下る先にもう 1つピークがある。
そのため、一旦大きく下った後、登り返しがあるのだが、さすがにこの頃になると短い距離ではあるものの登りは辛い。
それでも何とかピークをクリアし、一杯水避難小屋に向かって下る。
その避難小屋には 15時24分に到着。小屋の南側のベンチにて休憩する。
なお、前回ここで休憩した際には、テーブルもあったのだが、今は完全に撤去されてしまっている。
15時27分に出発、ヨコスズ尾根を下る。滝入ノ峰に登るバリエーション・ルートの取り付きを 15時56分に通過。
長く単調なスギ林の中の道を下り続け、東京都水道局日原第二配水所前に 16時43分に到着する。
この先 民家があるので、ザックの熊鈴を音がしないように手当てし、5分程休憩した後、登山道取り付き口には 16時57分に到着。
駐車場は左だが、ここはまっすぐ進んで日原街道へと下る。これは郵便局前の自動販売機に立ち寄って飲み物を購入するとともに、バス発着所のトイレ利用のためである。
そして、駐車場には 17時5分に戻り着いたのであった。
本日は、かねてから興味を持っていたタワ尾根に挑戦したのだったが、なかなか楽しい山旅であった。
ただ、曇りになってしまい富士山を見ることができなかったこと、そして長い距離に少しバテてしまったことが心残りである。
それにしても、初めてのコースを辿ることは大変楽しい。今後もこのようなコースにチャレンジしたいものである。 |