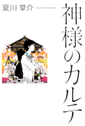|
余りに持ち上げられていると、かえって胡散臭く思ってしまい、読むのは止めておこうかと思ってしまうのが、少々へそ曲がりな私の性分。
そんなことで気にはなったものの、読むのは見送ろうと一旦決めた本書、手に取ったのはたまたまそこに借出しできる状態で本書があったから。
確かめる意味で一応読んでおこうか、と。
舞台は信州・松本平にある民間の一病院、本庄病院。
同じ松本平にある信濃大学医学部付属病院の病床数
600床には及ばないものの
400床と一般病院としては相当に大きい。
しかし、実態は大違い。慢性的な医師不足により、連続の徹夜で3日間睡眠を取れないまま、専門外の外科の治療をすることも日常茶飯事。
そんな苛酷な現場で日々診療に明け暮れる青年医師、栗原一止が主人公。本庄病院に勤務して5年目、新婚ちょうど1年。
この主人公が、かなり変わり者。漱石「草枕」が愛読書で、その影響を受けて口の聞き方がまるで漱石作品の登場人物のよう。その所為で変人として有名だが、患者や看護師からの医師としての信頼感は篤い、という人物。
地域医療の最前線における苛酷な状況、睡眠不足で疲れ切った顔の医師に点滴される側の方が不安ではないか、と主人公は自嘲して止まない。
そんな本庄病院の状況と対比されるのが、先進的な医療を担い、その一方で治療の及ばない患者を見捨てて恥じない大学の医局。
大学医局と一般病院のあり方も含め、最前線医療の実態をレポートのように伝える小説になっています。
その一方で、主人公である栗原医師、彼が新妻のハルさんと住む元旅館と言う古いアパート“御岳荘”の住人たち等々、登場人物のキャラクターはかなり仰々しく、戯画的。
そうした戯画的な部分に重きを置かず、現代医療の実態、そして医療とはどうあるべかを考えてみるところに、本書を読む意味はあるのではないかと思います。
満天の星/門出の桜/月下の雪
|