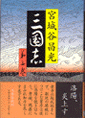|
|
|
11.奇貨居くべし・春風篇 12.奇貨居くべし・火雲篇 13.奇貨居くべし・黄河篇 14.奇貨居くべし・飛翔篇 15.奇貨居くべし・天命篇 16.管仲 17.香乱記 18.三国志・第1~2巻 19.三国志・第3巻 20.三国志・第4巻 |
|
【作家歴】、重耳、晏子、孟嘗君、楽毅、星雲はるかに、太公望、華栄の丘、子産、沙中の回廊 |
|
三国志(第5~12巻)、孔丘 |
| 公孫龍(巻一)、公孫龍(巻二)、公孫龍(巻三)、公孫龍(巻四) |
|
●「奇貨居くべし・春風篇」● ★★ |
|
|
1997年6月 2002年2月 |
秦・始皇帝の父とも言われる呂不韋 の、少年期から始まる人間としての成長物語。 面白いです! 今、というより、これからどんどん面白くなるような予感があって。何も知らない賈人(商人)の子・呂不韋が旅により瞬く間に成長し、無限の可能性を見せ始めるという筋立てにわくわくしてしまいます。とりあえずストーリィは、韓から趙へ。ただ、惜しいかな、これからという時に本巻は終了。続編がとにかく待ち遠しいです。 本篇は、孟嘗君の話もチョコッと出てきて、秦の実力宰相・魏ゼンが辞任するところまで。 ※「奇貨居くべし」とは、(呂不韋がこのように言って、後に秦の始皇帝の父となった人物を援助した故事から)珍しい品物だから後日利を得る為に今買っておこう、との意味。転じて、得難い機会だからうまくこれを利用しなければならない、の意味。(岩波書店・広辞苑から) |
|
●「奇貨居くべし・火雲篇」● ★☆ |
|
|
1998年3月 2002年2月 |
本巻は、前巻のような呂不韋の冒険的活躍はありません。むしろ、前巻で飛躍のきっかけをつかんだ呂不韋が、更に賢人たちと出会い自らを切磋琢磨し、成熟していく過程の内容です。その分ストーリィ としては面白みに欠け、ちょっと物足りないという印象。 ストーリィそのものは、藺邑が秦軍に襲われ、高告の家に滞在中だった呂不韋は捕虜として秦に連行され強制労働につかされる。その時知り合うのが孫子(筍子)。そこから脱出した後知り合うのが高名な人相見・唐挙、さらに孟嘗君にも出会い、薛の賓客として遇される。趙から秦へ、そして楚、魏、さらに薛へ |
|
●「奇貨居くべし・黄河篇」● ★★ |
|
|
2002年3月 |
1年ごとの刊行のため、以前のストーリィを忘れているというのが辛いところです。まとめて読むのが良いのは判っているのですが、ここまできたらもう止められない。 本編は、孟嘗君亡き後の波乱を経て、呂不韋がいよいよ自立し、躍進の兆しを見せ始めるという部分です。それだけに今後への期待、楽しみを呼び起こしてくれます。(でも1年後かあ...) |
|
●「奇貨居くべし・飛翔篇」● ★☆ |
|
|
2000年7月 2002年3月
|
毎年1冊ずつ刊行されて今回が4冊目。さすがに、3巻までの内容の記憶が薄れていて、興がもうひとつ乗り切れません。もうひとつ、宮城谷さんの作風も関係していると思います。 本巻は、いよいよ呂不韋が商人の道を踏み出す経緯一切。ただし、商人といっても、政商と言うに近い印象を受けます。 そして、本書の終盤において不韋は“奇貨”を手中とし、更なる大きな一歩を踏み出します。 次巻への期待が高まる一冊。 |
|
●「奇貨居くべし・天命篇」● ★★☆ |
|
|
|
漸く全5巻完結。ほっとした思いもあります。4年にわたり順次刊行されてきただけに、最初の方の記憶が薄れてきたこともありますし、いい加減結末を読みたい!という時期に至ったこともあります。 秦の丞相の地位にのぼった呂不韋がとった行政・外交は、従来とは違って民の視点から見直したものだと宮城谷さんは語ります。即ち、権謀術策=国の外交としていた従来の考え方を排除し、広く人の世から認知され得る行動を常とすること。 それは、呂不韋が貴人の出身ではなく、賈人(商人)という最下級とされた平民の出身だからこそ、それに加えて広く世の中を渡り歩いてきた経験があったからこそのこと。 また、これまでの呂不韋の行動ぶりも、けっして無理をせず、地道な努力を重ねたもの、自分だけの利益を考えることがなかったこと。そこに、従来の英雄とは一味違った呂不韋の魅力があります。 そして、呂不韋における国家運営の目的は、広く民を幸せにできる国を創るというものでした。それだけに、この長編には爽やかさ、気持ちの良さがあります。宮城谷作品の中でも、「孟嘗君」「楽毅」と並べて記憶に留めたい作品です。 現実社会でも、裏で画策すること=能力であると誤信している会社人間が多くいます。そうした人達は、本書から呂不韋という人物の健やかさを感じることができるのでしょうか。 |
|
●「管仲(上下)」● ★★ |
|
|
2006年7月
|
「管鮑の交わり」という言葉にて名高い、春秋時代初期の斉の名宰相・管仲を描いた作品。 名宰相に加え、覇者・桓公も登場する作品ですから、これまで宮城谷作品を読み続けた人であれば、読み逃すべきではない作品と思います。 とはいうものの、ストーリィとしては、時代を自力で切り開いた他の人物たち(各作品の主人公)の物語に比べると、起伏に乏しいのは事実。ストーリィ自体としては、面白くて夢中になるというものとはちょっと異なります。 その理由は、管仲が名宰相と称えられるに至ったのは、鮑叔というこれもまた稀な人物による推挙であり、桓公という稀にみる名君にまみえた故と言えるからです。 本書は、まず鮑叔と管仲の邂逅から語り起こされます。 本書は、鮑叔、管仲、桓公、そして鮑叔と管仲に仕えて彼らを支えた周辺人物たちを描く、見事な人間ドラマと言えます。 |
|
●「香乱記」● ★ |
|
|
2006年4-5月
|
秦の始皇帝の時代、故国・斉の独立を目指して立ち上がった田家の三兄弟、その末弟・田横を主人公とする歴史小説。
著名な人相見の許負から将来王になると予言されたものの、生命を狙われて斉を出奔せざるを得なくなった田横は、始皇帝の太子・扶蘇の元に至り厚遇を得ますが、始皇帝死去後に幾多の軍が乱立するという激動の渦中に身を置くことになります。
著者の宮城谷さんは「田横は僕の理想像」といいますが、正直なところ、田横という人物についてそれ程強い印象は受けません。 始皇帝後に項羽と劉邦が覇権を争った歴史だけでなく、斉という国の自立を守ろうとした田横という歴史があったことを知る点で、本書は興味深い。しかし、田横について観念的に過ぎ、また迫力という面でも、物足りないままに終わった作品。 |
|
●「三国志・第1~2巻」● ★☆ |
|
|
2004/10/30 |
北方謙三「三国志」を読み終えて間もないためパスするつもりはなかったのですが、図書館の新着本棚にちょこんと残っていたため、つい手が出てしまいました。 第1巻はまだ後漢王朝の時代。 |
|
2004年10月 2008年10月 2004/11/18 |
第1巻に引き続き、後漢王朝の衰退していく様が克明に描かれます。悪臣がのさばる一方、良臣の処せられることが繰り返され、誠に暗澹たる気分になります。もっとも、宮城谷さんの意図が衰退王朝の原因を実証するということであれば、相応の意義あることかもしれません。 悪意に満ちた帝の外戚・梁冀亡き後、今度は宦官が専横を極めます。そのどちらにしても国が乱すという意識、その結果を理解する器量のかけらも無かったという指摘には、国が滅びるというのはそんなものかもしれないと思います。 |
|
●「三国志・第3巻」● ★☆ |
|
|
2009年10月 2005/04/10 |
とにかく登場人物が多い。誰が誰でどんな人物なのか、とても記憶と整理が追いつきません。そのため、もうひとつ作品の中に入り込めないというのが、正直なところ。 前半は黄巾の乱とそれに振り回されるかのように勃興しあるいは没落する要人らの姿が描かれます。この辺りがとても整理の追いつかないところです。
北方謙三「三国志」は、3人の英雄たちに主眼を置いた英雄譚でしたが、本シリーズはそれとは異なり、この動乱と激動の時代を俯瞰的に見るところに特色があることが判ってきます。 |
|
●「三国志・第4巻」● ★ |
|
|
2009年10月
|
群雄割拠し、ますます混乱は深まっている巻。 どうしても北方謙三「三国志」と比較してしまうことが多いのですが、北方版「三国志」が英雄を画いた歴史エンターテイメントとしての色彩が強いのに対し、宮城谷版「三国志」は歴史を淡々と、俯瞰的に画いていくという姿勢が感じられます。 なお、この混乱に満ちた世界で誰が生き残り、誰が死んでいくのか。そしてその岐路はどこにあるのか。 |
宮城谷昌光作品のページ №1 へ 宮城谷昌光作品のページ №3 へ