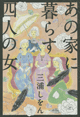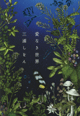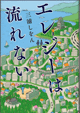| ●「シティ・マラソンズ City Marathons」● ★☆ | |
|
2013年03月
|
3人の女性作家による、NY・東京・パリという3都市のシティマラソン・ストーリィ。 まずは、三浦しをんさんの「純白のライン」。 それと対照的にあさのあつこさんの「フィニッシュ・ゲートから」は、人生ドラマ含み。しかし、「純白のライン」で単純な楽しさを味わった後となると、ドラマを作り過ぎ、という印象です。 近藤史恵さんの「金色の風」は、冒頭にミステリ風味あり。こちらも人生ドラマ風ですが、若い女性が主人公であるだけに瑞々しさがあります。パリを舞台にしての再スタート・ストーリィ。 いずれにせよ、女性作家3人各々の持ち味を生かした、シティマラソン・ストーリィ。主人公たちと一緒になって走り出す気持ちで楽しめます。 |