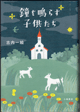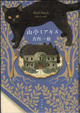| 「キネマトグラフィカ Kinematographica」 ★★ | |
|
2022年03月
|
老舗映画会社に入社した“平成元年(1989)組”と呼ばれた同期の男女6人。その入社から2018年の現在に至るまでの彼らの軌跡、そして彼らの4年目当時を回想として描く連作風長編。 6人の内4人は営業部に配属され、ローカルセールス、つまり地方の映画館を廻り、自社が手掛けた作品を上映してもらうという営業担当。 ・仙道和也は元山岳部。平凡なただのオヤジにだけはなりたくないと考えている。 ・水島栄太郎は映画好きで詳しく、自分こそ有用な人材と自負。それなのに現実はここでも余り者扱い。心を病んでいく。 ・葉山学はいい加減な男。楽ちんで楽しければそれでいい、という考え方。ちっとも学ばないところから仇名は「マナバヌ」。 ・北野咲子は初の女性総合職。映画に詳しい上に美人、努力家。しかし、いつも「女性」扱いされることに鬱積は絶えず。 ・小笠原麗羅は縁故入社の帰国子女で、咲子と同じ初の総合職、国際部配属。孤立を恐れず、旧弊なやり方を打ち破っていく。 ・小林留美は短大卒で、欠員補充の採用。25歳で結婚・子供2人が親から植え付けられた目標。しかし、相手を見つけられず。 仕事に夢、そして自分の能力を信じて、会社に入社してくるものだと思います。 しかし、現実は思ったより厳しく、夢ばかり語っていられないもの。そして、自分自身はというと格別な能力はなく平凡な一社員に過ぎないと思い知らされるもの。 本書に登場する6人、ことごとく性格もタイプも異なるという設定。したがってそれぞれの26年間も実に様々。 彼らの背景に、映画業界そのものの衰退がリアルに描き出されるところが興味尽きないところ。 主役は上記6人と言いつつも実際に印象が強いのは、“女性”というレッテルを貼られて我慢を重ねつつ、プロデューサーという地位を手に入れた咲子と、彼女の盟友である麗羅の2人です。 女性総合職のフロントランナーであった彼女らの苦労は、今からすると涙ぐましいばかりですが、といって現在でもその苦労が全く無くなったとは言えないように思います。 振り返るのは、また新しく踏み出すためであって欲しいと、信じたい。まだまだ人生は続くのですから。 2018年 桂田オデオン/1992年 発端 登録担当 小林留美/1992年 リレーその1 北関東担当 水島栄太郎/1992年 リレーその2 関西担当 仙道和也/1992年 リレーその3 東海担当 葉山学/1992年 リレーその4 九州担当 北野咲子/1992年 到着 海外事業担当 小笠原麗羅/2018年 桂田オデオン |