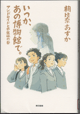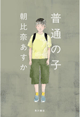| 「君たちは今が世界 All grown-ups were once children」 ★★☆ | |
|
2021年07月
|
小学6年生のクラスを舞台にした、小学生たちの連作ドラマ。 6年3組のクラスは男子、女子それぞれのリーダー格生徒が傲慢に担任を舐め切り、好き放題に女性教師を馬鹿にしている。 本来それを止めるべき立場の優等生は孤立させられ、誰もそれを抑えようとしない。 そしてついに、調理実習中に洗剤が混入するという事件が起き、担任する生徒たちを見切った幾田先生は、ある言葉を残して去っていく。 大人を馬鹿にし、誤ちを誤ろうともせず、逆に自分たちの有利性を主張する。その傲慢さ、身の程知らずには、嫌悪感を抱くばかりです。 しかし、彼らは本当にもう救いようのない子供たちなのか。 その子供たちの中に、あるいは子供たち同士の中に、葛藤や苦悩はなかったのでしょうか。 そうした問題があるかどうか、深く踏み込もうとせず、早々と生徒たちを見捨ててしまった幾田先生の行動は、教師とはいえやむを得ないものだったのか。 第一章の主人公は、友達といいながら、リーダー格生徒から格好のおもちゃにされているような男子生徒=尾辻文也。 第二章は、成績優秀だがクラスの中で身を縮めているような女子生徒=川島杏美。 第三章は、コミュニケーション障害のある生徒=武市陽太。 第四章は、傲慢・不遜な女王さまである前田香奈枝の隣にいることに、自分の位置を見出している見村めぐ美。 そして、それ以外にも、生徒たちの様々な姿が描かれます。 とにかく冒頭の「みんなといたいみんな」が圧巻。 息詰まるような展開、その迫力はもう言葉にはできない程。 子供であればこそ、多少の過ちを犯すのも仕方ないこと。 しかし、子供たちに一生取り返しのつかないようなことをさせてしまってはいけない、そんな状況に追い込んでしまってはいけない、それを留めるのが大人の役目、と思います。 それらを子供たち、先生たちと一緒に考えたくなる作品です。 ※幾田先生や山形先生と対照的に、「麦わらさん」「まっすぅのお母さん」が貴重な救いとなる存在と感じられました。 1.みんなといたいみんな/2.こんなものは、全部通り過ぎる/3.いつか、ドラゴン/4.泣かない子ども/エピローグ |