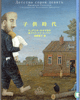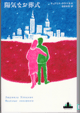ポーランド生まれのユダヤ人=ダニエル・シュタインは、ユダヤ人であることを隠してゲシュタポで通訳として働き、ナチスのゲットー襲撃から
300人のユダヤ人を脱走させて救う。そして自らも脱走した後、カトリックの神父となりイスラエルへ渡る。
本作品は、実在のユダヤ人カトリック神父をモデルにした長篇小説。
上下2巻にわたる大長篇ですが、漫然とダニエル・シュタインの生涯を語っていくのではなく、数多くの人の述懐、往復書簡、手記、日記、会話テープ等々をもって、時代も1950年代、60年代、80年代、現在と自在に前後して綴っていくという構成。
そうした構成があって、当時ポーランド等でのユダヤ人迫害によって苛酷な運命を送ることになった人々の姿や、ユダヤ人であるのにカトリック神父となりしかもイスラエルへ渡ったダニエル神父、戦後にダニエル神父と関わった人々の人生が、立体的に浮かび上がっていくという、素晴らしい作品になっています。
クレストブックスでの上下2巻というと、かなり読むのに重たいという気がしてしまいますが、上記構成のおかげで軽やかに、興味尽きず読み進むことができます。
本書に描かれているのは、多くの人々の苦難に満ちた人生。
子供を捨ててパルチザン運動に身を投じた人もいれば、その結果母親に捨てられたという思いをもって成長した娘もあり、修道院に受け入れられずイスラエルに渡って新たな人生を見い出した人もいます。
その他、ユダヤ人であるにもかかわらずキリスト教徒ということを通じて、ユダヤ教、キリスト教を比べて考える部分もあるといったように、本書ストーリィは国境を軽々と越えて実に多彩。
その多彩さが生きてくるのも、全てを淡々と、そして悠然と受け入れて躊躇することない、本書主人公ダニエル・シュタインという人物の魅力があってこそなのは言うまでもありません。
題名に「通訳」と冠されていますが、実際にダニエルが通訳の仕事を勤めたのは一時期のことに過ぎません。したがってその言葉の意味は、ダニエルが多くの人々の橋渡しをしてきたことを示していると解すべきでしょう。
ありとあらゆる小説の素材が盛り込まれている傑作長篇、頁数だけをとると長大な作品ですが、実際に読んだ印象は軽やかです。
是非お薦めしたい名作です。 ※ダニエル・シュタインのモデルとなったのは、オスヴァルト・ルフェイセン(1922−98)、キリスト教改宗後ブラザー・ダニエルと呼ばれた人物。正体を隠してゲシュタポで通訳を務めたことを初め、ローマ教皇ヨハネ・パウロ二世と旧知の間だったことも含め、本書ダニエル・シュタインのエピソードの多くは、全て事実に基づくものだそうです。作者のウリツカヤ自身、92年に本人と会って人物に魅了されたとか。
|