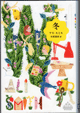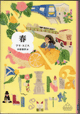| 1. | |
|
「両方になる」 ★★ ゴールドスミス賞・コスタ賞・ベイリーズ賞 |
|
|
2018年09月
|
15世紀のイタリア人画家の物語と、21世紀の英国人少女の物語、2つの物語を繋ぐ長編小説。 前半の「第一部」は15世紀、イタリア人画家=フランチェスコ・デル・コッサの物語。 しかし、このフランチェスコ、実は女性。当時、画家になれるのは男性のみ。そのため、画家を目指した時からフランチェスコは男性として生きてきたという経緯。 一方、後半の「第一部」は21世紀、英国に暮らす17歳の少女=ジョージ(ジョージア)の物語。母親を突然病気で失った後のジョージの、母親との思い出、クラスメイトのヘレナ・フィスカー(H)との関わりが描かれます。 気になるのは、前半と後半、「第一部」と「第二部」ではなく、同じ「第一部」と題されていること。 この意味は、連なる関係にあるストーリィではなく、パラレルワールドのように互いに並列した関係にある、ということではないでしょうか。 そして次に気になることは、2つの物語をそれぞれ見る<目>の存在。前半「第一部」の扉頁には人間の目の絵が描かれ、後半「第一部」の扉頁には監視カメラのような絵が描かれています。 時代も違えば国も違う、それを同様に眺める目など、現実にあるはずがありません。 しかし、小説という世界はそれを軽々と実現してしまう。 だからこそ2つの物語が並列することもありえるし、2つの物語が繋がることもできる、そこに本作の魅力があると感じます。 そのうえで、題名の「両方になる」とはどういう意味か。 そこは、自分でいろいろ考えてみることができる点が、楽しさなのではないかと思う次第。 ただ、このストーリィ構図、中々分り難いです。後半「第一部」は抽象的なところも多いですし。 ひととおり読み終えた後に、もう一度最初から読み直してみる、それが一番良い読み方なのかもしれません。 残念ながら私にはその余裕はなく、一度だけで終わりましたが。 |