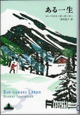| 1. | |
| 「ある一生」 ★★☆ グリンメルズハウゼン賞 原題:"EIN GANZES LEBEN" 訳:浅井晶子 |
|
|
2019年06月
|
20世紀初頭、アルプスを望む山岳地帯で、ひたすら地道に生きた一人の男が語った人生譚。 主人公はアンドレアス・エッガー。 私生児として生まれ、実母の義兄である大農場主フーベルト・クランツシュトッカーに引き取られて育ちますが、幼い頃からその扱いは住み込み労働者とまるで異ならず。 そのクランツシュトッカーに殴られ、片脚に障害が残る。 それでも18歳になって独立し、懸命に働いてなんとか我が家を構えます。 宿屋の使用人として雇われたマリーと出会い、工夫を凝らしてロマンティックに求婚、家族という幸せを手に入れます。 仕事も山岳ロープウェイの建設会社に移り、それなりに満ち足りた生活。でも、その幸せは突如として絶たれてしまう。 生涯残った障害、悲劇、そして戦争、捕虜、その後は山岳ガイドとして生きていく。 それなりのドラマありと思えますが、エッガー本人としてはただ地道に、目の前にある道を生きただけなのかもしれません。 名も知れぬ男性の、地味な人生かもしれませんが、そこにはストイックな生き方を感じます。 ふとアリステア・マクラウドのハイランダーたちの姿を思い出しますが、彼らに較べると本書のエッガーは、実に穏やか。 概ね満足のいく人生だったというエッガーの一言には、彼の生きた道の見事さを感じさせられます。 幸不幸、成功したかどうかという結果ではなく、自分がすべきことを十分にやって来た、という充足感がそこにあるからなのでしょう。 頁数も 150頁程度。シンプルなストーリィですので、とても読み易い。 お薦めです。 |