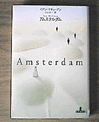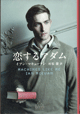|
|
|
|
|
1.夢みるピーターの七つの冒険 2.アムステルダム 3.土曜日 4.初夜 5.ソーラー 6.甘美なる作戦 7.未成年 8.憂鬱な10か月 9.恋するアダム |
| 1. | |
| 「夢みるピーターの七つの冒険」 ★☆ 原題:"The daydreamer" 訳:真野泰 |
|
2001年11月 2005年10月
|
マキューアンの新作かと思いきや、かなり以前の作品で、新装改版とのことでした。 これまで読んできたマキューアン作品の中では、最も前に刊行された作品。 邦題より原題に注目した方が、本作の内容がよく分かるというもの。 訳すると、「ぼんやりした空想に耽る誰か」という意味。 その誰かとは、本作の主人公であるピーター。 昼日中からついつい空想にふけってしまい、現実を置き去り。そのため傍から見ると、ボケーッとしているという子ども。 「七つの冒険」とは、そのピーターが空想で繰り広げるいろいろな冒険のこと。 私も子ども頃はいろいろと空想を繰り広げることがありましたが、さすがにピーターのようにすっぽり空想にはまり込んでしまうことは無かったよなぁ。 まず、「ピーターはこんな子ども」という処から面白い。 そから後、10歳の少年ピーターがどんな空想、“白昼夢”を繰り広げるのか、どうぞお楽しみに。 一度読み通した後に、改めて味わい直してみると、もっと楽しめると思います。 ※なお、「大人」では、大人はもう子どもの時代に戻ることはできないのだということを、つくづく感じさせられます。 ピーターはこんな子ども/1.人形/2.ネコ/3.消えるクリーム/4.いじめっ子/5.どろぼう/6.赤ちゃん/7.大人/著者のことば |
|
「アムステルダム」 ★☆ 98年度ブッカー賞受賞 |
|
|
2005年08月 1999/06/29 |
極めてあっさりとした文章。それでいて、何を描こうとするのか、題名がどう関係するのか、まるで見当もつかないまま読み進みます。 一人の女性モリーの葬儀に、かつて彼女と恋人関係にあった3人の男性が参列します。作曲家、新聞編集者、外務大臣と、それなりに社会的地位を確保している面々。 モリーが生前に撮ったという数枚の写真、そしてひとつの事件。そこから、二人は予期せぬ局面に転がり落ちるようにはまり込んで行き、自分達のろくでもない面を曝け出す羽目に陥ります。 現代人の悲喜劇を描いた作品、と言って良いでしょう。二人がそれなりの社会的地位を持っていた人間だからこそ失笑せざるを得ない、そんなふうに思います。 |
|
「土曜日」 ★★ |
|
|
2007年12月
|
ロンドンに住む脳神経外科医、ヘンリー・ペロウンの過ごすある土曜日、その一日のことを描いた長編小説。
ヘンリーは優秀な脳神経外科医であり、委ねられる手術は多いものの仕事には十分満足している。妻のロザリンドは弁護士であるため互いに多忙ですが、結婚以来2人の愛情関係には少しの揺るぎもありません。 何の不自由もない、比較的恵まれた生活を送っているヘンリーの土曜日が淡々と描かれていきます。 本作品の面白さは、ヘンリー・ペロウンが文学をまるで解さない人物である、というところにあります。 それでも最後、家族の危難が“詩”によって救われるという場面で初めてヘンリーが娘の詩を理解するに至ると、ホッとする気持ちになります。 ※本書では、英米軍によるイラク攻撃の是非も重要な話題となっており、興味惹かれる部分です。 |
|
「初 夜」 ★★☆ |
|
|
2009年11月
|
160頁余りの短めな長篇小説。それだけに、作者マキューアンの上手さが光る一作。
1962年の英国、結婚式を挙げたばかりのエドワード、フローレンスは初めての夜を迎える。 現代日本のような、恋愛といえば(結婚問題などお構いなしに)即セックスという小説世界とはまるで異なる、1962年が舞台。 お互い愛し合っているのは確かなことなのに、僅かなすれ違いが重なって、2人の歩みを狂わせて行く。 たった一夜の、それもありふれた事柄から、人生の扱い難さ、永遠とも思える悔恨を何と見事に描き出していることか。 |
|
「ソーラー」 ★★ |
|
|
2011年08月
|
若くしてノーベル賞を受賞したマイケル・ビアード。 ノーベル賞を受賞したぐらいですから真面目で優秀な物理学者かと思えば、これが有り得ない位の好色かつ狡猾。 53歳にして既に結婚5回。過去の離婚はすべてビアードの浮気の所為だというのに、その5回目も僅かな結婚期間の中で既に浮気11回。ビアードに対抗して妻のパトリスも浮気を始めれば、これには焦燥を感じるという身勝手さ。 そのうえ、パトリスの浮気相手が転んだ拍子に頭を打って急死したとみれば、もう一人の浮気相手の犯行に見せかけ、相手が実刑を受けても何の負い目を感じることなし。また、同僚のアイデアを横領して賞賛を得ても、自身の功績と疑うことなし。 いやはや何とも呆れかえった人物なのですが、余りに悪びれない態度の所為か、読み手もつい憎めず思ってしまう程。 こんな人物が現代社会にもしいたら、という趣向のブラックユーモアかと思ったのですが、よく考えてみると、実は結構ある話なのではないか?と思い当たった次第。 何でも自分に都合よく解釈し、自己肯定し、自分は正しいと公言して何の憚るところなし。マスコミが大物○○○、事業成功者、カリスマと煽り立てるが故に、世間もその人物が正しいのかもしれないと思ってしまう。 ビアードがノーベル賞受賞者という看板をもっているが故に社会で容易に許容されている事象とよく似ている、と思うのです。 決して本書主人公のマイケル・ビアードだけが特殊例なのではない。彼らの自己肯定を許してしまっているのは、もしかすると世間一般の我々自身なのかもしれないと思うと、本作品、ただの現代社会における風刺コメディとばかりは言っていられません。 表面的な悲喜劇の裏に、鋭い示唆を含めた怪作と受け留めたい一冊です。 |
| 6. | |
|
「甘美なる作戦」 ★★☆ |
|
|
2014年09月
|
英国国教会主教の娘に生まれ、子供の頃から読書好きだったにもかかわらず、母親の断固とした指示でケンブリッジの数学科に進んだセリーナ・フルーム。関係をもった大学教授からの勧めで英国諜報機関に就職。しかし、同機関で女性は下級事務職員としてしか扱われず、しかも給料は安いといいところなし。 そんなセリーナにある日チャンスが巡ってきます。国益に沿うよう、反共的な小説家に助成金を与えるという文化工作、名付けて“スウィート・トゥース(甘党)”作戦の担当者に、読書好きという経歴を買われてセリーナが抜擢されます。担当することになった新人作家はトマス・ヘイリー。 セリーナ、そのヘイリーとすぐに愛し合うようになります。果たしてセリーナの任務はどういう結果となるのか、そして2人の恋愛の結果は・・・というストーリィ。 主人公のセリーナ、いかにも不器用そう、そのくせいつも容易く男性と恋仲になるという風で、あまり好感を持てません。また、所々で作品執筆の一端を味わえる楽しみはあるものの、長ったらしいなぁと感じてしまうのが、読む方としては苦しいところ。 しかし最後の40頁位で、俄然面白くなります。まるでオセロゲーム、終盤で一気に裏返されて黒白が入れ替わってしまう様に喩えられます。 「好きなのは、自分の知っている人生がそのままページに再現されているような作品だ」というセリーナに対し、ヘイリーは「トリックなしにページに人生を再現するのは不可能だ」と言い返します。 人生にトリックなどまずないと思い込んでいる主人公ですが、実は本ストーリィ、至る所にトリックがあったと、最後にして判ります。どんなトリックだったのか、それを知るところに本作品の痛烈な面白さがあります。 2人の言葉がそのまま本作品の大きな鍵になっているとは、まるで予想つかず。 最後、本書に登場する小説家ヘイリーと、本書の作者であるマキューアンの姿が重なって見えてくるのですから、何とまぁ驚かされます。 途中で諦めず、最後まで読み通してください。そうすれば本作品の面白さに興奮すること間違いなし、です。 |
| 7. | |
| 「未成年」 ★★☆ 原題:"The Children Act" 訳:村松 潔 |
|
2015年11月
|
白血病で緊急入院したものの“エホバの証人”に属し宗教上の教えに基づき輸血を拒否する少年と、輸血の是非を問う判決を委ねられた女性裁判官との邂逅を描く長編。 50代後半の女性裁判官フィオーナ・メイが本書の主人公。 シャム双生児の片方を生かすための手術の是非等、これまでも彼女は幾つもの難しい裁判での判断を過たず行ってきており、その簡潔で合理的な判決文は美しいとさえ評価されている。 そのフィオーナが新たに担当したのは、命を救うため輸血措置の許可を求める病院側と、宗教上の理由から輸血を拒む両親とその本人アダム・ヘンリとの争い。 命を救うことは重要だが、本人の信仰心・意思も当然ながら尊重する必要がある・・・・その難しい裁きをどうフィオーナは乗り越えるのか。 それだけでも興味津々、ストーリィに引き込まれざるを得ないのですが、その後に予想もしなかったドラマが展開していきます。 裁判は所詮一瞬のもの。直面する課題について裁判で是非を決めることは簡単ですが、人はその判決だけで生きていけるものではない。 長年連れ添った夫との間に起きた問題に加えて、フィオーナはアダムとの問題に直面させられます。 人は何か信じるものを持たないと生きていけない・・・裁判、そして裁判官の限界を、一人の女性、一人の人間としてフィオーナは味わうことになる、というストーリィ。 マキューアンの文章は簡潔で凛々しく、音楽の旋律を聞くような美しさが感じられます。 その文章によって描き出される、もはや老年の域に達しようとしている女性裁判官フィオーナと少年アダムの邂逅を描いたシンプルな本書ストーリィは、儚くも美しいリズムを醸し出しているように感じられます。 本書について悲劇であるとか云々する必要はないでしょう。 ひんやりと美しい読了後の余韻を味わうことが全て、と思います。 |
| 8. | |
| 「憂鬱な10か月」 ★★☆ 原題:"Nutshell" 訳:村松 潔 |
|
2018年05月
|
財産狙いから、母親と叔父(父の弟)が父親を殺そうと策謀。 まさに現代版<ハムレット>というべき作品ですが、ハムレットであるべき主人公がまだ世に生まれ出ていない胎児とは! まさに驚天動地のストーリィですが、単に舞台設定の面白さに留まらず、それを活かしたスリリング、ブラック・ユーモアがふんだんに発揮されている処が実にお見事。脱帽です。 出版社を経営している父親のジョン・ケアンクロスは、人を世に送り出すことに献身的に尽くしているものの、自身は二流詩人どまり。穏やかな人物ですが、自分が親から受け継いだ家から妻によって追い出されている状況。 その妻のトゥルーディは、ジョンの実弟であるクローディと堂々たる不倫関係。 そしてクローディは遺産を食いつぶしており、トゥルーディと関係を結び、共謀して実兄の財産を狙っている。 主人公である胎児は、母親の胎内で、母親を通じて世間のニュースを知り、母親と叔父の殺害計画を見聞きし、何とか父親を救おうとヤキモキする、という次第です。 胎児である以上、2人の悪巧みを知って何とかしたいと思い、何とか食い止めようと切歯扼腕しても、そこは物理的に手も足も出せない訳で、だからこそ焦燥感は募る一方、スリリングこの上ない、という状況です。 一方、臨月だというのに母親と叔父は平気で交わり、その都度母胎内で子宮の奥に押しやられ恐怖感を抱いている主人公の姿は、ブラック・ユーモアという以外の何物でもありません。 最後、どういう結末が3人に、そして主人公である胎児に待ち受けているのか。最後の最後まで面白さたっぷり、全く飽きません。 いやー、面白かった! シェイクスピア・ファンには、是非、お薦め。 |
| 9. | |
| 「恋するアダム」 ★★ 原題:"Machines Like Me−And People Like You" 訳:村松 潔 |
|
2020年01月
|
表題にある「アダム」とは、主人公が購入したアンドロイド。 しかし、このアダム、これまでSF小説に登場したアンドロイドとはかなり違います。 何しろ、主人公の恋人となった女子学生ミランダから誘われてセックスするばかりか、主人公相手に「彼女を愛している」とまで宣言するのですから。 購入したアンドロイドを一緒にアップデートしようと誘い、ミランダと恋仲になろうとしていたチャーリー、まさかそのアダムと三角関係になるとは! これだけ聞くならSFコメディかと思える処ですが、大違い。 人間とアンドロイドを対比させるストーリィになっているのですから。 このアダム、人間同様に感情を持つうえに、感情と理性をきちんと整理して判断、行動をする。そこに揺るぎはありません。 そうなると人間より余っ程優れた存在、と思えてしまう。 さらに電源オフを拒否し、チャーリーが抵抗しようとするのを阻んで怪我さえさせてしまう(アイザック・アシモフ“ロボット三原則”はもはや霧の彼方か?)。 資金運用にも成功して資産を増やす等、完全無欠かと思われたアダムですが、同時期に製作されたアンドロイドは皆根源的な悩みを抱えてしまったらしい。そしてアダムもまた・・・。 アダムの存在を軸にして、人間という存在について考えざるを得なくなるストーリィです。 理性と同時に感情を合わせ持ち、時として感情に支配されて行動する人間という存在。その是非は・・・。 果たして、人間とアンドロイドは、お互いを認め合うことができるのでしょうか。 本ストーリィは、近未来の出来事としてではなく、パラレル世界での1982年を舞台として設定しています。 フォークランド戦争で英国が敗北し、サッチャーは英国民から非難され、カーターはレーガンを退けて大統領再選を果たす、という世界。 でも、人間というのが厄介で問題の多い存在であることは、どちらの世界でも違いはないようです。 |