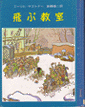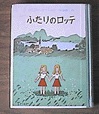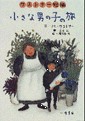|
|
|
|
|
3.飛ぶ教室 5.ふたりのロッテ 6.動物会議 7.サーカスの小びと 8.小さな男の子の旅 |
|
|
|
●「エーミールと探偵たち」● ★★★ |
|
|
1953年09月 1962年07月
|
児童文学の傑作、そして大人が読んでも間違いなく夢中になって読んでしまう本です。 主人公エーミールは、一人でノイシュタットからおばあさんのいるベルリンまで列車で旅します。しかも、胸のポケットには、お母さんから言付かった140マルクという
大金を持って。 エーミールを助けるのは、ベルリンの街で知り合った警笛のグスタフ、教授君、ちびの火曜日君ほか、多くの子供たち。 本書は、ケストナーにとって初めての小説であるだけに、いろいろな面白さが詰め込まれています。最初に主要な登場人物・場所が紹介されるのもユニークですし、エーミールの従姉妹ポニー・ヒュートヘンに対する少年たちの男の子らしい反応も、気持ちがわかるだけに愉快です。 本書は、児童文学の原点と言って良い作品だと思います。 |
※映画化 → 「エーミールと探偵たち」
|
●「点子ちゃんとアントン」● ★★★ |
|
|
1962年07月 1996/12/29 |
点子ちゃんは想像力豊かな、お金持ちの一人娘ですが、母親といえば着飾ってパーテイに行くことばかり夢中。一方、友達のアントンは勇敢な少年ですが、母一人子一人、母親は手術で退院したばかりで貧乏な境遇です。 ストーリィは、点子の家庭教師・アンダハルトが婚約者で泥棒のローベルトに貢ぐため、点子を連れ出して一緒に乞食の真似をさせたり、ローベルトが点子の家に泥棒に入るのを手伝ったり、というもの。 ストーリィだけを取り上げるなら、不自然な点もいろいろとありますが、そんなことは問題ではありません。それより、アントンと母親の関係が、ケストナー自身の母子関係を投影していることに注目されます。 久しぶりに読み直すと、家庭環境・貧富の差に影響されることなく、点子とアントンがしっかりとした親友関係を結んでいる素晴らしさに感動します。 大人の世界とは別に、子供は子供なりのきちんとした世界がある、というケストナーの主張を感じます。 |
※映画化 → 「点子ちゃんとアントン」
|
●「飛ぶ教室」●
★★★ |
|
|
2014年12月
|
私が子供の頃からの愛読書です。 本書はクリスマスの物語。舞台はキルヒベルクにある高等中学校の寄宿舎です。 彼ら少年たちは、大人に負けず劣らず、それぞれに悩み、苦しみを抱えています。子供だからといって決してひとくくりにできる存在ではないし、一様に幸福だなどとは言えない人生を背負っています。しかし、彼らには“勇気”があります。それがこの作品の素晴らしい点です。“純真”とか“無垢”というありきたりな少年世界は、この作品では用無しなのです。 冒頭でケストナーは、「賢さを伴わない勇気は乱暴であり、勇気を伴わない賢さなどはくそにもなりません! 世界の歴史には、おろかな連中が勇気をもち、賢い人たちが臆病だったような時代がいくらもあります」と述べています。そんなケストナーの考えを、 本書は体現した作品です。 主人公たちは、ただ賢いだけでなく勇気をもち、そして他人の気持ちを察していたわる優しさを備えています。大人になってもそんな気持ちを失っていない存在が、正義先生、禁煙さんです。本書では、心から感動を覚える場面がいくつもあります。 なお、「飛ぶ教室」は彼らが演じるクリスマス劇の題名。「授業、現地検証になる」というジョニー創作による5幕劇です。 |
※映画化 → 「飛ぶ教室」
|
●「エーミールと三人のふたご」● ★★☆ |
|
|
1962年8月
|
「エーミールと探偵たち」の続編。 何より感じることは、書かれているのは子供達のことですが、それは決して子供の世界のことではなく、大人とまったく同様の社会を子供たちが経験する、というストーリィだということです。つまり、言い換えれば、社会の出来事に大人も子供もないわけで、それにも拘らず子供達が工夫して難局を切り抜ける、というストーリィなのです。 登場人物は例によって、警笛のグスタフ、エーミールのいとこポニー・ヒュートヘン、ちびの火曜日君、ハンス・シュマウフ。さらに曲芸一家である三人のバイロンが登場します。 こういうことが普通に行われれば、理想的な社会だと思います。子供社会だけのことではなく、大人社会にも同じことが言えます。 素晴らしい、そして何より大事な人生教訓です。こんな言葉がさりげなくストーリイの中に織り込まれている、ケストナー作品の素晴らしさだと思います。 |
|
●「ふたりのロッテ」● ★★★ |
|
|
1962年5月
|
まさに名作!と言いたい作品です 夏季休暇で村にある子供に家に出かけたルイーゼは、そこで自分にそっくりな少女ロッテに出会います。やがて2人は自分たちが
双子であること、両親が離婚したことを知ります。 休暇後、2人は入れ替わってそれぞれの家へ戻ります。ロッテはウィーンの父親の元へ。一方、ルイーゼはミュンヘンの母親の元へ。そこから後の愛情溢れるストーリィは、読んでのお楽しみです。 この作品の根底には、ケストナー自身の家庭状況、母親に偏向した事実があるように思います。自分と瓜二つの兄弟がいて、両親が揃った明るい家庭、ケストナーの理想である家庭観を見る思いがします。現代の、すぐ安易に離婚してしまう夫婦の多い状況下では、特に見直すに適した作品かもしれません。 |
※映画化 → 「ファミリー・ゲーム」
|
●「動物会議」● ★★ |
|
|
1962年6月 1999/12/27 |
絵本向けの3作品を収録。 動物会議 原題:“Die Konferenz der Tiere” 1949 |
|
●「サーカスの小びと」● ★★ |
|
|
1963年発表 1964年8月 1997/06/21 |
小びとのメックスヒェン・ピヒェルシュタイナーとヨークス・フォン・ポークスとの友情を描くストーリィ。 |
|
●「小さな男の子の旅」● ★★ |
|
|
1996年1月
|
ほんの一息で読めてしまう短篇2作です。
2作ともケストナー初期の作品で、母親に関わるストーリィです。本当に短いけれども、ケストナーらしさがキラリと光っていて感動を覚えます。 小さな男の子の旅 原題:“Ein kleiner Junqe unterwegs” |