![]()
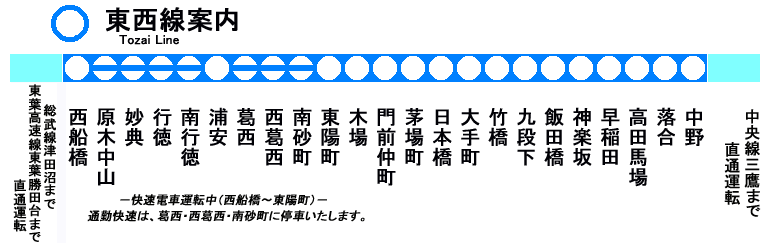
東京地下鉄東西線は、都市計画第5号線として、中野〜東陽町間で計画されていた路線です。1964年12月に営団地下鉄4番目の路線として、最初の区間(高田馬場〜九段下間)が開通しました。その後、JR線の混雑緩和のために、路線計画は西船橋まで延長され、1969年3月に、中野(東京都中野区)〜西船橋(千葉県船橋市)間30.8kmが全通しました。
現在、東西線は中野でJR中央線各駅停車と、西船橋ではJR総武線各駅停車(朝夕のみ、津田沼まで)および、東葉高速線と相互直通運転をしています。三鷹から東葉勝田台までは、約1時間20分前後を要します。また、東西線内の所要時間は、快速43分、各駅停車50分となっています(昼間時)。
西船橋延伸後の東西線の役割は、「JR総武・中央線のバイパス」となりました。それがゆえに快速種別が存在し、中野〜西船橋間はJR線各駅停車利用よりも、快速利用で約10分ほど東西線が速く走っています(快速待避待ちがあるのも、東西線の特徴の一つです。)。運行間隔は、朝の最短間隔が2分15秒、昼間が5分(快速は15分)、夕方は3分、深夜は5分〜10分間隔となっています。
路線の性質上、千葉県や東京西部からの通勤客を多く運ぶために、目下通勤路線としての役割を担っており、朝や深夜時間帯は非常に混み合っています。その混雑ぶりは日本の鉄道の中でも10指に入るほどで、特に関東圏私鉄では最も混雑する路線となっています(2006年現在)。
東西線は、文字通り東京を東西に横切って走っています。中野ではJR中央線と接続し、高田馬場では山手線と西武線に、飯田橋では再び中央線とまじわり、有楽町線・南北線・都営大江戸線とも接続します。九段下では、半蔵門線と都営新宿線、大手町では、丸ノ内線・千代田線・半蔵門線・都営三田線そしてJR線と、日本橋では、銀座線と都営浅草線、茅場町では日比谷線、門前仲町では再び都営大江戸線と接続しています。そして、終点の西船橋では、総武線各駅停車、武蔵野線、京葉線、東葉高速線と接続しています。このように、東西線は多数の路線と交差し、営団地下鉄・都営地下鉄の全路線と接続しています。
(このように、都心を横切る東西線では、電車の行先方向を「上り」「下り」とは呼んでいません。西船橋方面へ向かう電車を「A線」、中野方面へ向かう電車を「B線」と呼んでいます。)
また、東西線の開通は、沿線の発展を大きく助けました。特に、地上区間(南砂町〜西船橋)の”東西線効果”は、著しいものがありました。東西線開通以前、葛西・浦安・行徳の各地区は、都心15km圏内にありながら、都心まで2時間近くを要する「陸の孤島」でした。東西線の開通により、30分程度で都心に到達できるようになると、これらの地区は大きく発展することになりました。このうち、東西線延長開業時の葛西地区の人口は6万人ほどで、葛西駅の乗降客数は約1万2千人であったのに対し、現在の葛西地区の人口は220,458人(葛西事務所管内、統計江戸川より)であり、葛西駅と西葛西駅をあわせた乗降客数は、約18万人にもふくれあがっています。1979年には西葛西駅(南砂町〜葛西間に新設)が、1981年には南行徳駅(浦安〜行徳間に新設)が、そして2000年には妙典駅(行徳〜原木中山間に新設)が新しく開業しました。これでも利用客の伸びは止まらず、最近では、ホーム幅を広くする工事を行った駅もあります。
| 東西線が持つ東京メトロナンバーワン | |
| 営業キロ | 30.8km |
| 地上区間距離(※) | 13.8km |
| 平均駅間距離(※) | 1.4km |
| 最長橋りょう(※) | 1,236m |
| 自社保有車両数(※) | 470両 |
| 自社線内最高速度(※) | 100km/h(快速) |
| 平均輸送人員(※) | 120.7万人 (H15年度) |
| 最混雑率(※) | 198% (木場→門前仲町) |
| 注:※印がつくものは、東京の地下鉄ナンバーワン | |
東西線を走る電車は大別すると、東京メトロ所属の5000系・05系および07系、JR所属のE231系(800番台)、東葉高速鉄道所属の2000系の5種類が存在します。また、05系には、従来型の他、ワイドドア車や新デザイン車(新05系)などがあり、車輌のバリエーションは豊かなものです。また、これらの車輌は全て10両編成で、東西線内を走行しています。
また、東西線は、地下鉄にあって地下鉄でないような性格をも持っているために、様々な”ナンバーワン”を持っている路線でもあります。
(余談ではありますが、日本には数多くの「東西線」が存在しています。この東京メトロ東西線の他、札幌市営地下鉄東西線、京都市営地下鉄東西線、JR(西日本)東西線など、たくさんあります。「東西を横切る路線」ということで、多く採用されるのでしょうね。)
東京メトロ東西線の歴史へ
![]()
東葉高速鉄道東葉高速線は、1996年4月27日に開業した比較的新しい路線です。
現在、東葉高速線は、西船橋(千葉県船橋市)ー東葉勝田台(千葉県八千代市)間16.2kmを22分(東葉快速18分)で走っています。途中、北習志野では新京成線と接続し、東葉勝田台では、京成線と接続しています。このため、東葉高速線は東西線とあわせて、都心へのバイパス路線の役割を果たしています。
当初は、この路線は東西線の延長区間(正式には営団勝田台線(仮称))として計画されていました。しかし、営団のテリトリー(本来は東京都内とされていた)から大きく外れることもあり、営団側が申請を取り下げ、東葉高速鉄道で運行することになりました。
この路線は計画に12年、工事に12年を要した非常に時間のかかった路線の1つです。その原因としては、用地交渉の進行の大幅な遅れ、および、トンネル工事の一時中断などがあげられます。これだけ時間がかかったためか、最初は西船橋−八千代(仮称)間と八千代−勝田台間と分けて開業するはずだったものが、一度に全通することになりました。(個人事ではありますが、私が小学生になったころから「まもなく勝田台まで東西線が来る」という話を聞いていました。しかし、実際に開通したのは、私が中学生になってからでした。それだけ開業予定が延びたのですね…。)
そして、この影響は工事等にかかった総費用にも影響しました。この路線の建設等に使った費用が、予定より500億円以上も上回ってしまいました。これらの結果、運賃は初乗り200円、終点までの運賃600円(開業当初)という、開業当初は、都会を走る鉄道の中では全国で1,2位を争うほどの高額運賃となってしまいました。関係者によると、この運賃でも、安くできる限界なのだそうです。これは、既成市街地に鉄道を新設することの難しさを示すことになりました。
しかし、東葉高速線の開通により、沿線の住民の便は確かに良くなりました。以前まで、バス利用+京成線、JRで都心に向かっていた、飯山満や八千代地区では、直通45分以内(昼間快速利用)で都心に達することができるようになりました。これらの地区では、現在住宅地の造成が行われています。また、ダイヤ改正を行うたびに朝夕深夜の輸送力の増強(朝夕深夜の運転本数は、開業時ダイヤの約1.5〜2倍)を計り、1999年には、述べ利用者数は1億人を超えました。近年になると、東葉高速鉄道の利用者は伸び悩むようになりましたが、地域活動への参加や利用者の誘致などの営業努力により、利用者は増加の兆しを見せています。
東葉高速線を走る電車は、早朝の一部の電車を除いて、東京メトロ東西線と直通運転をしています。電車は、東葉高速鉄道所属の1000形、および営団地下鉄所属の5000系と05系が走っています。東葉高速鉄道の1000形(現在は全廃)も、もともとは東西線の5000系であり、そういった意味で、「東西線の車輌ばかり走っている」路線です。
また、昼間の東葉高速線を走る電車は、快速電車(東葉高速線内各駅停車)として走っています。朝夕には、東葉高速線内も快速運転をする「東葉快速」が2本ずつ(朝は中野方面で2本、夕方は東葉勝田台方面で2本)走っています。
東葉高速鉄道の歴史へ
![]()
![]()
東西線・東葉高速線運賃表
東西線・東葉高速線普通運賃表(PDF形式)
東西線・東葉高速線−JR線連絡運賃表
通過連絡運輸(JR−東西線−JR)運賃表(PDF形式)
通過連絡運輸とは?
一般に、他社線にまたがって乗車する場合、境界駅において運賃が打ち切りとなり、境界駅からは別会社線の運賃が適用されます。つまり、大手町から東西線・東葉高速線経由で東葉勝田台まで利用する場合は、西船橋で運賃が打ち切りとなり、東京メトロの運賃270円と東葉高速鉄道の運賃610円の合計880円が大手町−東葉勝田台間の運賃となります。3社線以上またがる場合も同様に、運賃は境界駅で打ち切りとなります。
では、船橋から吉祥寺まで東西線経由で利用する場合の運賃計算はどうなるのでしょうか。上記のルールを適用した場合、運賃はそれぞれの境界駅で打ち切りとなるので、船橋−西船橋(JR)間の130円、西船橋−中野(東西線)間の300円、中野−吉祥寺(JR)間の160円の合計590円が支払うべき運賃となるはずです。これでも、同区間をJRで乗り通した場合の運賃(690円)よりも安いのですから、JRの運賃がいかに高いかが分かるのですが…。
しかし、利用区間の両端部が同一の会社であるにもかかわらずこのような打ち切りを行うと、両端区間の運賃を合算するため、運賃が高額になり、この経路を利用しにくくなってしまいます。そこでとられた措置が「通過連絡運輸」です。この措置が行われる区間においては、境界駅での運賃打ち切りは行われず、JR線である両端区間の運賃計算キロを合算し、合算された運賃計算キロに基づいてJR側の運賃が計算されます。
したがって、船橋−吉祥寺間(東西線経由)についての運賃計算は…
船橋−西船橋間(2.6km)+中野−吉祥寺間(7.8km)でJR側の運賃計算キロが10.4km
10.4kmの電車特定区間の運賃は210円。これがJR側の運賃となります。
中野−西船橋間の東京メトロの運賃は300円。これが東京メトロ側の運賃となります。
そしてJR側の運賃と東京メトロ側の運賃を合算した510円が、通過連絡運輸適用時の運賃となります。
この東西線経由の通過連絡運輸が適用される範囲は、中央線(中野−三鷹間)・総武線(下総中山−千葉間)・京葉線(南船橋−千葉みなと間)です。通過連絡運輸制度そのものは、この東西線のケースの他にも北越急行やいわて銀河鉄道・青い森鉄道などでも適用されています(これらは制度適用範囲が広いため、東西線のケースよりもはるかにメジャーです)。