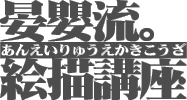
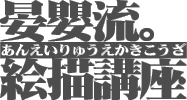
| まずはコレをやらないと何も始まりません。ここで普通は、アナログで描いてペン入れした原稿を取り込んでゴミを飛ばす…なんていう解説が入るハズなんですが、この頃の儂はスキャナを所持していなかったため、下描きからタブレットでちまちま描き起こすということをしております。 |
| ■平らなテスクチャ(以下『清盛』)を適用したもの(上)とデフォルトのベーシックペーパーを適用したもの(下)。左の細い線がいつも儂が下描きに使ってる鉛筆<シャープ>で、右のもくもくっとしたやつがチョーク<太>で描いたライン。下描きや本番はシャープなラインが出た方が個人的には嬉しいので清盛を、自然な画材の効果を見せたい時にはベーシックペーパー、と使い分けてますです。 |
|
| ■描きます(そんだけか)。1200*1200pix.など、画面にとうてい収まりきりそうにない絵を描く時には、まず同縮尺の小さい書類を作って全体を見渡しながらざっくりと下描きの下描きを描く。んで、大体のところが描き上がったらそれを原寸に拡大して細部の下描きをする、というもって回ったことをやります。虫眼鏡ツールで縮小して描けばいいじゃないかと思われるでしょうが、そうすると細い線がツブれて見えなくなったりするのであんまり好きじゃないんです。まぁそのへんは好みの問題ですネ。サンプルは400*400pix.だったのでそのまんま。 ■時々、顔のパーツ(目や鼻など)の形は納得いくのに位置が納得いかない時があったりするので、そういう時はその部分をなげなわツールで選択してフローターに変換、納得のいく位置に収まったら固定。CGのいいところです(笑)。 |
|
| <<<Top | Next>>> |