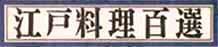 |
江戸時代食生活史関連 |
| ★ 年表-1 | ★ 年表-2 | ★ 年表-3 |
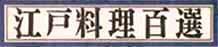 |
江戸時代食生活史関連 |
| ★ 年表-1 | ★ 年表-2 | ★ 年表-3 |
| 西暦 | 元号 | 将軍 | 国内事情 | 『江戸料理百選』を中心に構成 食生活史・料理本 |
海外事情 |
| 1787 | 七 | 家斉 | 松平定信、老中になり、 寛政の改革始まる(〜93) 長谷川平蔵、火付盗賊改方の長官に就任 |
合衆国憲法制定 | |
| 1788 | 八 | 田沼意次(70歳)没 | |||
| 1789 | 寛政元 | 棄捐令を発令 谷風、小野川、横綱の免許をえる |
仏:フランス革命、人権宣言 ワシントン、アメリカ合衆国の初代大統領になる |
||
| 1790 | 二 | 寛政異学の禁 | |||
| 1791 | 三 | 男女混浴禁止 | |||
| 1792 | 四 | ロシア使節ラクスマン、大黒屋光太夫 ら漂流民を護送し根室で通商要求 |
安房嶺岡牧場で白牛酪(バター?)が 製造される |
||
| 1793 | 五 | ルイ16世とマリー・アントワネット処刑 | |||
| 1794 | 六 | 洋学者がオランダ正月を祝い、 西洋料理を食す |
|||
| 1795 | 七 | 長谷川平蔵(50歳)没 | |||
| 1796 | 八 | 白牛酪が発売される | 清、阿片輸入禁止 | ||
| 1797 | 九 | ||||
| 1798 | 十 | 本居宣長が『古事記伝』を完成 | ナポレオン、エジプト遠征 | ||
| 1799 | 十一 | 防火・風紀の面から町々の煮売商・ 荷い屋台の煮売、夜間の蕎麦切売などを規制。 江戸王子村の料理屋、海老や・扇屋が開店 |
|||
| 1800 | 十二 | 昌平坂学問所開設 伊能忠敬、蝦夷地を測量 |
|||
| 1801 | 享和元 | この頃から江戸では、 山谷町八百屋善四郎の八百善、深川土橋の平清、 下谷龍泉寺町の駐春亭が開店し、化政期に かけて繁盛する。 紅屋志津麻により煉羊羹・鳥羽王などの菓子が 始められる。また、木原店の吉兵衛によって、 テンプラに初鰹が用いられ、薬研堀の川口忠七 により会席料理が始められたと言われる。 この頃、おまんずし、毛抜きずしが評判 |
|||
| 1802 | 二 | 蝦夷奉行を函館奉行と改称。 十返舎一九『東海道中膝栗毛』刊行 |
『名飯部類』 | ||
| 1803 | 三 | ||||
| 1804 | 文化元 | 初年頃、江戸では、 うなぎ飯が始められ、深川六間堀に松ずしができる。 また、大阪では、かすてら焼、橋々の 豆茶屋が繁盛する |
仏:ナポレオン皇帝に就任 | ||
| 1805 | 二 | ||||
| 1806 | 三 | NEW 料理書『料理簡便集』 | 神聖ローマ帝国滅亡 | ||
| 1807 | 四 | ||||
| 1808 | 五 | 間宮林蔵ら樺太を探検 | |||
| 1809 | 六 | NEW 式亭三馬『浮世風呂』 | 和製の砂糖が菜種屋や砂糖屋で 売り出され、江戸市中の菓子類に 使用されるようになった |
||
| 1810 | 七 | ||||
| 1811 | 八 | NEW 式亭三馬『浮世床』 ロシア艦長ゴローニンを国後島で逮捕 |
|||
| 1812 | 九 | ナポレオン、ロシア遠征 | |||
| 1813 | 十 | ||||
| 1814 | 十一 | 滝沢馬琴『南総里見八犬伝』 | オーストリア:ウィーン会議 仏:王政復古 ジョージ・ステーブンソンが蒸気機関車を発明 |
||
| 1815 | 十二 | 杉田玄白『蘭学事始』 | ナポレオンの百日天下 ワーテルローの戦い |
||
| 1816 | 十三 | ||||
| 1817 | 十四 | ||||
| 1818 | 文政元 | 伊能忠敬(74歳)没 | この頃、 白金三鈷坂の山中庵、雑司ヶ谷の向耕亭など の古い料理屋が途絶えた。 末年頃、江戸風の握り鮨が始まる |
南極大陸発見 | |
| 1819 | 二 | 小林一茶『おらが春』 | |||
| 1820 | 三 | 砂糖の取り引きが自由になる。 この頃、江戸不忍池の南に、茶屋・料理屋が 建ち並び賑わうが、天保年間には取り払われる |
|||
| 1821 | 四 | ||||
| 1822 | 五 | ||||
| 1823 | 六 | ||||
| 1824 | 七 | ||||
| 1825 | 八 | 外国船打払令を発令。 鶴屋南北『東海道四谷怪談』初演 |
|||
| 1826 | 九 | ||||
| 1827 | 十 | ||||
| 1828 | 十一 | シーボルト事件 | |||
| 1829 | 十二 | 松平定信(72歳)没。 | |||
| 1830 | 天保元 | NEW 第4回お蔭詣り(伊勢詣) | 仏:七月革命 | ||
| 1831 | 二 | ||||
| 1832 | 三 | NEW 吉原の大火 鼠小僧処刑 |
|||
| 1833 | 四 | 天保の大飢餓始まる(〜39) | 『万家至宝都鄙安逸伝』 | ||
| 1834 | 五 | ||||
| 1835 | 六 | 江戸の葉茶屋山本嘉兵衛が玉露茶を創製 | |||
| 1836 | 七 | 家慶 | |||
| 1837 | 八 | 大塩平八郎の乱 モリソン号事件 |
ヴィクトリア女王即位 | ||
| 1838 | 九 | ||||
| 1839 | 十 | 渡辺崋山、高野長英逮捕(蛮社の獄) | |||
| 1840 | 十一 | 橋場料理舗棹月楼柳屋が商売を始める | 英対清:阿片戦争勃発(〜42) | ||
| 1841 | 十二 | 家斉(69歳)没 水野忠邦、天保の改革を始まる |
|||
| 1842 | 十三 | 江戸端々の二十余ヵ所料理屋が 取り払いを命じられ、初物の売買禁止、 武家の衣食住の倹約令が出される |
南京条約 | ||
| 1843 | 十四 | ||||
| 1844 | 弘化元 | ||||
| 1845 | 二 | 江戸では、「丸山名物まるまるだんよ」と詠われた、 「まるぼうろ」という菓子が売り出された |
|||
| 1846 | 三 | この頃、 江戸の流行物として、はじけまめ・ 島屋だんよ・稲荷ずしが知られる |
|||
| 1847 | 四 | ||||
| 1848 | 嘉永元 | 仏:二月革命 | |||
| 1849 | 二 | ||||
| 1850 | 三 | ||||
| 1851 | 四 | ジョン万次郎ら米国から帰る | 清:太平天国の乱おこる | ||
| 1852 | 五 | ||||
| 1853 | 六 | 家定 | 家慶(61歳)没 ペリー、浦賀に来航 |
クリミア戦争おこる | |
| 1854 | 安政元 | 開国、日米和親条約締結 | 伊勢崎町塩河岸料理屋百川に おいて卓袱料理が始められる。 七月、流行病に牡丹餅が効くとされ、 人気を呼んだ入谷に松下亭という蕎麦屋、 業平橋の手前に在五庵という料理屋ができる |
||
| 1855 | 二 | 安政の大地震(江戸・近江に大地震起こる) | 地震後、江戸池の端の弁財天境内にあった 料理屋はすべて門外に移転させられた。 この頃、紅梅焼と称する菓子が売られる |
パリ万国博覧会 | |
| 1856 | 三 | アメリカ総領事ハリス下田に着任 | 函館で外国人に牛肉の供給を許可 | アロー号戦争(〜60) | |
| 1857 | 四 | 印:セポイの反乱おこる | |||
| 1858 | 五 | 家茂 | 家定(35歳)没 安政の大獄(吉田松陰処刑) 修好通商条約を締結(五国=米・蘭・露・英・仏) 江戸にコレラ(死者3万人) |
印:ムガール帝国滅亡 | |
| 1859 | 六 | ダーウィン『種の起源』 | |||
| 1860 | 万延元 | 桜田門外の変(井伊直弼暗殺) | 清:北京条約調印 | ||
| 1861 | 文久元 | NEW三遊亭円朝『怪談牡丹灯籠』 和宮、将軍家茂に降嫁(公武合体) |
米:南北戦争おこる(〜65) | ||
| 1862 | 二 | 公武合体、坂下門の変 寺田屋事件。生麦事件。 |
|||
| 1863 | 三 | 高杉晋作、奇兵隊編成。薩英戦争。 | 米:リンカーンの奴隷解放宣言 | ||
| 1864 | 元治元 | 池田屋騒動(新撰組、尊攘志士を襲う) 蛤御門の変。 仏・英・米・蘭4カ国連合艦隊下関を砲撃 長州征伐始まる。幕府が新撰組を作る |
|||
| 1865 | 慶応元 | リンカーン暗殺 メンデル「遺伝の法則」 |
|||
| 1866 | 二 | 慶喜 | 家茂(21歳)没。薩長同盟。農民一揆 | 横浜・江戸に弁当屋や洋食店(西洋料理店)が開業 | |
| 1867 | 三 | 高杉晋作(28歳)没 坂本龍馬(33歳)、中岡慎太郎(30歳)暗殺。 大政奉還、王政復古の大号令。幕府滅亡 「ええじゃないか」発生 |
独:マルクス『資本論』 | ||
| 1868 | 明治元 | 鳥羽伏見の役(1月)。戊辰戦争の開始(〜69) 彰義隊の戦い(5月)。慶喜水戸へ退却 江戸城開城。五箇条の御誓文 会津の戦い(9月)。明治維新。明治と改元 |
| ★ 年表-1 | ★ 年表-2 | ★ 年表-3 |
■ HOME ■