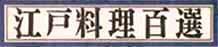 |
江戸時代食生活史関連 |
| ★ 年表-1 | ★ 年表-2 | ★ 年表-3 |
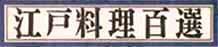 |
江戸時代食生活史関連 |
| ★ 年表-1 | ★ 年表-2 | ★ 年表-3 |
| 西暦 | 元号 | 将軍 | 国内事情 | 『江戸料理百選』を中心に構成 食生活史・料理本 |
海外事情 |
| 1709 | 六 | 家宣 | 綱吉(64歳)没 生類憐愍令廃止 幕府、新井白石を登用 |
鳥類・鰻・鯰・鰌の売買が解禁となる | ピアノの発明 |
| 1710 | 七 | ||||
| 1711 | 正徳元 | 江戸両国橋東詰の松屋三左衛門が飛団子を考案 | |||
| 1712 | 二 | 家宣(51歳)没 | |||
| 1713 | 三 | 家継 | |||
| 1714 | 四 | ||||
| 1715 | 五 | 仏:ルイ15世即位 | |||
| 1716 | 享保元 | 吉宗 | 吉宗が享保の改革を始める(〜45) | ||
| 1717 | 二 | 家継(8歳)没 大岡越前守(大岡忠相)、江戸町奉行に就任 |
|||
| 1718 | 三 | NEW 町火消しが初構成 | 鳥類減少のため、向こう三年間は鶴・ 白鳥・雁・鳧を贈答・食用とすることを禁止 浅草寺内の餅店の餅を伝法院僧正が 浅草餅と命名 |
||
| 1719 | 四 | ||||
| 1720 | 五 | 江戸町火消しいろは組を設置 | 鳥類の贈答が自由になる | ||
| 1721 | 六 | 目安箱を設置 | |||
| 1722 | 七 | 小石川薬園内に養生所を設置 | |||
| 1723 | 八 | ||||
| 1724 | 九 | ||||
| 1725 | 十 | ||||
| 1726 | 十一 | ||||
| 1727 | 十二 | ||||
| 1728 | 十三 | ||||
| 1729 | 十四 | 長崎の中国人商人、象を江戸に連れてくる | |||
| 1730 | 十五 | ||||
| 1731 | 十六 | ||||
| 1732 | 十七 | 享保の大飢饉(西日本の虫害) | |||
| 1733 | 十八 | ||||
| 1734 | 十九 | ||||
| 1735 | 二十 | 青木昆陽、吹上苑での甘藷試植に成功し、 救荒食物として担当奉行に施与 以後薩摩芋として徐々に広まる |
|||
| 1736 | 元文元 | ||||
| 1737 | 二 | ||||
| 1738 | 三 | ||||
| 1739 | 四 | ||||
| 1740 | 五 | オーストリア:継承戦争 | |||
| 1741 | 寛保元 | 十月〜翌三月までの重要な宴会には、 雁・鴨を 用いた饗膳が許可される。 魚鳥類・野菜の売買期日を定め、 初物売りの利を抑制 |
|||
| 1742 | 二 | 公事方御定書制定 | NEW 魚鳥類初物禁止令(大陰暦) | ||
| 1743 | 三 | 甘藷栽培を奨励 | |||
| 1744 | 延享元 | この頃江戸の名物として、 竹村の煎餅、回向院前の淡雪、 深川いせやの笊蕎麦、湯島の油揚げなどが知られた |
|||
| 1745 | 二 | 家重 | |||
| 1746 | 三 | ||||
| 1747 | 四 | ||||
| 1748 | 寛延元 | 「仮名手本忠臣蔵」大坂竹本座で初演 | 仏:モンテスキュー『法の精神』 | ||
| 1749 | 二 | 『仮名手本忠臣蔵』 | |||
| 1750 | 三 | 『料理山海郷』 | バッハ没 | ||
| 1751 | 宝暦元 | 吉宗(68歳)没 | この頃江戸では、 水茶屋葭簀、吉原五十軒編笠茶屋、 浅草二十軒茶屋あんどう、じがみ屋 などが知られる |
||
| 1752 | 二 | ||||
| 1753 | 三 | ||||
| 1754 | 四 | ||||
| 1755 | 五 | ||||
| 1756 | 六 | 長門府中の永富鳳兄弟が砂糖を製造 | 欧:七年戦争 | ||
| 1757 | 七 | 江戸真崎稲荷周辺に、田楽茶屋が 数軒でき繁盛する |
|||
| 1758 | 八 | ||||
| 1759 | 九 | ||||
| 1760 | 十 | 家治 | |||
| 1761 | 十一 | 家重(51歳)没 | |||
| 1762 | 十二 | 仏:ルソー『社会契約論』 | |||
| 1763 | 十三 | ||||
| 1764 | 明和元 | 輸出向けの俵物三品の増産を奨励 この頃江戸では、江戸で土平と称する飴が流行る |
英:産業革命 | ||
| 1765 | 二 | ||||
| 1766 | 三 | 平井満右衛門が江戸深川洲崎で、塩焼を 始めたことにより人が集まり、 大紋やという料理屋ができる |
|||
| 1767 | 四 | ||||
| 1768 | 五 | ||||
| 1769 | 六 | ||||
| 1770 | 七 | ●仏:ルイ16世即位 | |||
| 1771 | 八 | NEW 第3回お蔭詣り(伊勢詣) | 東埔塞瓜の小さいものを唐茄子と称し 各地に広まる。江戸で阿多福餅が売り出される 『卓袱会席趣向帳』 |
||
| 1772 | 安永元 | 田沼意次、老中になる | この頃江戸では、 下谷広小路金沢・本町鈴木越後の菓子屋、 浅草並木・下谷車坂の大仏餅、駒形正直の蕎麦切、 真崎甲子屋の田楽、中橋のおまんずし、 回向院前・車坂下亀やの淡雪なら茶、 神田柄木町山藤・大橋新地楽庵・ 浮世小路百川の卓被料理などのほか、 深川竹市・同洲崎升屋・塩浜大紋や・ 芝口春日野・深川八幡宮二軒茶屋などの 料理屋が知られる |
ポーランド分割開始 | |
| 1773 | 二 | ||||
| 1774 | 三 | 杉田玄白『解体新書』翻訳開始 | |||
| 1775 | 四 | 米:独立戦争(〜83) | |||
| 1776 | 五 | 上田秋成『雨月物語』 | 米:独立宣言 | ||
| 1777 | 六 | ||||
| 1778 | 七 | ||||
| 1779 | 八 | ||||
| 1780 | 九 | ||||
| 1781 | 天明元 | この頃江戸では、 塩瀬の饅頭、本町の色紙豆腐、芝の三官飴、 弥左衛門の薄雪せんべい、麹町の助惣やき、 両国の幾世餅などが流行し、 牛御前の葛西太郎・大黒屋孫四郎・ 武蔵屋権三郎の麦斗庵、真崎の甲子屋、 中洲新地の四季庵、いせ町裏川岸の百川、 永代寺山内の二軒茶屋、深川洲崎の升屋宗助 の望陀欄などの料理茶屋が知られる |
|||
| 1782 | 二 | 天明の大飢饉始まる(〜87) | 『豆腐百珍』『豆華集』 | ||
| 1783 | 三 | 浅間山の大噴火 | 『豆腐百珍続編』 | ||
| 1784 | 四 | 田沼意知の暗殺 | |||
| 1785 | 五 | 『万宝料理献立集』『万宝料理秘密前編』 『鯛百珍料理秘密箱』『大根一式料理秘密箱』 『諸国名産大根料理秘伝抄』 |
『ザ・タイムズ』発刊 | ||
| 1786 | 六 | 家治(51歳)没、田沼意次の失脚 最上徳内ら千島探検 |
江戸浅草・心月院門前の与市が、 菜(とこ)ろねの根を割麦のようにして食し、 また葛のように製し、食物にも糊にも 用いられる工夫をしたという |
| ★ 年表-1 | ★ 年表-2 | ★ 年表-3 |
■ HOME ■