1月30日 2004
同じ穴のムジナ
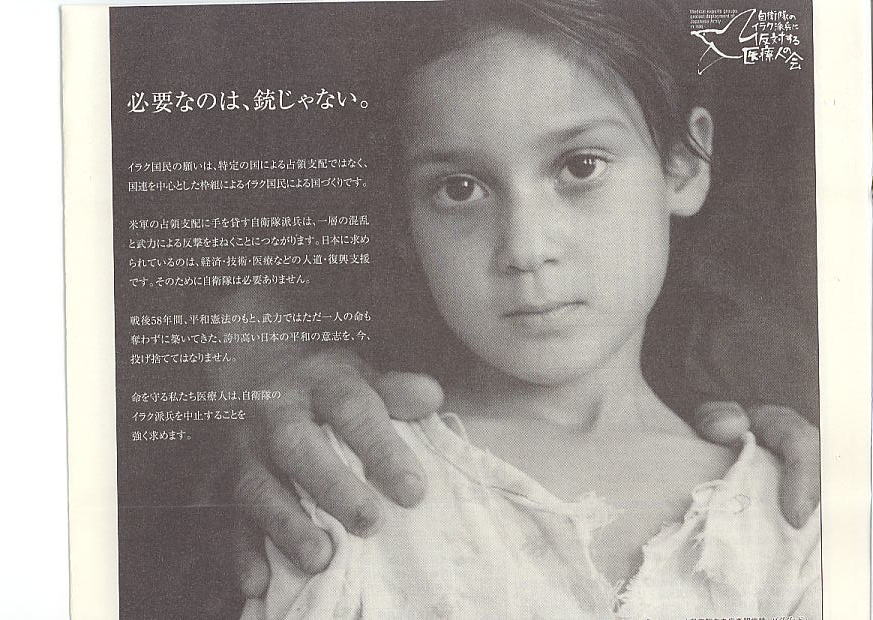
自衛隊がイラクに行くことに、反対する人の割合が減った。
それは、イラクで自衛隊がする予定の任務が、
人道援助であり、水の供給や、雇用の確保にあるから、
役に立つことはやるべきだという判断だと思う。
確かにその通りだけど、建て前がおかしい。
国連の要請の基に行くのならいいが、
アメリカの要請で行くのなら、占領軍の手先だ。
やることは同じでも、向こうでの評価も、国際的評価も違う。
元々、アメリカが、やるべきでない戦争をして、
イラクををむちゃくちゃにしたわけだから、
そのアメリカの要請で自衛隊を出すと
日本も同じ穴のムジナになってしまう。
せめて筋道を立ててもらいたい。
なんて言っても、所詮何も変わらないけど・・・。
でも、世論が、
既成事実に目をつむって容認してしまったら、しめしがつかない。
「イラクに自衛隊を派遣することの賛成ですか?」という質問自体も、
論点がすり替えられやすくなっている。
きちんと考えて、賛成反対を論じてほしいものだ。
僕は、マスコミの質問の形態を見直すべきだと思う。
でないと、首相は「世論から支持されている。」と言い出しかねない。
1月28日 2004
世界一高い広葉樹が紙に!
◇サイバーアクションにご参加ください!:
世界一高い広葉樹が伐採され、日本に売られ、紙や紙製品にされようと
しています。これらの木材チップを購入している日本の製紙企業に対し、購入
をとめるよう、日本の消費者である皆さんの声を届けてください!
http://www.greenpeace.or.jp/cyberaction/tasmania/index_html?sup
日本製紙は、「環境問題に配慮して、森林再生可能な伐採を行っている。」
と言っている。
その根拠は、
「彼らとその関係者が作った委員会の基準に沿って伐採を行っている。」から
だそうだ。
その基準が正しいという証明がなされない限り、信じがたい。
それに、世界一高い広葉樹は理屈抜きで守りたい。
賛同してくださる方は、上記のサイバーアクションに参加してください。
1月23日 2004
おやじの堕落・・・?
昨日1月22日はJAZZの日だそうだ。
1月Januaryの頭二文字のJaと、
ZZが22に似ているから、そうなったそうだ。
僕は、インストルメンタルジャズよりは
ジャズボーカルが好きで、
今から思えば、生意気なガキで、(兄やその友人の影響が大きい)
小学生の時にナットキングコールを聴いていたのが、
その始まりだった。
中学に入って、ニーナシモンに魅せられて、それからずっと、
JAZZボーカルを主に聴いてきた。
勿論、ハーレムノクターンなどのテナーサックスも好きだけど、
マイルスディビスやチックコリアは、退屈してしまう。
大学生になると、安物のウィスキーを飲みながら
夜更けによく聴いたものだ。
最近は、ゆっくりと酒でも飲みながら、
JAZZを聴くことがなくなった。
JAZZは、やっぱりウィスキーが合う様に思う。
本来はバーボンウィスキーなのだろう。
(僕が飲んでたウィスキーはサントリーオールドだった。
スコッチだから、ちょっと違うのかな。)
いまでは、ゆとりがなくなったのだろうか?
音楽は、ほとんど車に乗っている時に聴くだけになってしまっている。
しかし、車に乗っている時に聴くのは、どうしても、
メリハリのきいた、アップテンポのものになってしまう。
アニメソングとか、
60年代の(悲しき雨音などの)ヒットソング特集
がよく合うような気がするのは、僕だけだろうか?
「今夜は、ゆっくりJAZZを聴きながらウィスキーでも飲もうか」
と思ったが、「探偵ナイトスクープ」を見ないといけないし、
その後も、「スカイハイ」があるし・・・。
こうして、今日も、おやじはJAZZを聴かないで寝るのであった。
1月21日 2004
本当にそれでいいの?
鳥インフルエンザで世間は大騒動になってきた。
「種の壁を越えて、新型インフルエンザが流行すれば、
国内で三千二百万人が感染、三万〜四万人が死亡する可能性がある」。
という試算もある。
確かに人類にとって、SARSよりも遙かに脅威である。
しかし、その周囲の鶏を殺すだけで、
果たして事態が解決するのだろうか?
97−98年に香港で6人が死に、昨年はオランダで獣医が死んだ。
昨年末から韓国で流行っている鳥インフルエンザと
どうやら同じタイプのものがベトナムや日本で相次いで出現している。
鶏を大量に殺しているけれど、それは抜本的な対策ではなくて
脅威がひたひたと迫ってきている感じだ。
元々、鳥インフルエンザは渡り鳥が宿主
(ウィルスは持っているが発病しない)と言われている。
その渡り鳥が、鶏などの家畜にウィルスを感染させて
鶏などが大量死する。
その中で、ヒトにも感染するウィルスが出てきて、
更に人に感染することで、
更に人に感染しやすいウィルスが出現して、
ヒトからヒトに感染するようになって、
大流行が起こることが危惧されている訳だ。
では、鶏だけでなく、
渡り鳥も次々に殺しちゃえばいいのだろうか?
僕は、なんか間違っていると思う。
最近は、干潟が次々と無くなって、渡り鳥もその数がずいぶん減った。
何千キロも海を渡ってくる渡り鳥を歓迎こそすれ、排除したくはない。
それでなくても、彼らの居場所が少なくなって、申し訳ない状況なのに・・・。
人は、食用に、あるいは、
その卵を食用にするために多くの鶏を飼ってきた。
どっちにしろ殺すのだから、肉にするために殺すか、
感染防止で、ただ殺して土に埋めるかは結果は同じだけど、
なんだかずいぶん自分勝手な気がする。
SARSが発生したから、ハクビシンを大量に殺し、
狂牛病が出たから、牛を殺し、
鳥インフルエンザが出たから鶏を大量に殺す。
勿論、僕が厚労省の偉いさんだったら、
今している対処しかないのだから、そうするのだろうけど・・・。
なんか違うぞ!
僕は神を信じないけど、
「ばちが当たりそうだ。」と思ってしまう。
命と命のつながりって、そんなんじゃないように思う。
代替え案がある訳じゃないけど・・・。
なんだかあまりにも身勝手な気がする。
きっとうまくいかないように思えてしょうがない。
1月19日 2004
オプチミスト?
数日前、息子の受験する大学から封書が届いた。
返信用のそれではなく、手書きのものだ。
「何か特別のことがあるのだろうが、なんだろう?」
と思いながら、息子が封書を開けるのを待った。
「君だけ特別に合格にしてあげる!」
なんて書いてあるのではないかと、
めちゃくちゃ甘い考えを抱いていた。
世の中、そんなに甘くないのは、もう50年も生きてれば、
イヤってほど知っているのに・・・。
案の定、封書の中身は、
「入学願書を取り寄せてもらったが、
その手数料が、まだ払い込まれてないから
払え!」 というものであった。
これは、ただ単に、
僕が、オプチミストなのではなくて
僕の考えが甘いだけなのだ。
この甘さが、何年たっても治らないのは、
僕がオプチミストだから?
ではなくて、根本的に考えが甘いから・・・。かなぁ?
1月16日 2004
H5N1、おまえなのか?
世間が鳥インフルエンザで大騒動になっている。
どうしてそんなに騒ぎ立てるのか、ピンと来てない人もいると思う。
「たかだか鶏が大量死するくらいどうってことないじゃん。」
と思う人がいて当たり前だし、そう思える人のほうが、
マスコミに踊らせられていないのではないだろうか?
しかし、今回大騒ぎするのは訳がある。
大騒ぎする理由とは、ようするに、
1918年のスペイン風邪、57年のアジア風邪、
68年の香港風邪、77年のソ連風邪などのように
多くのヒトがそのために死んでしまうかもしれないからだ。
過去最大の被害を出したスペイン風邪では、
世界で4000万人以上が死亡したとされる。
スペイン風邪などの様に、
まだ人類が免疫を持ってないインフルエンザが流行ると、
人類の何%かが死の危機に直面する。
そして、その頃から変わりなく、
人類はインフルエンザに対する決定的治療法を持っていないからだ。
(確かに、タミフルやリレンザといった薬が出来たが、劇的な薬ではない。)
そして、そろそろ新しい型のインフルエンザが出現する時期を迎えている。
(歴史上、一定の周期で新しい型のインフルエンザが出現している。)
もう新たなインフルエンザウィルスが出現してもおかしくない。
では、どの様にして新しい型のインフルエンザが出現するのか?
今までの仮説は、
「鳥インフルエンザウィルスが突然変異して
人類にも感染するようになる。」というものなのだ。
もともと、鳥インフルエンザウィルスはヒトには感染しない。
というのは、
細胞には、その種独特のレセプター(鍵穴)があって、
(ヒトにはヒトの、鳥には鳥のレセプターがある。)
ウィルスはそのレセプターに結合してから細胞に感染する。
(鍵穴に結合する鍵がある。)
ヒトの細胞のレセプターと鳥の細胞のそれとは違うので、
鳥インフルエンザは普通、人には感染しない。
ところが、何らかの突然変異で、
鳥の細胞のレセプターにもヒトのそれにも結合するウィルスが出現すると
ヒトにも感染るようになる。
(ヒトの鍵穴にも、鳥の鍵穴にも合う鍵の獲得)
今問題なのは、
「ヒトにも感染る鳥インフルエンザウィルスが出現してきたこと」なのだ。
今のところ、鳥からヒトだけで、ヒトからヒトの感染はないと言われている。
しかし、もうすでに、ヒトには感染る様になったのだ。
ヒトからヒトに感染しない保証はもうどこにもない。
鳥インフルエンザのウイルスは表面のタンパク質(鍵)が
鳥特有のもので、今のところ人間には感染しにくいが、
ブタや人間の体内に入ると
人間に感染しやすい新型インフルエンザウイルスに変異する可能性があるからだ。
今回検出されたウイルスが
香港や韓国で見つかったものと同じ「H5N1型」だったことも、
不気味である。感染ルートの解明が出来るかどうかは難しい。
渡り鳥かもしれない。
(ウイルスの宿主のカモは無症状だが、
ニワトリでは下痢などの症状がみられ、死亡することもある。)
もしそうなら、すでに鳥の間にはかなり蔓延していることになる。
(鳥インフルエンザ:
A型インフルエンザウイルスが感染して起きる鳥の病気。
死亡率の高いものを高病原性鳥インフルエンザという。
ウイルス表面の抗原の型によってH5N1、H7N7などに分類される。)
鳥からヒトへのインフルエンザの蔓延が、どの様にして起こるのか?
まだ人類は知らない。
今、そのことが目の前で起こりつつある現場に
我々はいるのかもしれない。
とても興味あることだけど、
もしそうなったら僕などもろにあぶない!
どっちにしろ、SARSよりずっと怖い!
話は変わるが、
尊厳死の宣言文書に下記のことを追加した。
尊厳死宣言している場合、医療現場で、
助かるかもしれない状態での救命処置を差し控えられる可能性があるからだ。
「たとえば、致死的な原疾患のない状態での
心室細動などでの突然死に対しての蘇生術(ACLS)は、
この文書があるからといって、施行を差し控えないでください。」
1月15日 2004
麻婆豆腐
最近、麻婆豆腐をよく作る。
陳健一のレシピで作ると、とってもおいしくできる。
結構簡単なので、お披露目しようと思う。
4人前のレシピ
(我が家は大食いなのでこれで2人前くらい。
麻婆丼にする事がほとんどだけど、
豆腐を入れないで、焼きそばの麺にからめて担々麺風もいける。)
とても辛いので、レシピ通りだと子供は食べられないから、
豆板醤と一味唐辛子は、相手によって減らした方がよい。
大人でも相当辛いので、豆板醤は大さじ1くらいでも良いと思う。
無しでもいけるそうだが、僕にはちょっと・・・。
材料
木綿豆腐 一丁
ネギ 10cm
豚挽肉 120g(牛はまた違った味が楽しめる。)
一味唐辛子 小さじ1
トウチジャン 小さじ1/2
甜麺醤(テンメンジャン) 大さじ1
豆板醤 大さじ2
おろしニンニク 小さじ1
ガラスープ 200ml
老酒(紹興酒) 大さじ1
塩 少々
醤油 大さじ1
砂糖 少々
水溶き片栗粉 大さじ1強
油または鶏油 大さじ1
作り方
1.下ごしらえ
豆腐は1.5cm角の大きさに切り、ネギはみじん切りにする。
2.炒める
鍋を熱して油をなじませ、豚挽肉を炒める。
油が澄んできたら、
一味唐辛子 小さじ1
トウチ 小さじ1/2
甜麺醤 大さじ1
豆板醤 大さじ1〜2
ニンニク 小さじ1
を加えて炒める。
3.煮込む
2.にガラスープを加えて、
豆腐、老酒を入れて弱火にして、焦がさないように鍋を揺すりながら
しばらく煮込む。
4.仕上げる。
グツグツしてきたら、塩、醤油、コショウ、砂糖、ネギを加える。
水溶き片栗粉を少しずつ回し入れて、沸騰させる。
油(または鶏油)を加える。
一度試してごらんあれ。
そんじょそこらの中華料理屋の麻婆豆腐の百倍は美味いと思う。
1月13日 2004
どっちでもいいけど・・・
今日の夕刊で、BSE問題の一つである牛背骨の廃棄に関して、
厚労省と農水省で押し付け合いが起こっていて、
廃棄するにも出来ない状態になっているみたいだ。
厚労省は、「大豆の絞りかすが”食品でない”のと同様に牛背骨は食品ではない。」
と言って「牛背骨の廃棄の管轄は農水省だ。」と主張しているし、
農水省は、「ふぐの毒の部分と同じだから、管轄は厚労省だ。」と言っている。
まぁ、どっちでも良いけど、
僕の大好きなおからをバカにするなぁ〜!
ところで、テールスープってもう食べられなくなるの?
1月 7日 2004
結局、同じことだけど・・・。
今日、気が付いたら、別の水槽に移しておいたエビが死んでいた。
「どうせなら、ミエハルに食わせてやれば良かった。」
などと、罰当たりなことを言っていたが、
もし、実際にそんなことをしたら、
きっと、下の息子は怒ってしまうだろうな!
おもわず、にんまりしてしまった。
(これがおじさんの感性?)
1月 6日 2004
若者の感性
昨日、家の水槽で大事件が発生した。
以前から飼っているコメットという種類の金魚は、
大変元気で食欲旺盛である。
えさも豊富ですくすくと育った。
体長はすでに10cmを超えていると思う。
名前は、「ミエハル」である。
顔の柄が歌舞伎役者の様なので、
歌舞伎役者が見得を切ることからそんな名前になった。
他にもエンジェルフィッシュやカラフルなメダカの仲間がいる。
さらに、名前不明の貝やら石巻貝もいる。
そして、淡水のエビもいる。
今回の大事件は、このエビである。
はじめの頃は、ミエハルはそんなに大きくなく
エビはミエハルの口にはいるとはとうてい思えなかった。
ミエハルが大きくなってきても、
エビにそんなに関心は示す様子はなかった。
金魚はエビを食べる習性はないのだろうとたかをくくっていた。
エビもけっこう大胆に水槽の中を移動していた。
備長炭を重ねて作ったエビの家があって、
エビは普段、その中にいるけど、時々大胆に散歩していたし、
ミエハルや他の魚の目の前を泳ぐこともあった。
ところが、昨日、家族がミエハルの口から変なものが出ていることに気づいた。
よく見るとエビの足の様なものがある。
エビは4匹いたのだが、2匹に減っていた。
中学生の息子は、ひどくショックを受けていた。
夕食の食欲まで落ちていた。
水槽の中は、弱肉強食の世界である。
仕方のないことではあるが、にわかに受け入れがたかったのだろう。
そう言えば、以前に甥と海水浴に行って、クラゲを見つけた。
陸に揚げてつぶしていると、泣きながらやめてほしいと懇願された。
やはり、甥が中学生くらいの時であった。
彼の優しさにハッとして、胸を打たれた。
彼は、きっと将来良い医者になるのだろうと思った。
(かわいそうなことに、彼は医者になる以外の選択肢を親から提示されていない。)
中学生くらいの頃の、未完成だが優しい感性は大切にしていきたいものだ。
ちなみに、生き残ったエビは別の水槽で暮らすことになった。
1月 5日 2004
今年もよろしく!
あっという間に、今年が始まってしまった。
これからくる時を待つのは長いのに、
時が去っていくのはずいぶん早く感じられる。
そんな風に思うのは年をとったせいだろうか?
今日読んだ日医ニュースのオピニオンという企画に、
小柴昌俊さんの寄稿があった。
少しかいつまんで紹介したい。
ノーベル賞への道
小柴氏は、父親が軍人だった関係で、
当時のエリートコースの陸軍幼年学校を目指していた。
その準備中の中学一年の時に小児マヒとジフテリアに罹った。
ある朝目覚めると体が動かない様になる形で突然に発症した。
手足にマヒが残り、一度転ぶと一人では起きあがれない状態で挫折感を味わった。
ひたすらリハビリを行ったが、
右手のマヒは現在も残ってかなり不自由な生活を余儀なくされている。
そんな事情で、軍人はあきらめて高等学校に進むことにした。
ところが、その高等学校進学も2度の受験に失敗し、高校浪人を経験。
奮起してようやく一高に合格したものの、
捕虜となった父親に代わって家族を養うために、
肉体労働と家庭教師のアルバイトに明け暮れして、
「生活はどん底、成績もどん底」状態が続いた。
東大の物理をビリで卒業したという話は真実に近い。
そのため就職口もなく、とりあえず大学院へ。
そこでようやく自分のやりたいことにめぐり会えて
後は目標にまっしぐらであった。
「平成基礎科学財団」の設立
ニュートリノの発見が、人間にとってどの様に役に立つのか?
今、ニュートリノの発見が何かの役に立つ、
あるいは、商売に結びつくとは考えにくい。
しかし、19世紀末の電子の発見が、
現在のエレクトロニクス産業へと飛躍的に発展した事実もある。
基礎科学の発展なくして、人類の未来はないと言っても過言ではない。
本来このような地味な部分の支援は、
景気に左右されずに国が率先して行うべきである。
今のままでは日本の基礎科学は衰退の一途をたどることにもなりかねない。
そんなわけで、平成15年10月に「平成基礎科学財団」を設立した。
この財団は、
若い世代に基礎科学の楽しさを知ってもらうことを目的としている。
この財団の初期基金として
ノーベル賞およびウルフ賞の賞金全額(約4千万円)を寄付した。
この小さな種がいずれ芽を出し、実をつけてくれるのを期待したい。
若い人へのメッセージ
1.「学校の成績が人間の一生を決めてしまうことなんてない。
成績が悪くたってやりたいことはやれる。」
学業成績は、教えられたことを理解する、いわば、受動的認識である。
社会は、自ら考え、解決法を模索するという能動的態度が大きくものをいう世界である。
2.「いつか達成したいと思っている『卵』をもつこと。」
この卵を持っていると、情報過多の世の中でも、
おのずと情報の取捨選択が出来る。そうすれば、情報に振り回されることなく、
効率よく研究が進む。もし、運が良ければ、卵が雛にかえるかもしれない。
3.「人との出会いを大切に!」
私(小柴氏)が今日あるのは、良き人々との出会いのおかげである。
多くの人とのふれあいを大切にしてほしい。
決して、順風満帆ではなかったのだ。
「私は、小児マヒで人生の目標を打ち砕かれたが、
この病気にかからなければ、今日の自分はなかったとも言える。」と回想されている。