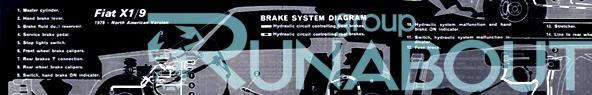|
■その時代背景
1960年代に入り、FIATはそれまでのRR式、コンパクトボディの600*1 ではボディやエンジンのキャパシティが小さいと感じてきた。そこで、1965年をめどに600より少し大きなモデルを造り、世代交代することを決める。こうして開発されたのが、Tipo100Gであり、1964年5月、850として発表された。翌年、この850にはクーペとスパイダー*2 が加えられる。セダンと同じホイルベース上に載るそのボディはクーペが社内デザイン、スパイダーのその素晴らしく優雅なデザインはあのカッロツェリア・ベルトーネによるもの(チーフデザイナーはGiorgio Giugiaro)だった。1965年から1973年まで、このオープン2シーターのBertoneは主に北米向けに輸出され、結果13万2536台もの大量生産を記録した。
その間、FIATとしては今までにないFWD(全輪駆動)への挑戦をしていた。FWDは過去に何度か試みたが(Tipo102)、結局コストがかかり信頼性に欠けるため実現しなかった。ダンテ・ジアコーサ率いる開発チームはエンジンをギアボックスごと横置きするという手法を考える。これなら、天地方向だけでなく前後方向の寸法も、ミニに比べて短くすることができた。当然幅は広くなってしまうが、それでも、ギアボックスの小型化、トレッドの拡張などで可能なことがわかった。これが世に言うジア・コーサ式!
とは言え、当時社長であったビットリオ・バレッタ*3 はこのモデルをいきなりFIATの市販車として発表するのはリスクが大きいと考え、いわばテストをかねてアウトビアンキ・ブランド*4 で販売することを決定した。そして、開発コードTipo109のこのFF車は1964年半ばアウトビアンキ・プリムラ*5 の名でデビューしたのだ。
続いてジアコーサは同じメカニズムでFIATブランドモデルの開発に出る。X1/1という、それまでと違った開発コードを与えられたこのモデルはプリムラの1089ccエンジンに対し1116ccから最終的に1290ccというサイズのSOHC方式をとり、しかもカムシャフトの駆動には124のDOHCエンジンと同じコグド・ベルトを使用していた。(それまではOHVが一般)さらに足回りはコイルを用いたマクファーソンストラット、リアはウィッシュボーン+横置きリーフの組み合わせによる独立懸架へと進化した。
【1969年3月】X1/1は128としてデビューし、その2年後、850クーペの後継者的位置づけで128スポルト・クーペ*6 を発表する。社内デザインによるクーペはホイルベースを2223mmとセダンのそれ(2448mm)より大幅に縮められており、ボディも小柄で軽快だった。1116ccエンジンは64hpにパワーパップされたほか、新たに1290cc75hpエンジンも設定された。またセダンのボディにこの1290ccエンジン(ただし67hp)を搭載した128ラリー*7 も追加される。
ここまでの流れを見れば、皆さんもおのずと察しがつくであろう。そう、850Spiderに乗るスポーツカー好きの若者はしばらくはそれで満足だったが、新しい128ベースの2シータースポーツをだれもが欲しがったのだよ明智君(古いか・・・)
X1/1からかなり遅れて開発がスタートしたX1/9プロジェクトはまさにこのような流れの中で始められたが、けしてこれが初めてではなかった。(ここが一般の解説書とは違うところ)あの850SpiderをデザインしたBertoneは数々のニューモデルが発表される中、FIATとのつながりを常に意識していた。従って、128セダンが発表される前に彼らは新しいFWDユニットでの“128Spider”の開発を1968-1969年ごろ始めていたのだ!!!
しか〜〜〜っし!BMCのミニと同様、FWDのパワーユニットではボディーをスポーティーにすることは難しかったのだよ。マーコス・ミニなどを見れば一目瞭然。するとベルトーネはミッド・エンジンという冒険的なコンセプトを考え出してしまったのだ!
Nuccio Bertoneはそれも面白いと考えた。なぜなら、Bertoneのデザイナーはランボルギーニ・ミウラ*8 やマルツァル*9 ですでにすばらしいMidShipデザインの車を生産していたし、それをより小さなスケール上で展開できることに魅力を感じていた。(ミウラで12気筒エンジンを横置きしたのはあまりにも無理があったことは確かだよ)
MGのデザイナーを2.3年後にあっと驚かせるその手法はFWD車からエンジン、トランスミッション、基本的サスペンションをそのままシートの後ろに移植することだった。言うなればそれは、後のフェラーリ512やポルシェ917にも通ずるミドエンジンレイアウトであった。ベルトーネはとりあえず、その手法(MR)と128ベースの手法(FF)をFIATに提示したが、首脳陣は伝統的FIATの新しい標準であるFFモデルのほうに、好感をもったようだ。
となると、Bertoneは世論の反応を見るためにスペシャルショーカーを発表する。これが我がクラブの名称ともなった“Runabout”というわけだ。FIATのミッドエンジン車として提案するこの車は2シーター・オープンボディーとして、大急ぎで開発が進められた。しかし、想定したエンジンはOHV903ccのAutobianchiA112用エンジンにすぎなかったのだよ。
【1969年11月】トリノショーで発表されたAutobianchi Runabout*10 はかなりの注目を集める。夢のようなフォルムのその車は2度と見ることのない走ることのできないショーカーだったのだよ。(しかしAutocar誌はエンジンが後ろにあることを完全に見落としていた;エンジンは載っていなかったとも聞く)
たしかに、このドリームショーカーはBertoneが128のパワーユニットをこの車に置き換えるまでプロトタイプにとどまった。しかし、その案は当時のFIAT社長Giovanni Agnelli*11 によってすぐに現実のものとなった。新しいミッド・エンジンのコンセプトは850Spiderの後継車として正式にFIATに受け入れられたのだ。
開発コードX1/9を名乗るこの車は北米の安全基準に合わせてボディーを設計することが必然だった。それはかなり難航したが結果的に余裕でクリアできる内容のものとなった。その製造を受け持つ当時のBertone工場はFIATのミラフォリオ工場の西、約5キロほど離れたトリノの郊外Grugliascoにあった。ボディプレス機やペイント室、組み立てラインなど、かなりの特殊化されたボディを大量生産することができた。そして、完成された車をFIATがテストし、世界中に販売する。おそらく、すべて車のボディにはBertoneのバッジが確認できるだろう。
【1971年11月】このような準備が着々と進んでいる中、FIATとBertoneはのトリノショーで彼らの全く知らない別の車が、開発中のX1/9に極似していることに驚くのである。問題の車はデ・トマソのブースより発表された、DeTomaso1600*12 でありカロツェリア・ギアのTomTjardaによってデザインされたものだった。
結局、それらが似ているのは偶然の一致ではないことがわかる。DeTomasoの歴史家Wallace Wyssによれば、彼らが1年はやく発表した車はイタリアの自動車雑誌に載った新しいベルトーネ車のデザインスケッチ(盗撮か?)をただ参照しただけだと。
デ・トマソのプロジェクトはRS1600ラリーに搭載されるフォードBDAユニット(16バルブ/ツインカム)を同じようにシートの後ろに横置きにするというものだった。また、別の見方としてTomTjardaの開発を助けるためベルトーネのエンジニアが裏で仕事したのではないかともうわさされる。デ・トマソはその後そのプロジェクトを実際に市販車に移すことはなく、そのプロトタイプカーは完全に消えてしまった。
|
*1 開発コードTipo100。ダンテジアコーサは同じモデルを異なる駆動方式;、RR(Tipo100), FF(Tipo102), FR(Tipo103)で進めていた

*2 当時ベルトーネのチーフデザイナージウジアーロによる850スパイダー
*3 1945年FIAT創設者ジャバンニが亡くなった後を継ぐ、孫のジャバンニ・アニエッリが後継ぎとして成熟するまでの中継ぎとして采配をふるった。もとは会計士
*4 アウトビアンキは1955年経営不振に陥っていたビアンキ社(1899年創立)にフィアットとタイヤ・メーカーのピレリが援助することで組織された会社で、いわばFIATの子会社的存在。

*5 Autobianchi Primula 128のパイロットモデルであるこの車はFIATの大規模な横置きエンジン開発プロジェクトの結果であり、最終的にはX1/9プロジェクトにも深くかかわりのあるモデルである。

*6 128 Coupe ボディは850クーペと同じ社内デザインによる。1290cc75hpのエンジンはX1/9とほぼ同じ。

*7 128 Rally 1971年スポルトクーぺとともに追加されたモデル
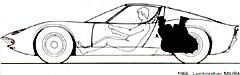
*8 Lamborghini MIURA 1966
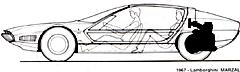
*9 Lamborghini MARZAL 1967

Bertone SHAKE 128のパワーユニットを使ったいわば、X1/9用テスト車?

*10 Autobianchi Runabout

*11 Giovanni Agnell 右は祖父のジョバンニ。FIATの初代社長。この写真は1951年当時、ジャンニは30歳。

*12 DeTomaso1600 洋書を読んでもまだ謎ではある。
|