| トップページへ | 身近な気象の目次 |
目次
2.1 はしがき
2.2 蒸発・降水を熱エネルギーの流れからみる
2.3 雨量計の捕捉率は風速と共に低下する
2.4 観測誤差の小さい暖候期(5~9月)の降水量の長期変化
2.5 温暖化で西太平洋の蒸発量は増えるか?
まとめ
文献
謝辞
本稿の作成にあたり東京大学の木村龍治名誉教授に
ご協力いただいた。ここに厚く御礼申し上げる。
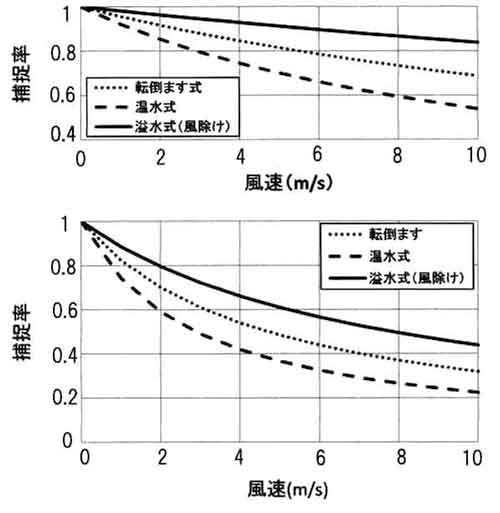
| トップページへ | 身近な気象の目次 |