| トップページへ | 研究指針の目次 |
目次
221.1 まえがき
221.2 大気汚染と混濁係数
221.3 暖候期(5月~9月)の海面熱収支計算に必要な諸要素
(1)平均放射量と平均気温
(2)海洋貯熱量・海洋運搬熱発散量
(3)海上の平均風速と相対湿度
221.4 暖候期降水量と日本周辺海域の蒸発量
(4)日本の暖候期の降水量観測値の長期変化
(5)日射量の違いによる日本周辺海域の蒸発量計算値の変化
(6)大気汚染による日射量計算値の減少
(7)日本の暖候期の森林蒸発散量
221.5 気温が+1℃と+2℃上昇時代の周辺海域の暖候期蒸発量の予測
(8)大気放射量増加の計算
(9)日射量の計算
(10)計算に必要な諸要素のまとめ
(11)温暖化と大気汚染の減少による日本周辺海域の蒸発量増加の計算
まとめ
付録
付録1 暖候期(5月~9月)の日平均日射量の計算
付録2 気象庁の全天日射量観測値の精度
文献
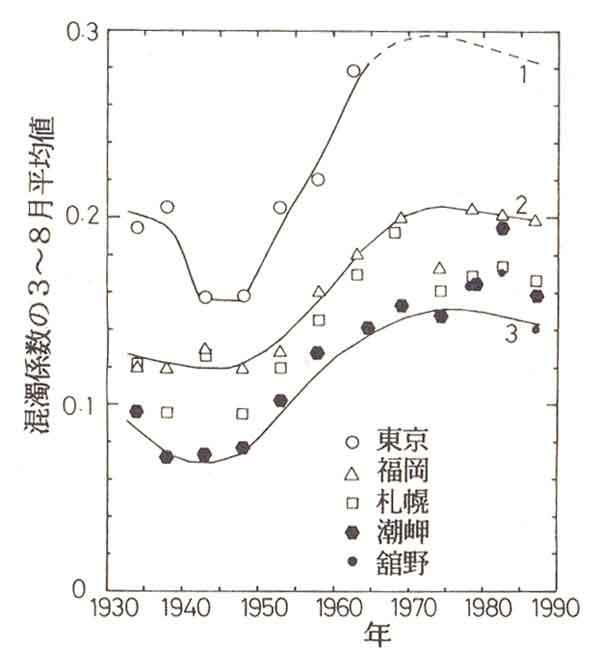
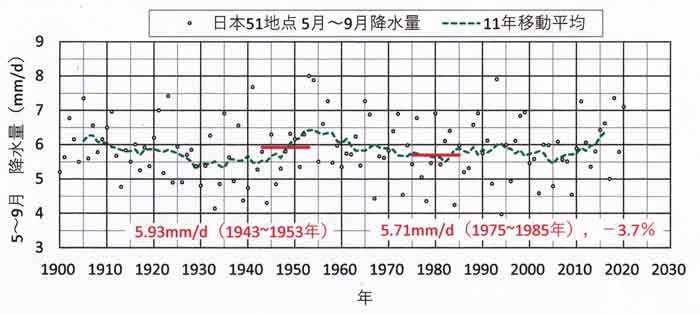
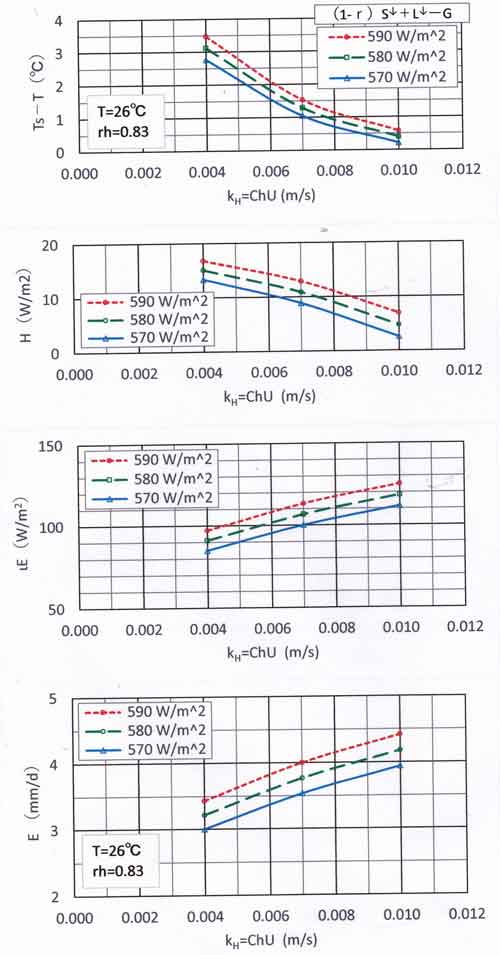

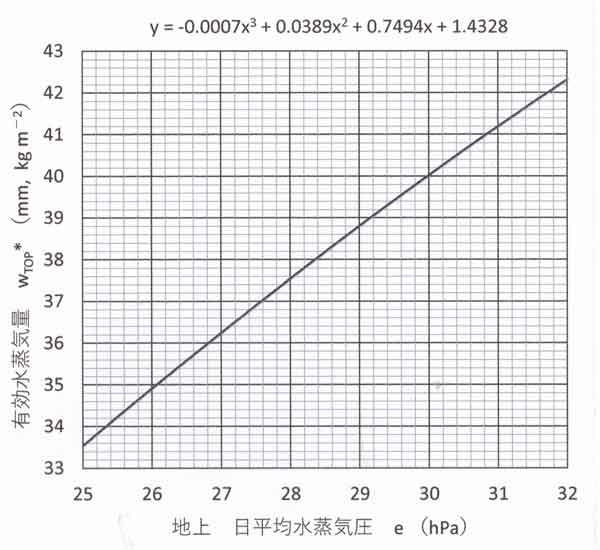
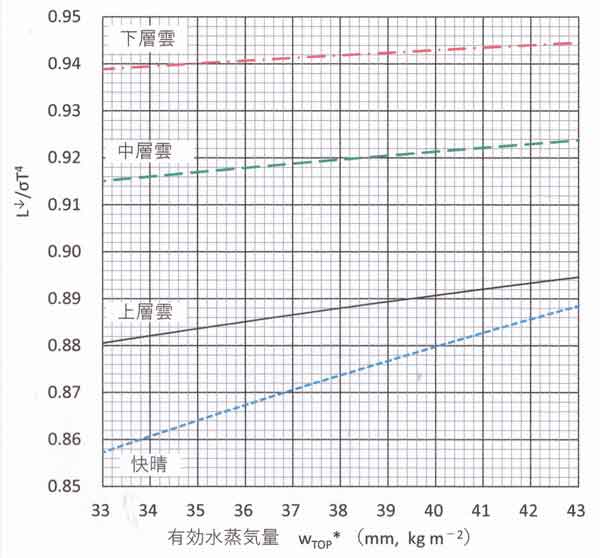
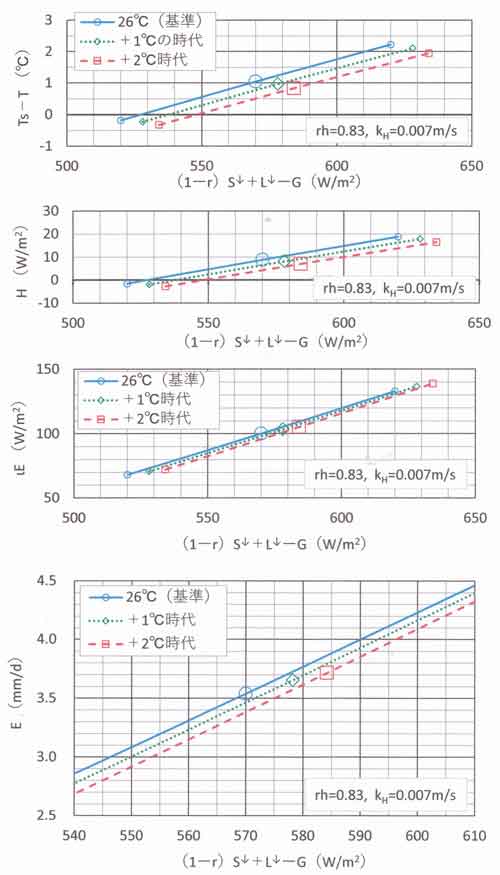
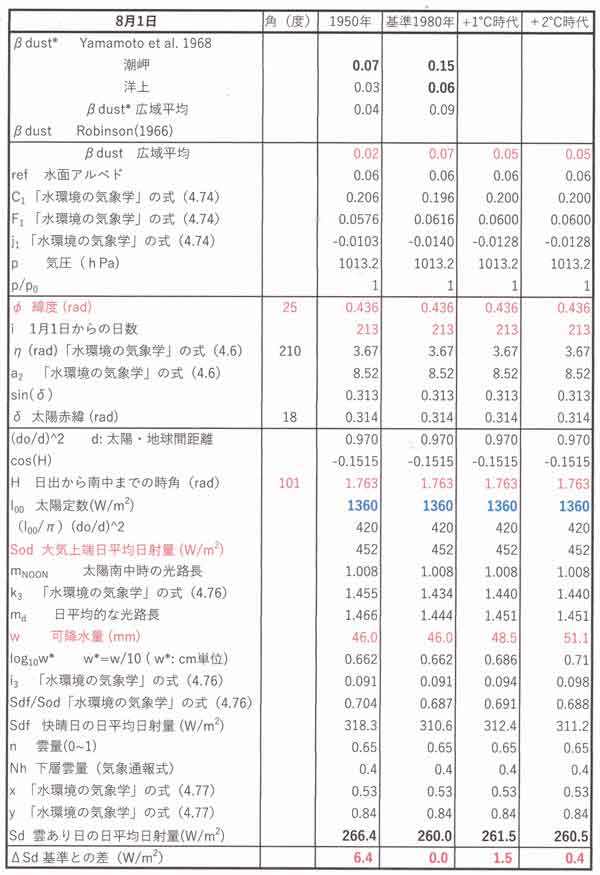
| トップページへ | 研究指針の目次 |