ことばをめぐるひとりごと
その13
貝の字になって泣く
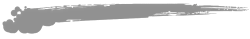 「〜の字になる」という言い方があります。たとえば、「大の字になる(=手足を伸ばして寝ころぶ)」「くの字になる(折れ曲がる)」「口をへの字に結ぶ(曲げる)」「八の字をよせて(=眉をひそめて)考える」など。「親子が川の字なりになって寝る」と言えば、子どもを挟んで夫婦が寝ている様子になります。
もう古くなった言い方では「膝にのの字を書く」というのもあります。正座をした人が恥ずかしがってもじもじする様子です。この際、逆引き辞典に頼っていうと、役者の路考さんが考えた帯の結び方は「やの字」と呼ばれました。その名のとおり、ひらがなの「や」に似た結び方だからだそうです。
こうした「大の字」などのかなり古い祖先と思われるものの一つが、「源氏物語」に出ています。それは「貝を作る」という言い方です。
「今日の御送りに仕うまつらぬこと」など申して、〔入道が〕かひをつくる
もいとほしながら、若き人は笑ひぬべし。
(明石巻)
これは、「泣く」ということです。しかし、どうして「泣く」ことが「貝を作る」なのでしょう? ある辞書によれば、「泣き出すときの口つきが、ハマグリの形に似ているところから」だと言いますが、ちょっと信用しがたい説です。また、別の解説では、「貝」の字の草書が、泣き顔に似ているからだと言います。これもどうもすっきりしません。
「大の字になって……」「くの字に曲がって……」などの言い方は、ものの形が文字でうまく表現されています。それに比べて、「貝」の字の草書を見ても、あまり泣き顔に似ているとは思えないのです。
そこで、「貝」の字をじっくり観察してみる。すると、「目」の下にチョンチョンと点が書かれています。見ようによっては涙のように見えます。
これは、目の下に涙が出ているので「泣く」だ、という一種の「字なぞ」と考えてはどうでしょうか。後世の「大の字」「くの字」などと同じで、うまく字の形をとらえているのです。偉い先生は、むずかしく考えて、かえって誤りに陥ることもないとはいえないでしょう。
(1997年記)
|