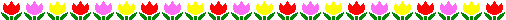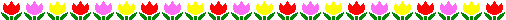(序)おことわり
さて、今回は件のコロ助の病気について、お医者さんに伺ったことを
まとめ直してみたレポートです。
第一弾のレポートと今回のレポートの内容に矛盾があったり、
表現が微妙に食い違っているような場合は、今回のレポートを
「正」としてください。
1回目のレポートの際、勘違いして書いた部分があります。
お詫びするとともに、このレポートをもって訂正させて頂きます。
|
(1)症状のおさらい
コロ助の症状についておさらいします。
1.腕の付け根部分の毛が抜け、露出した皮膚が赤みを帯びる。
2.脱毛部が、肘のほうに広がり、皮膚があれる。
3.荒れた皮膚が、赤黒く腫れ、コブ状にふくれる。
また、これらの症状への医師の答えは、
4.皮膚につく寄生虫によるものではないかと考えられているが、
その寄生虫の種類、名前については、特定されていない。
というものでした。
|
(2)発症のメカニズム
まず、動物の皮膚につき、同じような症状を引き起こすもので、
原因となる寄生虫や、治療方法のはっきりしている犬の場合について
まとめてみます。
動物の肌には、何らかの虫が寄生しており、それがふつうです。
彼らは、普段は宿主を困らせないのですが、宿主が体調や環境の変化で抵抗力を落
としたりすると、急激に増殖したり寄生する範囲を広げたり
して、宿主との暗黙のルールやバランスを破ります。
すると、普段は寄生されていることに気づかずいられるものが
かゆみや炎症などの刺激を引き起こし、宿主が患部を掻くことで、
さらに肌が弱くなり、症状が悪化する悪循環を引き起こします。
肌がただれたり、腫れて出血したりします。
犬の場合、疥癬(かいせん)虫やアカラスという寄生虫が知られています。
コロ助をはじめ、最近動物病院に持ち込まれるハムスターの多くに
みられる症状は、犬の疥癬虫による症状と良く似ているようです。
(犬の場合は、顔に症状が出るという点は違いますが)
また、疥癬虫に使う薬に、ハムスターの寄生虫も反応を示すので、
疥癬虫と良く似た系統のものではないかと考えられているそうです。
|
(3)なぜ寄生虫を特定できないのか
ではなぜ、「犬の寄生虫と良く似ている」ことまで分かっているのに、
ハムスターの寄生虫が種類や、名前を特定できていないのでしょうか。
1.ハムスター特にここ1.2年で急増したドワーフ系のハムスターについては、
症例や研究が少ない。学会の報告や動物医の機関紙などでも
「飼い方についての指導方法」などが紹介されるレベル。
2.これらの寄生虫は、真皮の深いところに寄生している。犬の場合は
患部の1部をえぐり取ってサンプリングし、顕微鏡で見るなどの検査が
可能ですが、犬に比べはるかに小柄なハムスターの場合、犬と同じようにサンプリ
ングしようとしても、患部の大部分を切り取ることになり
むしろ今の症状を悪化させることになる。
...という理由で、原因については、特定できないのだそうです。
|
(4)診断的治療
そこで、原因となる寄生虫を特定するよりも、その症状を治療することに
主眼を置き、診断的治療を行っているそうです。
つまり...
1.犬の疥癬の症状と似ていることから、ハムスターに寄生する疥癬と似た種類の
寄生虫によるものと仮定する。
2.疥癬の除虫に使用する薬品を投与する。
3.2.の治療方法で、ほとんどのハムスターが完治したため、この症状に
対する処置として、正しいものと判断する。
というのが、この場合の診断的治療です。
|
(5)もうちょっと難しい診断的治療
前回述べたように、治療には、「週1回お医者さんでの投薬(疥癬の薬)」
と、「毎日2回家で投薬(抗生物質)」の2つを併用していますが、
これについて...
1.コロ助のような症状が、寄生虫だけによるものでなく、寄生虫により引き起こ
された症状と、それに伴う細菌による合併症のおそれがある。
2.そのためクロラムフェニコール系の抗菌作用のある抗生物質を併用している。
3.初めての症例から、常に疥癬の薬と抗生物質を併用しており、
完治した症例について、どちらの薬が効果を上げているかは分からない。
(家で抗生物質を飲ませるだけでも治るかもしれない。)
この辺が、診断的治療という所以であって、「どちらが効いているか分からないが
、とにかくこの2つの薬の併用で完治した例が多いですよ。どうしましょうか」と、
飼い主に確認を求める必要を感じて、診断的治療について
説明しているのだそうです。それで、話がややこしく感じたのだ。
4.ただし、細菌だけでは、こういった症状は起こりにくく、やはり、主な原因は
、疥癬虫によるものとして、処置している。
のだそうです。
|
(6)まとめ
1回目のレポートから、この「診断的治療」がらみで、どうもわかりにくい
レポートになっていたような気がします。
先生の説明は、もっとうまいんですが...どうも申し訳ない。
今回、コロ助の病気を通じていろいろなことを勉強させてもらいました。
飼い主として、成長した(薬をやるのがうまくなった程度ですが)ところ、
人間的に成長した(少しだけ優しい顔ができるようになったような)ところ、
なんかも、あるように思います。
現場も人生も経験こそが宝...ですか。
ただ、上にも書いたように、ハムスターの病気について、確立された部分が少ない
事...少し心配ですが、
お医者さんに、このホームページのことをお話したところ
「僕らの知識や治療とは別に、そういった活動を通して飼い主さんが
意識を高めあうって云うのは大切なことだと思いますよ」
と、ずいぶんと興味をもたれて、いろいろとお話しました。
また逆に、「実際飼っている方がどうされているかというお話は、
非常に参考になるのでまた教えて下さい」ともいわれました
たいへんうれしいですね。あちゅこママさん!
|