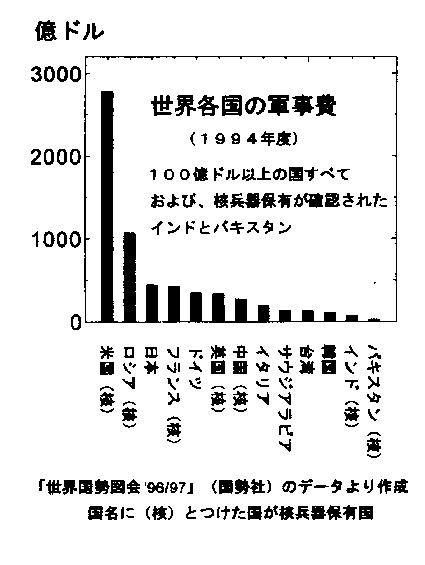原子力に必要な工程
原子力を利用しようとすれば、もちろん原子炉が必要だが、それ以外にも、ウランを掘ってくる作業から、燃料を加工する作業、生み出した放射性物質の始末の作業まで厖大な作業が必要となる。今回東海村で起きた事故は、そのうち燃料加工工場で起きた。
突発した事故
事故の本性に従って、今回もまた、事故は突然発生した。
高速増殖炉実験炉「常陽」の燃料用のウランを精製する作業を行っていた作業員が、ウラン溶液を「沈殿槽」と呼ばれる容器に注ぎ込んでいるときに、突然臨界状態が発生した。
燃料加工工場で、臨界事故を防止するためには、工場内の装置の形状や大きさに制限を付け、どんなにウランを集めようとしても、決して臨界にならないようにしておけばよい。事故を起こした作業の場合、一カ所に集めてよいウランの上限値は2.4kgであったが、沈殿槽はずんぐりした形状で、何故か140リッターもの容積があった。その中に、作業員がステンレスバケツを使った手作業でウラン溶液をそそぎ込み、合計で16.6kgのウランを入れたときに事故となったのであった。
作業員の被曝作業には、3人の作業貝が従事していて、それぞれの被曝量は18,10,3グレイ(グレイは物理的な被曝量の単位。人体の被曝量はシーベルトという単位で計り、1グレイは最低でも1シーベルト)と推定されている。吐き気、下痢、意識混濁など自覚的な急性放射線障害は、およそ1シーベルト以上の被曝をしなければ現れない。また、4シーベルトの被曝をすると半数の人が死に、8シーベルト以上の被曝をすれば、確実に死に至ると考えられてきた。3人の作業員は被曝後すぐに急性放射線症状を呈し、救急隊によって運び込まれた国立水戸病院では手の施しようがなく、放射線医学総合研究所、さらには東大病院へと移され、事故後すでに1月半たとうとしているが、存命で、闘病中である。
臨界収束作業
今回の臨界事故は、はじめの即発臨界で沈殿糟が破壊されず、その後も臨界状態が長期間続いたことが特徴であった。臨界を終わらせることは至上命令であり、そのために被曝覚悟の危険な作業が行われた。本抜き作業には、JCOの労働者が当たり、将来子供を作る可能性のある若い労働者は除外され、またあくまでも志願した労働者だけで行ったという。従事した作業員は、3人1チーム(1人は車の運転手)で数分毎の作業に従事したが、放射線業務従事者の年間線量限度(50mSv)を超えて被曝した人も10人近くに及んだ。また、緊急時の限度として設定されていた100mSvさえ超えて被曝してしまった人もいた。
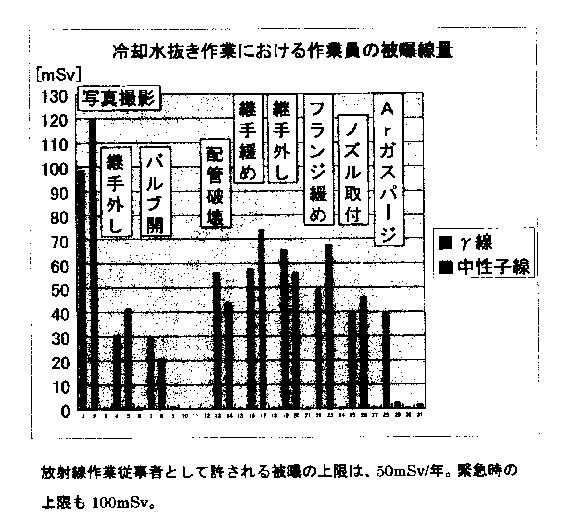
JCOには核分裂の連鎖反応で生じる中性子を検出する測定器すらがなかった。しかし、作業員の急性放射線症状を見て、JCOは事故後すぐに、臨界事故が発生したことを理解する。その後も、施設内や敷地境界に配置されていたガンマ線測定器が示す猛烈な線量を見て、JCOは13:56に東海村に行って、半径500m圏内の住民を避難させてくれるように要請する。
原子力施設の安全規制は国がすべて行うとされてきたため、東海村には何らの情報も流れてこなかったが、容易ならざる自体を前に、東海村は15:00になって、半径350m圏内住民の避難要請を出す。しかし、時すでに遅く、その時までに半径350m圏内の住民は、一般公衆が許される年間の被曝限度を超えて被曝してしまっていたし、事故が収束するまでの期間を考えれば、半径500m圏内の住民を避難させる必要があった。
希ガスによる被曝
核分裂の連鎖反応は不可避的に核分裂生成物を生むし、完全なガス体である希ガスの100%、揮発性のよう素の一部は周辺に漏洩した。特に、漏洩した希ガスは事故当日の風に乗って周辺各地に広がり、広範な地域のガンマ線モニタに異常値を記録させた。
日本には、世界に誇る「SPEEDI」という原子力防災専門のコンピュータ解析システムがあった。それによれば、事故現場から放出されてくる放射性物質の移動を時々刻々観測して、その移動の方向を予測し、住民を被曝から守るはずであった。ところが、そのシステムは全く動かなかった。周辺350m圏内の住民は、事故現場からおよそ1.3kmほどの地点にある舟石川コミュニティーセンターに避難させられたが、当日夜、事故現場からの風は舟石川に向かい、避難した住民たちを襲った。
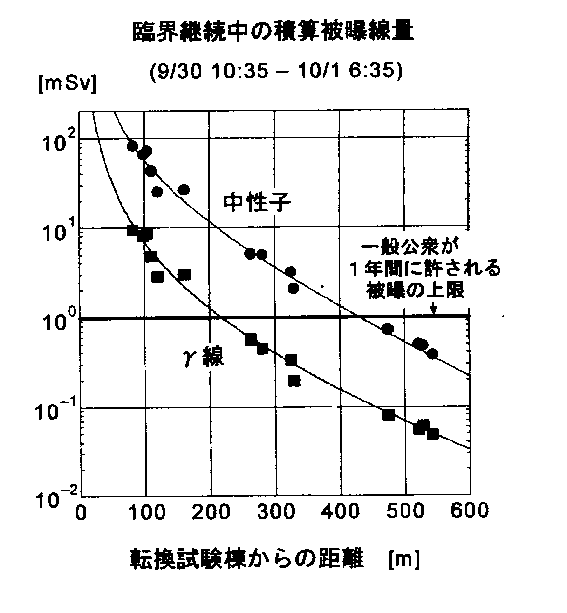
原子力施設の事故が起こった場合、希ガスに次いで環境に放出されやすいのは、よう素である。よう素は揮発性であるため、簡単に空気中に出てくるし、特に今回の事故の場合には、施設の換気系が動き続けていたり、建屋に換気扇が直接取り付けられていたりしたために、敷地境界を超えて、周辺環境にまで漏洩してきた。ただし、今回の事故の場合、核分裂したウランの量が1mgというような少量であり、漏洩してきた放射性よう素による汚染も、それ程大きなものではない。私が注意深く測ろうとしても、1km以上離れた地点の試料からは汚染が見付けられなかった。しかし、よう素を含めた放射性物質による汚染については、国が一切の情報を秘匿したため、50kmも100Ɠも離れた地点に住む人たちまでが深刻な不安に陥った。
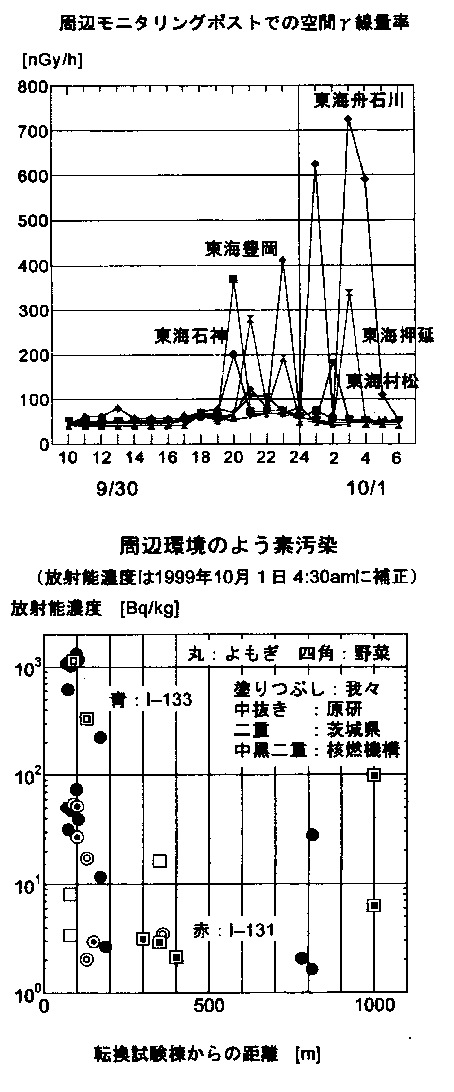
今回の事故の原因はいったい何なのだったのか?
事故当時、作業員はステンレスバケツでウランを硝酸に溶解し、それを沈殿槽につぎ込んでいた。一般には、原子力といえば、最先端の技術のように思われ、その現場でバケツが使われているということが衝撃として受け止められたようであった。しかし、何もかもが遠隔操作、コンピュータ制御で行われることなどありえず、どこでもそうであるように、原子力の現場においてもバケツの使用は同常的なことであった。その上、バケツを使うこの作業は、作業貝が独断で行っていたのではなく、会社のマニュアルとして定められていた。ただ、そのマニュアルは、この施設がはじめに国の認可を受ける時に提示されていたものからは変更されていた。
当初のマニュアルでは、ウランの溶解は別の槽で行われることになっていたし、溶解後はポンプで沈殿積とは別の貯塔と呼ばれる槽に移されることになっていた。その点をとらえて、国は勝手にマニュアルを変更したJCOに一切の責任があると主張している。しかし、施設を建設後、実際の作業にあわせてマニュアルを変更することなど、どこの現場でも行われているだろうし、それを許さないということであれば、現実の工場はどれひとつも動かないだろう。
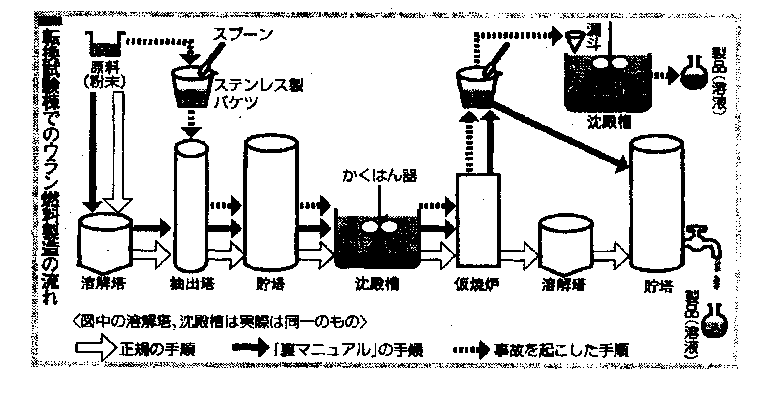
今回の事故の重要な教訓の一つは、原子力防災などもともと成り立たないということである。
科技庁が11月4目に示した評価によれば、敷地境界の外側で、事故後わずか25分の間に、最大で75ミリシーベルト(一般公衆が一年間にそれ以上浴びてはならないと法令で定められている被曝量に比べて、75倍)もの被曝をしていたという。その間、事故の深刻ささえ全く分からないまま、そして住民は何らの警告も受けないままひたすら放射線に被曝したのであった。
国、県、村などが事故後どのように対応したかを表に示す。
事故が発生したことは、ただちに消防暑に通報され、救急隊が被曝した作業員の救出にあたった。また、40分後には科技庁に、1時間後には東海村と、茨城県に通報されている。ところが、東海村が通報を受けて40分後には防災対策本部を立ち上げたのに対して、国では科技庁の中に災害対策本部ができたのが、通報を受けてから3時間15分、事故発生から計れば3時間55分もの時間がたってからであった。政府の事故対策委員会はそれから30分遅れたし、安全委員会の中に緊急助言者組織を作ることが決まったのはさらに30分遅く、事故発生から5時間もの時間がたっていた。その上、そうした組織が活動を始めるまでにはまたさらに長い時間が必要で、緊急助言者組織が初めて会合を開いたのは、実に事故後7時間半たってからであった。
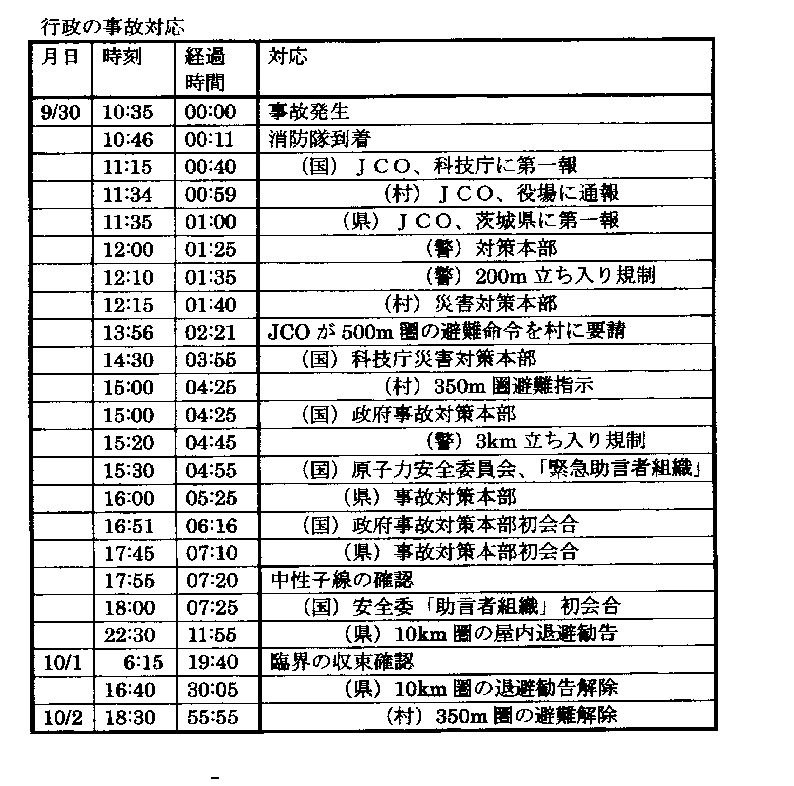
遅ればせながら始まった対応も、驚くべきものであった。臨界事故発生直後から、放射性希ガスが環境に漏洩したことは、モニタリングポストのデータを見れば、一目瞭然であった。放射性核種のうち、希ガスに次いで環境に放出されやすい核種はよう素であり、人体への影響も大きい。当然、よう素に対するモニタリングは、事故直後から精力的に行われたはずだと私は考えた。ところが、事故発生後、1日たっても、2日たっても、よう素を含め、希ガス以外の放射性核種がどのように環境に漏洩したかについては、まったく情報が出てこなからた。
東海村は、「原子力が地場産業」と言うように、日本原子力研究所(原研)、核燃料サイクル開発機構(核燃機構)をはじめ多数の原子力関連施設が立地し、事故が発生して以降、多数の専門家が事故への対応に当だったし、放射性物質による環境への影響も調べたはずであった。それでもなお汚染についての情報がないということは、汚染そのものが生じなかったということかもしれないと私自身が思いかけた。
それでも、よう素が全く漏洩しないでいてくれるとは思えなかったし、ちょうど10月2日の夜になって、荻野晃也さんが現地に行ってくれることになり、彼が採取してくれる試料を私が放射能測定することにした。彼が3日午前中にサンプリングした試料は直ちに宅急便で実験所に送られ、それを受け取った4日午前から私はGe半導体検出器によるγ線スペクトロメトリによって放射能測定を始めた。始めたとたんに、CRTのスペクトル上にI-131,I-133のピークが現れた。昼過ぎまでに概略を把握した私は、放射性よう素による環境汚染データをマスコミに公表し、あわせて科学技術庁に厖大に蓄積しているはずの関連データを公開させるように依頼した。マスコミからの問い合わせに対する科技庁の回答は、「放射性物質のデータはとりまとめ中で、いつ公表するかは分からない」というものであったという。
事故が発生した当日夜中になって、半径350m圏内の避難では不足であることが明らかになったが、夜中に避難範囲を拡大すれば「混乱が起きる」との理由で避難範囲の拡大は見送られ、住民はむざむざ被曝させられた。
原子力発電所が大事故を起こした場合には、まず何よりも風下に入らないようにしながら遠くに逃げることが大切であるにもかかわらず、国の防災計画では、住民は10mSv(許される被曝限度の10倍)から50mSvの被曝が予想されるようになってはじめて屋内退避するよう求められる。しかし、屋内退避などしても低減できる被曝量などごくわずかにしか過ぎない。
日本というこの国は、他の国と同じように、民を守る気などさらさらなく、ひたすら混乱の発生を防止することに腐心するのである。当然、国民に対して情報を明らかにしない方が得策だと考えている。かって、苦しい戦争に引きずり込まれた国民たちはいままた同じ歴史に引きずり込まれようとしている。
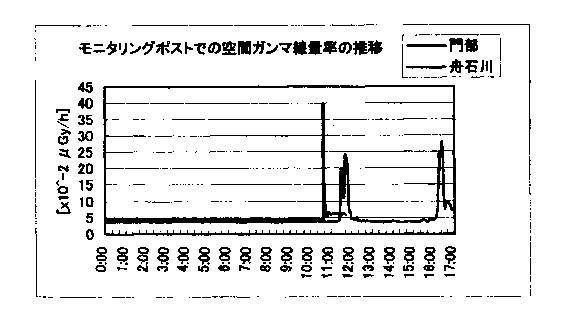
今回の事故と原子力発電所との比較今回の事故で燃えたウランの量はたかだか1mgである。広島原爆で燃えたウランは750gであるから、それの約100万分の1である。それでも、防災対策は実質的に機能しなかった。一方、今日標準的な原子力発電所では、1年間に1トンのウランが燃える。今回の事故に比べれば、10億倍に相当する。そうした施設で放射性物質が外部に放出されるような事故が起こった時に、なおかつ「お上」が有効な防災対策をとってくれると国民が期待するのであれば、また手ひどい痛手を受けることになる。もし、原子力発電所で大事故が起きても、国は住民を守りはしないし、住民自身ができる自衛手段もしれている。
原子力災害を防ぐただ一つの道は原子力そのものを廃止することである。
無意味なプルサーマル、そして原子力
いったい私たちは何のために原子力を利用しているのであろうか?原子力を推進している人々は、日本は資源小国であり、エネルギーが必要だから原発は必要だという。しかし、原子力の燃料であるウランはもともと大変貧弱な資源でしかない。原子力発電所で一度燃やした使用済燃料中にはプルトニムが生み出されていて、それを再度原子炉の燃料にするプルサーマル計画もあるが、資源的には全く意味がない。なぜなら、燃料に使えるプルトニウムは燃やしたウランのせいぜい20%程度でしかなく、その全量を完壁に使ったとしても原子力の資源が2割増しになるに過ぎない。
高遠増殖炉の役割
原子力を意味のある資源にするためには、高速増殖炉を利用できるようにしなければならない。しかし高速増殖炉は、現在の原子力発電所に比べてもはるかに大きな危険を抱え、当然、技術的にも難しい。一度は、高速増殖炉開発に向かった世界各国も、相次いで、その開発から撤退してしまった。その上、決定的な問題がある。高速増殖炉では、天然には存在しないプルトニウムを燃料とする。したがって、多数の高速増殖炉を作ろうとするならば、その燃料は自分自身で作り出す必要がある。1基の高速増殖炉を動かし、同じ大きさのもう1基の高速増殖炉を立ち上げるために必要なプルトニウムを生み出すのに要する時間を倍増時間と呼ぶが、その長さは90年という。今回のようにエネルギー消費を急激に増加させている社会では、気の遠くなるような長さの時間であり、こんなことでは、とうていエネルギー資源として役に立たない。
高速炉の真の役割
結局、高速増殖炉すらがエネルギー問題としては無意味なものでしかない。しかし、高速炉には決定的に重要な1つの役割がある。世界の高速炉開発を牽引してきたフランスのスーパーフェニックス(超不死鳥)のパンフレットには、自らが「プルトニウムの洗濯機」であると書かれている。現行の原子力発電所(軽水炉)で生み出されるプルトニウムは、そのうち燃えるプルトニウムの割合が60%-70%程度である。それに対して性能のよい核兵器を作ろうとすれば、燃えるプルトニウムの割合が93%以上である必要がある。高速炉では、燃えるプルトニウムの割合の少ない「汚い」プルトニウムを炉心で燃やしながら、ブランケットと呼ばれる場所に、燃えるプルトニウムの割合が98%というような超優秀な「きれいな」核兵器材料が生み出される。
核との関連 - 西村発言
もともと、原子力と核とは同じものであり、原子力利用を続けるかぎり、核の脅威からも逃れられない。先日の西村慎吾防衛政務次官の発言などは、あまりに下品すぎて引用する気にもならないが、日本政府の公式見解は、下記のようなもので、決して核保有を禁じているわけではない。日本には平和憲法がある、非核三原則があるなどと思っている傍らで、日本はすでに世界第3位の軍事大国になっている。
「自衛のための必要最小限度を越えない戦力を保持することは憲法によっても禁止されておらない。したがって、右の限度にとどまるものである限り、核兵器であろうと通常兵器であるとを問わずこれを保持することは禁ずるところではない。」