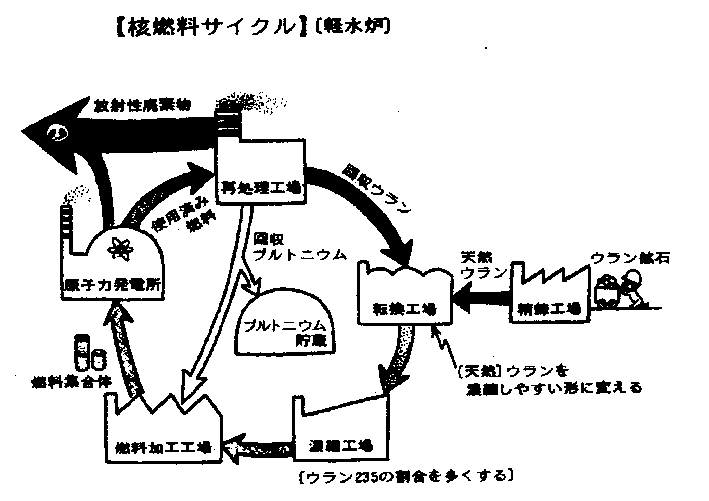|
小出 裕章(京都大学原子炉実験所) |
はじめに
以下の文章は講演会で配付されたもので、講演はこの資料にもとづいて補足する形で行われました。内容はほとんどこの資料通りでした。小出さんの許可を得て掲載します。脱原発の趣旨であればこれは転載できます。わが国を代表する誠実な行動する科学者小出裕章さんによるものですから、内容は信頼できます。科学技術庁よりもマスコミよりも、この報告こそが民衆が頼るべき情報だと思います。(清水 満)

原爆の構造と臨界
この世には核分裂性物質と呼ばれる物質がある。天然にはウラン(正確にはウラン235)があるし、人間が生み出した物質としてはプルトニウム(正確にはプルトニウム239)などがある。そうした物質は、中性子を吸収すると、核分裂反応を起こして原子核が2つに割れ、核分裂生成物となるとともに、吸収した中性子以上の中性子を新たに生み、そしてエネルギーを生む。
ウラン十中性子→核分裂生成物十平均2.5便の中性子十エネルギー
生み出された中性子の1個以上が次の核分裂反応に利用されれば、反応は持続的に続くことになり、そうした状態を「臨界」と呼ぶ。逆に、せっかく生み出した中性子のうち、1.5個以上が体系から逃げるなどして失われると、次の核分裂反応で使える中性子は1個以下となってしまって、反応は持続できなくなる。したがって、核分裂の連鎖反応が持続するかどうかは、生み出した中性子の次世代への引継効率に依っている。ごく大雑把にいえば、反応で生まれる中性子は、反応体系の体積に比例するし、体系から逃げる中性子は体系の表面積に比例する。体積に対する表面積の比は、体系を球にした場合がもっとも小さく(中性子が逃げにくくなる)、体系を細長くするとか、平べったくすれば、体積に対する表面積の比は大きくなる(中性子が逃げやすくなる)。.原爆では、2つに分けておいたウランの固まりを火薬の力で1つに合体させる(広島型:ガン・タイプ)、あるいは濃度薄く分散させておいたプルトニウムを火薬の力で中心部の爆縮させて(長崎型:インプロージョン・タイプ)、瞬間的に臨界状態を生み出し、一気に核分裂の連鎖反応を起こさせた。
形状管理と質量管理
結局、「臨界」状態が生じるか否かは、一定の形状に一定量以上の核分裂性物質が集まるか否かによっている。
原子炉は核分裂の連鎖反応を持続的に維持してエネルギーを取り出す装置であるから、炉心と呼ばれる部分に一定量以上のウランを集め、発生する中性子の一部を制御棒などの中性子吸収材に吸収させることで、次世代に引き継がれる中性子の個数を厳密に1.000000……に制御する。また、臨界状態を生じさせないためには、一定量以上の核分裂性物質が一定の形状に集まらないようにしさえすればよい。たとえば、核分裂性物質を取り扱う核燃料加工工場などでは、一つひとつの装置の形や大きさを制限し、その中に、どんなに核分裂性物質を集めても、決して臨界にならないように設計しておけばよい。
そのことは、長い核開発の歴史の中で十分に理解されてきた。1940年代から始まった核開発の初期には、米国でもソ連でも、何回も臨界事故を引き起こしてきたが、知識が蓄積された1980年代以降は、臨界事故は起きてこなかった(1997年のソ連の事故はごく特殊なもの)。しかし、「日本の技術は優秀だ」と言い続けてきたこの日本で、今回の臨界事故が発生した。それも、核開発史上3番目に大きな臨界事故であった。
生成されるもの
核分裂生成物、放射線、エネルギー
1kgのウランが燃えると、999g分の核分裂生成物(いわゆる死の灰、放射能)が生まれる。残りの1g分の質量がエネルギーに代わって、原爆の場合には、爆風、熱線、放射線となった。原子力発電の場合には、そのエネルギーを利用して、発電を行う。今回の東海村の日本核燃料コンバージョン(通称、JCO)の事故では、1mgほどのウランが燃えた。それによって放出されたエネルギーは家庭で燃やしている灯油2リッター分である。しかし、同時に生成された放射線と放射能は、JCOの労働者に致死量の被曝を与えた他、事故の収束作業に従事した労働者にも法令が許している限度の上限をはるかに超える被曝を与えた。さらに、周辺に漏れた放射線によって、周辺数百メートルに住む住民たちが法令の限度以上の被曝を受け、さらに遠方に住む住民たちも、流れてきた放射能によって被曝した。