
 |
マキカート・マキガスタービン発電に関する問い合わせ |
グリーンウッドさま
HP楽しく拝見させていただきました。
YAと申します。
エンジニアではありませんが、マキガスタービン発電やマキカートをみていると自分で作りたくなりました。
家庭用のマキガスタービン発電があれば使ってみたいです。
研究会などあれば教えてください。
以上
YA
YAさま
メールありがとうございます。
マキカートについて
マキカートは中古のガソリンエンジン搭載カートをまず手に入れることです。 ガス化工程で発生する木酢のミストがシリンダーに少量吸入されますので新品を使うのはもったいない。
マキガス化発電用に最近中国製で安い携帯発電機が市場に出てます。日本信販ではガソリン燃料で850Wの交流出力をもつ携帯発電機を29,800円で売っています。これにガス化炉をつければ、発電できますよ。実は私も買ってしまいました。しばらくキャンプ用 や非常用に使ったあとで、ガス化発電用に転用できるからと思ったのですが、買ったあとで、混合油を使う 仕様ではガス化発電に使う場合、別途潤滑油を供給する仕掛けが必要になるのであきらめました。
ガス化炉は溶接のできる鉄工所の親父と友達になってつくってもらったらどうでしょう。最低30万円くらいで造ってくれるのではないでしょうか。
設計のコツはバイオマス・ガス化発電設計計算プログラム
を参考にしてください。 といってもこのプログラムはエクセル上に書くだけで1ヶ月、化学熱力学的平衡計算の多変数解を得るのに最適化手法を使っていますので初期値をうまく設定させるのも面倒です。スペインの化学工学科の学生がこのプログラムをくれといってきたのですが、マニュアルを英訳しなければならないし、フォローアップが大変ですのでお断りしました。
これだけ面倒なことをしても物質収支や熱収支と化学平衡値がわかるだけです。反応物がガス中を拡散するにもある時間が必要ですし、不定形のマキや木炭の間を 空気が発生ガスが偏って流れないようにする必要もあります。これを全て計算する式がありませんので実機をうごかしてしらべなければなりません。そして得られたものがノウハウというものです。国連のFAOが発展途上国のためにこのノウハウをマニュアルにしてくれています。第二次大戦中、 スエーデンがマキ自動車を開発したときのノウハウをまとめたものです。 日本でも木炭車をつくりましたが誰もマニュアルは残してくれませんでした。
そのエッセンスはマキ消費量基準の炉床負荷(Hearth Load)と標準状態の発生ガス流量をスロート断面積で除したガス基準炉床負荷を
|
マキ基準炉床負荷(Wood basedHearth Load) |
ガス基準炉床負荷(Gas based Hearth Load) |
|
|
kg/cm2/h |
Nm3/cm2/h |
|
| シングル・スロート |
0.11 |
0.25 |
にすることと
◆スロートの角度は45-60度。
◆スロート下の還元ゾーンは最小で20cmは必要。火格子と灰溜まりに10cm位か。
◆空気吹き込みノズルはシングル・スロートの場合、炉中心部に向けて下向きまたは水平に吹き付けるように設置し、ノズル先端とスロートとの高度差はスエーデンのエンジニアリング・サイエンス・アカデミーの経験値からグリーンウッド氏が作った下式で計算する高度差か10cmの大きいほうとする。
(ノズル高)/(スロート径)=19.6*(スロート径)-0.64
◆ノズル流速は30-35m/secを推奨している。(この数値は小型の場合は圧力損失が過大になるため、炉内運転圧力が0.9atmより下がらないように、適宜落とす必要があろう。
◆スロート上部の火床開口部径はシングルスロートの場合、スロート径より10cm、ダブルスロートのい場合、20cm以上大きいこと。
◆エンジンのチョーク弁をガス発生系の流通抵抗と見合うように固定オリフィスを入れておくとチョーク弁の調節が不要となります。
というものです。
このノウハウに従いホンダの50cc、毎分6000回転の携帯エンジン発電機向けに計算しますと火床のスロート部(Troat Hearth)内径47mm、3個中心に向かって設置する空気吹き込みノズル(Nozzle)の内径は8mm、チョーク弁に直列に挿入する固定オリフィス内径が19mmとなりました。他の寸法は下図から適当に推定してください。あくまで計算結果ですから、実機では微調整は必要でしょう。
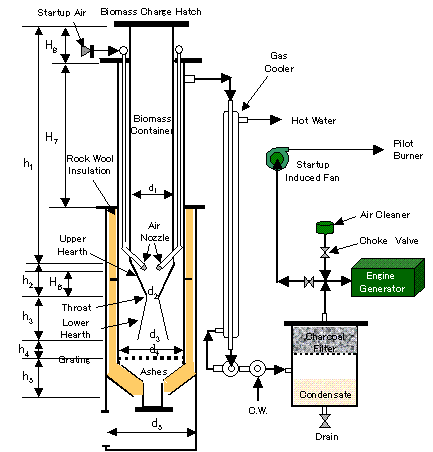
あなたはこういうものに興味をもたれたのでエンジニアの気質充分とお見受けしました。大体エンジニアはアタマのいいオタク気質の人間が選択する職業です。こういう人種が戦後の高度工業化社会を支えて、今の日本があるわけです。
でもあなたはエンジニアにならなかった。察するにホリエモンがねらったフジ・テレビの社員の平均給与が1,500万円、文化放送が1,200万円ですが、普通の製造会社のエンジアの平均給与は1,000万円をきるでしょう。 私の友人に一流の銀行と一流の鉄鋼会社に入社した兄弟がいます。いずれも役員にまでなりましたが、年収は2倍の差があると聞きました。 エンジアの弟は「バカらしくてヤッテラレナイよ」とはき捨てるようにいいます。
というわけで、あなたの選択は現時点では正しい。
しかしソニーが最近落ち目ですよね。あれはトップがフジテレビと同じように国民に人気のある芸能で儲けようと、夢中になり、エンジニアのハートをつかみ損ねたからと私はにらんでいます。 わたしはもうソニー製品に買いたいものはありません。
JALもそうですよね。トップが現場の叩き上げでないとこうなるのです。JALにパイロットの友人がおりますが、彼はJALで飛ばないほうがいいですよといいます。ゴーんさんはニッサンを救いましたね。それは彼が現場のたたきあげでエンジニアをしっかり掌握できたからです。
いまヒューズの伝記を映画にしたアビエータという映画が上映されていますが、彼こそエンジニア魂の権化で私の人生の師でした。
最近の中国を憎んでいる人が多いとおもいますが、かの国の政治家の殆どはエンジニア出身ですよ。理由は簡単です。頭がいいからです。しかし日本 国家のコックピットに座っている人に技術系出身はおりません。このまま飛んでいたらどうなると思います?
オット!大分脱線してしまいました。ご質問にもどりましょう。
マキガスタービン発電について
ターボチャージャーを転用して手作りのガスタービンをつくる趣味は米国で盛んです。LPGなどを燃料にするジェットエンジンをつくるのは比較的簡単ですし、日本でもソフィアなどが模型飛行機用に市販しております。
しかし発電するには発電機とつながなければなりません。そして回転数は10万回転ですので減速がむずかしい。ドイツ製のヘリ用の市販キットは40万円はします。それに燃料はLPGしかつかえません。
マキを燃料にするのはタービンを回すまではカナダのナイ鉄工所の親父がやっております。ビデオみましたか?でも発電までするのかかなり難しいのです。世界でまだだれもチャレンジしていないのではともおもいます。
研究会などどこにもございません。金も数百万円はかかるでしょう。でも誰かスポンサーがいればチャレンジしたいとおもってアイディアを公表している次第です。
自作ですべてイバラの道を自らあるかねばなりません。チャレンジしてみてください。ターボチャージャーはポンコツ自動車解体屋とお友達になればただで手に入るはずです。
あとは溶接のできる鉄工所の親父と友達になることですね。
ではがんばってください。
グリーンウッド
グリーンウッドさま
誠にありがとうございます。大変参考になりました。
いろいろ人脈を当たってみます。気長に趣味として取り組みます。
一方、もともとバイオマス発電に関心があります。
グリーンウッドさんの人脈でボランティア(リタイア)せれている方で150−300KWのディーゼル発電の設計ができ方がおられたら教えてください。
以上
YA
YAさま
150−300KWのディーゼル発電は設計などしなくとも市販されているのではないですか。舶用ディーゼルに発電機直結で簡単にできるとおもいますが。
私はエンジニアリング会社におりましたの発電設備もっぱら出来合いを買っていました。
たとえばヤンマーなどどうでしょうか。
http://www.yanmar.co.jp/index-gen.htm
に系統連携と分離のそれぞれのケースに広い商品がそろっていますよ。
グリーンウッド
グリーンウッドさま
通常ディーゼルの燃料は軽油ですがヨーロッパではルドルフディーゼルが1900年のパリ万博ではじめてディーゼルエンジンをお披露目したときに使用した燃料がピーナッツ油だったことから、現在ヨーロッパでは石油代替燃料として植物燃料であるバイオディーゼルが普及しています。CO2削減にもなります。
しかし、バイオディーゼルにするにはエステル化学変換させる必要があるのでコストは高くなります。そこで、ディーゼルエンジンを改造しエステル化させない方法で対応することで植物燃料をエステル化させない分低コストで調達できると考えています。
新エネルギーとして売電したいと考えています。
アドバイスお願いします。
以上
YA
YAさま
植物性廃食料油に10〜20%のメタノールと苛性ソーダ(触媒)を加えて混合撹拌し、加熱した後、しばらく静置して脂肪酸のエステル交換反応を促進させてディーゼル油にするということのようですが、不勉強でなぜ必要かまだわかっておりません。
油脂は脂肪酸とグリセロールとのエステル、即ちトリグリセライドが主成分ですが、メタノールとグリセリンを苛性ソーダ(触媒)の下で交換してメチル脂肪酸に変え、粘性や引火点を低くして、ディーゼル車で利用できるようにした燃料のようですね。もしかしたらグリセリンが副産物としてでてきますが、これはどう処理するのでしょうかね。
でも基本的にはエステル化は必須用件ではないでしょう。要は固形物がなく、常温で粘度が高かったり固まらなく、インジェクションノズルでシリンダー内に噴霧できる可燃液体ならなんでもディーゼル油に使えると思いますが。
グリーンウッド
グリーンウッドさま
的確な回答ありがとうごさいます。
さすがエンジニアだなと感じました。良くご存知ですね。
植物性廃食油はリッターあたり30円前後で再生業者で販売されています。(A重油の価格並みで、CO2削減ができることがメリットです)
ただし、レストラン、食品工場から一件一件回収するので大量供給はできません。 そこでバイオマス小規模発電所ができないか調べています。
売電価格は低いので大きな儲けは期待できません。また規模も小さいですが社会貢献度は高い仕事になると感じています。いろいろアドバイスをいただければ幸いです。これからも宜しくお願いします。
以上
YA
YAさま、
その後、このエステル交換反応をしらべてみました。水と苛性ソーダを廃植物油(WVO:waste vegetable oil)に加えると反応して脂肪酸ナトリウム(石鹸)とグリセリンが相分離します。これけん化反応といいます。
水の代わりにメタノール(エタノール)と無水苛性ソーダを混ぜてナトリウムメトキサイドをつくり、これに水分を分離したWVOを加えるとWVOのグリセリンとメタノール・(エタノール)がエステル交換してメチル脂肪酸(メチルエステル)とグリセリンができます。グリセリンは反応容器の底に沈み、メチルエステルは上澄みとなるのでこれをサイホンですくいとって出来上がりとなるとのこと。WVO中の遊離脂肪酸(FFA)はエステル交換をじゃまするため、これの中和のために無水苛性ソーダの使用量は増えるそうですね。そしてFFAは石鹸という副産物になるようです。
できたメチルエステル燃料を洗浄・乾燥してグリセリンや石鹸分、その他の不純物を取り除けばエンジンは喜ぶでしょうね。やらなくてもよいようです。
メチルエステルはセタン価が高いためインジェクション・タイミングを2-3度遅らせると、燃焼温度も低くなり、NOxの排出も抑制されるそうです。燃料系統にゴム部品が使われている場合は、取り替えないとエステルで劣化するそうです。
触媒としてつかう苛性ソーダは電気分解で製造するのでバカになりませんね。グリセリンをどう処分するのか不勉強で私は知りません。少量では多分廃棄するのでしょうけれどもったいないですね。工業化するには固定触媒を使って流通系にするのかもしれません。酸型ゼオライト、スルフォン酸型の陽イオン交換樹脂など考えられます。
メタノールはただ同然の天然ガスから合成して輸入してますので廃油程度の値段です。(この合成プラントの設計と建設は私の在籍したエンジニアリング会社の仕事の一部です)
植物油は光合成でつくったものですからカーボンニュートラル。なにより軽油税が要らない分、いいですね。
とはいえ廃油をそのまま燃すのがなんといっても一番。これをSVO: straight vegetable oilと呼ぶらしいですね。
軽油と植物油を混ぜて粘度を下げることも、エステル交換したメチル脂肪酸と混ぜてもいいですよ。
ではなんでエステル交換なんてめんどうなことをするのかとかんがえますと、市販されているディーゼル油(この製造プラントもエンジニアリング会社の専門です)の粘度が低いため、市販の車載高級ディーゼルエンジンの噴射ノズルがこれにしか対応していないためではないでしょうか。粘土が高い植物油を使うと噴霧がうまくできなくなり、シリンダー内の燃焼がよくなくなるとおもいます。具体的症状としては、まずコールドスタートが悪化する。それからフィルターが詰まり始める。じきにインジェクターが詰まって、燃料の噴射パターンが乱れてくる。やがてリングがくっついたり、シリンダー壁にグリースが付いたり、潤滑油の消費量が増えたりとあちこちに問題が出て、しまいにエンジンが止まるということのようです。スタートだけディーゼル油でおこない走行中は植物油という手もありそうですね。
以上は主としてhttp://journeytoforever.org/jp/biodiesel_make.html
を参考にしました。
発電用ならA重油などを使う大型の舶用エンジン、昔漁船が使っていた焼だまエンジンなら回転数もおそく、燃焼時間ももらえるので多分植物油に起因する問題はすくなくなるとおもいます。でも焼だまエンジンは始動までが面倒ですね。
いっそのことどんな燃料も使える外燃式のスターリングエンジンを使われたらいかがでしょうか。一緒にマキだってもせますよ。建設廃材なんでもござれです。ヨーロッパで市販されており、日本でも一部NGOが輸入して使っていると聞き及びました。日本製もまだコスト高でしょうがぼちぼちできてきたようです。
http://www.stirling-engine.com/
私は今、学研の模型スターリングエンジンの組み立てキットを買ってもっています。そのうちに組み立てて実際に動くかテストして本HPで報告する予定です。シリンダーの加熱部と蓄熱部は耐熱ガラス製ですので内部構造が透けてみえるところがミソです。
グリーンウッド
グリーンウッドさま
大変詳しく教えていただきありがとうございます。
1)エネサーブの小型発電機をイメージしています。エネサーブはA重油を燃料としていますが、そこを我々は植物燃料にしようとしています
2)スターリイングエンジンを見ました。価格がポイントですね。
以上YA
April 28, 2005