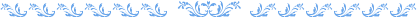|
コーリン、サーラス、エルクオンの三人がいた所から館まではそう遠くはなかった。コーリンを先頭に獣道を通り、館を目指した。
「まだ着かねぇのかよ」
「もうすぐよ。ここを抜ければ……、あっ!」
背の高い草をかきわけ、視界が広がった時、コーリンは小さく叫んだ。
目の前には深翠の美しい湖があった。見慣れた湖の側にはルクレリアの眠る館もある。が、その館は変貌していた。
館は緑で覆われていたのだった。
門、壁、屋根にいたるまで、無造作に緑の植物で覆われていた。
コーリンが館を出た時はこんな状態ではなかった。たった数刻離れただけでこんな状態になった不可思議な現状が信じられなかった。
「これは……」
「ずいぶんと変わった屋敷だな。これは姫さんの趣味かい?」
サーラスはその場に似合わないとぼけたことを言った。
「そんなことあるわけないでしょう! きっと邪妖精の仕業だわ。わたしが姫の相手を連れてきたから……」
「敵は俺たちが気に食わねぇようだな。ま、とにかく中に入るか」
サーラスは大剣を使い、門に掛かっている蔦を切り落とした。
「行くぞ」
コーリンとエルクオンはうなずき、サーラスの後に続いた。
館の内部も植物だらけだった。そこはまるで今通ってきた森のようだった。磨かれた廊下はその一片さえも見えない。
「コーリン。姫さんの部屋はどこだ?」
「ここを真っ直ぐ行って階段を上った二階。一番南の部屋よ」
「この先だな」
サーラスは大剣で次々に植物を切り倒し、道を作りながら進んだ。
階段を上りかけた時だった。
最後尾を歩いていたコーリンの足首に何かが絡みついた。あっ、という間もなくコーリンは足に絡みついた蔦に引きずられた。
「きゃっ!」
「コーリン?!」
サーラスが振り返った時、すでにコーリンは逆さに吊された状態になっていた。
『娘の命が惜しくば、これより先に進むな』
突如、姿なき声が聞こえてきた。
「なんなんだよ、一体! コーリンを離せ!」
サーラスはどことはなしに向かって叫んだ。
『ルクレリアは我のもの。近づく事は許さぬ』
「姫はあんたのものなんかじゃないわ! お願い、サーラス。わたしのことはいいから早く姫を!」
蔦がコーリンの首筋にのびた。そしてぎりっと締め付ける。
『どうする? このままではこの娘は死ぬぞ』
首に蔦が食い込み、息ができなくなる。
「サー……ラス。行って……」
苦しいのを我慢してコーリンは言った。
ルクレリアの目覚めこそ、コーリンにとって今一番大事なことだった。たとえ自分が倒れても、姫のために選んだ男性を連れて来ることができたのだから思い残すことはない、とコーリンは思った。
「ばか言うな! お前が死んだら姫さんが悲しむだろうが!」
サーラスは大きく跳躍し、剣を振った。
大剣はか細い蔦を次々に切り落としていく。三度目の跳躍でコーリンに絡みついた全ての蔦は切り落とされた。
蔦が切り落とされるのと同時にコーリンの体が落下する。
ちょうどその落下地点にエルクオンが立ち、コーリンをうまく抱きとめた。
自由になったコーリンはゴホッ、ゴホッと咳込んだ。
「大丈夫かい。お嬢さん」
「ええ。なんとか……」
『ええい! 小賢しい。こうしてくれるわ!』
足元を這う蔦が鋭い早さでサーラスの体にまとわりつき、動きを封じてきた。
「うわっ!」
蔦は次々にサーラスの体を縛り上げていく。体全体を、頭さえも覆い、サーラスの体が見えなくなっていく。
「サーラス!」
呼吸を整えたコーリンは、風の魔法を使いサーラスに絡み付いた蔦を切ろうとした。だが、いくら切っても、次から次にのびてくる蔦の動きが早すぎて追いつかない。
完全に姿が見えなくなり、動きを封じられたサーラスは一本の植物の柱と化した。
「このままじゃサーラスが……」
困り果ててつぶやいたその時、動くことのできない植物の柱から突然叫び声が聞こえてきた。
「っきしょう! なめるな!!」
紅い炎が突然空中に現れたかと思うと、それは一気に広がり、植物の柱を燃やし出した。
みるみるうちに植物の柱から人間の体が現れてくる。炎の中にいるのに、サーラスの服はどこも燃えていなかった。
「サーラス! 大丈夫なの?!」
「これっくらいのことで心配なんかするなよ。このサーラス様がこんなもんでやられる訳がないだろう」
左目で軽くウインクをする。
「さて、これ以上敵の思い通りにさせておくのは性にあわねぇ。いくぜ!」
大きく振り上げたサーラスの右手から炎が吹き出し、その炎は手当たり次第に広がり植物を燃やし始めた。
一瞬にして、廊下と階段を覆っていた植物は黒い燃え屑と化した。
「行くぞ。この上だな」
行く手を防ぐものが無くなった階段を駆け足で上る。そして二階の奥、その正面の扉の前に三人は立った。
「ここだな……」
サーラスは豪華な金細工のノブに手をかけ、扉を開けた。
そこはルクレリアがただ一人安らかな眠りについている筈だった。
「姫……!!」
喜び勇んで部屋の中に入ったコーリンの瞳に映ったのは、部屋いっぱいの緑、そして天蓋付きのベッドに絡みつく蔦だった。
「こっちもかよ」
サーラスは小さく舌打ちした。
『ルクレリアは誰にも渡さぬ』
再び姿無き声が聞こえてきた。
ベッドに絡みついた蔦がざわざわとうごめき、威嚇しているのがわかる。
「姫から離れなさい!」
コーリンは両手に『気』を集め、風を発した。しかし風の刃は、姫のベッドを覆う植物に傷ひとつつけることができなかった。
コーリンの風では効果がないことを見て、サーラスは腕を振り上げた。
「それなら俺様が灰にしてやるぜ!」
真紅の炎が植物へと走る。
しかし、先程とは違い、燃えるどころか炎は一瞬にしてはじき飛ばされた。
『お前らごときの魔法では我の体に傷ひとつつけることなどできぬわ』
「さすが本体だな。俺の炎にもびくともしないか」
焦ったふうもなく、サーラスは呟いた。隣にいたコーリンは呆然と立ち尽くしていた。
「おい、いくぞ」
突然、コーリンの頭上で声がした。一瞬コーリンは誰が誰に言ったのかわからなかった。
「え?! サーラス?」
見上げると、黒い瞳がじっとこっちを見ていた。
「お前の風の力を俺に貸せ。いいか、お前の最大限の力を俺に向けて飛ばすんだ」
「で、でも……」
「言う通りにしろ。姫さんを助けたいんだろ」
「わ、わかった」
コーリンはサーラスがどうするつもりなのかわからなかったが、自分自身ではルクレリアのベッドに絡まる蔦をどうすることもできなかったので、その言葉に従うことにした。
小さく呪文を唱え、両手に集めた『気』をサーラスに向かって放つ。
放たれた『気』は、どういうわけか『風』となる前にサーラスの右手に吸収された。
「いっくぜ!」
サーラスはコーリンの力とともに自分の『火』の力を放った。
炎が嵐のような勢いで部屋に広がっていく。サーラス一人の炎とでは勢いが断然違った。二人の力が一つとなり、倍増した力が植物を見る見るうちに焼き尽くしていく。
焼け焦げる異臭がコーリンの鼻をついた。
『ギャアァァァァァァァ』
断末魔の叫びが響く。
『……ルクレリア、我が愛しき姫……』
姿なき声の最後の言葉をコーリンとサーラスは聞いた。
「やったな……」
額に汗の浮かんだサーラスは、ふぅと一息つき、その場に座りこんだ。
「サーラス?!」
肩で息をして苦しそうにしているサーラスに、コーリンは慌てて駆け寄った。
「大丈夫だ。ちょっと無理な力の使い方をしただけだから」
サーラスは大きく深呼吸をした。
「最後は呆気なかったな。……コーリン、奴は姫さんの事が好きだったのか?」
「妻になって欲しいという申し出があったの。でも姫はそれを断ったから……。もとはこの付近の森を守る精霊だった筈よ……」
「そうか。奴もかわいそうだな」
サーラスはぼそっと呟いた。そのあと、何かに気付いたかのように言った。
「そうだ! 呪いをかけた者が死んだってことは、かけた呪いも解けるかもしれないぞ!」
「姫!」
サーラスにそう言われたコーリンは急いで視線をルクレリアに移した。
「あっ?!」
ルクレリアはまだ眠ったままだったが、どこをどう通ってそこまで行ったのか、すでに姫の側にはエルクオンが立っていた。
エルクオンはじっと黙ってルクレリアを見ていた。ふいに右手を姫の薄紅色に染まった頬にのばした。そしてコーリンとサーラスが止める間もなく、エルクオンは姫に口づけをしてしまった。
「あ−−−−−−−!」
あまりにも一瞬の出来事で、二人は為す術もなかった。
ルクレリアに口づけし、目覚めさせる役目はコーリンが選んだ人物の筈だった。それなのに、一瞬の隙をついて、コーリンが選んだのとはまったく違う人物、というよりも絶対に相手にしたくはなかった人物が口づけをしてしまった。それでは今まで苦労してきた事が全て水の泡となってしまう。
しかし、もう遅かった。
コーリンは体の力が抜け、へなへなと床に座り込んだ。その隣では、サーラスが困ったような顔でコーリンを見ていた。
当のエルクオンは涼しい顔でルクレリアを見つめている。
一瞬の間の後、ルクレリアの目元がピクリと動いた。そして瞳がゆっくりと開かれていく。空色の瞳が茶色の瞳をとらえた。
「あなたが……」
小鳥のさえずりのようなかわいらしい声が小さな唇から漏れた。
「ルクレリア姫。気分はいかがですか?」
「すっきりしているわ。頭の中にかかっていた靄がすべて消え去ったよう」
「それはよかった」
エルクオンとルクレリアは、呆然と床に座り込んでいる二人を無視して話し続けた。
「あなたがわたくしの呪いを解いてくださったの?」
「あなたのためにここまで来ました」
その会話を聞いて、コーリンはだんだん腹が立ってきた。エルクオンがここまで来るのに一体何をしたのか。邪妖精を倒し、ここまで来ることができたのはサーラスのおかげだ。何もせず、いつのまにかおいしいところだけ持っていこうとするエルクオンがルクレリアの伴侶になるのは許せなかった。
「姫! その男は……!!」
叫びかけたコーリンの言葉をさえぎるように、ルクレリアはコーリンに向かって極上の笑みを見せた。それは誰もが心を奪われてしまうような魅力的な笑みだった。
「コーリン。あなたがこの方を連れて来てくれたのね?」
「姫! わたしが選んだのはその男では……」
半年ぶりに見る極上の笑みの前では、最後まで言葉を続けることができない。
「嬉しいわ。こんな素敵な方が私の呪いを解いてくれたなんて」
「ひ、姫?!」
「ありがとう。コーリン」
ルクレリアはコーリンの言葉をろくに聞かずに満足そうに微笑んだ。そして優雅なしぐさでベッドから下りた後、コーリンに歩み寄って彼女を抱き締めた。その時、ルクレリアはそっとコーリンの耳元で小さく囁いた。
「さすがはコーリンね。私の好みにピッタリだわ。ありがと❼」
ルクレリアはそれだけ言うとすっとコーリンから離れ、エルクオンの側へと走り寄った。
「ひめぇ……」
どうしようもないくらい情けない声だったが、その声はルクレリアに届きはしなかった。
「……ま、しかたないんじゃない? 姫さんはエルクオンの事が気に入ったみたいだし」
サーラスは他人ごとのように呑気に言った。
「そんなぁ!」
「だけど姫さんが気に入った人物と一緒になる方が姫さんは幸福になると思わねぇか?」
「……」
サーラスの言葉はもっともだった。コーリンが認めた人でも、ルクレリア自身が気に入らなければ意味がない。やはりここはコーリンが諦めるしかなかった。
「ま、元気だせよ。ところでひとつ聞いてもいいか?」
「……なに?」
ぶ然としたコ−リンが覇気のない声で応える。
「お前、俺を姫さんの相手に選んだよな?」
「そうだけど、もう意味がないわ……」
「そうじゃなくて、俺を選んだ訳が聞きたいんだ」
「訳? それは姫の好みに合う人だから……」
「どうして姫さんの好みがわかるんだ?」
「だってわたしと姫の好みは同じ……!」
そう言った時、コーリンは何かに気づいたようにハッとした。
「と、いうことは俺はお前の好みってことになるよな?」
「そ、それは……!」
コーリンは真っ赤になって慌てた。姫の事ばかり気にしていたので、自分の気持ちに自分で気づいていなかった。
「俺はいいぜ。火と風の組み合わせっていうのも悪くないし、俺とはれるくらいの力の強さも気に入った。ま、俺には姫さんの相手はできねぇよ。それに昔から決まってるだろ?お姫様のお相手は王子様ってね」
見事なウインクでサーラスは合図した。
コーリンはちらりとルクレリアとエルクオンを見た。二人は今日初めて逢ったとは思えないくらいに幸福そうに寄り添っている。
その光景は、まさしくお姫様と王子様が出てくる絵物語の挿し絵のようだった。
諦めたように、でも安心したように溜め息をついた後、コーリンはサーラスに言った。
「わたしより強い人じゃなきゃ嫌だからね」
「まかせとけって」
寄り添う二人に負けないくらいの笑顔がそこにあった。
そしてその半年後。
ラクセルス大陸随一の大国ガ−ランディアの世継ぎとルオーク公国唯一の公女との婚儀が盛大に行われるのだった。
Fin
|
 小 説
小 説 小 説
小 説 眠り姫にキスを
眠り姫にキスを