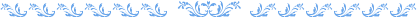|
光と水、そして緑にあふれたルオーク公国。
ラクセルス大陸の中では一番小さな国であった。その国の中心には、三本の尖塔があるルオーク城が建っている。そしてその城よりも少し南に移動したところ、深い翡翠色をした美しい湖の側に、城よりもひとまわり小さい館が佇んでいた。
その館の奥、湖側に面した大きな窓のある一室に二人の少女はいた。
一人は天蓋付きのベッドに横たわり、静かな寝息を立てている。緩やかに波打つ金色の髪、雪のように白い肌、ほんのりと染まった頬、形のよい薄紅色の唇。白いドレスを身にまとった、非のうちどころのない美しい少女。彼女はルオーク公国内外を問わず、その美しさで知られるルオーク公国公女ルクレリアだった。
そしてもう一人、黒髪の少女がベッドのすぐ側で、丸い鉄板に薄く張られた水を眺めていた。 黒髪の少女、名をコーリンという。闇夜のような黒い瞳は大きく、とても印象的である。
コーリンは鉄板の水に右手をかざし、小さく呪文を唱えた。その途端、水が風もないのに軽く揺らめく。呪文が終わるのと同時に水は静まり、そして何かを映し出す。水に映った光景は、深い森のようだった。背の高い木々が陽光を通さず、薄暗い。次に水は一瞬揺らめき、場面を変えた。今度は森の中の道なき道を歩く二人の人物を映し出す。
「今度こそ……」
コーリンはそれを見て、ぼそっと呟いた。そして腰まである長い髪を首の後ろで一つに結び直すと、キュッと右手を握り締め、ベッドで安らかな寝息を立てているルクレリアを見た。
「待っていてください。姫」
コツコツと足音を響かせ、コーリンは姫の眠る部屋を後にした。
陽光が遮られ、昼間とは思えない薄暗い森。
何本も生えている大木の一本にコーリンは登った。誰にも気づかれないように気配を消し、身動きせずにじっと様子を伺った。
耳をすますとガサガサと生い茂った植物をかき分ける音が聞こえてきた。その音はだんだんと近くなってくる。
音が近づくと同時に人の姿が見えてきた。
黒い瞳に映ったのは、二人の青年。コーリンはじっと青年達を見つめた。
ちょうどコーリンの真下を紅い髪をした男が通り過ぎた。その瞬間、コーリンは細剣に手をかけ、タイミングを見計らって飛び下りた。そしてそのまま空中で剣を抜き、紅(あか)い髪の男目掛けて剣を降り下ろした。
「覚悟!」
カキンッ、と剣と剣がぶつかり合う音が響いた。
殺気を感じ取った男は、とっさに鞘に入ったままの大剣でコーリンの剣を受け止めた。
「誰だ?!」
低い声が鋭く響く。
コーリンは素早く男から離れると、剣を構え直し、いつでも襲いかかれる体勢をとった。
「お前たちこそ何者?! この先にはローゼル国所有の館しかない。誰の許しを得てここまで来た!」
コーリンは凛とした声で言い放った。
「お前こそ誰だ? このサーラス様にいきなり襲いかかる無謀な奴め」
サーラスと名乗った紅い髪の男は、大剣を鞘から抜き、コーリンと同じ様に構えた。
その構えには一寸の隙もない。
しかしコーリンは素早さを武器に、再びサーラスに襲いかかった。
細剣を器用に操りサーラスを切り付ける。しかし剣の先はサーラスの服にさえ届かない。思った以上にサーラスの動きは素早かった。
「いい加減にしろ!」
理由もなく襲われたサーラスは不機嫌そうに怒鳴りながら大剣を横に一振りした。
コーリンは大剣を避けるように後ろに大きく跳躍した。着地すると、すぐさま剣を持っていない左の掌を天に向け、何かを呟いた。その瞬間、コーリンの掌に目には見えない何かが集まってきた。
「破っ!」
掛け声とともにコーリンの左手がサーラスに向かって伸びた。刹那、サーラスに向かって風が勢いよく吹き込む。
「くっ」
サーラスは両手で顔をかばうようにして風を受け止めた。
「立ち去りなさい。この先に近づく者はわたしが許さない!」
「お前、魔法剣士だな。そうとわかればこっちだって容赦しない!」
サーラスはコーリンの風をものともせず、姿勢を正して呪文を唱えた。
その途端、コーリンの足元から、いや、地面から直接炎が吹き出し、コーリンを取り囲むように炎が垂直に燃え上がった。
「?!」
「その炎は水じゃ消えないぜ」
コーリンは思いもかけない相手の攻撃に一瞬驚きひるんだが、瞳を閉じて呪文を唱えた。そして一気に『気』を放出した。その途端、炎は一瞬にして風に吹き消された。
「なんて奴だ……」
サーラスはまさか自分の炎が消されるなんて思ってもいなかった。思いもよらない力の持ち主に対し、この後どう対応すべきか戸惑う。
コーリンの方は息が荒くなっている。大きく深呼吸した後、サーラスの顔を見た。
「まだやる気か?」
「……」
コーリンは何も言わず細剣を鞘に収めた。そして真っ直ぐサーラスに向かって歩き出した。
「なんだよっ!」
一歩、二歩とサーラスは後ずさった。
コーリンは自分と同じ色のサーラスの黒い瞳を見つめた後、片膝を地につけ頭を下げた。
「どうか貴殿のお力をお貸しください。姫を、公女ルクレリア姫をお助けください」
いきなり襲いかかった態度と違う、その殺気のない申し出にサーラスは唖然として言葉を失った。
しばらく森は静まり返っていた。
「サーラス、そのお嬢さんの話を詳しく聞いてみたらどうだい?」
沈黙を破ったのは、木の影から姿を現した身なりのよい長身の青年だった。サーラスと同じくらいの年齢のようである。
「エルクオン」
サーラスは思い出したかのように振り返った。
「さあ、お嬢さんも立って……」
見るからに高貴そうなエルクオンが、優雅な仕種でコーリンに右手を差し延べた。
しかしコーリンはその手を取らず、素早く剣を抜き、エルクオンに切りかかった。
「エルクオン!」
サーラスが慌てて叫んだ。
エルクオンはすんでのところでコーリンの剣を避けた。しかし細剣はエルクオンの肩をわずかにかすめ、上等な絹で作られた服とマントを止める銀の止め金をはじき飛ばした。
「やっぱりあなたじゃダメだわ」
慣れた手つきで細剣を鞘に収める。
「何がダメなんだ! お前、誰に剣を向けたかわかっているのか?!」
いきなり剣を突きつけられたことに怒ったのは、エルクオンではなくサーラスだった。
サーラスはコーリンの肩をグイっと掴み、自分の方を向かせると怒鳴りつけた。
「こいつはな、ガーランディア国の世継ぎなんだぞ。お前ごとき者が近づくことさえできない奴なんだ。それを切り付けて、ダメだとぬかしたな!」
「たとえ皇子といえど、この男では姫を助ける役に値しないからそう言っただけです!」
「なにぃ!」
サーラスはサーラスで、自分が仕えている主人を馬鹿にされたことに腹がたったし、コーリンはコーリンで、必要のない人物に構うほど余裕はなかった。
二人は正面から睨み合った。
「まあ、二人とも落ち着いて」
またしても二人に割って入ったのはエルクオンだった。
「エルクオン、お前わかっているのか? この小娘はお前を馬鹿にしたんだぞ! 少しは怒ったらどうだ!!」
「落ち着け、サーラス。お嬢さんにはお嬢さんの事情ってものもあるだろう。それがはっきりしないうちは何も言う気はないよ」
にっこりと笑い、エルクオンはサーラスをたしなめた
「はん! まったくお前は甘いんだよ」
主従関係にあるとは思えない言葉使いでサーラスは呆れたように言い捨てた。そしてくるりと向きを変え、コーリンに目を向けると頭の先から足の先までじっくりと見た。
「で、女、俺に助けてとか言ったな。一体どういうことなんだ。言ってみろ」
サーラスは側にあった大木の根元に腰をおろした。エルクオンもその隣に座った。
コーリンはエルクオンを邪魔だといわんばかりにちらりと見た後、どうしたものかと戸惑ったが、意を決して二人の正面に膝を折った。そして静かな口調で話し始めた。
「実は……」
我はお前に深き眠りの呪いをかける。
お前の眠りはある男の口づけで目覚めよう。
しかし目覚めた時、お前は呪いを解いた男と結ばれなければならない。
どんな男であってもその男と結ばれるのだ。
お前は自分と結ばれる相手を、自分で選ぶことはできない。
お前に幸福な未来はない。
コーリンは、半年前に突然美姫ルクレリアに降り掛かった出来事について語った。
「それで呪いをかけられた姫さんは?」
「この森の先にある館で眠りについています」
「で、あんたが俺たちに襲いかかったこととどんな関係があるって言うんだ?」
「わたしは眠りにつく直前の姫と約束しました。姫を目覚めさせる男性はわたしがみつけると。この半年、わたしは姫に相応しい男性を探してきました。姫の噂を聞きつけて何人も男性が館に近づきましたが、誰一人として姫に相応しい人はいませんでした。だけどやっと、やっと見つけたんです! あなたが、サーラス様が姫に相応しい方なんです!」
コーリンに力説され、サーラスは思わず怯む。
「お、俺なんかよりも皇子のエルクオンの方が相応しいと思わねぇか?」
「ダメです」
サーラスの申し出はあっさりと一蹴された。
「その男はわたしがサーラス様に剣を向けた時、一目散に逃げ隠れた人です。とても姫に相応しいとは思えません。それよりもわたしの剣を受け、堂々と戦ったサーラス様。あなたのように勇気と力のある方こそ姫に相応しい方です」
「俺はただの傭兵なんだぜ? 剣を向けられば向け返す。ただそれだけだ。そんな男が姫に相応しいか?」
「身分など関係ありません。姫の好みに合う方こそ姫を幸福にしてくれる人なんです。あなたならきっと姫も気に入られると思います」
祈るように手を組み、コーリンはサーラスを見上げた。
サーラスは困ったように頭をかいた。
「いいじゃないか、サーラス。我々で姫をお救いしよう。それにこれは国王に頼まれた件でもあるのだからな」
「国王様に?」
「そうだよ、お嬢さん。我々はこの国に着いてすぐルオーク城に行き、国王に挨拶をした。その時、姫の件を聞いたのだ。そして国王直々に『姫を助けてくれ』と頼まれた。だから我々はこの先の館に向かっていたのだよ」
「国王様が……」
姫の件はコーリンに一任されていた。これも眠りにつく直前に姫が決めたことだった。
放っておけば、国王が勝手に姫の相手を決めてしまうかもしれない。自分の知らぬ間に政略結婚の道具にされるかもしれない。そう思った姫はコーリンに相手を探すように頼んだのだった。
十六歳にして、剣も魔法も究めたコーリンを国王自身も信頼していた。だからコーリンが姫に相応しい人を探し当てるまで待つつもりだった。しかし、国王も親である。半年も眠り続ける姫が心配だった。そんな時にたまたま外遊の途中に訪れたガーランディア国の世継ぎ。うまくすれば大国との繋がりもできる。また、エルクオンも好人物であり、年齢的にもちょうどよかった。国王はこれ幸いと頼んだのだった。
国王に頼まれたと聞いて、コーリンは国王の心中をすぐに理解した。が、エルクオンを姫の相手にするわけにはいかなかった。
国王の気持ちはわかるが、コーリンにとって主人はルクレリアただ一人である。姫に頼まれたことを全うしなければならない。
『私の好みに合う方をコーリンが選んで』
コーリンは姫の言葉を思い出した。やはり、エルクオンを姫の伴侶にすることはできない。
「サーラス様。さあ、行きましょう」
コーリンは立上がり、右手を差し延べた。
「……しかたないな。とりあえず館へ行くとするか。ところでお前の名前は?」
「コーリンです。姫の護衛役兼話し相手をしております」
「コーリンか。で、コーリン。俺に『様』なんかつけて呼ばないでくれるか。そんな風に呼ばれたらなんだか虫酸が走る」
「では何と……」
「サーラスでいいよ。それに敬語も使うな。使うならエルクオンに使え」
「そんな男には使いたくありません」
「私もえらく嫌われたものだなぁ」
エルクオンはそう言いながらもまったく気にしていないようである。
「とにかく、俺には敬語を使うなよ」
「わかりました、じゃなくて、えっと、わかったわ」
コーリンは素直にサーラスの言葉に従った。
それを聞いてサーラスはにっと笑い、コーリンの右手を握った。
後編へ続く
|
 小 説
小 説 小 説
小 説 眠り姫にキスを
眠り姫にキスを