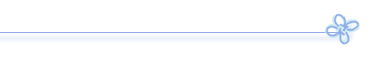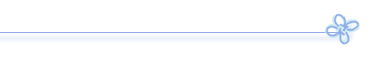|
ヒノエと望美が向かった先は、別当屋敷からそれほど遠くはない、ヒノエの両親が住まう別邸だった。
今日の訪問は別邸の使用人達にも知らされており、二人はすぐに案内された。
そして二人が案内された一室では、すでに湛快が待っていた。
「やっと来たか、放蕩息子」
「時間通りじゃねえか。時間もわからねぇほど、もうろくしたか? 親父」
「熊野に戻ったならすぐに来るもんだろうが」
「こっちにはこっちの事情があるし、準備ってもんがあるんだよ」
顔を合わせた早々、親子は憎まれ口を叩き合おう。それから二人はお互いに同じようににやりと笑った。
「いつまでも立ってないでこっちに来て座ったらどうだ。さ、お嬢さんも」
急に視線を向けられ望美はドキッとした。
慌てて湛快の向かう形で正座をすると頭を下げる。
「ご、ごぶさたしております!」
「お嬢さんにまた会えて嬉しいよ。いやぁ、以前にも増して美しくなったねぇ」
「親父、望美を口説くなよ」
「これだけ美しいお嬢さんなら口説き甲斐があるだろうなぁ」
「望美はオレの嫁だからな」
「お嬢さんみたいな可愛い女性を嫁に迎えられたら幸せだろうなぁ」
「だから、望美はオレが嫁に迎えるんだ!」
「それは、どうだろうな」
「ふん、なんとでも言え」
ヒノエは父の言葉に無造作に言い放った。
そのやりとり自体はただの軽い感じのものであった。不機嫌そうにしながらもヒノエ自身は特に気にした様子はない。けれど望美には何かひっかかりを感じた。
湛快の『それは、どうだろうな』と言った口調は息子をからかうような軽いものではないような気がした。もっとその言葉に重い何か、深い意味があるように思えてならない。
そう感じながらも、それは漠然とした思いであったため、望美は口に出して問うことはできなかった。
「親父、母上はどうした?」
「あぁ、あいつなら……」
ちょうどその話題に触れた時だった。
「奥方様の御見えです」
先導の侍女の声が聞こえてきた。
その言葉に、望美はピンッと背筋を伸ばす。
わずかな衣擦れの音とともに人の気配を感じた。
山吹色の衣が見えた瞬間、望美は深々と頭を下げた。
優雅に流れるような衣擦れの音が望美の耳に届く。やがてそれはぴたりと止まった。所定の位置に腰を下ろしたのだろう。
一瞬誰も何も言わず、静けさが漂った。
しんとした中で、凛とした女性の声が響いた。
「おもてをお上げなさい」
顔を下げたままの望美は、その声に従って顔を上げる。
望美が視線を前方に向けると、湛快の隣には、妙齢の女性が座っていた。
20代半ばから後半と言ってもおかしくはないと思うくらいに若く見える女性。
見た目の年齢はともかく、奥方様と呼ばれたこの女性が湛快の妻であり、ヒノエの母なのであろう。
栗色の癖のない長い髪は真っすぐに背中を流れ、十二単とは言わないまでも袿を何枚も重ねたその姿を見ると、まさに平安時代の姫君を思わせる感じがした。
「そなたが龍神の神子殿か?」
「は、はい!」
あまりに緊張して望美の返事はうわずってしまう。
「そうか」
それだけ言うと、檜扇で口元を隠したヒノエの母は、じっと望美を見つめた。
そのまっすぐな視線を望美は受け止める。
決してにらんでいるわけではないけれど、何かを挑まれたように感じる。
あまりに強いまなざしに、目を背けたくなる。
しかし、そうすることはヒノエの母から逃げることのように思えて、望美もまたまっすぐに視線をヒノエの母に向けた。
その場は静まり返り、物音ひとつ聞こえない。
長い間見つめ合っていたような気もするが、それはわずかな時間だった。
すっと檜扇がずれたかと思うと、ヒノエの母の口元がわずかに揺れた。
「さすがは龍神の神子殿。曇りのない清らかな瞳をなさっておる。わたくしはヒノエの母、丹鶴(たず)と申す」
「は、はじめまして! か、か、春日望美と申します!」
望美は再び頭を床にこすりつけるくらいにひれ伏した。
「そう固くならずとも良い」
望美は恐る恐る顔を上げて丹鶴の顔を見る。
その表情は幾分和らいでいるように思えた。
「母上、ごぶさたしております」
望美と母の対面に一段落したヒノエが挨拶を述べた。
母に向けるヒノエの口調は意外にも丁寧なものだった。
「やっと戻ったか、放蕩息子」
ヒノエへの丹鶴の最初の一言は、奇しくも湛快と同じであった。
「……母上までそのように言われるとは。私には何故そんなことを言われるのか覚えはありませんが?」
「何を言うか。書き置きひとつで熊野を飛び出しおってからに。残された近臣どもの苦労をわかっておるのか?」
「困らない程度の下準備はしておきましたよ。そのへんの抜かりはありません。ですから私が戻るまで何事も起こらなかったでしょう?」
「今なら何とでも言えよう。まぁ、良い。これからは熊野におるのであろう?」
「それはもちろん。今後は熊野のために一層力を尽くす所存です」
「それならば、もうくどくど言うまい」
「恐れ入ります」
「時に」
ヒノエと話をしていた丹鶴は不意に視線を望美の方へ向けた。
「聞くところによると、神子殿は異世界より参られたとか」
「は、はい」
「元の世界に帰りたいとは思わなんだか?」
遠回しな言葉ではなく、率直な質問にドキリとする。
その質問の内容は、考えないようにしていたことだった。考えてしまえば淋しい思いが心を襲う。
望美は即答できなかったが、一瞬の間のあとで言葉を紡いだ。
「……元の世界が全く気にならないとは言えません。これまで育ててくれた両親のことを忘れることもできません。元の世界にはたくさんの大事なものがあります。でも、私はヒノエ君に出逢ってしまったんです。ヒノエ君は、誰よりもそばにいたい、そばにいて欲しい、そう思えるただ一人の大事な人なんです。どんな選択肢があったとしても、ヒノエ君から離れるという選択だけは私にはできません。だから私は今ここにいます。私はこの世界でヒノエ君と幸せになりたいと思っています」
その言葉はヒノエの心にも大きく響いた。
望美は丹鶴を見た後、隣にいるヒノエの顔を見て微笑む。そしてこくりと頷いた。
望美のそのはっきりとした決意がヒノエには嬉しかった。
ヒノエもまた口元を緩め、同じように頷いた。
「これまでの全てを引き換えにして我が息子を選ぶか。その想いの強さは気に入るところよのう」
丹鶴の『気に入る』の言葉に望美は内心ホッとする。
全てを気に入ってもらうには時間がかかることだろうけれど、とりあえず初対面でこう言ってもらえたなら今日のところは及第というところだろう。
しかし、安心するのはまだ早かった。
「されど」
丹鶴は和やかに話をしていたその口元から笑みを消した。
「龍神の神子殿を別当の花嫁に迎えるわけにはいかぬ」
「?!」
「母上?!」
思いがけない丹鶴の言葉に望美もヒノエも驚愕する。
「……母上が反対されるとは思わなかった。その理由をお聞かせください」
「その娘を嫁に迎え、何の利がある?」
「利?」
「そう。源平合戦に終止符を打った今、その娘に価値はあろうか?」
その言葉に望美は自分の手をギュッと握りしめる。
戦いの最中であれば『龍神の神子』という肩書きだけでもずいぶんと優位になれる。けれど戦いが終わってしまえばその肩書きは何の役にも立たない。神子として望美が出来るのは怨霊を封印すること。怨霊がいない世であれば望美の力は必要とされないものである。
神子の力以外何の取り柄もなく、己の身しかないと思っている望美が一番危惧していたことをずばり指摘されたしまった。
望美には反論できる言葉は何もなかった。
強く握りしめた手が震え出す。
その時、大きな温かい手が望美の手を包み込んだ。
それはヒノエの手だった。
言葉をなくし、うつむいていた望美は隣にいるヒノエの顔を見た。
ヒノエは丹鶴を見ていたが、その横顔には何も迷いなく、望美の心に安心感を与えた。
「私の嫁に価値が必要ですか?」
ヒノエの声音はまだ落ち着いていた。もしかするとこう言われるのを予想していたのかもしれない。
「むろん。熊野別当という立場を考えれば、強き後ろ盾は必要であろう?」
「今のこの熊野にどんな後ろ盾が必要だというのです?」
「後ろ盾はないにこしたことはない。それに熊野以外からの力を入れることで、もっと熊野は大きくなるであろう。別当の妻は、熊野の妻でもある。なにより熊野に尽くす女でなければならない」
「だから、単身、何も持たない望美は受け入れられないと?」
「その通り」
しっかりと頷く母を見て、ヒノエは深くため息とついた。
「人の思いを大切にしろと申されていた母上の言葉とは思えませんね」
「母は母なりに息子のことを考えておる故にそう申したまで」
丹鶴は態度を崩さない。
ヒノエは一瞬にらむように丹鶴を見た後、目を伏せた。
「望美と出逢う前のオレだったら、利を求めて一番有利な女を娶ることを考えたかもしれない」
ヒノエの一人称が変わった。そしてそれまでの母に対する言葉遣いも変わる。
ヒノエはゆっくりと目を開けた。
「オレは望美を嫁に迎える」
「それは許さぬ」
「誰が何と言おうと、オレのことはオレが決める!」
ヒノエは声を大にして決意を表す。
「これまでオレは親父の跡を継いで熊野をまとめてきた。継いだものを失わないようにしながら、オレはオレなりに熊野の基盤を作った。熊野は熊野だ。他のどこからも介入は受けない」
「介入ではなく、熊野の繁栄のための協力者を増やすということだと思えぬか?」
「それは結局熊野の弱みを作ることになる」
熊野の中でだけで何もかも解決できるとは思わない。外にある力を入れることは必要なこともあるだろう。しかし、婚姻を理由にしてまで今の熊野に本当に他所の力は必要だろうか。
ヒノエの答えは否。
婚姻によって力をつなげることは手っ取り早い方法ではある。けれど全て良い方向につながるという保証はない。そこから綻びが生じることもある。婚姻を盾につけ込まれる隙を作ることになりかねない。
外からの力を受け入れるのは婚姻でなくてもできること。
今の熊野の情勢を見ても、婚姻によって力をつなげる必要はどこにもない。
必要性がない以上、望美を迎え入れないという理由にはならない。
「もう一度言う。オレは望美と結婚する」
「賛成できかねる」
ヒノエが決意を変えないように、丹鶴もまた変えることはなかった。
「……」
ヒノエは無言で一拍間を取る。
その間も丹鶴は表情さえ変えることはなかった。
「親父も同じ意見か?」
「お嬢さんのことは気に入っているよ」
丹鶴のようにはっきりとは言わないが、反対もしないということは湛快の意見も同じということだろう。
ヒノエは望美の手を引き立ち上がる。
「行こう、望美。これ以上ここにいても無駄だ」
「で、でも……」
望美はこの成り行きに戸惑う。こんな形でこの場を離れて良いとは思えない。けれどヒノエの望美の手を引く力が強過ぎて引きずられるように歩き出す。
「お待ちなさい、ヒノエ」
丹鶴は慌てることなく落ち着いた口調で声をかけた。
「もう話すことはない」
「そなたに紹介すべきお人がいる」
「紹介?」
この場の雰囲気には合わない申し出だった。
ヒノエが立ち止まったのを見ると、丹鶴は侍女に合図する。
「お通しせよ」
その言葉に従って、侍女は一人の女性を連れてきた。
年齢は望美と同じくらいだろうか。
ゆるやかに波打つ夕陽色の長い髪。整った顔立ちは美しく、まさに良家の姫君といった感じであった。
彼女はゆっくりとした動作で座ると、静かに頭を下げた。
「お初にお目にかかります、ヒノエ様。わたくしは胡蝶と申します」
ヒノエも望美もその女性を見つめた。
何故今彼女がこの場に現れたのか、二人の心に不吉な予感がよぎる。
そしてその不吉な予感は次の丹鶴の一言で確定となる。
「ヒノエ、お前の許嫁です」
「!」
予期せぬ丹鶴の言葉に、望美もヒノエも身体が硬直した。
第三話 第五話
<こぼれ話>
ついにヒノエ母と対面〜。
ヒノエ君が『母上』と呼ぶイメージから、ちょっと強気なこんな感じになりました。
お母さんの名前については歴史上諸説ありますが、遙かワールドということでうちでは丹鶴さんにしました。
そして!
それよりなにより、許嫁登場です!
両親公認の許嫁に、ヒノエ君と望美ちゃんの結婚はどうなる?!
|