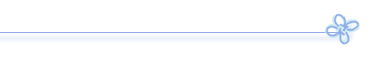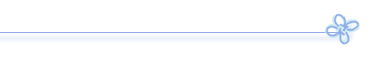|
望美が熊野へ来て3日目。
その日、望美は朝早くから寝所を出て、庭で木刀を手に素振りをしていた。
一点を見つめ、ただひたすら木刀を振っている。
剣を習い始めた頃、心を落ち着かせるには素振りをするのが良いと聞かされた。同じ動作を繰り返していくうちに、呼吸が整えられ、無心になれる。
戦の中にいた頃、望美は何か迷いや心配事がある時は気持ちを落ち着かせるためによく素振りをおこなっていた。
今、望美の心に迷いや心配事があるわけではない。けれど、じっとしていられないほどに心はざわめいていた。
どれくらい時間が経っただろうか。
「の、望美様!」
その声にハッとして望美は手を止める。
「望美様、何をなさっておいでですか?!」
望美の側へ駆け寄って来たのは侍女の凪乃であった。
別当屋敷に望美が着いて早々、ヒノエが望美付きにと選んだ侍女である。
「あ、おはようございます、凪乃さん」
「おはよう、ではございません。ご寝所に伺いましたらお姿が見えなくて心配いたしました。このような朝早くからそのようなことをなさっていかがされたのですか?」
「えっとこれはその……。ちょっと早くに目が覚めたから時間つぶしに……」
「時間つぶしなどなさらずにもう少しごゆるりとお過ごしくださいませ。それに本日は大事な日ではございませんか」
「だから、かな。どうにも落ち着かなくて」
苦笑いをしながら望美は答えた。
望美が朝から、いや前夜から落ち着かずにいたのには大きな理由があった。
それは、この日が望美にとって一大イベントとなる『ヒノエの両親にご挨拶』という日であったからである。
ただ挨拶するというのであったら気はラクだろうけれど、今回はただ挨拶をするというものではない。
ヒノエの結婚相手となるということを報告をし、そしてその承諾を得なければならないのである。
もちろん結婚に反対される筈がないと言うヒノエの言葉は信じてはいる。
が、万が一ということもある。
いくら大丈夫と言われても、両親の前で失態を演じないという保証はどこにもない。気をつければ気をつけるほど、何かをしてしまいそうな気がしてならない。
ヒノエの父である湛快とは以前に顔を合わせたことがあったが、改めてヒノエの結婚相手として挨拶をするのだから緊張せずにはいられないし、ましてや、母親の方とは初対面である。もしも何か不手際な事でもして気に入られなかったとしたら、この時点で結婚の話は白紙になってしまうかもしれない。
結婚への第一歩として、両親の承諾は不可欠なもの。最初からつまずくわけにはいかなかった。
そう考え、落ち着こうと思えば思うほど、余計なことを考えてしまう望美だった。
そうして、緊張のあまり前夜は遅くまで寝付けず、うつらうつらとした頃には外は明るくなり始め、そうなるともう寝るどころか目は冴えて来てしまい、結局ほとんど寝られなかったのだった。
「お気持ちはお察しいたします。ですが、何も心配なさることはありません。別当殿に全てをおまかせになられれば万事大丈夫でございますから。さ、早くご用意なさらないと、別当殿のお迎えの時刻となります」
「えっ、もうそんな時間?」
「身支度にはそれなりの時間が必要となります。こんなに汗をかかれて。すぐに湯殿の用意をいたしますので早くこちらへ」
「あ、は、はい」
望美は凪乃に促されるまま、それに従った。
◇ ◇ ◇
湯殿で身をきれいにした望美は、凪乃の手伝いのもと、身支度を始めていた。
着付けも終わり、ほぼ用意は終わろうかという時だった。
「望美、用意はできたかい?」
突然御簾の向こうからヒノエの声が聞こえてきた。
「え、あ、ちょっと待っ……」
望美が返事をするよりも先に、ヒノエは望美のいる室の中に入ってきた。
「オレが用意した衣装は気に入って……」
中に入るなり、言いかけた言葉が途中で止まる。
そしてその場に立ち止まったまま動けなくなっていた。
ヒノエの瞳にただ一人望美だけが映る。
うっすらとだが施した化粧。
紅をひいた艶やかな唇。
くせのない髪はサラサラと着物の上で揺れている。
ヒノエが望美のために選んだ薄桜色の袿を羽織ったその姿は、今まさに咲かんとする瞬間を迎えた美しい花のように見えた。
望美の姿に目を奪われ身動きできないヒノエ。
しかし、望美もまたヒノエの姿を見た瞬間、魔法にでもかかったかのように動くことが出来なかった。
ヒノエの姿はいつもの軽装ではなかった。
きっちりと襟を正した紺色の直垂姿。
いつもの軽装しか見たことのなかった望美にとって、初めて見るこの姿をしたヒノエはまるで別人のように見えた。
普段とは違う大人びた雰囲気は、いつも以上に『男』を感じさせられる。
トクンっと鼓動が高鳴る。
まだ自分の知らないヒノエがいる。
そしてその新しく知るヒノエに惹かれずにはいられない。
望美の心はどんどんヒノエで満たされ、好きという気持ちがあふれていく。
互いに相手への想いを強くし、しばらく見つめ合ったまま無言でいた二人だった。
しかしいつまでもそうしたままでいるわけにはいかず、先に動いたのはヒノエだった。
ヒュゥッと軽く口笛を吹く。
「驚いたな。こんなにも美しい花がこの世にあったとはね。とっても綺麗だよ、オレの姫君」
優しくヒノエに微笑まれ、望美は頬を赤く染める。
「ヒノエ君も……、その姿、とっても素敵だよ」
恥ずかしげにうつむきながら、望美は小さく告げる。
「望美にそう言ってもらえるとは嬉しいねぇ。こんな姿はめったにしないから『似合わないから嫌い』なんて言われでもしたらどうしようかと思ったよ」
「そんな、嫌うなんてことあり得ないよ! それにその姿は本当に似合ってるし、ヒノエ君はとってもカッコ良いんだから!」
力説する望美の様子を見て、ヒノエは嬉しそうな様子で笑った。
「そこまで強く言ってくれるなんてね。とっても嬉しいよ。ありがとう、望美」
何故か力が入り過ぎてしまった感じになり少し照れくさかったが、ヒノエが嬉しそうな様子を見せてくれたので望美も嬉しく思えた。
「それで、その、あのね。私の方こそホントに変じゃない?」
「変なわけないだろう? それともオレが選んだ衣装は気に入らなかった?」
「まさか。こんな綺麗な着物、見たことないよ。とっても気に入ってる」
「大丈夫だよ。よく似合ってる。まるで衣通姫のようだ。いやそれ以上だな。オレの自慢の姫君だよ」
ヒノエの言葉に照れる望美は、その頬を一層赤く染めた。
「言い過ぎだよ、ヒノエ君……」
「オレは本当のことしか口にしないよ」
「ヒノエ君ったら……」
端から見たらあきれるほどに甘い二人のやりとりである。
放っておけばいつまででも続きそうな様子ではあったが、そうもしていられない。
二人の間に入るのは至難ではあるが、簀子で控えていたヒノエに付き従ってきていた一人が、勇敢にも声をかけた。
「別当殿」
それを合図にヒノエの表情が少し引き締まる。
「そろそろ時間か」
ヒノエのその言葉に望美はドキッとする。
「じゃ、行こうか、望美」
「えっ、は、はい」
いよいよ、その時が来たのだと思うと、望美の体は緊張で支配される。
「では、お手をどうぞ」
スッと望美の前にヒノエは手を差し出した。
その手の上に望美は手を乗せる。
望美は平常心を保とう普通にしていたつもりだったのだが、その手はわずかに震えていた。
その小さな変化をヒノエは見逃すことはなかった。わずかな震えの意味を悟り、ギュッと望美の手を握る。
「オレにまかせてくれればいい。望美は普段通りの望美のままでいてくれれば大丈夫さ」
「でも……」
「オレは普段のままの望美が好きだよ。だからいつもの望美を親父達に紹介したいと思う。変に取り繕ったりしなくても、望美は十分魅力的だからね」
「普段の私なんて何の取り柄もないし……」
そんな望美の卑屈めいた言葉に、ヒノエは小さくため息をもらす。
「ホントに望美は自分のことをわかっていないね。望美はこのオレがたった一人惚れた最高の姫君なんだぜ。もっと自信を持って大丈夫さ」
「でも、やっぱり……」
「心配になるその気持ちはわからなくはないけれど、望美らしくねぇな。いつもの勢いはどうした? オレの両親に会うくらい、怨霊相手にすることを思えば平気だろう?」
「怨霊って……」
確かにヒノエの両親が望美の命を狙ったりするはずもないのだから、会うくらい恐ろしいわけでもないし平気なことだろう。
怨霊と両親とでは比べられるものではないと思うのたが、それを聞いたおかげで望美の気持ちはラクになった。
「そうだよね。避けて通れるものではないんだし、ぐずぐずしてるのは私らしくないよね。よぉし、気合い入れて。いざ、出陣!」
「その勢いだ」
ヒノエは楽しげに笑った。
第二話 第四話
<こぼれ話>
『ヒノエの両親にご挨拶』直前の二人です。
この時ちょっと迷ったのが二人の着るもの。
望美ちゃんは普通に着物で良いとして、ヒノエ君はどうしようかと……。
神職だと直衣の方が良いのか?と思いつつも、直垂の方が似合いそうなのでこっちにしました。
まぁ、今回はちゃんとした正装じゃなくても良いし〜(^^;)
|